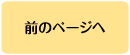税の学習コーナー > 学習・発展編 >
用語集
 用語集
用語集
- 確定申告
- 1年間の所得金額や税金を自分で計算して税務署に申告することです。
- 課税所得金額
- 1年間のすべての所得から、所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた所得のことをいいます。
- 関税
- 輸入品にかかる税金のことです。
- 間接税
- 税を納める人と負担する人が異なる税金のことです。間接税には、消費税や酒税、たばこ税などがあります。
- 源泉徴収
- 勤務先の会社があらかじめ本人の給与から所得税を差し引いて、本人に代わってまとめて納税することです。
- 公共事業
- 道路や下水道、ダムなどの整備を、国や地方公共団体が税金などを使って行う事業のことをいいます。
- 公債金
- 国の使うお金が税金の収入だけでは足りないときに、国が借金をして得るお金のことをいいます。
- 国債
- 国の使うお金が税金の収入では足りないときに、国が借金をするために発行する券のことをいいます。これは将来、一定の金額(利子)を上乗せして国が買い取ることを約束しています。
- 国税
- 国に納める税金のことです。国税には、法人税や所得税、消費税、酒税、たばこ税などがあります。
- 国民の三大義務
- 日本国憲法では日本国民の義務を定めています。「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の3つをいいます。
- 国会
- 国の議会のことをいいます。選挙で選ばれた国民の代表者が集まり、議論するところです。
- 固定資産税
- 土地や家屋などの財産にかかる税金のことです。
- 歳出
- 4月から翌年3月までの期間(会計年度)1年間の支出のことをいいます。
- 歳入
- 4月から翌年3月までの期間(会計年度)1年間の収入のことをいいます。
- 財務省
- 国の行政機関のひとつです。財政や予算、税制などに関する仕事を行っているところです。
- 資産課税
- 資産・財産に対して課税することです。資産課税には相続税や固定資産税などがあります。
- 自動車税
- 自動車を持っている人にかかる税金のことです。
- 社会保障
- 私たちが安心して生活していくために必要な公的サービス制度のことです。失業保険や生活保護、医療保険、年金制度、老人福祉、介護のしくみのことです。
- 酒税
- 日本酒、ビールなど、お酒にかかる税金のことです。
- 少子・高齢化
- 生まれてくる子どもの数が減り、65歳以上の高齢者が増えることをいいます。
- 消費課税
- 物品の消費やサービスの提供などに対して課税することです。消費課税には消費税や酒税、たばこ税などがあります。
- 消費税
- 商品の販売やサービスの提供にかかる税金で、消費者が負担します。
- 所得
- 会社からもらう給料や商売で得たお金などから、経費などを差し引いた残りの金額のことをいいます。
- 所得課税
- 個人や会社の所得に対して課税することです。所得課税には所得税や法人税などがあります。
- 所得控除
- 扶養控除や障害者控除など、その人の状況に応じて、税負担を調整するものです。
- 所得税
- 個人の所得に対してかかる税金のことです。
- 政府開発援助(ODA)
- O Official(=公の)、D Development(=開発)、A Assistance(=援助)の略です。先進国が発展途上国を援助する活動のことです。お金を貸したり、ダムや道路、病院をつくったり、病院で使う薬や注射器などを送っています。
- 税率
- 課税する金額に対して用いられる税額の割合のことです。
- 相続税
- 相続(親などの財産を受け継ぐこと)により財産を取得した個人にかかる税金のことです。
- たばこ税
- たばこにかかる税金のことです。
- 地方公共団体
- 都道府県や市区町村のことをいいます。地方自治体ともいわれています。
- 地方税
- 地方公共団体(都道府県や市区町村)に納める税金のことです。地方税には、住民税(道府県民税と市町村民税)や自動車税などがあります。
- 直接税
- 税を納める人と負担する人が同じ税金のことです。直接税には、所得税や法人税、住民税(道府県民税と市町村民税)などがあります。
- 内閣
- 内閣総理大臣とそのほかの大臣が集まる組織です。予算案を作成する仕事も行っています。
- 法人
- 株式会社など、法律上の権利義務の主体とされているものをいいます。
- 法人税
- 会社の所得に対してかかる税金のことです。
- 予算
- 1年間の歳入と歳出の予定を示した計画をいいます。
- 累進課税
- 課税所得金額などが大きくなるにつれて、税率が高くなるしくみのことです。
- 賦課・徴収
- 税金についての相談に応じたり、正しく税金が納められているか調べたりして、税金を集めることをいいます。

このページの先頭へ