番号制度概要に関するFAQ
(1) 国税分野における利用
Q1-1 マイナンバー(個人番号)・法人番号はどういった分野で利用されますか。また、国税の分野では、マイナンバー(個人番号)・法人番号はどのように利用されますか。(令和5年9月1日更新)
(答)
マイナンバー(個人番号)は、社会保障制度、税制、災害対策などの分野において、法令又は条例で定められた事務で利用が可能です。国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー(個人番号)を利用することとしています。
なお、法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用することができます。
Q1-2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務行政はどのように変わったのですか。
(答)
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にはマイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載していただくこととなりました。これにより、国税当局においては、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるものと考えています。
Q1-3 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入について、国税当局はどのような対応をしたのですか。
(答)
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にはマイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載していただくこととなりました。このため、国税当局においては、マイナンバー(個人番号)・法人番号が記載された申告書や法定調書等の受付・読み取りなどが可能となるよう、国税関係システムの整備を行いました。
また、番号法において、「国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する」と規定されていることから、国税庁は法人番号の“付番機関”となります。このため、法人番号の指定・通知等の業務を適切に行うために必要な体制整備やシステム構築を進め、平成27年10月からは、法人番号の指定・通知等の業務を行っています。
(参考)
番号法により、国税分野においてマイナンバー(個人番号)を利用することが可能とされました。また、番号法整備法や税法の政省令の改正により、![]() 申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の方(※1)のマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加する、
申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の方(※1)のマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加する、![]() 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方等(※2)が告知すべき事項にマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。
法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方等(※2)が告知すべき事項にマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。
- (※1) 控除対象扶養親族、事業専従者など
- (※2) 配当等を受領する方、株式等の譲渡対価を受領する方など
Q1-4 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、納税者にとって、どのようなメリットがありますか。(令和2年1月6日更新)
(答)
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入を契機とした納税者利便の向上施策として、住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から(原則として平成29年1月以降に提出するものから)住民票の写しの添付が不要とされました。また、事業者負担の軽減施策として、平成29年1月から、国と地方にそれぞれ提出する必要がある給与・公的年金等の源泉徴収票及び支払報告書のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)が可能となりました。
さらに、平成31年1月から、e-Taxメッセージボックスに格納された申告等に係る情報がマイナポータル(※)からも閲覧可能となりました。そのほか令和元年9月からは、記帳・決算説明会等の各種説明会の開催案内も閲覧可能となりました。
引き続き、マイナポータルを活用した納税者利便の向上に努めてまいります。
(※) マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。マイナポータルについての詳細は、デジタル庁ホームページをご参照ください(デジタル庁ホームページに移動します)。
Q1-5 マイナポータルの利用による、国税分野での利便性の向上について教えてください。(令和2年1月6日更新)
(答)
平成29年1月、マイナポータルとe-Taxとの認証連携を開始したことにより、マイナポータルにログインすれば、e-Tax用のIDとパスワードを入力することなく、メッセージボックスの閲覧、納税証明書に関する手続、源泉所得税に関する手続、法定調書に関する手続の利用ができるようになりました。
今後の予定として、年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります(マイナポータル連携)。
国税庁においては、マイナポータルとe-Taxとの認証連携が可能となる手続の拡大など、引き続き、更なる利便性の向上に向けた検討を進めています。
(2) 税務関係書類への番号記載
Q2-1 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務手続はどう変わったのですか。
(答)
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
このため、申告する必要のある方や法定調書の提出義務がある方などは、申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する場合には、その提出される方や一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。また、法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方は、法定調書の提出義務がある方に対してマイナンバー(個人番号)・法人番号を提供することが必要となります。
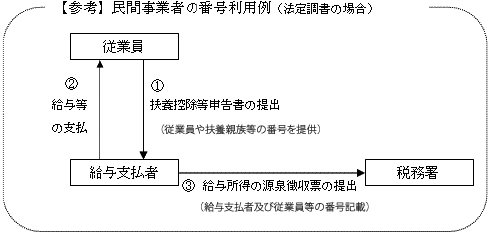
なお、なりすましを防止するため、税務署等がマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、本人確認を行うこととされています。したがって、申告する必要のある方や法定調書の提出義務がある方などが、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際には、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示などにより、本人確認をさせていただくことになります。
また、法定調書の提出義務がある方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合など、他人のマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、法定調書の提出義務がある方が本人確認を行う必要があります。
※ 本人確認について、詳しくは本人確認に関するFAQを参照して下さい。
(参考1)不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)
(参考2)契約先から報酬などを受け取る方は契約先へマイナンバーの提供が必要です(PDF/550KB)
Q2-2 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務関係書類の記載事項は、どう変わったのですか。(平成30年6月29日更新)
(答)
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴う税制上の対応として、 平成25年5月に番号法整備法、 平成26年5月に税法の改正政令、 平成26年7月に税法の改正省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出される方や一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号を追加するなどの措置がなされました。
具体的には、
- イ 申告書等を提出される方
- ロ 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
- ハ 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
- ニ 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
- ホ 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)
のマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。
なお、納付書や所得税徴収高計算書については、マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要はありません。
また、その後の税制改正において、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直し(※)が行われ、一定の書類についてはマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。
※ 税制改正について、詳しくは、
- 平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)
- 平成30年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。
Q2-3-1 申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合、必ずマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載しなければなりませんか。(平成30年6月29日更新)
(答)
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。
Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年9月7日更新)
(答)
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。
(答)
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
Q2-4 マイナンバー(個人番号)・法人番号を記載する必要がある申告書や法定調書等の税務関係書類はどのようなものがあるのですか。(平成30年6月29日更新)
(答)
申告書や法定調書等の税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、
-
 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
所得税や贈与税については、平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書にあっては平成28年中に提出するもの))から、
-
 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
-
 消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
消費税については、平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から、
-
 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
-
 酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
酒税・間接諸税については、平成28年1月分の申告書から、
-
 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
-
 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)
申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから(税務署等のほか、給与支払者や金融機関等に提出する場合も含みます。)
必要となります。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。
Q2-5 所得税の準確定申告書付表や消費税申告書の付表6、相続税の申告書や贈与税の申告書付表には、複数の相続人が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人が自らのマイナンバー(個人番号)を付表等に記載して二人目の相続人に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
また、マイナンバー(個人番号)が記載された付表等を渡された二人目の相続人は、一人目の相続人の本人確認を行う必要がありますか。(平成27年12月25日掲載、平成28年7月15日更新)
(答)
所得税準確定申告書の付表や消費税申告書の付表6(死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書)、相続税の申告書や贈与税の申告書付表の作成に当たり、複数の相続人がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人が当該付表等にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。
また、相続人間での本人確認は不要です。
なお、当該付表等に記載された相続人の本人確認は税務署の職員が行いますので、準確定申告書等の提出の際には、各相続人の本人確認書類の写しを添付していただくようお願いします(各相続人のうち税務署の窓口に来られるご本人の本人確認書類については、その写しの添付に代えて、本人確認書類を提示していただいても差し支えありません。)。
- ※1 このケースにおいて、一の相続人のマイナンバー(個人番号)が記載された当該付表等を受け取ったその他の相続人は、番号法の規定により、そのマイナンバー(個人番号)を書き写したり、コピーを取る等を行うことはできませんので、付表等の控えを保管する場合は、記載されたマイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。
- ※2 所得税準確定申告書の記載方法については、確定申告書の記載例のページをご覧ください。
(3) その他
Q3-1 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは具体的に誰を指しますか。
(答)
番号法において、「個人番号利用事務実施者」とは、「個人番号を使って番号法別表第一で定める事務(個人番号利用事務)を処理する者」をいい、国税分野では、国税庁長官をはじめ、国税局や税務署等において国税の賦課又は徴収に関する事務に従事する者が「個人番号利用事務実施者」となります。
また、番号法において、「個人番号関係事務実施者」とは、「法令に基づき、個人番号利用事務に関し他人の番号を利用した事務(個人番号関係事務)を行う者」をいい、国税分野では、例えば、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した源泉徴収票を提出する源泉徴収義務者の方や、他人のマイナンバー(個人番号)を記載した法定調書を提出する義務がある方などが「個人番号関係事務実施者」となります。
なお、番号法においては、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者を併せて「個人番号利用事務等実施者」としています。
Q3-2-1 特定個人情報(マイナンバー(個人番号)を含む個人情報)の提供については番号法で制限されていますが、国税分野において、特定個人情報の提供を行うのはどのような場合ですか。
(答)
マイナンバー(個人番号)は、番号法で規定する場合以外は提供をしてはならないとされています。
国税分野において、特定個人情報の提供を行うことができる場合としては、
-
 個人番号関係事務実施者からの提供(例:民間事業者が自身のマイナンバー(個人番号)及び従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した源泉徴収票を税務署へ提出)【番号法第19条第2号】
個人番号関係事務実施者からの提供(例:民間事業者が自身のマイナンバー(個人番号)及び従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載した源泉徴収票を税務署へ提出)【番号法第19条第2号】
-
 本人(代理人)から個人番号関係事務実施者への提供(例:従業員等が本人のマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書を勤務先へ提出)【番号法第19条第3号】
本人(代理人)から個人番号関係事務実施者への提供(例:従業員等が本人のマイナンバー(個人番号)を記載した扶養控除等申告書を勤務先へ提出)【番号法第19条第3号】
-
 本人(代理人)から個人番号利用事務実施者である国税庁長官(税務署等)への提供(例:本人又は代理人が、本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を税務署等へ提出)【番号法第19条第3号】
本人(代理人)から個人番号利用事務実施者である国税庁長官(税務署等)への提供(例:本人又は代理人が、本人のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を税務署等へ提出)【番号法第19条第3号】
-
 本人から委託者への提供(例:申告書等作成のため、本人から税理士へマイナンバー(個人番号)を提供)【番号法第19条第5号】
本人から委託者への提供(例:申告書等作成のため、本人から税理士へマイナンバー(個人番号)を提供)【番号法第19条第5号】
-
 地方税法等に基づく、国税庁長官から市区町村長等への国税又は地方税情報の提供(例:国税庁長官から、マイナンバー(個人番号)を含む所得税申告書の情報を地方税当局へ提供)【番号法第19条第9号】
地方税法等に基づく、国税庁長官から市区町村長等への国税又は地方税情報の提供(例:国税庁長官から、マイナンバー(個人番号)を含む所得税申告書の情報を地方税当局へ提供)【番号法第19条第9号】
-
 租税に関する法律の規定による質問、検査等が行われる際の提供(例:税務調査の際、調査対象者がマイナンバー(個人番号)を含む情報を税務署へ提供)【番号法第19条第14号】
租税に関する法律の規定による質問、検査等が行われる際の提供(例:税務調査の際、調査対象者がマイナンバー(個人番号)を含む情報を税務署へ提供)【番号法第19条第14号】
などがあります。
Q3-2-2 個人で所有している不動産を法人に賃貸していますが、その法人(借主)から、法定調書に記載するためにマイナンバー(個人番号)の提供を求められました。この場合、マイナンバー(個人番号)を提供しなければならないのですか。(平成28年12月22日掲載、平成30年1月4日更新)
(答)
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴い、平成28年1月1日以後の支払に係る「不動産の使用料等の支払調書」には、支払を受ける方の氏名及び住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
税法上、法人又は不動産業者である個人の方(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。)は、同一人に対するその年中の不動産の使用料などの支払金額が15万円を超える場合には、税務署へ「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要となるため、その支払を受ける方(貸主)に対してマイナンバー(個人番号)の提供を求めることになります。
ご質問の場合については、不動産の借主である法人が「不動産の使用料等の支払調書」を税務署へ提出する場合には、当該調書に支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があるため、支払を受ける方は、当該法人に対し、マイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。
なお、マイナンバー(個人番号)を提供する場合には、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける方が本人確認を行うため、マイナンバーカード等の提示等が必要になります。詳しくは、本人確認に関するFAQのQ1-1を参照してください。
また、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける不動産の使用料などの支払をする方は、提供を受けたマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を取り扱う際には、それら特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。詳しくは、Q3-5を参照してください。
※ 不動産の使用料などの支払を受ける方(貸主)が法人の場合には、支払をする方(借主)に法人番号を提供する必要があります。
(参考)不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします(PDF/114KB)
Q3-3 支払金額が少額であり、法定調書の提出が必要とされる金額にも満たない場合には、税務署等に法定調書の提出義務が生じませんが、その場合であっても、マイナンバー(個人番号)の提供を求める必要がありますか。
(答)
法定調書の提出が必要とされている金額に満たない支払金額であるため、法定調書を提出しないことが明らかな場合には、マイナンバー(個人番号)の提供を求めることはできません。
ただし、年の途中に契約を締結するなど、その年は法定調書の提出が不要であっても、翌年に法定調書の提出が必要とされることが明らかな場合には、翌年の法定調書作成・提出事務のためにマイナンバー(個人番号)の提供を求めることができます。
(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A Q4-2参照(個人情報保護委員会ホームページへ移動します))
Q3-4 社会保障・税番号<マイナンバー>制度の周知・広報はどのように行っていますか。(平成30年1月4日更新)
(答)
国税庁では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度の定着のため、国税庁ホームページに同制度についての特設サイトを設け、国税の社会保障・税番号<マイナンバー>制度に関する情報や法人番号の最新情報を掲載しているほか、関係民間団体や業界団体等に対する説明会等の実施、関係省庁と連携して新聞やインターネット広告などを通じた広報を行うなど、積極的な周知・広報に取り組んでいます。
Q3-5 事業者がマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を取り扱うに当たって、注意すべきことはありますか。
(答)
マイナンバー(個人番号)は番号法に定められた利用範囲を超えて利用することはできないほか、特定個人情報をむやみに提供することもできません。
また、特定個人情報を取り扱う際は、特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。具体的な措置については、平成26年12月に特定個人情報保護委員会(現:個人情報保護委員会)より「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が示されていますので、このガイドラインに沿った措置が必要になります。
国税に関する手続において、事業者の方は、従業員や顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した書類の作成・保管等を行うことになります。事業者の方は、その取扱方法や事業規模等に合った措置が必要となります。ガイドラインや当該ガイドラインに関するQ&Aにおいて、それぞれの対応方法が詳しく解説されていますので、ご確認の上、必要な対応を行ってください。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」はこちら。(個人情報保護委員会ホームページへ移動します)
特定個人情報の適正な取扱いに関するQ&Aはこちら。(個人情報保護委員会ホームページへ移動します)
Q3-6 顧客とメールにて資料の送受信を行っていますが、マイナンバー(個人番号)を含む資料についても、従来どおりPDF等のデータに読み込み、メールの添付資料として送受信を行ってもよいですか。
(答)
必要かつ適切な安全管理措置がなされているのであれば、問題ないと考えます。
Q3-7 税務調査において、安全管理措置が適当かどうか確認することはありますか。
(答)
特定個人情報の安全管理措置の適否の判断については、個人情報保護委員会が所掌しており、国税当局は判断する立場にないため、確認をすることはありません。
Q3-8 従業員等のマイナンバー(個人番号)が記載された給与所得の扶養控除等申告書などが漏えいした場合、担当者や企業は罰せられますか。 (平成30年6月29日更新)
(答)
刑事罰については、過失による情報漏えいの場合、ただちに罰則が適用されるということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。民事の場合については、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。
デジタル庁ホームページよくある質問 Q4-7-1にて解説されていますので、ご参照ください(デジタル庁ホームページに移動します)。
【参考】
適切な安全管理措置の講じ方の詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご確認下さい(個人情報保護委員会ホームページに移動します)。
Q3-9 マイナンバー(個人番号)の指定を受けた後に国外へ転出した者が帰国した場合には、出国前と同じマイナンバー(個人番号)が指定されますか。(令和2年5月25日更新)
(答)
マイナンバー(個人番号)の指定を受けた方が国外へ転出をした後に再び帰国した場合でも、出国前に指定されたマイナンバー(個人番号)は変更されません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)については、マイナンバー(個人番号)の指定を受けた方が国外へ転出をする際に市区町村長へ返納する必要がありますが、返納されたマイナンバーカード(個人番号カード)は、国外への転出により返納を受けた旨が表示され、国外転出者へ還付されることになります。
((デジタル庁ホームページよくある質問Q2-8及びQ3-19参照(デジタル庁ホームページへ移動します))
Q3-10 海外勤務者等のマイナンバー(個人番号)を会社等のデータベースで保管してもよいですか。
(答)
将来帰国することが予定されている者であり、帰国後の源泉徴収票作成事務等でマイナンバー(個人番号)を利用することが予定されている場合など、必要があれば保管してもよいと考えられます。
Q3-11 事業者から個人番号関係事務を受託し、事業者に代わり番号の収集、本人確認及び収集した番号を法定調書などの税務書類に記載する業務を行う場合に、税理士法の観点で注意することはありますか。(平成27年12月25日掲載)
(答)
税理士法は、税理士又は税理士法人でない者は、原則として、「税理士業務」を行ってはならないと規定しています(税理士法第52条)。
ここでいう「税理士業務」とは、他人の求めに応じて、租税に関し、![]() 税務代理、
税務代理、![]() 税務書類の作成又は
税務書類の作成又は![]() 税務相談を業として行うことをいいます(税理士法第2条第1項)。
税務相談を業として行うことをいいます(税理士法第2条第1項)。
また、![]() の税務書類とは、申告書のほか、法定調書や源泉徴収票などの租税に関する法令の規定に基づき作成し、かつ、税務官公署に提出する書類をいいます(税理士法第2条第1項第2号、税理士法施行規則第1条)。
の税務書類とは、申告書のほか、法定調書や源泉徴収票などの租税に関する法令の規定に基づき作成し、かつ、税務官公署に提出する書類をいいます(税理士法第2条第1項第2号、税理士法施行規則第1条)。
したがって、税務書類の提出義務者、税理士又は税理士法人以外の者が税務書類の作成を行うことはできません。
ただし、![]() の作成とは、税務書類を自己の判断に基づいて作成することをいいますので(税理士法基本通達2−5)、提出義務者である事業者自身が税務書類の記載事項のうち番号以外の部分を自己の判断に基づき作成したのであれば、個人番号関係事務の受託者が事業者に代わり収集等した番号のみをその税務書類に記載したとしても、上記
の作成とは、税務書類を自己の判断に基づいて作成することをいいますので(税理士法基本通達2−5)、提出義務者である事業者自身が税務書類の記載事項のうち番号以外の部分を自己の判断に基づき作成したのであれば、個人番号関係事務の受託者が事業者に代わり収集等した番号のみをその税務書類に記載したとしても、上記![]() の「税務書類の作成」に該当しません。
の「税務書類の作成」に該当しません。
なお、税理士法第52条の規定に違反した場合には、税理士法第59条の規定により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
Q3-12 マイナンバー(個人番号)が記載された書類の保管を依頼されたのですが、私は個人番号関係事務実施者ではありません。マイナンバー(個人番号)の提供を受けることは番号法上問題ないですか。(平成27年12月25日掲載)
(答)
番号法では、第19条各号に規定している場合を除き他人のマイナンバー(個人番号)を収集・保管することを禁止しており、第19条第5号において、特定個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合のマイナンバー(個人番号)の提供を認めています。
このため、個人番号関係事務実施者ではない方がマイナンバー(個人番号)が記載された書類を保管するためには、保管を依頼した方との間で第19条第5号により特定個人情報の取扱いに関する委託契約を締結する必要があります。
Q3-13-1 外国の金融機関に口座を開設する際や外国の暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う際に、納税者番号としてマイナンバー(個人番号)の提供を求められたのですが、提供することに問題ないですか。(平成28年11月18日掲載、令和8年1月28日更新)
(答)
国際的租税回避の防止を目的として、銀行等の口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際的な統一基準(以下「共通報告基準」(CRS))及び暗号資産交換業者等が保有する暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換するための国際的な統一基準(以下「暗号資産等報告枠組み」(CARF))がOECDにおいて策定されているところであり、交換の対象となる情報にはマイナンバー(個人番号)も含まれています。
そのため、日本と共通報告基準又は暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換が可能な租税条約がある国・地域(注1、2)に所在する金融機関又は暗号資産交換業者等から、所在地国・地域の共通報告基準又は暗号資産等報告枠組みの実施に関する法令に基づいて、税務当局へ報告を行うためにマイナンバー(個人番号)の提供を求められることがあります。この場合、当該外国の金融機関又は暗号資産交換業者等にマイナンバー(個人番号)を提供することは問題ありません。
- (注1) 令和8年1月1日現在、共通報告基準に基づく自動的情報交換の実施に参加する又は今後参加を予定している171か国・地域(日本を除く。)のうち、日本と共通報告基準に基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域は※2のとおりです。
- ※1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について(令和7年6月)(令和8年1月1日以降用)(PDF/255KB)
- ※2 共通報告基準に基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況(令和8年1月1日現在)(PDF/135KB)
- ※3 AEOI:STATUS OF COMMITMENTS(OECDホームページ内の共通報告基準に基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況の一覧へ移動します。)
- (注2) 令和8年1月1日現在、暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換の実施に参加する又は今後参加を予定している75か国・地域(日本を除く。)のうち、日本と暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域は※5のとおりです。
- ※4 非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度の導入について(令和7年6月)(令和8年1月1日以降用)(PDF/227KB)
- ※5 暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況(令和8年1月1日現在)(PDF/130KB)
- ※6 Jurisdictions committed to implement the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)(OECDホームページ内の暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換の実施時期に関する国際的な状況の一覧へ移動します。)
Q3-13-2 国内の居住者が外国の金融機関や外国の暗号資産交換業者等に対してマイナンバー(個人番号)を提供することの根拠を教えてください。(平成28年11月18日掲載、令和8年1月28日更新)
(答)
各国・地域との間における共通報告基準又は暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換のため、日本と共通報告基準又は暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域(注1、2)の金融機関又は暗号資産交換業者等から各国の法令を根拠としてマイナンバー(個人番号)の記載を求められるケースは、番号法第19条第3号に規定された場合に該当することから、このケースにおいては、自己宣誓書(Self-Certification)等の書類にマイナンバー(個人番号)を記載することは問題ありません。
- (注1) 令和8年1月1日現在、共通報告基準に基づく自動的情報交換の実施に参加する又は今後参加を予定している171か国・地域(日本を除く。)のうち、日本と共通報告基準に基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域はQ3-13-1※2のとおりです。
- (注2) 令和8年1月1日現在、暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換の実施に参加する又は今後参加を予定している75か国・地域(日本を除く。)のうち、日本と暗号資産等報告枠組みに基づく自動的情報交換が可能な租税条約等がある国・地域はQ3-13-1※5のとおりです。
Q3-14-1 預貯金口座への付番制度について教えてください。(平成30年1月4日掲載)
(答)
平成27年9月に番号法をはじめとする関係法令が改正され、金融機関等(注)は、平成30年1月以降、預貯金者の情報をマイナンバー(個人番号)又は法人番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととされました。
(注) 預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業共同組合をいいます。
Q3-14-2 預貯金口座の付番で、金融機関等にマイナンバー(個人番号)の提供を行うことは義務なのですか。(平成30年1月4日掲載)
(答)
平成30年1月から預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)の付番が始まりましたが、金融機関等へのマイナンバー(個人番号)の提供は、法令上、義務とはされていません(注)。
(注) 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)や法定調書の対象となる金銭等の支払等の際のマイナンバー(個人番号)の記載・告知義務が所得税法等で規定されている取引を除きます。

