No.6505 簡易課税制度
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |
対象者または対象物
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者(注)
(注) 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において恒久的施設(※1)を有しない国外事業者(※2)は、簡易課税制度の適用を受けられません(※3)。
(※1)「恒久的施設」とは、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、例えば、国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場もしくは鉱山その他の天然資源を採取する場所またはその他事業を行う一定の場所などを言います。詳しくは、No.2883 恒久的施設(PE)(令和元年分以後)を参照ください。
(※2)国外事業者とは、所得税法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。
(※3)令和6年9月30日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間の初日において恒久的施設(PE)を有しない場合には、簡易課税制度の適用はありません。
計算方法・計算式
簡易課税制度を適用する場合の仕入控除税額の計算については、次のとおりです。
基本的な計算の方法
イ 第1種事業から第6種事業までのうち1種類の事業だけを営む事業者の場合
(算式)
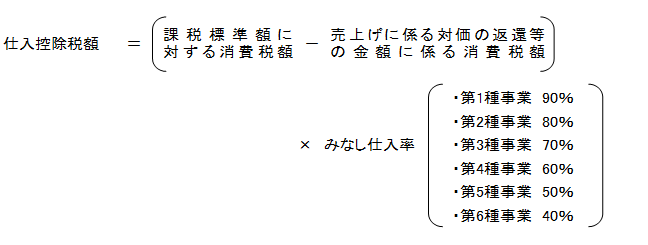
ロ 第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合
(イ)原則法
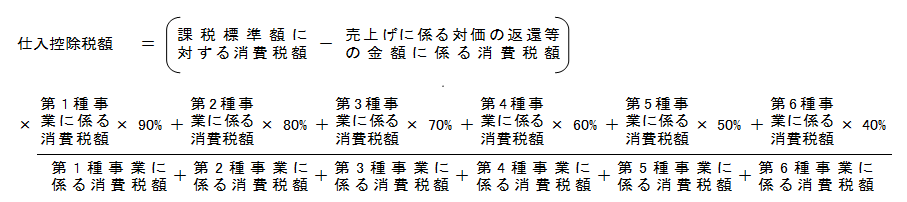
(ロ)簡便法
次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
A 貸倒回収額がある場合
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
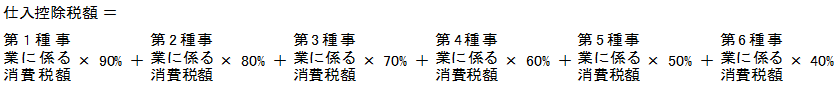
特例の計算
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
例えば、3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業および第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合の計算式は次のとおりです。
(イ)原則法
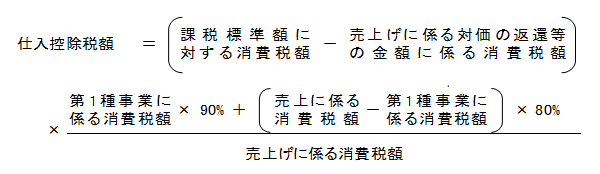
(ロ)簡便法
次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
A 貸倒回収額がある場合
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
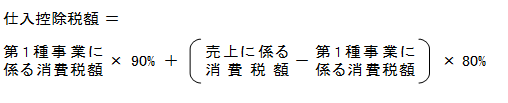
事業区分をしていない場合の取扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
手続き
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます(注)。
なお、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その登録を受けた日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
おって、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者のこの経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注)簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。
災害その他やむを得ない事情がある場合
災害その他やむを得ない事情により、その課税期間開始前に消費税簡易課税制度選択届出書または消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出ができなかった場合には、その届出期限についての特例が適用できる場合があります。
詳しくは、コード6630「やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合」、コード6632「災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合」を参照してください。
提出書類等
注意事項
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんのでご注意ください。
なお、この届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合またはその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。
根拠法令等
消法30、37、消令56、57、57の2、消規17、平28改正法附則51の2、平30改正令附則21の2、消基通13-1-3、13-1-3の5、13-1-5の2
関連リンク
◆各種様式
関連コード
- 6509 簡易課税制度の事業区分
QAリンク
お問い合わせ先
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

