よくあるご質問とその回答
(令和4年6月10日付で改正された移転価格事務運営要領(事務運営指針)の内容に基づいています。)
1 事前確認関係
【質問1−イ】事前確認には、どのような類型があるのですか。
〔回答〕事前確認の類型としては、(1)相互協議を伴う事前確認と(2)相互協議を伴わない事前確認があります。
- (1) 相互協議を伴う事前確認
相互協議を伴う事前確認は、独立企業間価格の算定方法等について、日本の税務当局と外国税務当局との間で相互協議を行い、その合意に基づいて確認するものです。外国税務当局による課税についての予測可能性も確保されます。
このようなメリットがあるため、日本を含む多くの国で相互協議を伴う事前確認が行われています。
【基本的な手続の流れ(イメージ)】
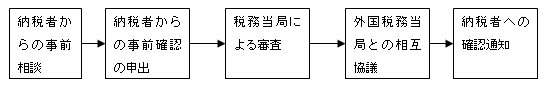
なお、相互協議を伴う事前確認の場合には、事前確認の申出とは別に、相互協議の申立てが必要となります。相互協議の申立てについては、平成13年6月25日官協1−39ほか7課共同「相互協議の手続について(事務運営指針)」をご覧ください。 - (2) 相互協議を伴わない事前確認
相互協議を伴わない事前確認は、日本の税務当局が外国税務当局との相互協議を行わずに独立企業間価格の算定方法等について確認するものです。国外関連者が外国税務当局により課税されるリスクの回避までは保証されませんが、相互協議を伴う事前確認に比べ、通常、処理が早くなります。
【基本的な手続の流れ(イメージ)】
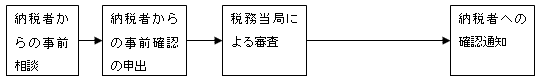
なお、平成22年1月1日以後に通知が行われた事前確認(平成25年12月31日時点で有効でないものを除く)の内容(法人名、取引概要、算定方法等)については、BEPS行動計画5の最終報告書の勧告に従い、事前確認の対象となる取引を行う国外関連者等の所在地国の税務当局に対して、租税条約等に基づき自発的に情報提供を行うことになっています。
【質問1−ロ】国外関連取引の規模が小さいため、移転価格課税を受けるリスクが小さいと考えられる場合でも、事前確認の申出を行った方がよいのですか。
〔回答〕事前確認を受けることにより、移転価格課税の回避や予測可能性の確保が図られるのは確かですが、他方で書類作成等のための事務や費用等もかかることになりますので、仮に納税者の皆様が移転価格課税を受けるリスクが小さいとお考えになるのであれば、事前確認の申出を行わないという選択肢もあり得ます。
ご質問に関して、移転価格課税を受けるリスクが小さいと考えられるような場合に、事前確認の申出を行うべきかどうかについては、あくまで納税者の皆様ご自身のご判断になりますが、事前相談においては、このようなご相談も受け付けています。
【質問1−ハ】国外関連取引の規模が小さいため、外国税務当局から移転価格課税を受けるリスクが小さいと考えられる場合でも、相互協議を伴う事前確認の申出を行った方がよいのですか。
〔回答〕【質問1−イ】の回答のとおり、相互協議を伴わない事前確認の場合には外国税務当局からの課税リスクが残ることになりますが、相互協議を伴う事前確認と比較して、一般的に、処理期間が短縮され、書類作成等のための事務や費用等が軽減されますので、仮に納税者の皆様が外国税務当局から移転価格課税を受けるリスクが小さいとお考えになるのであれば、相互協議を伴わない事前確認の申出を行うという選択肢もあり得ます。
ご質問に関して、外国税務当局から移転価格課税を受けるリスクが小さいと考えられるような場合に、相互協議を伴う事前確認の申出と相互協議を伴わない事前確認の申出のいずれを行うべきかについては、あくまで納税者の皆様ご自身のご判断になりますが、事前相談においては、このようなご相談も受け付けています。
【質問1−ニ】事前確認の申出書を書いたり、提出資料を準備するのは難しそうですが、税理士などに依頼しなければいけないのですか。
〔回答〕事前確認の申出書や提出資料を準備していただくためには、独立企業間価格の算定方法等をご理解頂いた上で資料の作成等を行っていただくことが必要になります。事前相談の際に、国税局の担当者が説明いたしますが、不安な方は、税務代理を委嘱した税理士にご相談されるのも一案です。
【質問1−ホ】事前確認の申出書はいつまでに提出すればよいのですか。
〔回答〕事前確認の申出は、確認対象事業年度のうち最初の事業年度(確認対象初年度)開始の日までに行っていただく必要があります。
(注) 確認対象初年度開始の日が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は国税通則法施行令第2条第2項((期限の特例))に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日が申出書の提出期限となります。
申出書は国税通則法第22 条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定が適用される書類には該当しません。そのため、郵送で提出する場合には、通信日付印に表示された日は提出日とはならず、申出書は提出期限までに納税地を所轄する税務署(調査課所管法人に該当する法人にあっては納税地の管轄国税局)へ到達する必要があります。
なお、申出書に添付する資料の一部について、申出期限までに提出できなかったことについて相当の理由があると認められる場合には、資料の提出に通常要する日数を勘案して、45日を超えない範囲内で提出期限を設定し、当該資料の提出を猶予する取扱いも行っています。
【質問1−ヘ】事前確認審査はどのように行われるのですか。
〔回答〕事前確認審査においては、国税局の審査担当者が実際に会社や事業所に臨場し、独立企業間価格の算定方法等に関する説明をお聞きすることになります。その際、事前確認申出書の添付資料(後述の「事前確認申出時の提出書類」をご覧ください。)以外の各種のデータや分析資料の提出及び説明をお願いすることもありますが、的確かつ迅速な審査のために、ご理解・ご協力をお願いいたします。
【質問1−ト】事前確認審査においてポイントとなるのはどのような項目ですか。
〔回答〕事前確認審査のポイントは、個々の申出内容によって異なりますが、基本的に以下のような項目を中心に審査を行うことになります。(以下の用語については、「用語の解説」をご覧ください。)
- 独立企業間価格の算定方法と検証対象法人
- 確認対象取引の範囲と取引単位
- 比較対象法人の選定と差異調整
- 利益分割要因の決定と測定
- 利益率等の範囲の設定と補償調整
- 重要な前提条件
【質問1−チ】事前確認にはどれくらいの期間がかかるのですか。
〔回答〕事前確認に要する期間については、相互協議を伴わない事前確認か相互協議を伴う事前確認か、新規申出か更新申出か、更には内容の複雑性や納税者の皆様の資料の提出状況などによって異なるほか、外国税務当局との関係もありますので一概には言えませんが、これまでの実績によれば1件当たりの処理期間は平均2年程度です。
納税者の皆様のご理解をいただくとともに、的確かつ迅速な審査のため、資料の早期提出にご協力をお願いいたします。
【質問1−リ】事前確認後に何か報告を行う必要があるのですか。
〔回答〕事前確認の通知を受けた後は、確認を受けた各事業年度(確認事業年度)の確定申告書の提出期限又は所轄税務署長等があらかじめ定める期間内に、次の事項を記載した報告書を提出していただく必要があります。
- 事前確認を受けた国外関連取引(確認取引)について事前確認の内容に適合した申告を行っていることの説明
- 事前確認する旨の通知を受けた法人(確認法人)及びその国外関連者の確認取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類(事前確認の内容により局担当課が必要と認める場合に限る。)
- 重要な前提条件の変動の有無に関する説明
- 確認取引の対価の額が事前確認の内容に適合しなかった場合に、確認法人が行った補償調整の説明
- 確認法人及び確認取引に係る国外関連者の財務状況
- その他確認事業年度において確認取引について事前確認の内容に適合した申告が行われているかどうかを検討する上で参考となる事項
なお、各国税局の担当部署ではこの報告書等に基づき、事前確認の内容に適合した申告が行われているかどうかのチェックを行っています。
報告書をご提出いただく際には、「年次報告書自主点検チェックシート」(PDF/141KB)をご活用ください。
【質問1−ヌ】確定申告の内容が事前確認の内容と異なった場合は、どのように取り扱われるのですか。
〔回答〕確認事業年度に関しては、確定申告後に確認取引の対価の額が当該事前確認の内容に適合していないことにより所得の金額が過少となっていたことが判明した場合には、補償調整を行い自主的に修正申告書を提出していただくこととなります。税務当局の指摘等によらず、自主的にご提出いただく修正申告書については、国税通則法第65条第1項及び第5項(過少申告加算税)に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」には該当しません。
また、修正申告書が同条第5項の調査通知後に提出された場合であっても、事前確認の内容に適合させるための部分は、同項に規定する「調査通知がある前に行われたもの」として取り扱われます。
なお、上記の取扱いは、あくまで確認取引に係る加算税に関するものであり、修正申告に伴い増加する本税額の納付が必要であることはもとより、確認取引以外の取引に係る修正申告については加算税が賦課される場合があることにご留意ください。
2 事前相談関係
【質問2−イ】事前相談は、個人でも行うことができるのですか。
〔回答〕移転価格税制は「法人」のみに適用されますので、事前相談を行うことができるのは「法人」のみです。
【質問2−ロ】事前相談は、どのような法人でも利用できるのですか。
〔回答〕事前相談ができるのは、国外関連者との取引を行っており、これについて事前の確認を受けようとする法人です。
【質問2−ハ】事前相談はいつまでに行う必要があるのですか。
〔回答〕事前相談については、期限等はありません。しかし、申出に当たっては、独立企業間価格の算定等のために必要な資料を提出していただく必要があるため、それらの準備に要する期間を考慮していただき、できるだけ早めに相談されることをお勧めします。
なお、事前相談は、原則として予約制としておりますので、相談を希望される方は管轄国税局の担当部署に事前にご連絡の上、予約をお願いいたします。
【質問2−ニ】事前相談の際には、どのような資料を用意する必要があるのですか。
〔回答〕事前相談の際には、相談をより円滑に行うため、例えば、確認対象取引や確認対象取引を行う組織の概要、国外関連者との資本関係などに関する資料をできるだけご用意ください。また、資料のうち、外国語で記載されているものについては、日本語訳を添付してください。
なお、事前相談は、ご用意いただいた資料の範囲内で行っております。このため、相談内容に応じ必要となる資料のご提示又はご提出がない場合には、十分な相談に応じられなくなることがありますのでご留意ください。
(注)事前確認申出時の提出書類について
事前確認の申出時において必要となる資料については「事前確認申出時の提出書類」をご参照いただき、申出時までにご準備ください。なお、ここに掲げる全ての資料が揃わない場合でも、お気軽にご相談ください。
【質問2−ホ】事前相談の内容は公開されるのですか。
〔回答〕事前相談の内容は非公開です。また、この相談は、税務代理を委嘱した税理士を通じた匿名の相談でも構いません。ただし、匿名の相談の場合には、事実関係の説明が不十分となり、実質的に事前相談ができなくなってしまうこともありますので、実際に事前確認を予定している取引について具体的に説明してください。
【質問2−ヘ】事前相談を行った場合、必ず事前確認の申出を行わなくてはならないのですか。
〔回答〕事前確認の申出を行う必要があるかどうかは、あくまでも納税者の皆様の判断によります。したがって、事前相談を行ったからといって必ず事前確認の申出を行わなければならないということはありません。
【質問2−ト】事前相談を行った場合、税務調査は実施されないのですか。
〔回答〕税務当局との間で事前相談を行ったとしても、移転価格に関する税務調査を妨げるものではありません。ただし、仮に税務調査が行われた場合であっても、納税者の皆様の同意を得ることなしに、事前相談において提出された資料(事実に関する資料を除きます。)を調査に使用することはありません。
3 その他共通
【質問3−イ】事前相談や事前確認審査はどの部署が担当することとなりますか。
〔回答〕事前相談は、原則として、国税局審査担当部署及び国税庁担当課の担当者が対応し、相互協議を伴う事前確認の場合には、この二者に国税庁相互協議室の担当者が加わります。
また、事前確認申出後の事前確認審査は、国税局の審査担当部署が担当することになります。
【質問3−ロ】事前相談及び事前確認審査には手数料が必要ですか。
〔回答〕わが国においては、事前相談及び事前確認審査については、手数料は不要です。
なお、相互協議を伴う事前確認については、相手国において手数料が必要な場合もあります。
【質問3−ハ】文書回答手続と移転価格税制上の事前相談及び事前確認手続とはどのように違うのですか。
〔回答〕文書回答手続は、納税者の皆様から、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービスです。詳しくは、「事前照会に対する文書回答等について」をご参照ください。
一方、移転価格税制に係る事前確認及びこれに関する事前相談は、個別性・秘密性が極めて高いという事情があるため、文書回答手続とは別の手続として設けられています。
(ご参考)事前確認申出時の提出書類
- イ 確認対象取引の内容、当該確認対象取引の流れ及びその詳細を記載した資料
事前確認を受けようとする国外関連取引に係る取引規模を記載した取引関係図等の資料です。確認対象取引以外の取引についても確認対象取引に関連する場合には、これらに含めてください。また、取引価格の決定方法、取引条件(取引通貨、引渡条件、決済条件、値引き・割戻しの有無)、契約関係、資金の流れ、為替リスクの負担状況等についても説明をお願いします。 - ロ 確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の事業の内容及び組織の概要を記載した資料
申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の組織図等の資料です。 - ハ 確認対象取引において確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者が果たす機能、負担するリスク及び使用する資産に関する資料
例えば、研究開発機能であれば、基礎研究、製品開発等についての説明、製造機能であれば、生産計画、設備投資、工程管理、品質管理、在庫管理、PL負担等についての説明を、販売機能であれば、販売戦略、販売計画、広告宣伝、販売活動、顧客管理、価格決定、受注・発注、物流業務、在庫管理、製品保証等についての説明をお願いします。また、確認対象取引において、無形資産が使用されている場合は、併せてその内容等についての説明をお願いします。 - ニ 確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等及びそれが最も適切な方法であることを説明した資料
事前確認を受けようとする独立企業間価格の算定方法、国外関連取引、当該国外関連取引を行う国外関連者、事前確認を受けようとする事業年度、比較対象取引の選定過程及び差異の調整等並びにそれらが最も適切であることについての説明資料です。 - ホ 事前確認を行い、かつ、事前確認を継続する上で前提となる重要な事業上又は経済上の諸条件(条件に相当する確認対象取引に係る経済事情その他の要因等を含みます。)に関する資料
例えば、確認を行う上で前提となる事業内容、売上規模、新製品等の導入、市場の状況、為替変動などが考えられます。 - ヘ 確認申出法人と確認対象取引に係る国外関連者との直接若しくは間接の資本関係又は実質的支配関係に関する資料
確認対象取引に係る国外関連者以外の法人が確認対象取引に関連する場合には、それも含めてください。 - ト 確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の過去3事業年度分(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を含みます。)の営業及び経理の状況その他事業の内容を明らかにした資料(確認対象取引が新規事業又は新規製品に係るものであり、過去3事業年度分の資料を提出できない場合には、将来の事業計画、事業予測の資料など、これに代替するもの)
確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の過去3事業年度分の有価証券報告書又は類似の資料です。確認対象取引が新規事業である等の理由により、これらの資料を用意できない場合には、将来の事業計画、事業予測の資料等、これに代替するものをご用意ください。 - チ 確認対象取引に係る国外関連者について、その国外関連者が所在する国又は地域で、移転価格に係る調査、不服申立て又は訴訟等が行われている場合には、その概要及び過去の課税状況を記載した資料
確認対象取引に係る国外関連者について、その所在する国又は地域で移転価格に係る調査等が行われている場合には、その概要及び過去の課税状況について簡潔に説明する資料です。 - リ 確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等を確認対象事業年度前3事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を含みます。)に適用した場合の結果など確認対象取引に係る独立企業間価格の算定方法等を具体的に説明するために必要な資料
上記「ニ」において説明された独立企業間価格の算定方法について、当該算定方法を確認対象事業年度前3事業年度に適用した場合の結果等についての具体的な説明資料です。 - ヌ 確認申出法人が属する多国籍企業グループ(租税特別措置法第66条の4の4第4項第2号に規定する多国籍企業グループをいいます。)の最終親会社等及び当該確認申出法人に係る親会社等(同項第5号に規定する親会社等をいいます。)のうち当該確認申出法人を直接支配する親会社等が当該最終親会社等でない場合の親会社等の概要(法人名、本店又は主たる事務所の所在地等)を記載した資料(相互協議を伴わない事前確認の申出の場合に限ります。)
平成27年10月に経済協力開発機構(OECD)から公表されたBEPS行動計画5の最終報告書の勧告にしたがい、相互協議を伴わない事前確認の内容については、最終親会社等、確認申出法人を直接支配する親会社等及び確認対象取引に係る国外関連者の所在する国又は地域の税務当局に、租税条約等に基づき自発的に情報提供を行うことになっています。当該情報提供に必要な情報について提供をお願いしています。 - ル その他事前確認に当たり必要な資料
確認申出法人及び確認対象取引に係る国外関連者の事業の概要の説明等、事前確認審査に参考となるその他の資料があればご用意ください。

