同一の者による支配関係のある法人間で行われる株式交換の適格判定について照会する場合の説明資料の記載例(記載例4)
《照会の前提となる事実関係について》
1 組織再編成の概要
※当事会社の名称、組織再編成の態様、実行日などを記載してください。
株式会社A社(東京都●区●1-1-1(●署))は、同社を株式交換完全子法人、株式会社B社(東京都■区■1-1-1(■署))を株式交換完全親法人とする株式交換(以下「本件株式交換」といいます。)を行う予定です。なお、株式交換契約の効力発生日は、平成×年4月1日です。また、本件株式交換後、B社が営む●●事業を分社型分割によりA社に移転する予定です。
2 組織再編成の目的・経緯・背景
A社とB社は、同じ企業グループに属する兄弟会社の関係にあります。この度、グループ全体の資本関係及び事業体制を見直すこととし、B社を持株会社化するとともに、B社及びA社がそれぞれ営んでいる●●事業をA社の下に集約させることを予定しています。具体的には、A社を株式交換完全子法人、B社を株式交換完全親法人とする株式交換を行い、その後、分社型分割によりB社が行う●●事業をA社に引き継がせることを計画しています。
3 組織再編成の当事会社が行う事業の内容及び組織再編成後の事業の異動状況
(1) A社の事業
![]() 主な事業
主な事業
●●業(・・・する事業。平成×年度の売上金額は××円。従業員100人)
![]() その他の事業
その他の事業
▲▲業(・・・する事業。平成×年度の売上金額は××円。従業員20人)
(2) B社の事業
●●業(・・・する事業。平成×年度の売上金額は××円。従業員×人)
(3) 組織再編成後の事業の継続見込み
A社は、株式交換及び分社型分割後においても●●業(分社型分割によりB社から引き継ぐ事業を含みます)を引き続き営む見込みです。また、A社の従業員120人は、引き続き●●業又は▲▲業に従事することを見込んでいます。
4 組織再編成の当事会社の資本金及び株主の状況
| 株式交換完全子法人 | 株式交換完全親法人 | |
|---|---|---|
| A社 | B社 | |
| 設立年月日 | 昭和Y年4月1日 | 昭和Z年4月1日 |
| 決算期 | 3月 | 3月 |
| 資本金 | ○○○円 | ○○○円 |
| 株主 | X社(30%)、Y社(70%) | Y社(60%)、Z社(40%) |
5 資本関係の変遷
※一連の組織再編成の内容を記載するとともに、組織再編成前後の資本関係を図示してください。
(1) 上記4のとおり、Y社は、本件株式交換前にA社及びB社の発行済株式の50%超を保有しています。
(2) Y社は、本件株式交換後もB社の株式(発行済株式の総数の50%超)を継続して保有する見込みです。
(3) B社は、本件株式交換によって取得することとなるA社の発行済株式の全てを継続して保有する見込みです。
(4) B社は、本件株式交換後に●●事業を分社型分割により分割しますが、分割後においてもA社の発行済株式の全てを継続して保有する見込みです。
(5) 本件株式交換及び分社型分割前後のA社及びB社の資本関係は次のとおりです。
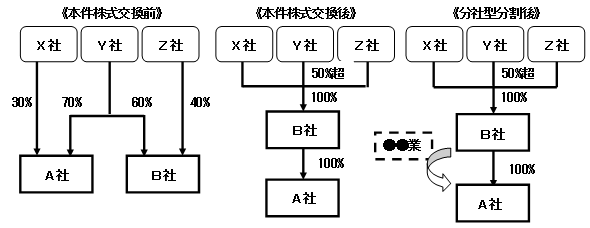
6 組織再編成に伴い支払う対価の有無とその内容
本件株式交換の対価として、株式交換完全子法人であるA社の株主(X社・Y社)には、株式交換完全親法人であるB社の株式のみが交付されます。
7 照会者において確認したい事項
1から6の事実関係がある場合、本件株式交換は、適格株式交換に該当すると考えて差し支えないでしょうか。
(注)株式交換の前に「支配関係」がない場合には、上記の事実関係のほか、当事会社の事業規模(売上金額・従業者数・など)、役員の継続見込み、株式の継続保有見込みなどについても説明していただく必要がある場合があります。
《確認したい照会事項に対する照会者の見解とその理由について》
※記載が困難な場合には、分かる範囲で記載してください。
【関係法令】※平成28年4月1日現在の法令を基に作成しています。
1 支配関係
支配関係とは、一の者が法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下「当事者間の支配の関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいいます(法法2十二の七の五)。
そして、上記の政令で定める関係とは、一の者が法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下「直接支配関係」といいます。)をいい(法令4の2![]() 前段)、この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある法人が他の法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有するものとみなされます(「みなし直接支配関係」法令4の2
前段)、この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある法人が他の法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有するものとみなされます(「みなし直接支配関係」法令4の2![]() 後段)。
後段)。
2 適格株式交換
株式交換前に株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続することが見込まれている場合の株式交換のうち、次の(1)及び(2)の要件の全てに該当するもので、当該株式交換完全子法人の株主に当該株式交換完全親法人の株式以外の資産が交付されないものは、適格株式交換に該当します(法法2十二の十六ロ、法令4の3![]() 二)。
二)。
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(法法2十二の十六ロ(1))。
(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(法法2十二の十六ロ(2))。
【照会者の見解】
1 株式交換前における当事会社間の関係
本件株式交換前において、Y社は、A社及びB社の発行済株式の総数の50%超の数の株式を保有しています(直接支配関係)。したがって、Y社とA社との間及びY社とB社との間にはそれぞれY社による支配関係があることとなりますので、A社とB社との間には同一の者(Y社)による支配関係があることとなります。
2 適格株式交換に該当するか
(1) 支配関係の継続見込みについて
1のとおり、本件株式交換前において、株式交換完全子法人であるA社と株式交換完全親法人であるB社との間には同一の者(Y社)による支配関係があります。
また、本件株式交換後において、Y社との間に直接支配関係があるB社はA社の発行済株式の総数の50%超の株式を保有することとなりますので、Y社はA社の発行済株式の総数の50%超の株式を保有するものとみなされます(みなし直接支配関係)。したがって、Y社とA社との間及びY社とB社との間にはそれぞれY社による支配関係があることとなり、A社とB社との間には同一の者(Y社)による支配関係があることとなります。そして、Y社はB社の発行済株式の50%超の数の株式を継続して保有すること、B社はA社の発行済株式の全部を継続して保有することが見込まれていますので、本件株式交換後において、株式交換完全子法人であるA社と株式交換完全親法人であるB社との間には、同一の者(Y社)による支配関係が継続することが見込まれているといえます。
(2) 従業者の継続見込みについて
株式交換の直前における株式交換完全子法人であるA社の従業者120人は、引き続きA社の業務に従事することが見込まれています。
(3) 主要な事業の継続見込みについて
株式交換完全子法人であるA社の株式交換前に営む主要な事業(●●業)は、本件株式交換後も引き続きA社において営まれることが見込まれています。
(4) 株式交換の対価について
本件株式交換の対価として、株式交換完全子法人であるA社の株主には株式交換完全親法人であるB社株式のみが交付されます。
(5) 上記(1)から(4)のとおり、本件株式交換は、上記(関係法令)の2に定める要件を全て満たしますので、適格株式交換に該当することとなります。

