- ホーム
- 税の情報・手続・用紙
- 税について調べる
- 所得税(確定申告書等作成コーナー)
- 確定申告をすれば税金が戻る方
(参考) 申告や納税について知っておきたいこと
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く。)も申告が必要です。
還付申告は、平成30年2月15日(木)以前でも行えます(税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。
| 区分 |
概要 |
 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
|
年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 |
 給与所得者 給与所得者
|
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受けられる場合 |
 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
|
雑損控除や医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受けられる場合 |
 年の中途で退職した後就職しなかった方 年の中途で退職した後就職しなかった方
|
給与所得について年末調整を受けていない場合 |
 退職所得がある方 退職所得がある方
|
次のいずれかに該当する場合
- ●退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
- ●退職所得の支払を受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税等の源泉徴収税額が正規の税額を超えている
◎退職所得は次の式で計算します。
- ●一般退職手当等(特定役員退職手当等以外の退職金)のみの場合
(一般退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額※1) × 0.5
- ●特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下である方が支払を受ける退職金のうち、その役員等としての勤続年数に対応する退職金として支払を受ける退職金)のみの場合
特定役員退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額※1
- ●一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方がある場合(
 + +  ) )
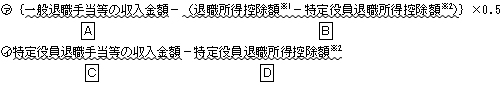
なお、次の(1)又は(2)に当てはまるときは、上記によらず次によります。
- (1) A < Bのとき
(特定役員退職手当等の収入金額 + 一般退職手当等の収入金額) − 退職所得控除額※1
- (2) C < Dのとき
{一般退職手当等の収入金額 − (退職所得控除額※1 − 特定役員退職手当等の収入金額)} × 0.5
- ※1 退職所得控除額は、次のとおりです。
- ●勤続年数が20年までの場合
40万円 × 勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
- ●勤続年数が20年を超える場合
70万円 × 勤続年数 − 600万円
障害者となったことにより退職した場合は、上記で計算した金額に100万円を加算します。
- ※2 特定役員退職所得控除額は、次のとおりです。
- ●特定役員退職手当等に係る勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間の重複がない場合
40万円 × 特定役員等勤続年数
- ●特定役員退職手当等に係る勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間の重複がある場合
40万円 × (特定役員等勤続年数 − 重複勤続年数) + 20万円 × 重複勤続年数
◎退職所得の収入金額と退職所得控除額については、申告書第三表「○ 退職所得に関する事項」欄に記載し、特定役員退職手当等がある場合には、その収入金額と退職所得控除額を上段に括弧書きで内書きしてください。
|
 予定納税をしている方 予定納税をしている方
|
確定申告の必要がない場合 |
 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
総合課税の配当所得や原稿料などがある方 給与所得者
給与所得者 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 年の中途で退職した後就職しなかった方
年の中途で退職した後就職しなかった方 退職所得がある方
退職所得がある方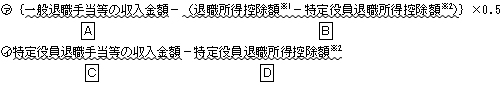
 予定納税をしている方
予定納税をしている方
