第2章 モデル事業推進に向けて
第2節 共同化と連鎖化のための留意点
1. 視点を変える
現在は、競争力の時代である。従来型の商売では、ひしめく競合や消費者の厳しい選択眼に応えて行くことが困難になってきている。また商品の差別性も少なく、画期的な商品が開発できてもすぐに模倣品が出現、開発投資を回収できないまま低価格競争に巻きこまれるのが現実である。
何とかここまで商売を続けてくることができたため、今後も何とかなると考えている中小酒類小売業者が多い。
他方では、後継者もなく廃業している店も多い。廃業した店舗の顧客が、生き残っている中小酒類小売業者へ流れ込んできていることで、商売が成立している例も見られる。この店も、いずれは顧客が新規店舗へ流出し、顧客の飲酒量が加齢とともに減少し、購買力が低下することにより、売上高減少は避けられない。
だからこそ、今の段階で今後とも商売を継続展開していく意欲のある店舗は、あらゆる可能性を追求し、競争力を強化していかなくてはならない。
重要なのは、従来の考えを変えることである。中小酒類小売業者が、単独でどのように頑張っても、大手スーパーマーケットやディスカウントストアのような新業態と同じレベルの消費者サービスはできない。新規業態にはできないサービスや品揃えに、敢然と取組めばよいのである。単独の小さな力では解決できないことも、志を同じくする仲間と連携すれば大きな力を持つことができる。新しい商売の枠組みを追求して、精力的に取組まなくては、中小酒類小売業の将来は暗いといって間違いない。
米国の経営学者レビットは、成熟化し、停滞・混沌とした黒雲のただ中にある現代こそ、未来に向かって、包括的なひとつの大志を堅持し、これを現実化することが重要である、という「ブルースカイ戦略」を提唱している。この戦略は、酒販業界に当てはまるものである。
自分たちの商売に覆いかぶさっている暗雲は、消耗戦とも言える価格競争、消費者に対して“商品”関連情報の提案が行われておらず、単に“物”を動かそうという状況を意味している。この暗雲の中でもがいていても収益は上がらない。この暗雲を超えていくと、無限に広がる青空(ブルースカイ)が存在し、競争に巻き込まれない自分の商売ができるという考えである。
もはや時間は残されていない。勝ち残るための戦略を構築し、戦略に基づいて組織構成と戦術選定を行い、消費者に選ばれる中小酒類小売業者にならなくてはならない。
2. 事例に学ぶ留意点
今回調査したモデル組合は、全て成功しているわけではない。単独ではできないことを、仲間同士が力を合わせて、大きな成果を得ようとして取組んだ好例である。
やる気を持って個別に頑張るのも素晴らしいが、今回の事例を見ても、共同化や連鎖化では、個店でできない活動が実現できる。
真似できるものは真似をし、反面教師とするところはしっかりと確認する。自分自身が、仲間と共同化したり連鎖化したりする際には、何に気をつければよいのかを、これらの事例から十分に学べるであろう。
組織小売業の成長、購買手法の変化、消費者の価値観の変化と生活様式の変化などは、中小酒類小売業者にとっては大きな脅威になっている。消費者志向に立ち、ニーズにしっかり応えていくのも、決して容易なことではない。顧客にタイムリーに対応するための情報力や発信力も必要である。これらを持ったうえで、更に個別の努力を自分の店にあった形で展開すればよい。
すぐに共同化や連鎖化へ突入できるかというと、そうではない。すぐに始めて、簡単に成功するなら皆がやっている。共同化や連鎖化に取組みながら、失敗した組合や中小酒類小売業者は少なくない。
活路の一つが共同化や連鎖化にある以上、検討する価値は高い。複数の人間が集まれば趣味や志向、また背負っている事情も異なる。物事の判断基準も進め方も違う。だから、新しい発想やビジネスが生まれる、と前向きに捉えることが重要である。
本報告書で紹介した5つの事例の成功要因、失敗要因を分析すると、共同化や連鎖化のため、成功するために必要な留意点を以下のように集約できる。
|
|
3. 共同化や連鎖化を成功させるために必要な留意点
(1)参加者全員がビジョンを持ち、共有しなくてはならない。
![]() 強い意識を持つ
強い意識を持つ
人間はイメージしたものにしかなれないし、イメージがなければ行動が取れない。例えば一流のプロスポーツ選手で、とにかく一生懸命やっているうちにプロになっていましたと言うコメントを聞いたことがない。
子供が『野球選手になりたい』と漠然と答える中、大リーグで活躍するある日本人選手は、「一流のプロ野球選手になりたい」と明確なビジョンを小学生時代から持っていたと言う話がある。
成り行き任せで大成はしない。ましてや、共同化や連鎖化など多くの人間や組織が関係するものであれば尚更である。多くの人間が集い、同じ目的を持って活動しても、中小酒類小売業者の事情や環境、あるいは望んでいる達成すべき水準には、大きな隔たりがある。どのようなものを得て、どのような姿になりたいのかをしっかりと描かなくては、どう取組んでよいのかわからない人も多いはずである。
共同事業の場合、全体の事業が最終的にどのような形になるのか、その結果を得て、中小酒類小売業者がどのような形になるのか、これらを具体的な状態としてイメージすることが重要である。
![]() ビジョンとは
ビジョンとは
ビジョンは、数値で語れるものではない。各個店や協同組合の“将来のあるべき姿や理想像”を文章やイラスト等で表現したものがビジョンである。
今回のモデル事例の中で「ビジョンづくり」に取組む組合が紹介されているが、大変有効なことである。
ビジョンは、共に活動していく構成員や関係者の夢や希望である。他人が作ったビジョンに賛同すると言うことも有効ではあるが、ビジョン策定の場に自らが参加し、十分に語り合い、説得しあい、ともに納得したカタチのビジョンを共有することが理想である。
共同化や連鎖化を円滑に進めていくには、どのようなビジョンを持てばよいのか。例えば共同事業のビジョンは、決して共同購買による低価格仕入、それに伴う低価格戦争への参入ではない。安売りが夢とか希望では淋し過ぎる。共同購買で生まれてくる多くの付加価値を見つけ出し、価値ある商売を実現できるかを考えたい。
ビジョンは、環境変化に伴って変化しても構わない。目指し続けられる自分達の理想郷を描くべきである。ノルマではなく、共同して勝ち得る喜びである。
(2)明確な目標設定を行い、達成のために計画を立てなくてはならない。
![]() 数値目標を持つ
数値目標を持つ
目標とビジョンは混同しやすいが、目標とはビジョンを達成するための基準数値である。目標を数値化せず、むやみに「PB商品を作ろう」、「低価格で仕入れよう」、「情報化を推進しよう」と掛け声をかけても、成功しない。
「頑張る」とか「努力する」と言う言葉も同様だが、数値が伴わなくては漠然とした意向にしか捉えられない。
設定すべき数値目標には、様々なものがある。以下を参考にしてみよう。
|
|
|
その他にも多数あるが、明確に設定している個店や協同組合は少ない。また目標を設定しても、共同活動を展開する構成員達に共通認識、共通目標を浸透させることができなければ、目標も絵に描いた餅となってしまう。
![]() 数値目標の設定
数値目標の設定
数値目標は皆の合意で設定することが重要である。一部の幹部が設定した目標であれば、全員で達成しようと言う気持ちにはならない。特に、高いレベルの目標の場合、最初から諦めてしまう。さらに未達成の場合には、責任を一部の者に負わせ、反省も修正もないままに仕切り直されてしまうことが多い。
近年、人事評価に成果主義を取り入れる企業が増えている。単純に上層部がノルマを設定し、その達成度で人事評価を行う企業では、従業員の動機づけが図りにくく、思うような成果が得られない例も多い。しかし本人と上層部が相談して目標を設定した場合、取組み意欲が高く、達成のための工夫もふんだんになされるため、良い成果をあげている。大手自動車製造業N社の外国人社長が取り入れたマネジメント手法は当該手法であり、V字回復の駆動力になったことは記憶に新しい。共同化や連鎖化においても、参考にしたい手法である。
共同化や連鎖化においては、参加者、特に幹部が機能分担することも増えるため、各ポジションで明確な活動目標数値を設定しておかなくては、全体統合が展開しにくい。結果として、運営がうまくいかなくなる場合が多い。
内側に向けたものでも、対外的なものでも構わない。数値目標は「いつまでに達成するか?」を宣言した形で共有化しておくべきである。
酒類業界は、時間をかけて活性化策を検討・実行することはできない。中期的な3年間の目標、それを達成するために短期的に分割した1年目の目標を設定しなくてはならない。それ以上の期間目標は変動要素が多いため、ビジョンの設定で留めておけば良い。
(3)明確な方針を持つ
![]() 方針なくして路線は定まらず
方針なくして路線は定まらず
ビジョンを持ち、期間目標を設定したら、次はどのような方針で進めていくのかを全員で共有しておかなくてはならない。
方針とは「どのような組織」と見られたいかを基準として、考えていくと設定しやすい。「経営理念」が行うことの宣言であるなら、「方針」はどのようなやり方で行うのかと言う姿勢を表すものである。
「商品開発型組織として、独自の強みを活かして業界をリードする組織」とか「ユニークな商品とサービスで顧客満足を追求する組織」、あるいは多少漠然としているが、「若者の意気込みが形となったエネルギッシュな組織」などがある。
組織の方針を決めておけば、その路線に合わない活動は展開しなくて済む。組織方針は、無駄な活動をさせない、指針としての役割を果たしてくれる。
組織方針は、「行動規範」と言う言葉でくくることもできる。例えば、共同化や連鎖化するのであれば、「全員にメリットが享受できる活動を展開する」と言う方針を設定しておけば、抜け駆けや排他的な活動を抑制することができる。
成功する組織には、必ず「一貫性」がある。これは、方針に基づいて運営されているからと考えて良い。
![]() 「高い志」・「スピード」・「顧客満足」
「高い志」・「スピード」・「顧客満足」
近年言われている経営戦略の重要要素として、「高い志」・「スピード」・「顧客満足」をあげることができる。成り行き任せではないはっきりとした意志、その志の高さが、組織の利害関係者をしっかりとつなぎとめ、結束力を高めていくとされている。
誰も志の低い仲間とは、一緒にビジネスを行いたくないはずである。例えば、共同購買を約束した仲間が、抜け駆けして安い仕入先を探し出し、結束を乱す例が多い。このような志の低い仲間を信じられるはずがない。高い志を持つという方針を決めなくてはならない。
また「スピード」も重要な取組み方針の要素となる。時代の変化は早く、のんびり構えていては、環境変化に追いつけず、折角立案した名企画も、陳腐化する危険性が高まる。
酒販業界に最も欠けている志向性の一つに「顧客志向」がある。顧客満足を勝ち得ない組織は、顧客を当然のように失っていく。そして、その現象の中で、新規の顧客も獲得できなくなっていくのが常である。
常に、顧客第一主義、顧客満足追求を運営方針に掲げて組織化しなくては、どのような共同化や連鎖化事業は成立しない。
あまり多くの方針を設定しても、多数の人間が協働して展開する事業であれば、徹底しにくい。皆で合意できる3つくらいの方針を設定すべきである。>
(4)環境をしっかり把握する
![]() 外部環境と内部資源
外部環境と内部資源
共同化や連鎖化事業を展開するときに、どれだけ環境把握ができているかが大きなポイントになる。自分達のやりたいことだけ、都合の良いことだけを展開して成功することはありえない。正確に市場の現実を見つめ、取組むべき課題を見極めてスタートしなくてはならない。
環境把握は、外部環境と内部資源を見極めることからスタートしていくのが定石である。外部環境については、競争のあり方をあらゆる側面から考察しておかなくてはならない。
![]() SWOT分析
SWOT分析
環境分析で一般的に行われるのが、SWOT分析(強みと弱み/機会と脅威を分析すること)である。SWOT分析を行うことにより、自分達の置かれた状況を確認でき、なぜ共同事業・連鎖化事業が必要なのかが明確になる。
図表2−2−1 SWOT分析のアプローチ
強み
仲間と発揮できる強みを列挙する。 |
市場機会
どのような環境が
追い風になるか列挙する。 |
<ポイント> (強み×機会) 機会には強みを活かす (弱み×脅威) 弱みと脅威の鉢合わせを回避 (強み×脅威) 強みを強化し、脅威を排除する (弱み×機会) 機会を活かし、弱みをなくす |
弱み
仲間との連合でも生じる弱みを列挙する。 |
脅威
どのような環境が
向かい風になるか列挙する。 |
SWOT分析活用の場合、「顧客から求められている商品やサービスは何なのか」という視点が重要である。市場ニーズがないビジネスを展開しても収益は得られない。直接的にニーズが顕在化していなくても、顧客に受け入れられる土壌があれば良い。この部分が市場機会(チャンス)であり、共同事業で発揮できる強みを投入するのである。
競争環境や事業そのものの市場における構造をしっかり理解しておかなくては、
一生懸命やったが、成功しなかったと言う結果になりかねない。以下のポイントを整理しておかなくてはならない。
- 業界内の直接的な競合状況はどうなっているのか?
- 自分達以外に、新規に参入してくる事業体やサービス・商品はあるか?
- 自分達が展開する事業以外で、顧客ニーズを満たす代替的な事業は何か?
- 顧客の購買意思決定の仕組みはどうなっているのか?選別の基準は何か?
- 仕入の仕組みは安定的に維持できるか?変化して苦労することはないか?
(5)商品に思い入れや知識を持つ
仕組みだけで商品が売れるわけではない。共同事業で開発したPB商品や低価格で仕入れた商品を、全員が上手く個店のビジネスに活用できている例は見られない。確実に格差が生じている。
原因は、商品やサービスの価値を扱う者の理解度や思い入れの差である。なぜその商品が良いのか、なぜそのようなサービスを行うのかを十分に理解していなくては、顧客に伝えることができない。
何でこれを仕入れたか分からないと言う商品を、誰が売れるであろうか。
PB商品も重要だが、「まずはNB商品を安価に仕入れたい」と言う発想を持つ共同購買事業が多いのも当然である。
しかし、差別化商品を持ったり、ユニークなサービスを展開したりしなければ、今後競争には勝ち残っていけないことを考えると、知識の習得や思い入れは必須となる。
商品規格については、書面で確実に連絡されているが、もっと販売に広がりを持たせる、売ることに想いを深められる情報が必要である。
以下のようなポイントをしっかり押さえ、商品やサービスのメリットを確認し合うことが共同事業展開には欠かせない。
![]() 商品の開発意図
商品の開発意図
形、味、香り、容量、素材、様々な要素の組合せで商品は構成されている。PB商品では、ラベルを張り替えただけのようなものが少なくないが、本来は独自に開発する意図がなくてはならない。顧客のことを知り、商品の価値を活かすために、このようなモノを開発した、という意図を全員で確認しておかなくてはならない。漠然とよさそうだと言う情報では、商品は買っていただけない。「なぜ私達はこの商品を扱うのか」を、信念を持って伝えることから商売は始まる。
![]() 商品が消費者に与えるメリット
商品が消費者に与えるメリット
消費者が商品を買うのは、それを食べたり飲んだり使ったりして、ニーズを満たすためである。消費者自体ニーズに気づいていないこともあり、売り手側がコミュニケーションを展開することで、購買意欲を刺激することが実現するのである。売り手が、消費者のメリットを理解していなくては、説得力あるコミュニケーションは展開できない。
![]() 類似品とはどのような差異があるのか
類似品とはどのような差異があるのか
消費者は、多くの商品の中から、自分に必要なものを選択し、購買する。消費者が目にする商品の中には、当然、競合品が含まれており、比較されている。明確な差異がなければ、安いもの、買いやすいものを購入する。顧客を逃さないためには、差異をわかりやすくアピールしなくてはならない。
(6)コミュニケーションを取る
![]() 分かり合うことの重要さ
分かり合うことの重要さ
コミュニケーションとは、相互の意思疎通のことである。したがって、一方的な情報発信は、コミュニケーションではない。「伝えてあるのに、理解されていない。」とか、「ダイレクトメールも、ファックスも何回も送っているのだから、知らないのはおかしい。」等が、共同事業の連絡不徹底の現場でよく聞かれる。
情報の発信は、絶対に欠かしてはならない。しかしそれだけでは不充分である。相手に伝わったのかを確認し、理解されなくては意味がない。報道記事でも当該新聞や雑誌を読まなくては、理解されることはない。
共同事業では、規模が大きくなればなるほど、階層に分かれて、さらには分科会などが持たれ、組織全体のコミュニケーションが円滑に展開できない例が多い。
一部の人だけが情報を得ている場合、組織運営が円滑に進まなくなる。もちろん情報には、共有するタイミングもあるため、すべてをコミュニケーションする必要があるわけではない。しかし、力を合わせて行う活動に関して、コミュニケーションが持たれないのは問題である。
図表2−2−2 公式組織の概念図
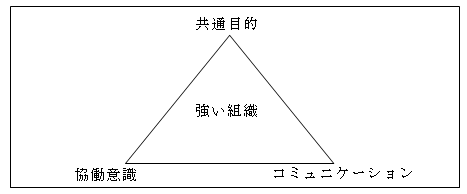
![]() 強い組織を目指そう
強い組織を目指そう
図表2−2−2は、組織論の創始者バーナードが提唱した「公式組織」の概念を簡易に記したものである。個別店舗の仕事ではなく、共同・連鎖化という枠組みの中では、共通の目的を持ち、その目的を達成するために、円滑なコミュニケーションを維持しながら協働することが重要である。
コミュニケーションを進める方法は多岐にわたる。構成員の置かれている環境を考慮しながら、手法は選択すべきである。「分かっているはず」と言う前提は、時にはボタンの掛け違いを生じる。積極的にコミュニケーションを取っていくように心掛けなくてはならない。
(7)意識の高いメンバーで運営
![]() 意識があるから変われる
意識があるから変われる
共同・連鎖化事業を展開する際に、「委員会」や「分科会」組織を構成することになる。中小酒類小売業者の集まりでは、多くの場合、ベテランと言われる高齢者がそのメンバーになることが多い。若手は毎日の店頭商売や配達で多忙を極めるため、継続的に行われる会合には参加できない。やむを得ず、ベテランの登場ということになるのである。
ベテランや高齢者の存在を否定するものではない。当報告書にある事例組合では、ベテランが委員会の意思決定に寄与している例もある。要するに、意識が高ければ、変化を作っていけることを示している。
「何があっても達成する」という強い意志を持つメンバーで構成しなくては、組織体は途中で困難に直面したとき、撤退し、停滞してしまう。対応方法は考慮しながら、前向きに進む意識の高さが必須である。
古い話であるが、アメリカ合衆国は、宇宙開発において当事のソ連に大きく差をつけられていた。1961年にJ.F.ケネディ大統領は、明確な目標設定をした。「わが国は60年代末までに、人類を月面に着陸させるという目標に取組むべきだと考えている。」この発言は、NASA(米国宇宙開発局)のメンバーの意識を大きく高ぶらせた。意識が高まったメンバー、実現に積極的に取組むメンバーによってプロジェクトは推進された。公約通りに、アポロが月面着陸を果たしたのである。
問題は、やるかやらないかであり、やるためには「意識」が必要なのである。
![]() 意識を高める方法
意識を高める方法
意識を高めるにも、様々な方法が存在する。一番簡単なことは、獲得しなくてはならないゴールを設定し、その必要性を理解することである。
ゴールを設定できても、ハードルが高すぎた場合、意欲の減退を誘発することがある。これを回避するためには、中間ゴールをいくつか設定すると良い。多くの成功事例を参考にして、取組み方の代替案を複数準備しておくことも考えられる。実現を推進する方法が複数存在することは、大きな心の支えになり、不安をなくすことに役立つ。
外部との連携も有効である。他人との連携は、自らが勝手にペースを落とすこともできず、お互いに触発しあいながら目標を目指すことが可能である。当報告書にある取組み事例では、中小企業診断士をうまく活用し、目標の達成に貢献させている。
大きな組織になれば、意識の低い構成員も生まれてくる。これはやむを得ないことであり、一方的な排除も難しい。より大きな成果を挙げるために、高い意欲を持てるよう、意識的にコミュニケーションを継続展開していくことが求められる。
(8)組織を作る
中小酒類小売業者が行う共同・連鎖化事業は、上下関係の組織体を作ることではない。便宜上意思決定機関や業務の流れが生じることはあるが、基本的に参加者全員が個人事業主である。このような環境で活動組織を作るには、明確な価値観と仕組みが必要である。緩やかな連携、参加も不参加も自由などとルールがなければ、共同事業はできるはずがない。
図表2−2−3「組織システム」は、組織構成及び運営上において留意すべきポイントを整理したものである。
図表2−2−3 組織システム
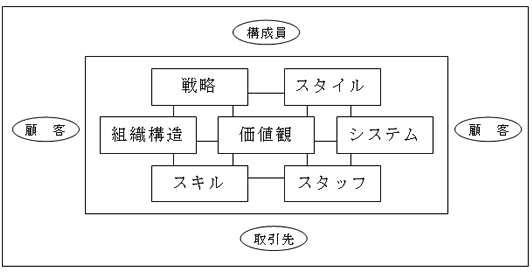
![]() 戦略
戦略
いかなる方法で共同事業・連鎖化事業を推進していくのかの戦略を策定する。
![]() スタイル
スタイル
組織文化に配慮しつつ、採るべき「目に見える行動様式」を考える。
![]() 組織構造
組織構造
戦略を実行するための「組織」や、組織と個店との関係やメンバーに与える権限を明確にする。
![]() 価値観
価値観
ビジョンや理念を明確にする。共同事業の位置づけなども重要なポイントとなる。
![]() システム
システム
共同事業を運営するための制度や方針を明確にする。構成員を動機付けるための「報告制度」や「計画策定方針」などがあげられる。
![]() スキル
スキル
構成員の持つ、購買力や商品発掘力、販売力など、共同事業を推進していく上で活用できる様々な技術や能力を洗い出す。
![]() スタッフ
スタッフ
組織を動かす人々について「人数・職種・職責」などを明確にする。つまり、共同事業の組織とはいえ、組織は単なる構造ではなく、戦略や文化、システム等が多元的に適合することで、その成果を生み出していることを確認しなくてはならない。
(9)事業領域(ドメイン)を定める
共同・連鎖化事業を推進していくにあたっては、その事業領域を定めてスタートしなくてはならない。事業領域は、事業の進行経緯に合わせて変化させても良いが、常に活動実施者はその領域を意識して行動しなくてはならない。事業領域は経営の世界では「ドメイン」と呼ばれ、「誰を相手に」、「どのような強みを活かして」、「どのような欲求に対応していくのか」の3点で定義する。
図表2−2−4 <ドメインの3次元定義>
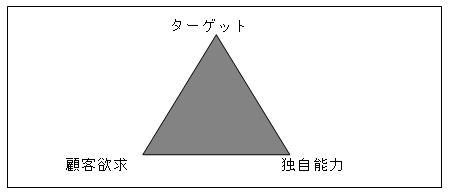
- 顧客ターゲットを明確にする
- 顧客ターゲットのどんな欲求に対応するのかを決定する
- 顧客欲求に対して、どんな技術的強みを提供するのか
中小酒類小売業者は、酒を主体にビジネスを展開してきた。しかし酒販免許の緩和に伴い、あらゆるシーンで消費者は酒類を購買できるようになった。この流れは止められない。
では中小酒類小売業者の今後の事業領域は、どのようなものであるべきなのか。「酒屋だから酒のことは分かっている」と、とても自信に満ち溢れた言葉を聞くことがある。これからの時代は、分かっている酒を使って「何をする酒屋」なのかが重要である。折角、共同・連鎖化事業で大きな力を得るのであれば、新しい事業領域を切り開いていくことを考えることが必要である。
ただし、個々の中小酒類小売業者と共同事業を行う組織体の事業領域がまったく同一である必要はない。一部分が重複していれば良い。共同による新しい取組みが新しい事業領域を持つことにつながれば、各個店にも好影響を与える。
世界的に有名なドメイン設定例に、コンピュータをはじめとする情報機器を製造販売するIBM社の事例がある。『IBMはコンピュータを売るのではなく、顧客の問題解決に奉仕する。我が社はコンピュータ・メーカーではなく、問題解決企業である。』というものである。
共同・連鎖化事業の大きな目的を達成するためには、組織の存在意義を明確にする意味でも、ドメイン設定は欠かせない。
(10)戦略計画を策定する
多くの共同事業は取組むべきテーマを設定して、効率良く目標達成しようとしている。本来であれば、戦略を持って中長期計画を立て、更に短期計画で事業を展開していくことが重要である。行き当たりばったりのビジネスでは、ロスも生じ、より多くの価値を得ることができない。
共同事業の運営のスタート台として、戦略的中期事業計画が挙げられる。戦略計画のない事業は、海図のない航海に等しく、危険であり、非効率である。計画があるから、ギャップの修正も早くできるのである。
戦略に基づいた事業計画が重要な理由には、以下のものがある。
- 現在の事業が成功していても、将来の保証はない。
- 現在は事業環境の変化が激しく、あらかじめ予測を立て、対応・準備をしておく必要がある。
- 資源配分の必要性が重要になってきている。
- 世代別思考基準・価値基準が異なってきており、共通行動指針が必要になっている。
事業計画をしっかりと持つことができれば、共同事業の望ましい将来像をデザイ
ンし、それを達成するためのよりよい方法・プロセス・システムを考えることできる。また、必要な行動策(それをしなければ、望ましい将釆像を得ることができない)を立案することもできる。さらに、共同事業の望ましい将来像を達成するための方針、実行計画、手続き、方法などを決定することができる。
計画立案を確実に行うことが、どのような事業を展開するにあたっても必要なのである。
図表2−2−5 設定期間別分類による経営(事業)計画の概要
| 計画名 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 長期事業計画 | 主として10年 |
|
| 中期事業計画 | 主として3年 |
|
| 短期事業計画 | 1年間 |
|
(11)顧客志向になる
経営理念を持つ大半の企業は、表現の違いはあるものの「顧客を大切に」を掲げている。しかし、本当に顧客志向が徹底できている企業は少ない。ましてや、緩やかな連携を基盤とする共同・連鎖化事業を行う組織では、その徹底は難しい。
「売れない」、「競合が強い」と嘆く中小酒類小売業者や組合は多いが、「顧客が何を望んでいるのか。それに応えよう。」という行動をとる例は少ない。今回のモデル事業においても、まだまだ顧客志向の認識は低い。
消費者は「安い」と言うだけで、購買行動を起こしているわけではない。昨今のこだわり食材ブームや健康志向を背景に、組織小売業でも単価の高い商品が買われている。
ただし、どこでも買えるNB商品などは、安い店で買う。当然のことである。しかし「買い方」、「買うタイミング」、「組合せての購買」を考慮すると、あながち価格がすべてではないと言える。
もっと顧客のことを考えなくてはならない。共同化や連鎖化は、事業運営の技術なのである。顧客に満足を与え、売り手と買い手の双方にメリットのある取引を実現するためなら、もっと顧客志向に立脚すべきである。
当報告書内の事例にも見られる、酒蔵の4種小瓶詰め合わせなど、顧客を見ていない悪例ともいえる。たまたま4つの蔵があったから、地酒をアピールしようといのが取組みの動機である。しかし「誰が」、「いつ」、「どんな気持ちで」、「何のため」に買うのかがイメージできていない。顧客の心理と購買基準をしっかりと考慮し、顧客満足を得られる活動を展開しなくては成功など望めない。
共同化や連鎖化によって得たいゴールは、「収益の増大」である。そのためには「顧客の確保」が絶対条件となる。顧客に信頼され、定着して愛顧を獲得するためには、以下の点に留意して活動に取組まなくてはならない。
![]() 差別性を確立する
差別性を確立する
まずは確実な差異が必要である。同じものなら買い慣れた店で買う。ありふれたイベントなら興味を持たない。どこにでもある情報なら要らない。当活動の差別性や特色のある商品や販売促進企画を明確に作り上げなくてはならない。
![]() 顧客の立場に立つ
顧客の立場に立つ
顧客の生活により深く関係する活動を展開しなくてはならない。顧客と店舗の関係性が高まれば取引は促進される。
![]() 顧客に理解させる
顧客に理解させる
活動の結果得られる顧客の価値をしっかり理解させることが重要である。理解できれば、愛着も高まり、一層の定着を図ることができる。
(12)データを重視する
![]() 事業展開には裏づけが必要
事業展開には裏づけが必要
共同・連鎖化事業を展開するに当たっては、各種のマーケティング情報を始め、しっかりとした情報を収集しておかなくてはならない。
思い込みで事業展開しても、コストの浪費にしかならない。「観光客に購入してもらいたい」、当然の要望である。だからといって、土産物を共同開発して、共同販売しようと言うのは、あまりにも短絡的である。観光客は、どんな年代の、どんな人たちが、どのような経路で行動し、何を購入しているのかを調べることから始めなくてはならない。
日常使用される商品にも同様のことが言える。どのような商品が、なぜ売れているのかを考える必要がある。各種の統計や定性情報をタイムリーに収集し、市場をしっかりと確認した上で、事業展開していかなくてはならない。消費者が何を求めているのか不明なままでは、中小酒類小売業者の活性化につながる施策の展開は難しい。
![]() データの収集
データの収集
官庁やシンクタンクから発行される各種白書や統計を読むことは、社会の流れを把握するのに有効である。「国民生活白書」や「インターネット白書」など、中小酒類小売業者が顧客とする生活者の動向を再確認することができる。
「家計調査年報」も公表されているデータとしては使い勝手が良い。細かい食関連の消費動向が読み取れ、品揃えや販売促進に役立つ。
自分たちが収集する情報も欠かせない。商圏内における販売実績や顧客数などは、欠かせないデータである。これらの情報やデータは、中小酒類小売業者の持つ情報を統合すれば、さらに効果的に活用できるが、なかなか自店の情報を出したがらないのが中小酒類小売業者である。
共同化や連鎖化を進める場合、組織として情報収集をすることが望ましい。取組もうとする事業が、“市場にどの程度浸透しているのか”、“競合はどのような手立てで取組んでいるのか”、“顧客は当事業を受け入れ、活用することが可能なのか”を調べることなく、思い込みでスタートし、莫大なロスを生むことも珍しくない。
自分たちが収集する情報を得るためには、以下のような方法が考えられる。
- 観察調査
- 質問紙によるアンケート調査
- 面談で行うインタビュー調査
- 座談会方式で行うグループ・インタビュー調査
- 関係者に関連情報を聞くデプス・インタビュー調査
- 販売する商品を直接顧客に確認するユーステスト
- テスト販売を行って顧客の反応を確認するテストマーケティング
その他にも多数あるので、中小企業診断士や専門家に相談すると良い。
(13)自分たちなりの競争戦略を持つ
どのような共同化や連鎖化も、史上初と言うことはない。市場には何らかの形で、先発している事例が存在する。競合と自分たちの力関係や市場での位置づけを考えながら、事業展開の方法を探っていかなくては、失敗してしまう。位置づけは、前述の自分達が収集するデータと各種公表データで、把握することができる。
市場での位置づけについて、理論的に検証が進んでいるのが、次の図表で表した市場地位別競争戦略である。自分たちの行う事業は、自分たちがどの地位にいるのかで採択する戦略は変わってくる。一般的に共同事業では、早期に戦略が構築されていることは少ない。商品優先、仕組み優先で戦略すら存在しないことも多い。これから共同化や連鎖化を志向するなら、自分達の市場地位を確認した上で、戦略を策定したい。
図表2−2−6 市場地位別競争戦略の概要
| 1.市場リーダー 業界や市場においてナンバー1の企業 最大の市場占有率を持ち、常に市場の開拓・拡大を狙っている |
採択する戦略
最大の市場占有率維持全方位フルカバレッジ戦略を採択
|
|
| 2.市場チャレンジャー 業界や市場で2位以下の上位であり、トップを目指す企業 経営資源もトップ企業同様に有している |
採択する戦略
市場地位向上リーダー対抗差別化戦略を採択
|
|
| 3.市場フォロワー 業界や市場において、地位はチャレンジャーよりも下位。保守的な追随者としての地位に甘んじていることが多い企業 経営資源もリーダー、チャレンジャーに比べると劣ることが多い |
採択する戦略
価格による優位性確保上位企業模倣戦略を採択
|
|
| 4.市場ニッチャー 大手企業やブランドとの競争を避け、特定分野でのシェアを追求する企業 当該市場が成長し、他社が複数参入し始めるとリーダーの位置での戦略が必要になる |
採択する戦略
特定市場での市場占有率ナンバー1特定化・集中化戦略を採択
|
(14)情報機器の活用を推進する
![]() 現代の事業はITなくして考えられない
現代の事業はITなくして考えられない
時代はIT化が急速に進展している。携帯電話の登録台数は7,000万台を超え、パソコンの家庭内普及率も50%を超えた。大掛かりなシステムがなくても、簡易なプログラムで経営管理や販売促進が可能なIT技術やハードウェア(機械・設備)も続々市場に現れている。
このような環境にあっても、中小酒類小売業者の情報化はまだ進んでいない。しかし、一部の先進的な中小酒類小売業者が参加して行うのであれば、情報化に積極的に着手していくことも可能である。
小学校でもパソコンを指導する例は多い。携帯電話はますますその機能を高め、財布代わり、テレビ代わりになってきている。今後もより簡単で、安価な情報機器は現れると思うが、現段階のITを活用する意欲がなくては始まらない。
全国でIT研修を実施している。民間でも手取り足取りアドバイスするスクールや、自治体レベルでも講座を開催している。積極的に活用し、共同化や連鎖化の推進には、必須の技術として活用しなくてはならない。
![]() 時代に対応するためにIT化に取組もう
時代に対応するためにIT化に取組もう
全員のレベルに合わせるために、ハイテクを活用できず、わざわざ古典的な手法を用いているようでは、競争社会では生きていけない。
構成員が不平等になるような仕組みでは成功しないが、少しずつでも効率を高めるために先端技術は取り入れることを前提にしておくべきである。
以下、生活者のインターネットの活用状況について紹介する。
図表2−2−7 インターネットの浸透状況
□日本のインターネット人口 7,007万2千人
- 日本のインターネット人口は2005年2月調査時点で7,007万2千人
- 2004年2月調査の6,559万4千人と比較して、447万8千人増
- インターネット世帯浸透率は82.8%
□家庭からのブロードバンド利用者数 3,224万4千人
- 家庭からのブロードバンド利用者数3,224万4千人。2004年約1千万人増加
- 日本全世帯におけるブロードバンド普及率は、36.2%
□インターネットは複数の手段から実施される
- インターネット利用者の31.9%が、携帯電話からもパソコンからもアクセスするサイトがあると回答
□インターネットは購買行動に浸透
- インターネット利用者の31.9%が、携帯電話からもパソコンからもアクセスするサイトがあると回答
インターネットによって、実店舗での買い物が減ったと感じる人は46.5%
出典:「インターネット白書2005」インプレス
(15)常に選択と集中を考える
![]() 市場を選択して投資を集中する
市場を選択して投資を集中する
選択と集中は、いかなる組織や事業にも求められるテーマである。共同化や連鎖化を行うにあたって、当然経営資源には限りがある。有限の資源であれば、どの活動に投資を集中するのかを戦略的に決定しなければ、推進力は分散し、市場への影響力は大変弱いものになってしまう。
例えば、「地産地消」をテーマとすれば、観光客向けに彩を持たせるものとは違う売り方をしなくてはならない。また観光客向けに力を入れようというのであれば、商品形態も販売経路も、地元向けとは変えなくてはならない。
「情報化の推進」と言うテーマでは、一度にすべてのプログラム開発やシステム構築を行うのではなく、身近で使いやすいものから始める、と言うような選別が行われて当然である。
「PB商品に特化」するなら、NB商品の薄い利幅を嘆いている場合ではない。
活動を起こす際には、必ずターゲットが存在する。それが一般消費者であったり、組織の構成員であったりする。ターゲットは必ずいくつかに分類ができる。経営資源に余裕があれば、すべてのターゲットに対して万遍なく、十分にアプローチできる。しかし、現実的に資源に余裕がない場合、ターゲットを絞ったり、展開内容を絞ったりしなくてはならない。
![]() 市場を細分化してみよう
市場を細分化してみよう
市場細分化という概念がある。消費者をあらゆる基準でいくつかのグループに分類して、自分たちの展開する事業に最も有効なグループを探し出すのである。
市場は均質ではないため、ニーズも購買能力も異なる。バラツキある市場に事業を一斉展開するには、無理がある。あまねく広い市場に対して事業展開を行うのであれば、シンプルで分かりやすいものに絞るべきである。分類したグループのいずれかに絞るのであれば、深く集中的に戦力を投下すべきである。また、いくつかのグループに対応するのであれば、キメ細やかな戦略策定が求められる。
どのような事業展開するにも、必ずターゲットあるいは展開テーマを絞って取組まなくてはロスが大きい。
図表2−2−8 市場細分化の概念
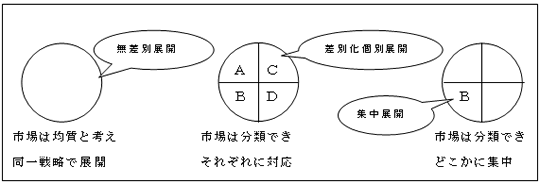
(16)リスクマネジメント(危機管理)を考える
![]() リスクマネジメントが求められる背景
リスクマネジメントが求められる背景
消費者の志向は多様化し、商品や事業の寿命はますます短縮している。この環境において、新たに共同化や連鎖化に取組むのであれば、迅速に、大胆に行わなくてはならない。積極的に事業展開するのであれば、当然リスク(危機)の発生機会も増大する。現代、事業はその存在に公共性、社会性を求められ、あらゆる局面で責任を問われている。製造物責任や環境汚染のリスクを始め、生活者の便宜保全に至るまで、消費者の評価は厳しい。
![]() リスクの認識と対応方法を考えよう
リスクの認識と対応方法を考えよう
リスクは通常「危機」と訳されるが、さらに拡大して「危険」や「障害」もリスクの範疇に含める。リスクは、大きく以下の3つに分類することができる。
1)ハザードリスク
従来からのリスク概念であり、事業に悪影響を与える可能性のある事柄で、地震、
水害、台風、火災など外来のものである。
2)不確実性リスク
結果の予測が困難で、想定外のケースが発生するリスクをいい、投資や開発などに伴うリスクである
3)事業機会リスク
新しいビジネス機会には、必ずリスクが伴うものであり、統制することを前提とするリスクである。事業機会リスクには、新しいマーケティング手法の導入や新製品発売などに関わるものがあげられる。共同化や連鎖化は、必ず事業機会リスクを伴うものである。
これらのリスクに対応していくには、以下の4つの手法が考えられる。各組織の実情、展開する事業の内容に合わせて活用していかなくてはならない。
・ リスク回避
事業成果として得るリターンに対してリスクが大きすぎる場合、取組みを断念できるのであれば、最初からそのリスクを回避すると言うスタンスを取る。
・ リスク軽減
リスク発生頻度や被害の大きさを軽減する。解決策を講じながら、分散させる。
・ リスク移転
事業成果として得るリターンに対してリスクが大きすぎる場合、取組みを要する場合は、保険などによるリスク分散を図る。
・ リスク受容
リスクは保険などで負担の分散をしない方が経済的であると考え、リスクをよ
り良く管理するようマネジメントプロセスを強化していく。

