生命保険契約から生ずる個人所得の課税の在り方
寺内 将浩
研究科第44期
研究員
要約
1 研究の目的
生命保険は、公的な救済制度と並び「万一の保障」(リスクの移転)として文化的生活を保障する機能を果たしていると言われている。しかしながら、現在販売されている生命保険商品を概観すると、これらは決して「万一の保障」という領域には留まらず、多分に貯蓄(投資)性を有している。
ところで、生命保険商品から生ずる満期保険金、死亡保険金及び解約返戻金(相続や贈与に該当するものを除き、以下「一時金等」という。)は、現在、一時所得に分類され、所得金額の計算上、収入金額から保険料の総額が控除されている。この取扱いは、生命保険の本質的機能が伝統的に保障的機能にあると説明されてきたことに由来するものと考えられるが、例えば、養老保険は預貯金に近似した商品として説明されて販売されているところであり、変額保険など更に貯蓄(投資)性を高めた商品も多数見られる現状を考えれば、すべての一時金等を一律に取り扱うことに疑問なしとはしない。
そこで、本研究においては、生命保険契約から生ずる一時金等の個人所得課税に焦点を当て、保険数理や保険会計などの観点から一時金等の性質について分析を行い、現行所得税法上の問題点及び課税のあるべき姿について考察することを目的とする。
2 研究の概要
(1)生命保険の構造
保険契約者が支払う保険料及び保険金受取人が受け取る一時金等は、保険数理・保険会計の観点から、次のとおり整理することができる。
- イ 保険料の構成要素
保険契約者が支払う保険料は、 一時金等の支払に充てるための純保険料、
一時金等の支払に充てるための純保険料、 保険経営の諸費用に充てるための付加保険料、
保険経営の諸費用に充てるための付加保険料、 入院給付特約などの特約に係る給付に充てるための特約料で構成されており、予定死亡率、予定利率及び予定事業費率を基に算出される。このうち、
入院給付特約などの特約に係る給付に充てるための特約料で構成されており、予定死亡率、予定利率及び予定事業費率を基に算出される。このうち、 の純保険料は、将来における一時金等の支払のためにその一部を積み立てておく必要があることから、更に
の純保険料は、将来における一時金等の支払のためにその一部を積み立てておく必要があることから、更に 保険会社において積み立てられる貯蓄保険料と、
保険会社において積み立てられる貯蓄保険料と、 積み立てられずに、各保険期間に他の保険契約者へ移転されていく危険保険料とに分類される。
積み立てられずに、各保険期間に他の保険契約者へ移転されていく危険保険料とに分類される。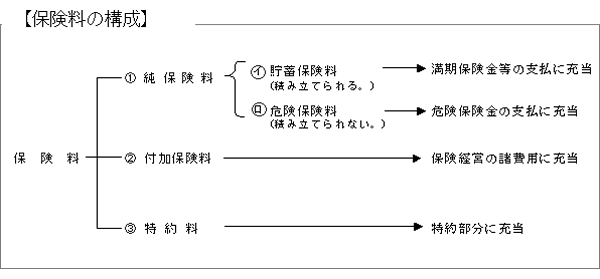
- ロ 一時金等の構成要素
保険金受取人が受け取る一時金等は、 貯蓄保険料の累積額、
貯蓄保険料の累積額、 それに付された利子相当額、
それに付された利子相当額、 他の保険契約者から移転される危険保険料部分(危険保険金)の三つの要素に分解することができる。
他の保険契約者から移転される危険保険料部分(危険保険金)の三つの要素に分解することができる。
具体的には、満期保険金及び解約返戻金(以下「満期保険金等」という。)は、 と
と の要素により、死亡保険金は、
の要素により、死亡保険金は、 、
、 及び
及び の要素により構成されている。
の要素により構成されている。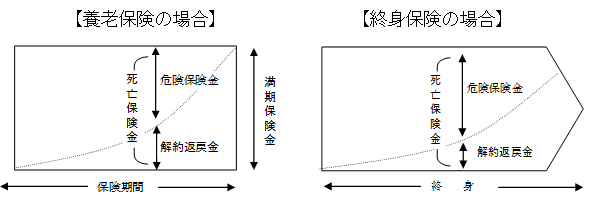
(2)所得区分の問題
現在、一時金等は一時所得として取り扱われているが、裁判例等を検討すると、一時所得の該当性は、具体的には 所得の基礎に源泉性を認めるに足る継続性・恒常性がないこと(以下「所得の非源泉性要件」という。)、
所得の基礎に源泉性を認めるに足る継続性・恒常性がないこと(以下「所得の非源泉性要件」という。)、 一時金として支払われたものであること(以下「一時性要件」という。)、
一時金として支払われたものであること(以下「一時性要件」という。)、 給付が抽象的・一般的な労務・役務行為に密接・関連しないものであること(以下「役務の非対価性要件」という。)という点にあると考えられる。
給付が抽象的・一般的な労務・役務行為に密接・関連しないものであること(以下「役務の非対価性要件」という。)という点にあると考えられる。
これを上記(1)のロで整理した一時金等の構成要素に着目して検討すると、次のとおりである。
-
イ 満期保険金等の所得区分
満期保険金等を構成する貯蓄保険料の累積額は、同じく満期保険金等の構成要素である利子相当額を得るための元本となり、保険期間中に継続的に利子相当部分を生み続ける。そして、この元本と利子相当部分は、解約権の行使により、保険期間中いつでも現金化することができることから、満期保険金等の所得者は、常に引き出し可能な預貯金を保有していたのと同じ状態にあったものと言える。よって、満期あるいは解約によって得られる満期保険金等は、その所得の基礎に源泉性を認めるに足る継続性・恒常性を有していると言え、所得の非源泉性要件を満たしていないものと考えられる。
また、所得者が行う貯蓄保険料の支払行為は、保険会社による貯蓄保険料の利用(投資・運用)を前提とした積立行為であり、満期保険金等の純所得部分たる利子相当額はその利用の結果として得られたものであるから、ここに役務の対価性を見出すことも十分に可能である。そうすると、満期保険金等は役務の非対価性要件も満たしているとは言えない。
したがって、満期保険金等を一時所得として整理するのは適当ではなく、また、利子所得ないし譲渡所得のいずれにも該当しないことから、雑所得として整理するのが適当と考えられる。 -
ロ 死亡保険金の所得区分
満期保険金等の場合と同じく、死亡保険金も貯蓄(投資)的要素、すなわち、貯蓄保険料の累積額とそれに付された利子相当額をその構成要素として有している。この貯蓄部分は、具体的には死亡時における解約返戻金相当額をもって計ることができ、上記イで述べたとおり、当該部分は所得の非源泉性要件及び役務の非対価性要件をいずれも満たしていないと考えられることから、一時所得ではなく、雑所得として整理するのが適当と考えられる。
一方、死亡保険金の残りの構成要素である危険保険金部分は、死亡事故という偶発的な要因によって突如として発生したもので、しかもこれは他の保険契約者が支払った危険保険料が死亡事故の発生を期に移転したものである。よって、その基礎には所得源泉性を認めるに足る継続性・恒常性があるとは認められない。また、この部分は、生命保険の相互扶助関係、いわゆる「持ちつ持たれつ」といった関係が如実に現れた部分であって、これを労務・役務の対価と観念することも困難である。さらにこの部分は一時金として支払われたものであることから、一時所得の要件のすべてを満たしており、一時所得として整理するのが適当と考えられる。
なお、死亡保険金は、上記のとおり死亡事故発生時まで増加(発生)を続けた雑所得部分と、死亡事故発生時に発生した一時所得部分に二分されることになるが、このような所得の二分化は、例えば長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡したケースにおいても見ることができ、学説・判例においても是認されていることから、死亡保険金の課税においても採り得べきものと考えられる。
(3)控除すべき金額の問題
所得税法施行令第183条第2項は、危険保険料、貯蓄保険料、付加保険料及び特約料を「保険料の総額」として、一律に一時金等から控除する旨規定しているが、これについては、収入した一時金等と対応しない支出が過剰に控除される点が指摘されている。入院給付金など特約に係る給付の多くが非課税であることにかんがみれば、これは見過ごすことのできない問題と言える。
上記(2)のとおり一時金等の所得区分を整理することができたが、そこから控除する保険料についても、その一時金等と対応するもののみを控除すべきと考えられ、具体的には次のとおりである。
-
イ 満期保険金等から控除すべき金額
貯蓄保険料は、それ自体が満期保険金等の構成要素であるとともに、利子相当部分を生む元本となる。したがって、貯蓄保険料は、満期保険金等の稼得に必要な支出と観念でき、満期保険金等の必要経費に該当するものと考えられる。
一方、危険保険料は保障的機能に、特約料は特約に係る支出であって、貯蓄(投資)的機能に対応するものではない。したがって、これらはいずれも貯蓄(投資)的機能が発現して得られた満期保険金等の稼得に必要な支出とは言えず、その所得金額の計算の際に控除する必要はないものと考えられる。
また、付加保険料は、生命保険が持つ貯蓄(投資)的機能と保障的機能の両機能に対応する支出と言えるが、そこから各機能に対応する部分を合理的に算出することは困難である。所得税法上、所得の稼得に必要な部分を明確に区分することのできない家事関連費は必要経費に算入できないこととされており、よって、保険会社の協力等により合理的区分が可能とならない限り、付加保険料は満期保険金等の必要経費に算入できないものと考えられる。 -
ロ 死亡保険金から控除すべき金額
上記イのとおり、貯蓄保険料は貯蓄(投資)的機能に、危険保険料は保障的機能に対応する支出である。よって、貯蓄保険料は貯蓄(投資)的機能が発現して得られた雑所得部分から、危険保険料は保障的機能が発現して得られた一時所得部分から控除すべきと考えられる。
また、死亡保険金は貯蓄(投資)的機能と保障的機能の両機能が発現して得られた所得であるから、その両機能に対応する付加保険料は、死亡保険金に占める雑所得部分の額と一時所得部分の額の割合をもって合理的にあん分し、各部分からこれを控除する方法が考えられるが、満期保険金等の所得金額の計算の際には付加保険料を控除しないこととすることから、これとのバランスを図り、雑所得部分からは控除せず、一時所得部分からその全額を控除する方法も考えられるところである。
なお、特約料は特約に係る保障を得るための支出であり、死亡保険金の雑所得部分及び一時所得部分のいずれにも対応しないものであることから、死亡保険金からは控除すべきでないと考えられる。
(4)課税方式
これまでの整理を基に生命保険商品に対する課税方式を検討するに、他の金融商品との課税の中立性の確保の観点から、預貯金等と競合すると考えられる雑所得部分に源泉分離課税制度を導入し、一時所得部分は現行どおり総合課税に留め置くのが適当と考えられる。
これは、生命保険契約の長期性から生ずる束ね効果問題の解決策、更には満期保険金等に係る申告が不要となることから、申告手続の簡素化にもつながるものと考えられる。
3 結論
本研究では、生命保険商品の貯蓄(投資)的機能の高まりを背景に、保険数理・保険会計の観点から一時金等の性質・構造を分析し、その課税の在り方を考察した。その結果、 満期保険金等は、雑所得に分類して貯蓄保険料を控除する、
満期保険金等は、雑所得に分類して貯蓄保険料を控除する、 死亡保険金は、貯蓄相当部分(死亡時における解約返戻金相当額)を雑所得に、危険保険金部分を一時所得に分類し、雑所得部分からは貯蓄保険料とこれに対応する付加保険料を、一時所得部分からは危険保険料とこれに対応する付加保険料を控除する(付加保険料については、その総額を一時所得部分から控除する方法も考えられる。)、
死亡保険金は、貯蓄相当部分(死亡時における解約返戻金相当額)を雑所得に、危険保険金部分を一時所得に分類し、雑所得部分からは貯蓄保険料とこれに対応する付加保険料を、一時所得部分からは危険保険料とこれに対応する付加保険料を控除する(付加保険料については、その総額を一時所得部分から控除する方法も考えられる。)、 課税の中立性などの観点から、雑所得部分に源泉分離課税制度を導入し、一時所得部分は総合課税に留め置くのが適当であると結論付けた。
課税の中立性などの観点から、雑所得部分に源泉分離課税制度を導入し、一時所得部分は総合課税に留め置くのが適当であると結論付けた。
生命保険商品の多様化や貯蓄(投資)的機能の高まりを考えると、一時金等をすべて一律に取り扱う現行の制度は、もはや妥当とは言えない。他の金融商品との課税の中立性の確保の観点からも見直しが必要と考えられるのであり、上記のように、所得の本質に着目した課税をすべきと考える。
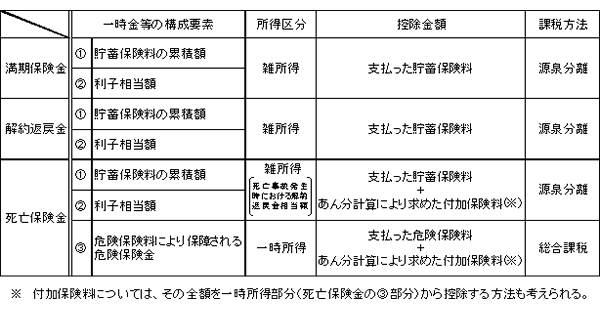
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
論叢本文(PDF)・・・・・・786KB

