所得税の財源調達機能と所得再分配機能のあり方についての一考察
鳴島 安雄
税務大学校
研究部主任教授
要約
1 研究の目的(問題の所在)
所得税は、財源調達に基幹的な役割を担うとともに、所得再分配機能においても重要な役割を担っている。所得税の負担構造は、税率のみではなく、給与所得控除や基礎控除等の人的控除との組み合わせにより決定されるものである。所得税の負担については、平成元年の消費税の導入を含む税体系全体にわたる税制改革から平成19年の税源移譲に伴う改正に至るまで幾多の軽減措置等が図られた。特に、所得税の税率構造については、消費税の導入その後の消費税率の引上げに伴い、所得税率の刻み数を減少させ税率のブラケット幅を拡大する等大幅な累進緩和が図られた。更に、税源移譲に伴い個人住民税の税率を一律10%とする一方で所得税の最低税率を10%から5%に引き下げる等の見直しを行った結果、所得再分配機能を担うのは所得税が中心となった。
そこで、本稿では、所得税が基幹的なものと位置づけられ、所得再分配機能が適切に発揮されているかどうかを検証するとともに、税制改革以降における経済・社会の構造変化を踏まえて、所得税の負担構造に密接に関連する 基礎的な人的控除のあり方、
基礎的な人的控除のあり方、 給与所得控除のあり方、
給与所得控除のあり方、 税率構造のあり方について考察する。
税率構造のあり方について考察する。
2 研究の概要(現状等)
(1)所得税の機能と消費税導入を含む税制改革から税源移譲後に至るまでの所得税の負担構造の変遷等(第1章)
所得税は、公共サービスの財源調達に基幹的な役割を担うとともに、所得再分配機能においても重要な役割を担っているほか、経済の自動安定化機能を有している。
今後の所得税のあるべき姿を描く上で、所得税の負担構造の見直しがその時々の経済・社会の構造変化の中でどのような考え方の下に行われてきたのかを理解し、評価することが重要である。
昭和25年で実現されたシャウプ勧告に基づく税制改正以来、税制全般の見直しが行われたのは、昭和62年・63年に行われた消費税導入を含む抜本的な税制改革である。その後、消費税率の引上げに伴う税制改革が行われた。これらの税制改革に伴う所得税の改正では、我が国の終身雇用、年功序列型の賃金設定を基本とする社会状況の中で、所得水準の上昇と平準化、消費の多様化・サービス化、人口構成の高齢化等の経済・社会の構造変化を踏まえ、働き盛りの中堅所得者層の負担累増感を緩和する等の観点から、個々人のライフサイクルを通じてある程度長い期間にわたり相当程度の収入の伸びを見込んだ場合でも大多数のサラリーマンが就職してから退職するまでの所得税の税率が一本(10%)ないし二本(10%、20%)で済むよう、所得税率の刻み数を減少させ税率のブラケット幅を拡大する等の税率構造等の見直しが行われた。これにより、所得税負担は大幅に軽減された。
その後、景気に配慮した減税等が行われ、平成19年の税源移譲に伴う改正では、納税者の税負担を極力変動させないとの考え方の下、個人住民税の税率を一律10%とする一方で、所得税の税率構造については、最低税率を10%から5%に引き下げるとともに最高税率を37%から40%に引き上げる等の見直しが行われた。その結果、所得税負担は、高所得者層において若干増加したものの、中低所得者層においては、大幅に軽減されている。
こうした累次の改正により所得税負担は大幅に軽減されている。
(2)所得税収等の変化及び所得税の税負担構造の現状と分析(第2章)
所得税の財源調達機能及び所得再分配機能を検証するため、所得税収、納税者数及び所得税の負担状況の推移並びに所得税の負担状況を表した実効税率のグラフ及び民間給与の実態調査等からみた給与収入階級別の分布状況等を分析する。
- イ 所得税の税収について見ると、平成20年度の所得税収は国税収入の3割程度(33%)を占めており、基幹的な地位を占めているものの、消費税導入前の昭和61年度は4割(40%)であったことと比べると相当低下している。また、歳出・歳入のギャップを見ても、昭和61年度には8割弱(78%)であったが、その後の景気情勢や減税等により歳出が増加し国税収入が減少したことから、歳出総額に対する国税収入の割合は低下し続け平成20年度の歳出総額に対する国税収入の割合は5割程度(52%)と歳出・歳入ギャップは一層拡大している。更に、消費税の導入等により直間比率は是正されたが、所得税の租税負担率は昭和61年度6.3%から平成19年度4.3%と低下しており主要諸外国と比較して最も低い状況にある。また、給与所得に係る課税総所得金額に対する平均税率は昭和61年度15.9%から平成20年度10.3%と低下している。
- ロ 所得税の納税者数について見ると、平成19年の就業者数6,412万人に対し納税者数は5,265万人と8割を超える水準となっており、昭和61年と比較して納税者割合は増加している(昭和61年73%⇒平成18年82%)。
- ハ 給与所得者の給与収入階級別の分布状況から、所得税の納税者数、給与総額及び所得税額の構成を見ると、昭和61年分と比べて、平成19年分はいずれも増加しているが、特に給与総額が著しく増加している(対昭和61年:納税者数で116%、給与総額で144%)。一方、累次の税率構造のフラット化や最低税率の引下げ等により所得税額はそれほど増加していない(対昭和61年:所得税の総額で107%)。また、所得上昇に伴い納税者が給与収入階級の高い方にシフトしているものの、高い給与収入の少数の納税者によって多くの所得税負担額を依存している(給与収入1,000万円超1割弱の納税者(6%)で所得税額の5割弱(47%))。
- ニ 昭和61年分と平成19年分の給与所得者(夫婦子2人世帯)の所得税の実効税率のグラフを用いて、所得が上昇するにつれてどの程度の所得税負担が増加するのかというのを測定する尺度として所得税の累進度(傾き)の変化を示したのが、次のグラフである。
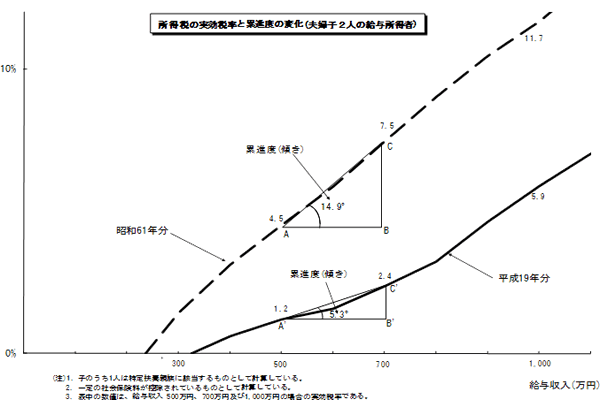
これを見ると、給与収入500万円の所得税額を起点A(A´)として給与収入の金額が200万円増加した場合において、その増加後の給与収入700万円の点B(B´)とその金額に対する所得税額の点C(C´)を線で結んだ三角形の起点A(A´)の角度の傾き(増加給与収入の金額に対する増加所得税額の割合)を、それぞれ比較すると、昭和61年分と比べ平成19年分の傾きが3分の1と相当程度小さくなっている。また、このグラフの形状を見ても、中低所得者層において、昭和61年分はお椀をかぶせた状態でなだらかに負担が増加していく形状から、平成19年分はより深くえぐれた形状となっており、所得税の大幅な累進緩和等によって所得税の累進性が相当程度低下していることがわかる。
更に、平成19年の税源移譲の前後の給与所得者(夫婦子2人世帯)の税負担状況を比較して見ると、税源移譲後では給与収入941万円までは所得税負担額が個人住民税負担額より少なくなっており、給与収入1,559万円を超えると税源移譲前の所得税負担額よりも税源移譲後の所得税負担額が多くなっている。なお、給与収入822万円までは、税源移譲後の所得税負担額が税源移譲前の個人住民税負担額より少なくなっている。 -
ホ 昭和61年分から平成19年分までの民間給与の実態調査の給与収入階級分布状況から所得税の累進性について検証したのが、次のグラフである。
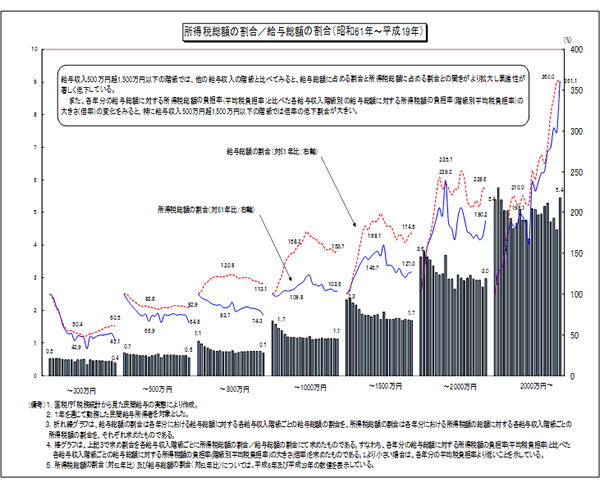
まず、折れ線グラフは、 各年分における給与総額に対する各給与収入階級別の給与総額の割合と各年分における所得税総額に対する各給与収入階級別の所得税額の割合の変化を示したもので、これを見ると、給与収入500万円を超え1,500万円以下の各階級において、他の給与収入階級と比べて、それぞれの割合の開きが拡大している。
各年分における給与総額に対する各給与収入階級別の給与総額の割合と各年分における所得税総額に対する各給与収入階級別の所得税額の割合の変化を示したもので、これを見ると、給与収入500万円を超え1,500万円以下の各階級において、他の給与収入階級と比べて、それぞれの割合の開きが拡大している。
次に、棒グラフは、 各年分における給与総額に対する所得税総額の負担率(平均税負担率:昭和61年分6.0%から平成19年分4.4%と27ポイント低下)と比べた各給与収入階級の給与総額に対する所得税額の負担率(階級別平均税負担率)の大きさ(倍率)を示したもので、各年分の平均税負担率の値を「1」とし、その値より小さい場合は、階級別平均税負担率が平均税負担率より低いことを示している。これを見ると、給与収入2,000万円を超える階級を除き、平均税負担率に対する階級別平均税負担率の倍率は低下しているが、特に、その低下割合が大きいのは給与収入500万円を超え1,500万円以下の各階級である。
各年分における給与総額に対する所得税総額の負担率(平均税負担率:昭和61年分6.0%から平成19年分4.4%と27ポイント低下)と比べた各給与収入階級の給与総額に対する所得税額の負担率(階級別平均税負担率)の大きさ(倍率)を示したもので、各年分の平均税負担率の値を「1」とし、その値より小さい場合は、階級別平均税負担率が平均税負担率より低いことを示している。これを見ると、給与収入2,000万円を超える階級を除き、平均税負担率に対する階級別平均税負担率の倍率は低下しているが、特に、その低下割合が大きいのは給与収入500万円を超え1,500万円以下の各階級である。
このことから、給与収入500万円を超え1,500万円以下の各階級において、他の給与収入階級と比べて、特に累進性が低下していることがわかる。 - ヘ 更に、平成19年分に確定申告書を提出した者のうち総所得金額を有する者の確定申告事績から、世帯類型、年齢区分及び課税総所得金額階層別の分布状況並びに給与収入のある者の給与収入階級の分布状況等を検証する。
- (イ) 課税総所得金額別の分布状況を見ると、平成19年の改正前で所得税率10%が適用されていた課税総所得金額330万円以下である者は全納税者の8割(課税総所得金額195万円以下67%、195万円超330万円以下13%)を占め、算出税額の総額の2割弱(18%)しかカバーしていない。一方、最高税率が適用される課税総所得金額1,800万円超の納税者はごく少数(2%)で算出税額の総額の4割強(41%)をカバーしている。
- (ロ) 世帯類型別の状況を見ると、扶養控除の適用を受けていない者は、申告書全体の7割強(単身世帯47%、夫婦世帯26%)を占めており、算出税額の概ね6割を占めている。また、扶養控除を適用している者は、全体の3割弱であり、そのうち、子供の扶養控除を適用している者は全体の2割強(21%)、子供の扶養はなく両親等の扶養控除を適用している者は1割弱(7%)となっている。
- (ハ) 年齢階層別(10歳ごとに区分)の分布状況を見ると、60歳代の申告者が3割弱(28%)と最も多く、50歳から79歳までの申告者が全体の6割強を占めている。算出税額では、50歳代が3割弱(25%)と最も多く、40歳から69歳までの申告者が全体の7割を占めている。
- (ニ) 世帯類型別に年齢階層及び課税総所得金額階層の分布状況を見ると、
 子供のいる世帯では、申告者全体の課税総所得金額階層別の構成に比して課税総所得金額が高い階層に存在するものの、共働きで子供のいる世帯は、夫婦子供世帯より課税総所得金額が低い階層に多く存在している。また、子供1人世帯より子供2人世帯の申告者が比較的若い年齢層に多く存在している。更に、夫婦子供世帯と共働き子供世帯を総所得金額階層別で見ても、夫婦子供世帯よりも共働きで子供を扶養している世帯の割合が低所得階層で高くなっている。
子供のいる世帯では、申告者全体の課税総所得金額階層別の構成に比して課税総所得金額が高い階層に存在するものの、共働きで子供のいる世帯は、夫婦子供世帯より課税総所得金額が低い階層に多く存在している。また、子供1人世帯より子供2人世帯の申告者が比較的若い年齢層に多く存在している。更に、夫婦子供世帯と共働き子供世帯を総所得金額階層別で見ても、夫婦子供世帯よりも共働きで子供を扶養している世帯の割合が低所得階層で高くなっている。
次に、 単身世帯と夫婦世帯(子供のいない世帯)では、両世帯とも60歳代の申告者が最も多く、次いで、70歳代の申告者が多い。また、60歳未満の申告者は、給与所得を有するケースが多く、60歳以上の申告者は、公的年金等に係る雑所得と給与所得による申告が多い。更に、60歳代と70歳代の申告者は、課税総所得金額195万円以下の階層に多く存在していることがわかる。
単身世帯と夫婦世帯(子供のいない世帯)では、両世帯とも60歳代の申告者が最も多く、次いで、70歳代の申告者が多い。また、60歳未満の申告者は、給与所得を有するケースが多く、60歳以上の申告者は、公的年金等に係る雑所得と給与所得による申告が多い。更に、60歳代と70歳代の申告者は、課税総所得金額195万円以下の階層に多く存在していることがわかる。 - (ホ) 給与収入のある者は申告者全体の5割弱(49%)となっている。この給与収入のある者について、給与収入階層別の分布状況を見ると、給与収入500万円以下の者は7割弱(68%)となっており、給与総額は3割強(32%)、給与所得控除総額(13.5兆円)の5割弱(48%)を占めている。一方、確定申告義務のある給与収入2,000万円を超える者はごく少数(3%)であるものの、給与総額の2割弱(18%)で、給与所得控除総額の1割弱(7%)を占めており、2,000万円を超える部分の給与所得控除総額は1,900億円となっている。
- ト 給与所得者(夫婦子2人世帯)の個人所得課税及び消費税の税負担並びに社会保険料負担の給与収入に応じた実効負担率の状況を見ると、給与収入の低い者ほど、給与収入の高い者より給与収入に対する消費税及び社会保険料の負担割合が高くなっていることがわかる。
今後、社会保険料や消費税の負担が増加すると、租税負担と社会保険料負担をあわせた実効負担率のグラフの形状は、全体としてなだらかなグラフとなり相対的に高所得者層の累進性が低下すると見込まれることから、今後の所得税の負担構造の見直しに際しては、高所得者層の累進性を高めていくことが求められるものと考える。
(3)所得税の負担構造に影響をもたらす経済・社会の構造変化等(第3章)
今後、消費税を含め税体系全体のあり方について抜本的な見直しが求められている。個人所得課税については、平成21年3月の所得税法等一部改正法(平成21年法律第13号)附則において、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造の見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の撤廃等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討するといった基本的な方向性が示されており、今後の所得税の負担構造の見直しに影響をもたらす経済・社会の構造変化の実像等を検証する。
- イ 少子・高齢化の進展については、出生数の減少や合計特殊出生率の低下等により平成16年に総人口が減少し今後も減少すると予測されている。また、団塊の世代(昭和22年から昭和24年に生まれた者)が平成24年には65歳に到達し平成25年(2013年)には4人に1人が高齢者となる。このようなことから社会的な扶養力が急速に弱まっていくとされている。
-
ロ 経済成長の推移については、右肩上りの高度経済成長期から安定成長期に、その後のバブル崩壊を経て低成長期へと推移し、平成20年に入って景気回復が足踏み状態となり、世界経済の減速に伴い景気は後退局面に入り、平成20年末以降も、我が国の景気は急速な悪化が続いている。高度経済成長期に定着化された標準的モデル(戦後家族モデルや日本型雇用慣行)が壊れ、その見直しが必要である。今後は、労働力人口の減少や家計貯蓄率の低下等を通じて供給面から我が国経済に制約が生じることが懸念され(潜在成長力の低下等)、社会の活力の維持・確保が重要な課題となることから、貯蓄の効率的活用や女性や高齢者の一層の社会参画等が求められる。
賃金指数については、景気回復局面が始まった平成14年以降、ほとんど伸びていない(平成17年=100:平成19年100.7(対昭和61年比123.3%)。ただし、パート労働者の賃金指数は、ここ数年、一般労働者等の賃金指数より高い伸びとなっている(平成17年100:平成19年102.3)。また、消費者物価指数(総合)は、平成10年まで上昇傾向が続いたが、その後デフレ状況が続き、平成18年には前年比0.3%増となりデフレ状況が改善された(平成17年=100:平成19年100.3(対昭和61年比113.2%)。 -
ハ 家族形態の変化については、近年、未婚化・晩婚化・長寿化の進展に伴って更に世帯規模が縮小し、家族世帯類型の多様化が進み、「夫婦と子供のみの世帯」は、もはや標準ではなくなっている。
「片働き世帯」は減少し「共働き世帯」が急増しており、特に25歳から34歳までの妻のいる世帯(若年層世帯)の共働き率は、近年顕著に増加傾向にある。また、結婚や出産を機にそれまで就労していた女性の約7割が退職しており、その後の出産後の就業については、パートタイムで再就職する割合が増加している。こうした若年層の子育て世帯の平均所得金額は300万円から500万円程度と見込まれている。 - ニ 働き方の多様化については、高度経済成長期に定着した日本型雇用慣行が壊れ、企業と従業員の間の安定的な関係が揺らぎ、正規雇用者の割合が大幅に低下している。また、パート・派遣労働者等の非正規雇用者の割合が急上昇するなど、雇用形態の多様化が進んでいる。
- ホ 格差問題については、近年関心が高まっており、とりわけ雇用の分野での格差はより複雑な問題を抱えており、多様な雇用形態が可能になる中で、雇用形態の違いによる所得格差がより鮮明になっている。
(4)今後における所得税の負担構造のあり方についての考察(第4章)
上記(1)及び(2)で述べたとおり、消費税導入を含む税制改革以降における累次の所得税の改正により所得税の財源調達機能及び所得再分配機能は、税制改革以前と比較して著しく低下している現状にある。こうした現状を踏まえ、今後の所得税の負担構造の見直しに当たっては、今後の税体系全体における消費税の役割も踏まえつつ、社会保障制度とともに所得再分配を担う存在として、所得税の役割を適切に発揮させていくことが一層重要となる。また、個々人や社会全体の活力を引き出す観点から、個人の経済・社会活動の多様な選択について、税制がこれをできる限り阻害しないよう中立的な仕組みにしていくとともに、国民に分かりやすい簡素な仕組みとする必要がある。上記(3)の経済・社会の構造変化を踏まえて、所得税の負担構造のあり方について考察する。
- イ 個人単位課税の下では、基礎的な人的控除は、総所得金額等から家族に関わる様々な控除として一定額を差し引かれるものであり、家族構成など個々人の生活上の事情を斟酌して、納税者の担税力に即して超過累進税率により課税するものであることから、稼得した所得は、個人の総合的担税力を表すものとして最も優れており、所得減殺要因を勘案する基礎的な人的控除は、所得控除が適切な制度であると考えられる。しかしながら、近年、個々人の生活事情も様々であり、配慮すべき事情についての国民の価値観も多様化していることから、基礎的な人的控除の見直しについては、所得控除や税額控除の意義等を踏まえ、少子・高齢化の進展、家族形態の変化、女性の社会進出などの経済・社会の構造変化に対応して、税額控除を採用することが適当かどうかを含め検討するとともに、制度が相当複雑化している割増・加算措置の所得控除の廃止を含めた見直しにより基礎控除に簡素化・集約化する必要があると考える。
- ロ 配偶者控除等については、個人単位課税を徹底し「家族の就労に対する中立性」や「世帯単位での税負担の公平」を図る等の観点から、配偶者控除を廃止し、社会人が就労し所得を得ると一人ひとつの基礎控除を取得し、そして結婚し家族を形成した場合には、夫婦の働き方如何にかかわらず、夫婦それぞれが基礎控除を持ち、その基礎控除二つ分の控除額を享受する「移転的基礎控除」の導入を検討する必要があると考える。具体的には、配偶者控除及び配偶者特別控除を廃止し、夫婦それぞれが各々に基礎控除を持ち、一方の配偶者(妻)の所得が、基礎控除の額に達しなかった場合には、その妻の所得と基礎控除の額の差額を他方の配偶者(夫)の基礎控除の額に加算できる制度である。なお、この制度は、配偶者の所得を把握する必要があることから、簡素で分かりやすい制度とするため、二段階程度の簡素な形での消失控除による移転的基礎控除を検討する必要がある。
- ハ イで述べたとおり、総合所得税においては、扶養控除を含む基礎的な人的控除は、所得控除が適切な制度であると考えられる。しかしながら、少子化が進行する中、子育て世代に係る構造変化が大きく変貌し、子育て世代の年齢層の人口は既に減少に転じていることを踏まえれば、真に必要な世帯に対し経済的支援を集中するなど、子育て支援策への集中・重点化を図ることが重要である。扶養控除については、人的控除の簡素化・集約化の要請に加え、低所得者層である若年の子育て世帯への税負担軽減による支援の観点からは所得控除としての扶養控除には限界があることから、扶養控除に係る割増や加算措置を含め廃止し、税額控除に一本化すべきであると考える。これは、扶養控除の廃止、次に述べる給与所得控除や税率構造の見直し等により得た限られた財源を、単身・夫婦世帯を含む中高所得者世帯から低所得者の子育て世帯へと財源を集中的にシフトさせるものであるといえる。なお、税制措置であることから非納税者にはその効果が及ばない、あるいは税額控除額に満たない低所得者には効果が小さくなるといった問題がある。このような低所得者世帯には、低所得者層を対象とした個人住民税からの税額控除や非納税者の子育て世帯に対する現物給付等の子育て支援策が考えられる。
- ニ 給与所得控除については、働き方が多様化する中で、人々の働き方やその選択に中立的な税制とする観点から、給与所得控除の性格(勤務費用の概算控除及び負担調整特別控除をあわせ持つ性格)、勤務実態にかかわらず一律に控除されるという問題や働き方の多様化に伴う実額控除の拡大の要請を踏まえ、現行の給与所得控除の枠組み全体を勤務に伴う経費の概算控除と捉えた上で、より純粋な概算控除に向けて、「定額控除」と「定率控除」を組み合わせた制度とすることが適当であると考える。具体的には、給与所得控除の最低保証額をパート等の賃金水準の伸び等を勘案して引上げた額を「定額控除」部分とし、この定額控除を「勤務費用の概算控除」と「負担調整特別控除」の双方を加味したものと整理する。その上で、この定額控除の額を超える部分については、給与収入に応じて逓減する「定率控除」とし一定の給与収入の水準で概算控除の頭打ち(定額)とする。なお、今後の超高齢化社会において、働き方が多様化し就業しながら年金収入を得る高齢者が多くなり、世代間・世代内の公平を徹底する観点から、公的年金等控除の見直し等を行うほか、給与所得控除と公的年金等控除を統合した概算控除とするといったことも検討すべきであると考える。
- ホ 税率構造については、所得税の財源調達機能や所得再分配機能が低下している現状を踏まえると、今後、消費税率の引上げにより公的負担全体の負担構造が現在よりも逆進的となる中、所得税をさらに軽減する余地はなく、上記の基礎的な人的控除や給与所得控除等の見直しによる財源を活用し、所得再分配機能を発揮させるとともに、子育て支援や所得格差の是正等の観点から、低所得者の夫婦と子供からなる世帯よりも単身世帯や夫婦世帯を含む中高所得者世帯が、相対的により大きな負担増となるよう見直す必要があると考える。
3 おわりに
消費税の導入や消費税率の引上げに伴う税制改革以降、基礎控除等の人的控除の引上げや給与所得控除の見直し等のほか、所得税率の刻み数を減少させ税率の引下げとブラケット幅を拡大する等の累次の改正の結果、国税収入に対する所得税収の割合が低下するとともに、国民所得に対する所得税の租税負担率も低下し主要諸外国と比較しても最も低い水準となっており、所得税の財源調達機能が低下している。また、所得税の納税者の大多数を占める給与所得者について、給与収入階級の分布状況等を見ると給与収入500万円を超える中堅所得者層を中心に累進性が大幅に低下している。更に、雇用者所得等の伸びがマイナスないし鈍化傾向にある経済状況においては所得税の累進性が低下していること等から経済自動安定化機能が弱くなっている。こうした現状を踏まえると、今後の所得税の「あるべき姿」を考える上で、これ以上、基幹税としての所得税の機能を劣化させる余地はない状況にあるといえる。
また、終身雇用等の日本型雇用慣行が揺らぎ、働き方が多様化し共働き世帯が増加するなど、経済・社会の構造変化が激しく変貌しており、こうした構造変化に対応した所得税の負担構造となっていないのが現状である。
今後、消費税率の引上げにより公的負担全体の負担構造が現在よりも逆進的となる中、税制の基本原則である公平・中立・簡素を踏まえ、所得税の負担構造の見直しについては、経済の活力維持の要請も踏まえつつ、消費税率の引上げによる分配構造の変動に対し、所得再分配機能を適切に発揮させる。つまり、一定の所得水準以下は負担減、それ以上は負担増とすることにより、所得税の累進度を高めることを通じ、公的負担全体の累進度をある程度維持する必要があると考える。
また、こうした負担構造の見直しに当たっては、特に、少子・高齢化の進展、家族形態の変化、働き方の多様化や格差問題といった経済・社会の構造変化への対応等の観点から行われる諸控除、給与所得控除及び税率構造の見直し並びに子育て支援措置を適切に組み合わせる必要がある。その際、「単身・夫婦世帯を含む中高所得者世帯」から「低所得者の子育て世帯」へと財源をシフトさせるといった基本的考え方に基づき、扶養控除の廃止等により確保される財源を用いた税額控除の導入等により、真に経済的支援を要する子育て世帯に集中的な支援を実施する。
特に、基礎的な人的控除等の諸控除の見直しについては、
- (イ) 少子・高齢化、人口減少社会が進行する中、ライフステージを通じて広く公平に負担を分かち合うため、これまでの個々人の生活事情に配慮してきた結果、様々な歪みを生じさせている諸控除を根本から整理し、様々な要因による所得をできるだけ課税所得に取り込むこと。
- (ロ) その上で、所得税のあるべき姿は、将来の社会の担い手である子供を社会全体で育むとの観点から、ライフステージの中での人々が迎える就労、結婚、出産、育児といった様々な局面に応じ、簡素化・集約化された基礎控除と税額控除や概算控除化された給与所得控除により、必要な配慮を行う。例えば、個人が就労し社会人となり、最低生活費を超える収入がある場合は、一納税者として税を負担する(基礎控除と給与所得控除の概算控除化)。その後、結婚し夫婦となり、子供を生み育てる礎となる「家族」を築く場合、これに一定の価値を認め、家族の働き方如何にかかわらず、税負担が軽減される(基礎控除の共有化)。更に、夫婦が子供を生み育てる期間に入ると税負担が集中的に軽減され、扶養期間終了後は、子育ての社会的費用を社会全体で賄うとの観点から、再び他の世代と同様の税負担を負う(扶養控除の税額控除化)。
- (ハ) これは、基礎控除の共有化・扶養控除の税額控除化により、結婚・出産・育児を支援することを通じ、「子育ての社会化」を進めるとともに、少子化への歯止めにも資することになる。
また、給与所得控除の見直しについては、給与所得控除の性格、勤務実態にかかわらず一律に控除されるという問題点や働き方の多様化に伴う実額控除の拡大の要請を踏まえ、現行の給与所得控除の枠組みを全体として勤務に伴う経費の概算控除と捉えた上で、その仕組みについては、定額控除の部分と定率控除の部分による概算控除とし、給与収入の一定以上を限度額とする頭打ちを設ける。
いずれにせよ、今後における所得税の負担構造の実際の改正においては、経済・社会の構造変化に対応して、租税の基本原則である公平・中立・簡素といった視点を踏まえ、現行の税制及び財政状況、経済社会情勢、各種所得者の所得及び税負担の状況、国民生活の現状、国民の意識など様々な要因を勘案しつつ、社会保障制度、消費税など他の税制度と併せたところで検討を行い、国民的な議論並びに平成21年3月の所得税法等一部改正法附則で示された税制改革の道筋及び基本的方向性等を踏まえて、消費税負担の引上げ等を含む税体系全体の見直しを行っていく必要があると考える。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
論叢本文(PDF)・・・・・・2,516KB

