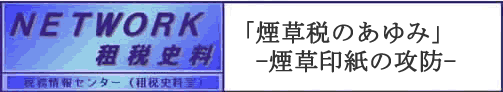
現在、たばこにはたばこ税が課されていますが、昭和60年(1985)にたばこ消費税が創設されるまで、長い間、たばこには専売制度が採られていました。少し複雑なのですが、この専売制度の前にもたばこ税(明治時代には煙草と漢字で書かれていました。以下「煙草」と言います。)がありました。今回は、この煙草税について説明します。
そもそも、全国で統一された煙草への課税は、明治8年(1875)の雑税整理(旧幕時代から続く各地の約1,500種類の雑税を全国的に整理し、国税と地方税の区別に先鞭をつけた税制改革)に伴い公布された煙草税則まで遡ります(翌年施行)。それまで、煙草へは各地で独自に課税されていました。この税則が出された理由は、当時の日本の租税体系が地租に偏りすぎていたため(明治9年度の段階で租税収入全体の8割を占めていた)、それを多少なりとも軽減することでした。年は遡りますが、明治6年の地租改正条例では、煙草などの物品税による収入が年間200万円を超えた場合、地租率を1%まで下げることを宣言していました。当時の日本で、煙草は有望な税源の一つとみなされていたといえるでしょう。
煙草税は、煙草営業税と製造煙草税とからなり、煙草営業税は卸と小売とに、それぞれ年額10円、5円を課すこととしました。製造煙草税の方は従価税で、定価5銭未満だと1厘、同じく10銭未満だと5厘、20銭未満は1銭、30銭未満は2銭、40銭未満は3銭、と決められていました。製造煙草税は印紙で納税することとされ、印紙は売買の際に貼付するように規定されていましたが、その煩雑さ等も影響し、印紙の不貼付、流用という脱税が横行しました。煙草税則実施から明治15年までの煙草税の平均歳入は24〜25万円、うち煙草営業税が約20万円、製造煙草税は4〜5万円を占めるに過ぎなかったのです。
壬午事変(明治15年)などの日清関係の緊張による軍備拡張のため、その財源として酒税とともに煙草税の増税及び課税方式の改正(営業人の中に製造人が加えられる、印紙税の課税標準を卸売定価とし、印紙貼付部には製造人の印章による消印をすることなど)が明治15年(翌年施行)に行われましたが、脱税の横行により、税収を上げられませんでした。大蔵省はその理由を
 税率が低価格な煙草ほど高率となるため、脱税を誘引しやすい
税率が低価格な煙草ほど高率となるため、脱税を誘引しやすい 特に帯状の印紙を使うと、破らずに抜き取ることで印紙の流用が可能となる
特に帯状の印紙を使うと、破らずに抜き取ることで印紙の流用が可能となる 製造人の手を経ないで無印紙の煙草が流通する事案が続出した
製造人の手を経ないで無印紙の煙草が流通する事案が続出した
と分析しています。そのため、明治21年にも大幅な改正(すべての煙草について定価の20%とし、帯型印紙を廃止するなど)が行われましたが、密造・密売による脱税を根絶することはできませんでした。
日清戦争後(明治27年〜28年)、日本の財政は急激に増大し、増税の必要がでてきます。中でも、酒税の増徴、営業税の創設と並んで、煙草税は有力な税源とみなされましたが、脱税の横行が問題になりました。そこで、課税方法を改めることとし、印紙方式から、すでにフランスなどで導入されていた専売方式へ変更することとなったのです。明治29年に葉煙草専売法が発布され、同31年より施行されました。これにより、煙草税則が廃止されます。さらに、明治37年、日露戦争の戦費を調達するために、煙草の完全専売制度へ移行されました。
明治時代の煙草税から専売制度への移行の過程は、軍事費やインフラ整備費などで財政が急速に拡大する中での脱税との戦いの歴史とも言えるでしょう。
(研究調査員 今村 千文)





