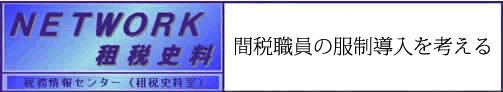
明治33年(1900)2月から導入された間税職員の服制について、租税史料室の展示では、大体、次のよう解説している。
江戸時代の末期に、欧米諸国との間で結ばれた修好通商条約は、治外法権を認め、関税自主権を否定されるなど、日本にとっては不利な内容に満ちていた。明治に入り、いく度もの条約改正交渉を重ね、明治27年、陸奥宗光外相のときに結ばれた日英改正条約により、治外法権が撤廃されることになり、日清戦争後の明治32年7月から発効した。同時に、それまで横浜港などの居留地に限られていた外国人の居住が、国内どこでも自由となり、内地雑居が実施された。内地雑居により外国人にも国内税法が適用されることになり、明治29年に創設された税務署では、外国人に直接対応する間税職員に、より一層規律ある服装が望まれるようになったところから、明治33年1月、間接国税の検査に従事する職員に服制の導入が発令され、同年2月1日から実施に移されたのである、と。
しかし、この服制導入解説には、外国人との接触は直税・間税などの税務職員全体にかかわる事柄であるから、なぜ間税職員のみに服制が導入されたのか、という疑問について充分な答えを見出せない。
当時、間接税の中心は酒税である。酒税の収入は明治32年、それまで首座にあった直接税の中心地租を超えて初めてトップとなり、その後は、基幹税としての地位を長く保った。したがって、間税職員といえば大概は、酒税検査などを執行する職員を指す。一方、酒税の納税者は酒造家である。酒造家は仕込みの終わった酒を売り、その代価から酒税の相当分を納税する。すなわち、酒は酒造家の個人財産であるとともに、酒には国税の酒税が含まれるから、明治29年に成立した酒造税法の下で、間税職員による酒税確保のための検査は、厳格を極める必要があった。
酒税検査は単に、納税期限前の造石量検査だけで済むわけではない。すなわち、蒸米と麹で酒母(しゅぼ)を造り、酒母が持つ強力な発酵作用を原動力として、これに蒸米と米麹と水を、発酵の状態を見極めつつ、日を追って3回に分けて添加し、増量して、醪(もろみ)を造るという、初添え、仲添え、留添えの三段仕込み、酒槽(さけふね)で醪を濾過する搾り、その後の滓(おり)引き、完成品とするための火入れ、といった各醸成過程、これらの醸成過程で使う様々な酒道具とその操作法などに加え、原料・販売・労働にかかわる各種な帳簿、造酒の実際を手掛ける杜氏や酒男などの技量にいたるまで、造酒の全範囲に精通した上で、納税者である酒造家を直接の相手として、細部にわたり正・不正を詳細に検査しなければ、厳格な酒税の執行は望めない。
服制導入から1か月後の明治33年3月、政府は間接国税犯則者処分法を成立させ、間税の犯則者に対する厳格な処分法を定めた。同法制定後の4月、大蔵省主税局長目賀田種太郎は「間税検査員の技術に関する講習」に際し、間税職員の服制導入理由について大体、次のように訓示している。
此ノ服制ニ付テモ各員ハ少シク間税検査ナル職務ノ何タルヤヲ玩味シ考究スヘキモノアリ、何トナレハ間税ノ事務ハ直税ト異ナリ、専ラ事実ノ発生ニ基キテ税ヲ課スルモノナルカ故ニ、庁外ニ於テ執務スルコト其ノ多キニ居リ、加之間税ノ検査ナルモノハ能ク其ノ系統脈絡ヲ糺ストキハ、査定以外ニ所謂間税ノ監視ヲモ含メルモノニシテ、即査定ハ単ニ課税物件ノ数量ヲ確定シ、監視ハ其ノ数量ヲ定ムルト同時ニ課税物件ノ逸脱ヲ監視スルニ在リ、而シテ這般間税官吏ノ服制ヲ定メラルヽニ当リ、大蔵大臣ガ閣議ヲ請ハレタル要領ノ一ハ、己ニ内地雑居ニモ至リタル今日ニ当リ、間税ノ監視即間税警察ノ職務執行上、世人一般ニ対シテ其ノ官吏タル品位ヲ保タシメンカ為メ、一ハ又庁外ニ於ケル執務ノ便ヲ与ヘンカ為メニ服制々定ノ必要アリト云フニアリ
間税警察とは、課税物件の逸脱を取り締ることである。酒税では間税職員が酒造場で、造酒の専門家で納税者でもある酒造家を相手に、課税物件である造酒の全範囲を視野に入れ、その細部にわたり正・不正を検査し、取締りに当たることである。明治33年4月の「間税検査員の技術に関する講習」が、間接国税犯則者処分法の制定に伴い、間税職員に課税物件の取締技術、すなわち、造酒の全範囲を対象とした、酒税の検査技術を修得させるところにあったことは指摘するまでもない。ここに、間税職員には酒税の執行に当たり、世間一般に対しても、納税者である酒造家に対しても、「官吏タル品位ヲ」保つため、及び「執務ノ便ヲ」得るための服装が望まれるようになったのである。
したがって、間税職員の服制導入を促した理由は、内地雑居による外国人への国内税法の適用を主因とするよりも、間接国税犯則者処分法の制定による厳格な酒税執行の必要性を主因とする、と考えることができる。
(研究調査員 鈴木芳行)


