連帯納付義務の承継等に関する諸問題
岩淵 浩之
税務大学校
研究部教授
要約
1 研究の目的(問題の所在)
相続税法34条は、相続税及び贈与税(以下「相続税等」という。)の徴収を担保するため、本来の納税義務者以外の者に、連帯して納付する責任(連帯納付義務)を負わせている。同条では、連帯納付義務の対象となる納付義務者やその責任の範囲(受忍限度額)を規定しているにすぎず、連帯納付義務の成立や確定について明文の規定は置かれていない。
このような相続税等の連帯納付義務について、贈与の発生後、当該贈与に係る贈与税の法定申告(納付)期限前に、贈与者が死亡した場合に、その相続人が、被相続人である贈与者(連帯納付義務者)が死亡した後に成立した附帯税について、連帯納付義務を負うか否かが問題となっている。
国税通則法(以下「通則法」という。)5条1項は、相続人は、その被相続人に課されるべき国税(相続開始時に、納付義務は成立しているが、納付すべき税額が確定していない国税)等を納める義務を承継すると規定しており、被相続人の死亡後に成立した附帯税に係る連帯納付義務は、承継の対象とならないようにもみえる。
他方、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継するとした民法896条の規定からすれば、贈与者は将来附帯税が発生した場合に、その連帯納付義務を負うべき地位にあるとみることもできるため、この連帯納付義務を負うべき地位を相続により承継すべきものとも考えられる。
以上のような状況から、連帯納付義務者の相続人に対し、上記の附帯税に係る連帯納付義務の履行を求めることについて、その適否及び法的整理を明らかにする必要が生じている。
2 研究の概要
(1)相続税等の連帯納付義務
イ 連帯納付義務の意義
わが国の相続税は、納付の引当てとなる相続財産が分割され、各人別に納税義務が課されると、その中に無資力者等がいる場合は徴収不足を来すおそれがあり、税負担の公平を保てない場合が生じ得る(贈与税についても、納税義務を受贈者に限定すると、徴収不足を来し、税負担の公平を保てない場合が生じ得る。)。
そこで、これらの事態に対処するため、相続税法34条の連帯納付義務の制度が設けられており、その意義(目的)は、相続税等の徴収の確保を図ることにある。
ロ 連帯納付義務の性質
相続税等の連帯納付義務は、本来の納税義務に対して、補充性はなく、付従性があり、本来は納付する義務のない他の相続人等の納税義務を負担するものである。
また、連帯納付義務は、相続等により受けた利益等を限度に納付責任を負うのに対し、民法の連帯債務の規定を準用する通則法8条の連帯納税義務は、各納税義務者が、別個独立の納税義務を制限なく負担することから、相続税等の連帯納付義務と民法上の連帯債務とは、その性質を異にするものである。
以上によれば、相続税等の本来の納税義務者が負担する納税義務と連帯納付義務の関係は、民法上の主たる債務と連帯保証債務の関係に類似するものであり、連帯納付義務は本来の納税義務を担保するために課される特別の責任であると解される。
ハ 相続税等の連帯納付義務の成立時期
![]() 連帯納付義務の担保的機能と成立時期
連帯納付義務の担保的機能と成立時期
相続税等の連帯納付義務は本来の納税義務の担保的機能を有することから、本来の納税義務と連帯納付義務の成立時期は同一であるべきものと考えられる。
![]() 連帯納付義務の担税力と成立時期
連帯納付義務の担税力と成立時期
納税義務は課税要件の充足、すなわち担税力を基準に成立するとされており、連帯納付義務については、相続等により財産を取得した時点で担税力が生じるとみることができるため、連帯納付義務の成立時期は、本来の納税義務と同一であると考えることができる。
![]() 連帯納付義務の裁判例と成立時期
連帯納付義務の裁判例と成立時期
最判昭55.7.1民集34・4・535頁(以下「最高裁昭和55年判決」という。)は、相続税の連帯納付義務の確定について、本来の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずると判示しており、学説上もこの考え方が有力である。
また、下級審であるが、東京地裁平成25年3月21日判決は、贈与税の連帯納付義務の成立及び確定は、主たる納税義務の成立及び確定という事実に照応して法律上当然に生ずると判示している。
これらの裁判例によれば、連帯納付義務の成立については、相続税等の本来の納税義務の成立という事実に照応して、法律上当然に生ずるものと考えることが自然である。
![]() 小括
小括
上記![]() から
から![]() によれば、相続税等の連帯納付義務の成立・確定は、本来の納税義務の成立・確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものと考えることが相当である。
によれば、相続税等の連帯納付義務の成立・確定は、本来の納税義務の成立・確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものと考えることが相当である。
ニ 相続税等の連帯納付義務の範囲(連帯納付義務は附帯税に及ぶか)
附帯税は、本税たる国税債権に附加して負担せしめる国税の一種であり、いずれもその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税であるとされている(通則法60条4項、69条)。この規定により、各税法上「何税」と規定されている場合には、原則としてその税に係る附帯税が含まれることになる。
また、相続税法51条の2は、連帯納付義務者が本来の納税義務者の相続税を納付する場合、延滞税に代えて利子税を納付することとしており、連帯納付義務の中に延滞税が含まれることを前提とする規定となっている。
さらに、裁判例でも上記の内容等を理由として、連帯納付義務には延滞税が含まれると判示したものがあることから、相続税法34条の連帯納付義務は、本税のほか附帯税に及ぶと考えることが相当である。
ホ 附帯税の連帯納付義務を負うべき地位の成立
![]() 本来の納税義務者の本税と附帯税の法的関係
本来の納税義務者の本税と附帯税の法的関係
相続等により財産を取得した場合、本来の納税義務者には、相続税等の本税の納税義務が成立し、これにより、本税を法定期限までに申告・納付する義務が成立する。
そして、上記の申告・納付義務の成立により、法定期限までに申告・納付義務を履行できなければ附帯税が課せられる法的責任、すなわち、相続税等の附帯税を負うべき地位が成立する。
![]() 連帯納付義務者の本税と附帯税の法的関係
連帯納付義務者の本税と附帯税の法的関係
相続税等の本来の納税義務者が負担する納税義務と連帯納付義務の関係は、民法上の主たる債務と連帯保証債務の関係に類似すること、そして、相続税等の連帯納付義務は附帯税に及ぶことから、本来の納税義務者に、相続税等の本税の納税義務が成立すれば、連帯納付義務者に本税の連帯納付義務が成立し、本来の納税義務者に相続税等の附帯税を負うべき地位が成立すれば、連帯納付義務者に附帯税の連帯納付義務を負うべき地位が成立する。
この場合、連帯納付義務の成立は、本来の納税義務の成立という事実に照応して、法律上当然に生ずることから、下図〔1〕から〔5〕は、全て同時に成立し、下図〔4〕の本税の連帯納付義務が成立すれば、同時に、下図〔5〕の附帯税の連帯納付義務を負うべき地位が成立すると考えることができる。
これらの関係を図で表すと次のようになる。
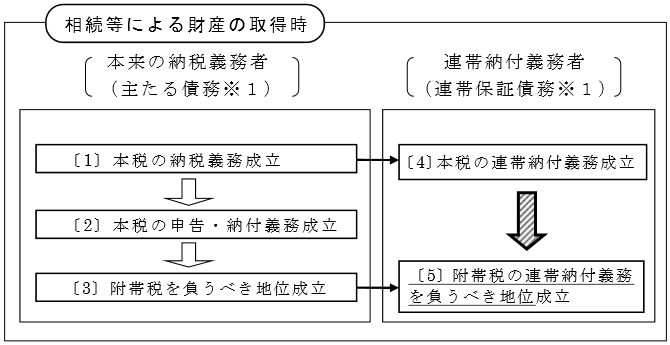
※1 相続税等の本来の納税義務者が負担する納税義務と連帯納付義務の関係は、民法上の主たる債務と連帯保証債務の関係に類似する。
※2 上記〔1〕から〔5〕は、相続等による財産の取得が発生すると全て同時に成立するため、〔4〕が成立すれば自動的に〔5〕が成立することとなる。
![]() 小括
小括
本研究課題では、相続開始時において、本来の贈与税の法定申告期限・法定納期限が到来していないため、贈与税に係る附帯税の納税義務は成立しておらず、従って、附帯税の連帯納付義務も成立していない。
しかしながら、贈与財産の取得後に相続が開始しているため、相続開始前に、贈与税本税の納税義務が成立しており、従って、その本税の連帯納付義務も成立していることとなる。そして、本税の連帯納付義務が成立しているため、連帯納付義務者に附帯税の連帯納付義務を負うべき地位が成立していると考えることができる。
そうすると、この附帯税の連帯納付義務を負うべき地位が、相続による承継の対象になるか否かが問題となる。
(2)通則法5条1項と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位
納税義務は担税力を基準として課され、その意味で納税義務者の個別性が強調されることから、租税法律主義に照らし、みだりに納税義務の承継を認めることは適当でなく、相続により特定の納税義務を承継するためには、通則法5条1項の要件を満たすことが必要と考えられる。
通則法5条1項は、相続人は、被相続人に課されるべき国税等を納める義務を承継すると規定するのみで、被相続人が有していた税法上の地位が承継の対象になるか否かについて明文の規定を置いていない。
しかしながら、通則法5条1項の立法趣旨からすると、同項と民法896条の相続による承継の範囲は同一であるとみることができるため、通則法5条1項の課されるべき国税等には、原則として、当該各国税に係る一切の税法上の地位が含まれると考えることが相当である。
そうすると、このような通則法5条1項の規定に照らし、附帯税の連帯納付義務を負うべき地位が、承継の対象となる「税法上の地位」に当たるか否かが問題となる。
そこで、上記のとおり、通則法5条1項と民法896条の相続の効力(相続による承継の範囲)は同一であるとみることができるため、附帯税の連帯納付義務を負うべき地位について、学説及び裁判例が豊富な民法の相続の効力に関する規定に照らし、その承継の対象に該当することとなれば、当該地位は通則法5条1項により承継すると考えることができる。
(3)民法における相続の効力と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位
イ 財産法上の法的地位と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位
民法896条の規定により、相続人は、相続の開始により、被相続人の一身専属的な権利義務を除き、物権、債権、債務、無体財産権、その他明確な権利義務といえないものでも、財産法上の法的地位といえるものであれば、全て包括的に承継すると解されている。そして、租税法も財産法と同種の性質を有しているため、租税法の規定により成立する権利義務は、上記の財産法上の法的地位に該当すると考えられる。
附帯税の連帯納付義務を負うべき地位とは、通則法及び相続税法を根拠として成立し、将来において、本来の納税義務者に附帯税が発生した場合に、その附帯税について連帯納付義務を負うこととなる法的責任をいうことから、当該地位は相続により承継する財産法上の法的地位に該当するものと考えられる。
ロ 一身専属的な権利義務と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位
民法896条本文は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継の対象としつつ、その例外として、被相続人の一身専属的な権利義務は相続人に承継されないものとしている(同条ただし書)。この一身専属的な権利義務とは、被相続人の人格、身分等と強く結びついたものであり、相続人に行使・帰属等を認めること又は義務を負わせること等がふさわしくないものが該当する。
![]() 租税債務の性質と一身専属的な権利義務
租税債務の性質と一身専属的な権利義務
附帯税の連帯納付義務を負うべき地位を含む租税債務は金銭債務であり、その性質は、被相続人の人格、身分等と強く結びついたものとみることはできないため、一身専属的な権利義務に該当しないと考えられる。
![]() 民法上の保証債務と相続税等の連帯納付義務の相続性
民法上の保証債務と相続税等の連帯納付義務の相続性
相続税等の連帯納付義務の性質は、民法上の連帯保証類似の債務と解されている。そして、連帯保証債務も保証債務の類型に属するため、相続税等の連帯納付義務が相続性を否定される民法上の保証債務の性質と同質のものであるか否かが問題となる。
民法上の保証債務では、通常の保証債務(連帯保証を含む。)が相続性を有することに異論はないが、身元保証債務など被相続人との個人的信用関係が契約締結の基礎となり、かつ、責任の限度額等が不明確であるなど責任を負う範囲が広範すぎる場合は、一身専属性があるとして、判例上、相続性が否定されている。
相続税等の連帯納付義務は、相続により受けた利益を限度とするなど、その責任の範囲は限定されており、民法上の保証債務の相続性の基準からみても、一身専属性はないとみることが相当である。
![]() 加算税と一身専属的な権利義務
加算税と一身専属的な権利義務
一般に刑罰は一身専属性があるとして相続による承継の対象とされていないことから、制裁的性格を有する加算税が一身専属的な権利義務に該当するか否かが問題となる。
この点について、租税債務のうち加算税は、刑罰としての性格を有しておらず、申告秩序維持のための納税義務違反に対する行政罰と解されるものであり、明らかに刑罰には当たらないことから、一身専属性はないと考えられる。
ハ 小括
上記イ及びロによれば、附帯税の連帯納付義務を負うべき地位は、通則法及び相続税法を根拠とするため財産法上の法的地位に該当し、一身専属的な権利義務にも当たらないことから、民法896条の規定に照らし、相続による承継の対象に含まれるとみることが相当である。
そうすると、通則法5条1項と民法896条の相続による承継の効力は同一であるとみることができるため、附帯税の連帯納付義務を負うべき地位は、通則法5条1項の要件を満たし、相続による承継の対象に適するものと考えることができる。
3 結論
相続税等の連帯納付義務は、相続税等の徴収の確保を目的とする特別の責任で、その性質は民法上の連帯保証債務に類似する。この連帯納付義務の成立は、本来の納税義務の成立という事実に照応して、法律上当然に生ずるもので、その責任の範囲は、本税のほか附帯税に及ぶ。
本研究課題では、相続開始前に、相続税等の本税の連帯納付義務が成立しているため、その税法上の地位である附帯税の連帯納付義務を負うべき地位も成立しているとみることができる。
次に、通則法5条1項と民法896条の相続による承継の範囲は同一とみることができるため、通則法5条1項で承継の対象となる課されるべき国税等には、当該各国税に係る一切の税法上の地位が含まれると考えられる。
また、附帯税の連帯納付義務を負うべき地位は、民法(相続関係)の規定に照らし、相続による承継の対象に該当することから、通則法5条1項の承継の対象に適するものである。
本研究課題では、相続税等の本税の連帯納付義務が通則法5条1項の「課されるべき国税」に該当し、その税法上の地位として同時に成立する附帯税の連帯納付義務を負うべき地位とともに相続人に承継されると考えることができる。
したがって、相続税等の連帯納付義務者の相続人は、将来、本研究課題における相続税等の附帯税が発生した場合に、当該附帯税の連帯納付義務を負うこととなる。
目次
| 項目 | ページ |
|---|---|
| はじめに | 113 |
| 1 問題の所在 | 113 |
| 2 研究の進め方 | 114 |
| 第1章 相続税・贈与税の意義と課税方式 | 115 |
| 第1節 相続税の意義と課税方式 | 115 |
| 1 相続税の意義 | 115 |
| 2 相続税の課税方式 | 116 |
| 3 わが国における相続税の課税方式 | 119 |
| 第2節 贈与税の意義と課税方式 | 123 |
| 1 贈与税の意義 | 123 |
| 2 贈与税の課税方式 | 123 |
| 3 わが国における贈与税の課税方式 | 124 |
| 4 小括 | 124 |
| 第2章 相続税等の連帯納付義務の諸問題 | 126 |
| 第1節 制度の概要と沿革 | 126 |
| 1 相続税法34条の連帯納付義務の概要 | 126 |
| 2 相続税等の連帯納付義務の沿革 | 131 |
| 第2節 連帯納付義務の意義及び性質 | 138 |
| 1 相続税等の連帯納付義務の意義 | 138 |
| 2 相続税等の連帯納付義務の性質 | 141 |
| 3 相続税と贈与税の連帯納付義務の同一性 | 153 |
| 第3節 連帯納付義務の成立及び確定 | 154 |
| 1 相続税等の本来の納税義務の成立及び確定 | 155 |
| 2 相続税等の連帯納付義務の確定 | 157 |
| 3 相続税等の連帯納付義務の成立 | 166 |
| 第4節 連帯納付義務と附帯税 | 170 |
| 1 附帯税の性質 | 170 |
| 2 連帯納付義務の責任の範囲(連帯納付義務は附帯税に及ぶか) | 171 |
| 3 附帯税の連帯納付義務を負うべき地位の成立 | 174 |
| 第3章 納税義務の承継と税法上の地位 | 178 |
| 第1節 納税義務の承継の制度の概要 | 178 |
| 1 納税義務の承継(概説) | 178 |
| 2 納税義務の承継に関する制度の概要 | 179 |
| 第2節 納税義務の承継の沿革と立法趣旨 | 182 |
| 1 納税義務の承継の沿革等 | 182 |
| 2 納税義務の承継規定の立法趣旨 | 186 |
| 第3節 納税義務の承継の効果 | 188 |
| 1 相続による税法上の地位の承継 | 188 |
| 2 納税義務の承継の効果に関する学説と裁判例 | 189 |
| 3 小括 | 190 |
| 第4章 民法における相続の効力と保証債務の相続性 | 192 |
| 第1節 民法における相続の効力 | 192 |
| 1 被相続人の財産に属した一切の権利義務 | 192 |
| 2 一身専属的な権利義務 | 193 |
| 第2節 民法上の保証債務の相続性 | 193 |
| 1 相続による債務の承継 | 194 |
| 2 身元保証債務の承継 | 195 |
| 3 信用保証債務の承継 | 196 |
| 4 保証債務の相続性に関する判断基準 | 196 |
| 第5章 研究課題の考察 | 198 |
| 第1節 研究課題の概要 | 198 |
| 1 研究課題の前提(事例の概要) | 198 |
| 2 研究課題の論点 | 199 |
| 第2節 研究課題の考察 | 200 |
| 1 相続税等の連帯納付義務の意義及びその性質 | 200 |
| 2 相続税等の連帯納付義務の成立時期 | 202 |
| 3 相続税等の連帯納付義務の範囲(附帯税関係) | 204 |
| 4 附帯税の連帯納付義務を負うべき地位の成立 | 205 |
| 5 通則法5条1項と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位 | 207 |
| 6 民法上の相続の効力と附帯税の連帯納付義務を負うべき地位 | 210 |
| 7 結論 | 214 |
| 結びに代えて | 215 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

