相続税と所得税の関係について-「生保年金二重課税事件」を素材とした考察-
篠原 克岳
税務大学校
研究部教授
要約
1 研究の目的
相続税と所得税の関係をみると、相続税法が相続財産を時価で課税する一方、所得税法は相続財産のキャピタル・ゲイン(含み益)につき相続時には原則として課税を繰り延べ、相続後に生じたキャピタル・ゲインと合わせ一括して課税している(取得費等の引継ぎ)。前者は相続による経済的価値の移転に着目した課税であり、後者は資本所得への課税であり、従来理論的には、両者に「二重課税は存在しない」と整理されてきた。
ところが、いわゆる「生保年金二重課税判決」(最判H.22.7.6)は、所得税法9条1項16号の趣旨を「相続税・贈与税と所得税の二重課税を排除したもの」と解した上で、年金型生命保険契約に基づく年金支給額について「年金支給額のうち相続税の課税対象となる部分については所得税法9条1項15号〔現16号〕により所得税の課税対象とはならない」旨判示した。本判決は生保年金の取扱いにつき二重課税の存在を認めたものであり、相続税と所得税の関係についての従来の理解に根本的な疑義を投げかけている。
そこで本研究では、上記判決を素材として相続税と所得税の関係について改めて理論的な検討を行い、また、問題点への対処につき検討を行った。
2 研究の概要
(1)相続財産に付着する「潜在的所得税債務」の問題(本文中【図7】参照)
イ 相続税と所得税の「棲み分け」
相続財産が相続時点で有する含み益αへの所得課税は、原則として相続時には繰り延べられ、相続人がこれを第三者に譲渡した時点で相続後に生じた資本所得βと合わせて行われる(所法60![]() )。例外的に、限定承認の場合には相続時にαが課税されるとともに相続財産の取得価額が時価A+αに引き上げられ(みなし譲渡所得課税)、譲渡時点でβが課税される(所法59
)。例外的に、限定承認の場合には相続時にαが課税されるとともに相続財産の取得価額が時価A+αに引き上げられ(みなし譲渡所得課税)、譲渡時点でβが課税される(所法59![]() 、60
、60![]() )。いずれにせよ、時間を通じてみればα+βすなわち資本所得が過不足なく課税対象となっている。一方、相続税においては時価評価によりA+αが課税対象となる(相法22)。
)。いずれにせよ、時間を通じてみればα+βすなわち資本所得が過不足なく課税対象となっている。一方、相続税においては時価評価によりA+αが課税対象となる(相法22)。
このように、所得税はα+β、相続税はA+αを課税することで両者の「棲み分け」が整理され、両者に二重課税は存在しないとされてきた。
そして、この「棲み分け」は相続税と所得税の関係の基本形となり、所法60![]() 適用外の所得においても同様に整理されてきた。例えば預金については、元金と経過利子の合計(A+α)が相続課税され、他方、相続時には経過利子(α)への所得課税は行われず、利子受取時に利子の全体(α+β)が課税される。
適用外の所得においても同様に整理されてきた。例えば預金については、元金と経過利子の合計(A+α)が相続課税され、他方、相続時には経過利子(α)への所得課税は行われず、利子受取時に利子の全体(α+β)が課税される。
ロ 「潜在的所得税債務」の存在
ところで、相続人はいずれ譲渡時点で含み益αにかかる所得税αt(tは所得税率)を負担するのだから、相続人にとって実質的な「相続財産の経済的価値」は、時価から当該所得税額を控除した金額、すなわちA+α(1−t)となる筈である。このことは、限定承認の場合にみなし譲渡所得税額αtが債務控除(相法13、14)される結果、相続課税対象がA+α(1−t)となることとの権衡から考えても明らかであろう。当該所得税額αtは言わば「潜在的所得税債務」と考えることができる。
つまり、現行相続税法は、本来課税すべき「相続財産の経済的価値」よりもαt相当額を過大に課税対象としている。(過大な税額はαstである。)
【図7】潜在的所得税債務
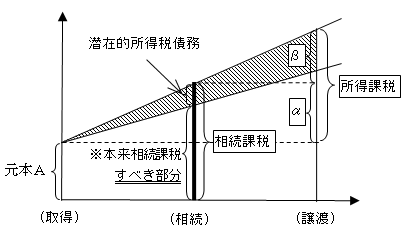
ハ 現行法の調整方式
この問題は過去、「相続税納付のために相続直後に相続財産を売却すると税負担が重くなる」という文脈で論じられ、その結果、昭和45年に「譲渡所得課税において当該資産に対応する相続税額(A+α)s(sは相続税率)を取得費に加算する」という調整方式(措法39)が導入されることとなり、「相続税評価からαtを控除する」という理論整合的な調整方式は採用されなかった。
ただし、現行相続税法においても、立木に関しては被相続人に帰属すべき山林所得税(αtに相当)を債務控除する趣旨で評価が割り引かれており(相法26)、また、通達により預貯金の既経過利子等について同旨の調整がなされており(評基通203等)、一部資産では潜在的所得税債務を考慮した評価がなされている。
このように、現行法における相続税と所得税の調整はパッチワーク的であることを否めない。
ニ 「二重課税」は存在するか?
なお、「相続税と所得税に二重課税があるか」という問題に関しては、経済学における所得概念と、租税法上の所得概念を区別して議論すべきである。
すなわち、経済学的には所得とは労働所得+資本所得(経済的価値の創出)であり、相続・贈与(経済的価値の移転)は所得ではないが、租税法上の「所得」は包括的所得概念により個々人に流入する経済的価値の総計として定義されるので、経済的価値の移転も受け手の「所得」に含まれる。したがって、経済学の観点では所得は所得税と相続税とで二重に課税されていることになるが、租税法上は「経済的価値の創出」と「経済的価値の移転」はそれぞれが別の「所得」なので、それぞれを課税することを二重課税とは考えない。(ただし、相続においては被相続人の地位を相続人が承継するため、理論的には別人格への課税である「経済的価値の創出への課税(αへの所得税)」と「経済的価値の移転への課税(A+αへの相続税)」が共に相続人に帰することとなり、相続人は「(αについて)所得税と相続税が二重に課税されている」という印象を受けるだろう。)
潜在的所得税債務の調整は相続課税上の問題として捉えるべきものであり、二重課税の問題ではない。
(2)生保年金二重課税事件(最判H22.7.6)
イ 概要(本文中【図14】参照)
本事案は年金型生命保険に基づく年金給付金につき雑所得としての課税の是非が争われたものであるが、前述の「棲み分け」の構図に当てはめて極く単純化すれば、以下のように整理される。すなわち、課税庁が被相続人が受給する年金給付金のうちα+βに相当する部分を雑所得として課税したところ、一審はα、βともに所得非課税とし、二審は原処分どおりα+βへの所得課税を認め、そして、最判はαを非課税としβへの所得課税のみ認めた。
前述のとおり、最判がαを非課税としたのは所得税法9第1項16号によってである。最判は、同号「の趣旨は,相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値〔A+α〕に対しては所得税を課さないこととして,同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される」と述べた。これはつまり、αには相続税が課されているので所得税を課税すべきではない、という論理操作を行ったことになる。この判決が従来の相続税と所得税の「棲み分け」に重大な疑義を投げかけていることが理解されよう。
【図14】本最判による所法9![]() 16の解釈
16の解釈
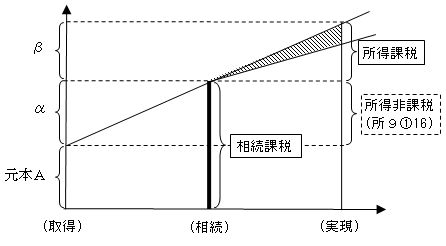
ロ 本判決の射程
本判決の所得税法9条1項16号の解釈は、相続人における取得費等を相続税評価A+αに引上げる意味を有する(step-up basis)から、取得費等の引継ぎ(carry-over basis)を定める所得税法60条1項と明らかに矛盾するが、同項には既に実務に膨大な蓄積があり、最高裁も直近では平成17年にその適用を認めている(いわゆるゴルフ会員権贈与事件)ところであって、本判決が同項を死文化させることまでもを意図したとは考えられない(それを窺わせる叙述も無い)。そこで、本判決の射程が同項適用外の所得に対しどこまで及ぶかが論点となる。
この点につき税制調査会の「最高裁判決研究会」報告書(H22.10.22)は、「本判決の直接の射程は、相続税法24条により評価される相続財産(定期金)に限定されると考えるのが相当」と限定的に解した。そして、平成23年度税制改正において、相続財産に基因する利子所得、配当所得、一時所得、雑所得の全般に関し所得税法60条1項と同趣旨の規定が置かれ(所法67の4)、法の間隙が埋められた。こうして、定期金以外の財産に関しては従前と同様の「棲み分け」が維持されている。
(なお、定期金に関しては、本判決に対応するために平成22年10月に所得税法施行令の改正、法令解釈通達の発遣が行われ、平成23年度税制改正において過去に支払われた定期金に関する所得税の還付のための所要の手当てもなされた。)
ハ 検討
私見では、そもそも本事案の本質的な問題点は、潜在的所得税債務を考慮しない相続課税にある。しかし、訴訟が所得税につき提起され、所得税が論争の中心となったため、潜在的所得税債務の問題については、余り論じられていない。
立法経緯からみて、所得税法9条1項16号は相続による経済的価値の移転について相続課税と一時所得課税(資本所得課税ではない)の重複を防ぐ趣旨で設けられた規定であり、同号を「取得費等の引上げ」の趣旨に解した最判の解釈には疑問がある。経済理論的にみても、取得費等の引上げは被相続人の保有期間に生じた資本所得αを非課税とすることになるので公平性・中立性の観点から問題があり、賛成できない。最判の論理を拡大すると資本所得課税の根幹を揺るがすこととなりかねず、その射程を限定的に解した税調研究会の見解を支持したい。
本事案に関するもう一つの重要な視点は、争点が生命保険契約に基づく給付金にあったことである。従前、被相続人が保険料を負担していた場合の生保給付金は、一時金受取ならば所得非課税、年金受取ならば雑所得課税とされ、その不均衡が夙に指摘されていた。本判決はそうした事情を踏まえて理解されるべきだろう。
(なお、このような不均衡が生じる根本的な原因は、生命保険金を一時金で受け取る場合には所得と相続が同時に発生するため、所得税法9条1項16号が経済的価値の移転としての所得A+α(=相続)と資産価値の増加としての所得α(=受取保険金−支払保険料)の両方に適用されてしまう、という法の欠陥にある。)
(3)潜在的所得税債務の調整
イ 理論的検討
- 相続税と所得税の関係については、「包括的所得税には遺産取得税を、支出税には遺産税を組み合わせるべき」という議論があるが、遺産税・遺産取得税のいずれであっても、資本所得課税を行う以上、相続税評価において潜在的所得税債務を控除すべきことに変わりはない。
- 潜在的所得税債務は、限定承認の場合と同様(みなし譲渡所得課税)の計算を行って算出すべきである。
- 現行相続税法上の債務控除は「確実と認められるもの」(相法14)に限られるので、潜在的所得税債務を相続税評価から控除するには新規立法が必要である。
- 諸外国の状況を見ると、米英はαを非課税とし(step-up basis)、加豪はαを死亡時譲渡所得課税するが相続税そのものを廃止している。
ロ 具体的控除方式(簡便法の検討)
- 執行面では、みなし譲渡所得課税を行う場合と同様の計算を広範に行うことになるので、事務負担が増加する。事務負担軽減の観点から、何らかの簡便法を検討する必要があろう。
- 第一に、相続財産の種類毎に潜在的所得税債務を見込んだ割引率を設定する方式が考えられる(現行相法26方式の拡大)。これにより事務負担の増加はほぼゼロに抑えられるが、資産の保有期間にはかなりのバラつきが見込まれるので割引率を定めるのは困難かも知れない。
- 第二に、所得課税時にαs相当額を所得から控除する方式が考えられる(現行措法39方式の改善)。この方式では所得税の事務処理が煩雑化する恐れがある。
- 第三に、相続人において「みなし譲渡所得課税」の選択を可能とする方式が考えられる。そもそも潜在的所得税債務は相続財産に含み益が無ければ生じないので、含み益の存否の計算を納税者に委ねることで事務負担の軽減が期待できる。しかし、選択者が増えれば事務負担の増加は避けられない。
3 結論
資本所得課税には種々問題もあるが、我が国においては、包括的所得税であれ二元的所得税であれ、資本所得課税は継続される方向にある。また、相続税についても、格差固定化防止の観点からその重要性が認識されている。資本所得課税と相続課税を共に存続させる以上、潜在的所得税債務の控除による両者の調整が必要である。
実証的に考えると、措法39による調整に加え、![]() 土地等の相続税評価は「安全率」により実勢より割安に見積もられている、
土地等の相続税評価は「安全率」により実勢より割安に見積もられている、![]() 昭和63年まで有価証券譲渡益は非課税だった、
昭和63年まで有価証券譲渡益は非課税だった、![]() 生命保険金は一時金受取ならば所得非課税、定期金受取の場合は旧相法24により過少に評価されていた、といったことから、主要な相続財産について潜在的所得税債務の問題が顕在化せず、そのためこの問題が今日まで十分整理されず残されてきたのかも知れない。
生命保険金は一時金受取ならば所得非課税、定期金受取の場合は旧相法24により過少に評価されていた、といったことから、主要な相続財産について潜在的所得税債務の問題が顕在化せず、そのためこの問題が今日まで十分整理されず残されてきたのかも知れない。
しかし、現行法のようなパッチワーク的な対応では調整しきれない部分が残り、また却って不公平な取扱いを生じ得るので、根本的な整理が必要と考える。
目次
| 項目 | ページ |
|---|---|
| 序論 | 12 |
| 1 問題の所在 | 12 |
| 2 本稿の構成 | 12 |
| 第1章 相続財産に付着する「潜在的所得税債務」 | 14 |
| 第1節 相続税と所得税の「棲み分け」 | 14 |
| 1 相続税と所得税の交錯 | 14 |
| 2 両者の「棲み分け」 | 19 |
| 第2節 「潜在的所得税債務」の問題 | 25 |
| 1 潜在的所得税債務 | 25 |
| 2 過大となる相続税額 | 26 |
| 3 現行法における調整方式 | 28 |
| 第3節 「二重課税」なのか? | 32 |
| 1 経済学上の所得概念 | 32 |
| 2 租税法上の所得概念 | 32 |
| 3 小括 | 33 |
| 第2章 生保年金二重課税事件 | 34 |
| 第1節 生命保険金に関する従前の取扱い | 34 |
| 1 保険料負担者と保険金受取人が同一人の場合 | 34 |
| 2 被相続人が保険料を負担していた場合 | 35 |
| 第2節 事案と判決の概要 | 39 |
| 1 事案概要 | 39 |
| 2 判決概要 | 40 |
| 第3節 本判決の意義と射程 | 42 |
| 1 本判決の意義 | 42 |
| 2 本判決の射程 | 44 |
| 3 考察 | 45 |
| 第4節 「定期金」に関する国の対応 | 49 |
| 1 非課税部分の配賦方式 | 49 |
| 2 必要経費の控除 | 50 |
| 第5節 補論:「現在価値」と「所得」について | 52 |
| 1 「現在価値」概念 | 52 |
| 2 現在価値と「所得」 | 53 |
| 第3章 潜在的所得税債務の調整方式の検討 | 56 |
| 第1節 理論的検討 | 56 |
| 1 相続税の類型論との関係 | 56 |
| 2 潜在的所得税債務の具体的算出方法 | 56 |
| 3 債務としての確実性 | 57 |
| 4 相続税法13、14条(債務控除)との関係 | 58 |
| 5 相続財産が「含み損」を有する場合 | 59 |
| 6 諸外国の状況について | 59 |
| 第2節 具体的控除方式 | 60 |
| 1 理論に忠実な方式(基本案) | 60 |
| 2 簡便法その1(相続税評価における割引き) | 61 |
| 3 簡便法その2(所得課税における控除) | 61 |
| 4 みなし譲渡所得課税の選択制 | 62 |
| 結論 | 64 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

