相続税・贈与税の納税義務者制度に関する研究
宮脇 義男
税務大学校
研究部教育官
要約
1 研究の目的(問題の所在)
納税義務者とは「租税法律関係において租税債務を負担する者」と定義されるが、相続税法を含む各個別の租税法において、納税義務の定めは、言うまでもなく、課税物件、課税物件の帰属、課税標準及び税率と並んで、課税要件(納税義務の成立要件)の構成要素の一つとされるところである。
こうした相続税・贈与税における納税義務者制度の類型としては、財産の移転者側(遺言執行人等の第三者・贈与者)に納税義務を課す類型と財産の取得者側(相続人・受贈者)に納税義務を課す類型とに大別することができ、法定相続分課税方式という遺産取得課税方式を基調とする課税方式を採用する我が国の相続税法においては、財産の取得者である個人に納税義務を課すことを基本としつつ、個人以外の一定の主体に対する納税義務等、種々の仕組みを講じているところである。
一方、最近における我が国の相続税制を巡る状況を見ると、平成21年12月に閣議決定された「平成22年度税制改正大綱」において、今後、格差是正の観点から、課税ベースや税率構造の見直しを目指していくとの方向性が示されており、これを受け、平成22年12月に閣議決定された「平成23年度税制改正大綱」においては、相続税の基礎控除の引下げや最高税率の引上げを含む税率構造の見直し等の改正案が示され、法改正の実現はなされなかったものの、平成23年の通常国会に関連法案が提出されていたところである。
こうした相続税・贈与税の課税強化がなされる状況を踏まえると、今後、相続税制に対する信頼性の確保が更に求められることとなるが、その一方で、相続税・贈与税の納税義務者制度を巡る最近の大きな動きとしては、まず、贈与時の住所が国内にあったか否かが争われていたいわゆる「武富士事件」について、最高裁(最判平23.2.18)において、国内に住所があったとの課税庁側の主張が認められず、国側敗訴が確定したことを挙げることができる。また、国境を越えた人や財産の移動の活発化に伴い、外国の信託を用いて外国国籍の親族へ財産を贈与する等の方法によって、贈与税の負担軽減を図るといった事例が見られるほか、新たな非営利法人制度や信託制度の発足によって法人制度や信託制度の多様化が図られたことに伴い、将来世代をも含む親族全体の相続税等の負担軽減を専ら図ることを目的にこれらの制度を活用することが見込まれる状況に置かれている。こうした状況を受け、「平成22年度税制改正大綱」においても、法人等を利用した租税回避への対応など、課税の適正化の観点からの見直しを引き続き行っていくとの方向性が示されているが、こうした状況を踏まえると、相続税・贈与税について、現行の納税義務者制度の枠組みのままでは、今後、適切な課税の実現が困難となるといった状況も考えられる。
そこで、現行の相続税・贈与税の納税義務者制度の枠組みについて、問題点等の検討・分析を行い、今後の対応の方向性を研究することが必要と考えるところである。
2 研究の概要
(1)現行法における相続税・贈与税の納税義務者制度等の概観
相続税は基本的に相続・遺贈といった無償の財産の移転に担税力を見出して課税する租税である一方、相続によって財産を取得する主体は、相続の本質からいって自然人である個人に限られることとなる。また、贈与税は、生前贈与による相続税の回避を防止するという相続税の補完税としての性格を有している。こうしたことから、我が国の相続税・贈与税は、財産の取得者である個人に納税義務を課すことを基本としている。すなわち、相続税の納税義務者について、現行相続税法は、その類型の一つとして「相続又は遺贈により財産を取得した個人」(相税1の3一)を掲げ、また、贈与税の納税義務者についても、相続税の場合と同様に、その類型の一つとして「贈与により財産を取得した個人」(相税1の4一)を掲げている。このように、相続税・贈与税の納税義務者に関する定めは、「相続・遺贈・贈与」という課税対象の発生形態と「個人」という課税対象の帰属主体の属性とがそれぞれ限定されているところにその特色を見出すことができるといえる。
こうした特色を有する我が国の相続税・贈与税の現行の納税義務者制度は、主に、個人に対するものと個人以外の主体に対するものとの二つの枠組みから構成されている。
![]() 個人に対する納税義務者制度
個人に対する納税義務者制度
財産の取得者である個人については、国内に住所を有するか否かにより、取得した財産の所在地が国内であるか否かにかかわらずすべての取得財産を課税対象とする「無制限納税義務者」と国内に所在する取得財産のみを課税対象とする「制限納税義務者」とに大別され(相税1の3〜2の2)、所得税や法人税と概ね同様の考え方が採用されている。
しかし、制限納税義務者制度については、国境を越えた人や財産の移動の活発化に伴い、我が国と外国との間での相続税・贈与税の課税方法や課税対象の違いを利用し、相続発生の直前に財産を国外に移転して国外に住所を有する子供に相続させることや、子供が国外に住所を移した直後に国外へ財産を移転してその国外財産をその子供へ贈与することによって、相続税・贈与税を回避するといった手法が一般に紹介されており、いわゆる「武富士事件」も、こうした手法を利用したものである。
こうした状況を受け、平成12年度の税制改正において、財産の移転者及び取得者の双方が過去5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある場合で日本国籍を有する取得者(相続人・受贈者)については、相続や贈与の時点で国内に住所を有していない場合であっても、国内外を問わずすべての取得財産を課税対象とする「非居住無制限納税義務者」(相税1の3二、1の4二)の類型を新設するという適正化措置が講じられ、これにより、制限納税義務者の範囲が制限されたところである。
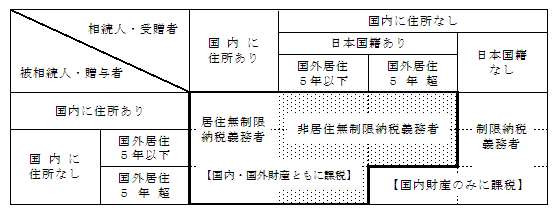
![]() 個人以外の主体に対する納税義務者制度
個人以外の主体に対する納税義務者制度
我が国の相続税・贈与税の納税義務者制度においては、上記のとおり、課税対象の発生形態が相続、遺贈及び贈与に限定され、課税対象の帰属主体の属性が個人に限定されていることとなるが、遺贈及び贈与については個人以外の主体(法人等)も帰属主体となり得るため、両者の対応関係にズレが存在することとなり、そこに相続税・贈与税固有の税負担回避が発生し得る要因が生まれることとなる。
こうした相続税・贈与税の税負担回避に対処するために現行相続税法においては、種々の措置を講じており、個人以外の主体に対する納税義務もその一つと位置付けることができる。すなわち、相続税法においては、一定の人格のない社団・財団や持分の定めのない法人等といった個人以外の主体に対しても、個人とみなして相続税・贈与税の納税義務を課しており(相税66)、こうした取扱いは相続税法固有の仕組みであるといえる。そして、この相続税法第66条については、近年において、新たな非営利法人制度の発足に対応して、平成20年度の税制改正において、個人とみなされる法人の範囲の見直し等がなされているところである。また、この他、新たな信託制度の発足に対応して、平成19年度の税制改正において、受益者等が存しない信託の受託者に対して相続税・贈与税を課税するといった措置が講じられているところである(相税9の4)。
(2)相続税・贈与税の納税義務者制度を巡る「新たな事例」
![]() 総説
総説
相続税・贈与税の納税義務者制度に関する現行の枠組みは、上記のとおり、近年において、個人に係る無制限納税義務者の範囲の拡大や納税義務者とされる法人等の範囲の拡大などの見直しがなされているものの、今日まで基本的に維持されている。このうち、「個人に対する納税義務者制度」について講じた適正化措置(非居住無制限納税義務者制度の新設)については、「武富士事件」の最高裁判決において、「贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をするという行為が課税実務上想定されていなかった事態であり、このような方法による贈与税回避を容認することが適当でないというのであれば、法の解釈では限界があるので、そのような事態に対応できるような立法によって対処すべきである」との指摘がなされている点について、現に立法的に解決を図ったものであるといえる。したがって、改正後の制度の下においては、武富士事件と同様のスキームによる贈与税の負担回避を封じているといえる。
一方、適正化後の制度の下においても、相続人(受贈者)が日本国籍を有しないか、又は、被相続人(贈与者)若しくは相続人(受贈者)が過去5年以内において国内に住所を有していなかった場合(国外居住5年超の場合)には、この制度の対象外となるため、国外財産の取得が課税対象とはならないこととなり、適正化後の制度においても課税上の問題を生じさせることとなるが、近年において実際に、そうした事例が出現している状況にある。
![]() 名古屋地裁平成23年3月24日判決(平成20年(行ウ)第114号)
名古屋地裁平成23年3月24日判決(平成20年(行ウ)第114号)
本事例は、原告Xが米国ニュージャージー州の法律に準拠して行われた信託契約によって受益者となったことについて、課税庁Yが、原告Xは信託受益権の贈与を受けたとみなされるとして贈与税の決定処分等を行ったことに対し、その全部の取消しを求めたものである。
本事例において、本件信託契約における委託者は原告Xの祖父C、受託者は米国の信託会社D、そして信託財産は米国債券とされている。また、原告Xは米国カリフォルニア州で出生し、米国国籍を取得している上(日本国籍なし)、本件信託の設定時においてはまだ乳児であった(原告Xの両親ABは共に日本国籍あり)。したがって、本事例は、祖父Cから孫である原告Xへという、世代を跳躍して財産を移転した事例であるが、原告Xが日本国籍を有していないことから、原告Xが本件信託の設定時において日本に住所を有していない上に本件信託契約における信託受益権が国外財産と判断されれば、原告Xに対して贈与税を課税する手立てを失うこととなる。また、祖父Cは日本に住所を有していることから、贈与者課税を採用している米国においても課税できないこととなり、日米両国において課税ができないという「国際的な二重非課税」の状態が生ずることともなる。
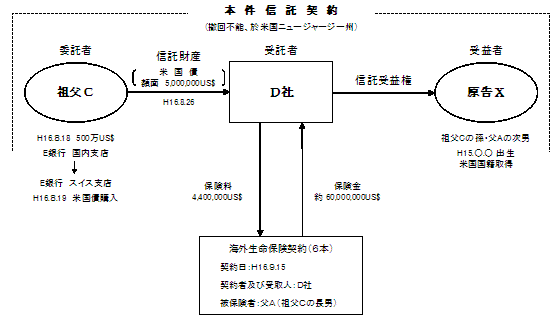
本事例の具体的な争点としては、イ.本件信託の設定行為が旧相続税法第4条第1項にいう「信託行為」に該当するか否か、ロ.原告Xが同条第1項にいう「受益者」に該当するか否か、ハ.本件信託が生命保険信託に該当するか否か、ニ.原告Xが相続税法第1条の4第3号の制限納税義務者に該当するか否か、及びホ.本件信託財産が我が国に所在するものであるか否かであった。そして、裁判所は、上記イについては、信託行為に該当すると判断して原告X側の主張を退けたものの、上記ロについては、「原告Xは、本件信託の設定時において、本件信託による利益を現に有する地位にあるとは認められない」と判断して課税庁側の主張を退けており、これにより、上記ハからホまでの争点を判断するまでもなく、本件課税処分は違法と判断し、国側敗訴の判決を言い渡している。
(3)検証・考察−「新たな事例」(名古屋地判平23.3.24)を巡る考察を足掛かりとして−
上記の「新たな事例」を巡る考察を一つの足掛かりとして、相続税・贈与税の納税義務者制度を巡る概ね以下のような事項について、関連する論点の検証・考察を行なった。
![]() 個人に対する納税義務者制度
個人に対する納税義務者制度
イ 住所要件・国籍要件について
「新たな事例」においては、原告Xを出生時点から米国国籍とすることや米国における滞在日数を多くすることなどによって非居住無制限納税義務者制度における「住所要件」及び「国籍要件」を回避しようとしている意図が窺われる。
対応策としては、まずは「国内に住所を有していたか否か」に関する適切な運用や事実認定を通じて、課税の適正化に務めることが必要である。この点について、武富士事件においては香港と日本における滞在日数を検討していることから、「新たな事例」においても米国と日本における滞在日数を検討すると、本件信託契約の締結の時において原告Xは日本に住所を有していたものと判断される可能性はあるものと考えられる。しかしながら、武富士事件の最高裁判決における以下の判示を踏まえると、そうした運用や事実認定には自ずと限界があり、今後、類似の事例が発生した場合には、相当の困難が伴うものと考えるところである。
「 一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものであり、主観的に贈与税回避の目的があったとしても、客観的な生活の実態が消滅するものではないから、上記の目的の下に各滞在日数を調整したことをもって、現に香港での滞在日数が本件期間中の約3分の2(国内での滞在日数の約2.5倍)に及んでいる上告人について前記事実関係等の下で本件香港居宅に生活の本拠たる実体があることを否定する理由とすることはできない。このことは、(相続税)法が民法上の概念である『住所』を用いて課税要件を定めているため、本件の争点が上記『住所』概念の解釈適用の問題となることから導かれる帰結であるといわざるを得(ない)」
また、いわゆる住所複数説に関して、武富士事件の最高裁判決における補足意見において「これまでの判例上、民法上の住所は単一であるとされている。しかも、住所が複数あるとする考え方は一般的に熟しているとまではいえないから、住所を東京と香港とに一つずつ有するとの解釈は採り得ない」との否定的な見解が示されているところであり、国内に住所を有するとの判断を一層困難とさせるものと考えられる。
ロ 今後の方向性
こうした住所概念の下、武富士事件の最高裁判決においては、贈与税回避を容認できないのであれば立法によって対処すべきこと、そして、この点については既に平成12年度の税制改正において納税義務者制度の適正化措置が講じられていることを指摘している。この適正化措置は、住所要件の適用を財産の取得時という一時点に限定することなく、国籍要件の枠内で過去の一定期間にまで拡大するとともに、財産の移転者側にも同様の住所要件を付加したものであるが、この適正化措置も「新たな事例」に関してはいわば機能しているとはいえない。したがって、立法によって対処すべきとの武富士事件判決の判示を積極的に解し、今後、更なる適正化を検討すべきであると考える。
すなわち、「新たな事例」において、祖父Cは贈与時点において国内に住所を有していた上、原告X自身についても、国籍法上、日本人夫婦の子が外国で出生した時に日本国籍の留保をしなかったことによって日本国籍を喪失した場合であっても、20歳未満であること等の要件を満たすときは日本国籍の再取得が可能とされており、これらの点を考慮することなく、財産の取得時に日本国籍を有していなければ無条件に制限納税義務者とされる現行の仕組みは見直す必要がある。
例えば、現行の非居住無制限納税義務者制度について、相続人・受贈者が財産の取得時に日本国籍を有していなくても、被相続人・贈与者側において、財産の移転時に国内に住所を有している場合や、財産の移転時には国内に住所を有していなくても過去5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある場合には、無制限納税義務を課すといった見直しを行うことが考えられるほか、将来的には、国内居住要件を適用する過去の期間(現行5年)を延長することを検討すべきと考える。
なお、「個人以外の主体に対する納税義務者制度」の取扱いとの関連において、相続税法第66条の適用によって個人とみなされた一定の非営利法人等について個人に係る納税義務者制度の規定(相税1の3、1の4)を適用するに当たっては、その法人等の住所はその主たる営業所又は事業所の所在地にあるものとみなすこととされており(相税663)、その所在地の如何によってその法人等が国内に住所を有するか否かを判断することとなる。これに対して、個人の非居住無制限納税義務者制度に係る国籍要件については特段の手当てはなされていないため、その法人等に係る国籍要件の適用に当たって疑義が生ずるところである。この点について、受益者等が存しない信託の受託者に対して相続税・贈与税を課税する旨を定める相続税法第9条の4については、その信託の受託者は、個人に係る非居住無制限納税義務者制度の規定の適用に当たっては日本国籍を有するものとすることとされ(相税令1の121二)、これによって一定の手当てがなされているところであり、相続税法第66条の規定により「個人」とみなされた法人等に対しても同様の手当てを講ずるべきか否かの検討を要するものと考えるところである。
![]() 個人以外の主体に対する納税義務者制度
個人以外の主体に対する納税義務者制度
イ 「新たな事例」との関連性等
「新たな事例」においては、祖父Cは信託契約に基づき受託者Dに財産を移転したことから、私法上の財産の帰属者は受託者とされている。また、原告Xが信託の設定に関する旧相続税法第4条第1項に規定する「受益者」に該当しないとの判断がなされた背景としては、本件信託契約については、(イ)原告Xの受益は受託者の裁量によるものであることや、(ロ)限定的指名権者(受益者指名権を有する者)が別途存在し、いつでも原告X以外の者に受益させることができることから、原告Xはそもそも受益権を有していないのではないかとの主張がなされていたことにある。そして、仮に、本件信託が受益者等の存しない信託に該当するとすれば、こうした信託は、機能的には持分の定めのない法人等にも通ずるところがあるものと考えることができる。したがって、こうした点を踏まえれば、「新たな事例」を巡る考察は、一定の持分の定めのない法人等や受益者等が存しない信託の受託者を対象とした上記の「個人以外の主体に対する納税義務者制度」の取扱いとも関連性を有するものと考えることができる。
まず、「新たな事例」における判決において、原告Xが旧相続税法第4条第1項に規定する「受益者」に該当するか否かの判断に当たっては、相続税法第5条ないし第9条といった他の「みなし課税」制度の規定が、共に、受贈者とされる者が贈与とみなされる行為によりもたらされる利益を現に有することとなったと認められる時に、贈与があったとみなして課税をしているという理解を示している。しかしながら、相続税法第5条以下に規定する「みなし課税」制度は、各々の「みな課税」制度の中で、課税すべき対象を特定し、その課税対象の性質に応じて課税すべきタイミングを個々に定めているものであり、その課税対象の背後にある法制度や社会・経済状況の変化等に対応して、種々の見直しの積み重ねがなされてきた結果であるといえる。したがって、相続税法第5条以下に規定する「みなし課税」制度は信託行為とは関係のない制度であって、これらの規定を根拠に「受益者」に該当するか否かを判断することは、そもそも適切ではないと考える。
また、「新たな事例」における判決は、限定的指名権者(父A)の指名によって、原告X以外の者が本件信託の利益の分配を受けることができることを指摘しているが、本件信託においては、限定的指名権が行使されて新たに受益者が指名されない限り、原告Xが受益者であることは明らかであるといえる。
次に、「新たな事例」における判決において、原告Xは旧相続税法第4条第1項に規定する「受益者」には該当しないとの判断がなされると、それではどの時点で課税がなされるのかという疑問が生ずる。まず、判決の考え方に従って、被保険者である父Aが死亡したとき又は保険の満期が到来したときに課税がなされるとした場合、これは受託者Dが実際に受益者である原告Xに分配できる状態となったときを捉えているが、信託受益時課税の考え方に相当近づくこととなるため、信託行為時課税を採用していた旧相続税法第4条の考え方に反することとなり、適切ではない。また、委託者である祖父Cが死亡したときとした場合、祖父Cの死亡は保険事由には該当せず、受託者Dにおいて保険金を得ることはないため、課税できないということになる。したがって、こうした点を踏まえれば、原告Xは「受益者」に該当し、信託行為時に課税がなされるべきものと考える。
ロ 今後の方向性
旧相続税法第4条は、平成18年における信託法の全文改正に対応して、平成19年度の税制改正において抜本的な改正がなされたところであるが、新たな制度は改正前の制度における信託行為時課税という信託課税の考え方そのものを大きく変更したものではなく、同様の考え方は新たな規定である相続税法第9条の2においても、基本的に維持されている。したがって、新たな規定においても、原告Xは同条第1項にいう「受益者」に該当し、信託行為時に課税がなされるべきものと考える。
しかし、もし仮に、「新たな事例」における裁判所の判断を現行相続税法第9条の2以下の規定にそのまま当てはめるとすると、原告Xは同条第1項にいう「受益者」に該当しないこととなるが、そうなると、「新たな事例」における本件信託は「受益者等が存しない信託」(相税9の4)に該当することとなり、受託者Dに対して課税が及ぶこととなると考えられる。この場合、受託者Dは外国法人であり、制限納税義務者に該当するため、信託受益権(信託財産)の国内財産の該当性が問われることとなる。なお、父Aの死亡や保険の満期によって将来的に受益者等である原告Xが存することとなる場合には、相続税法第9条の5の規定により、原告Xに対して課税が及ぶこととなると考えられる。この規定は信託を利用する世代を跳躍した財産の移転に対処したものとされているが、この場合、受益者等が存しない信託と同様の機能を有する持分の定めのない法人等に対しては同様の措置が講じられていないため、課税関係の均衡化を図る必要がある。
また、一定の持分の定めのない法人等を対象とした現行の「個人以外の主体に対する納税義務者制度」においては、法人等に財産を移転した時(入口段階)における相続税・贈与税の課税に対処したものであるが、その法人等に財産を移転した後、その法人等を実質的に支配している者に相続等が生じた場合における相続税の課税にまでは対処していない。
すなわち、持分の定めのない法人等の場合は、その法人等の財産に対する持分が存在しないため、法人等の制度上、法人に帰属する財産を特定の被相続人の遺産として構成する手段は存在しない。そのため、法人に財産を移転した時に相続税・贈与税を課税した後は、その財産に対する相続税・贈与税の課税は及ばないこととなる。この結果、仮に、ある特定の個人が特定の法人を実質的に支配しているような状態にあったとすると、財産を法人に移転した後、その個人が死亡して後継者が相続した場合には、相続人が引き続きその法人を実質的に支配していても、その法人の財産は遺産を構成しないため相続税の課税に取り込むことができない。結局、代々、相続税の負担なく法人の財産が引き継がれることとなり、個人に帰属する財産が引き継がれる場合と比較して、課税上のアンバランスが生ずることとなる。
そこで、このような、個人が実質的に支配している状態にある法人等については、財産をその法人に移転した時に相続税・贈与税の課税対象とするほか、移転後もそのような状態が継続し、その支配していると認められる個人について相続が発生した場合には、その個人の相続財産とみなして相続税の課税対象とするといった措置を講じる必要がある。
![]() 財産の所在場所の判定
財産の所在場所の判定
相続税・贈与税の納税義務者の区分は、上記のとおり、取得した財産の所在地の如何にかかわらずすべての取得財産を課税対象とするのか、それとも、国内に所在する取得財産のみを課税対象とするのかといった、相続税・贈与税の課税財産の範囲を画する基準として機能している。
「新たな事例」においては、本件信託契約における信託受益権の所在場所が争点の一つとされていたほか、武富士事件の最高裁判決における補足意見においても、「本件贈与は、法形式上は、Bらが、外国法人たるオランダ法人の総出資口数中その9割に当たる720口を上告人に無償で譲渡する贈与契約であるが、・・・、その実質は、要するに、オランダ法人を介在させて、国内財産たる本件会社株式の支配を、Bらが、その子である上告人に無償で移転したという至って単純な図式のものである」と述べられていることに見られるように、相続税・贈与税の納税義務者制度について考察するに当たっては、関連する制度として、財産の所在場所の判定の在り方についても併せて考察する必要がある。
例えば、武富士事件を受け、財産の所在場所の判定方法を規定する相続税法第10条について、「内国法人を、外国法人を通じて間接保有するようなかたちのスキームが形成され、かつ、納税者が非居住者になるという行為が行なわれた場合に、当該外国法人の株式を一定の範囲で国内財産とみなすという改正を行なうこと」といった見直しを検討すべきと考えるところである。
3 結論
本研究では、現行相続税法における相続税・贈与税の納税義務者制度について、まず、その特色や制度の枠組み等について概観した上で、相続税・贈与税の納税義務者制度を巡る「新たな事例」として、名古屋地裁平成23年3月24日判決を取り上げ、この「新たな事例」を巡る主な問題点等を明らかにするとともに、その問題点等のいずれもが、現行相続税法における相続税・贈与税の納税義務者制度の枠組みに関連性を有していることについて明らかにした。そうした上で、この「新たな事例」を巡る考察を一つの足掛かりとして、現行相続税法における相続税・贈与税の納税義務者制度の主な枠組みごとに、関連する論点の検証を進めてきたところである。
上記1において最近における我が国の相続税制を巡る状況について述べたとおり、相続税・贈与税の課税強化の方向性を踏まえると、今後、相続税制に対する信頼性の確保が更に求められることとなる。したがって、相続税・贈与税の納税義務者制度を巡っても、本研究において考察した種々の論点を中心に、より一層の適正化に努めていく必要がある。
目次
| 項目 | ページ |
|---|---|
| はじめに | 279 |
| 1 問題の所在 | 279 |
| 2 本稿の構成 | 280 |
| 第1章 相続税・贈与税の納税義務者制度 | 282 |
| 第1節 租税法における納税義務者制度について | 282 |
| 1 納税義務の成立と確定 | 282 |
| 2 課税要件の構成要素としての納税義務者制度 | 283 |
| 第2節 相続税・贈与税の納税義務者制度の類型 | 283 |
| 第3節 現行法における相続税・贈与税の納税義務の成立と確定 | 284 |
| 第2章 現行法における相続税・贈与税の納税義務者制度等の概観 | 286 |
| 第1節 現行法における相続税・贈与税の納税義務者制度の特色 | 286 |
| 第2節 個人に対する納税義務者制度 | 287 |
| 1 現行法における定め | 287 |
| 2 無制限納税義務者と制限納税義務者 | 290 |
| 3 居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者 | 291 |
| 4 特定納税義務者 | 292 |
| 5 一覧 | 292 |
| 第3節 個人以外の主体に対する納税義務者制度 | 293 |
| 1 人格のない社団又は財団等に対する課税 | 294 |
| 2 受益者等が存しない信託等の特例 | 298 |
| 第4節 納税義務者の属性の違い等に基因する税額の加算等 | 301 |
| 1 相続税額の加算制度 | 301 |
| 2 相次相続控除制度 | 303 |
| 3 財産移転の形態 | 303 |
| 第5節 小括 | 305 |
| 第3章 相続税・贈与税の納税義務者制度を巡る「新たな事例」 | 308 |
| 第1節 総説 | 308 |
| 第2節 名古屋地裁平成23年3月24日判決 | 309 |
| 1 事例の概要等 | 309 |
| 2 争点 | 312 |
| 3 裁判所の判断 | 313 |
| 第3節 小括 | 317 |
| 第4章 個人に対する納税義務者制度 | 319 |
| 第1節 「新たな事例」との関連性 | 319 |
| 第2節 沿革 | 319 |
| 1 概要 | 319 |
| 2 平成12年度税制改正前 | 320 |
| 3 平成12年度税制改正 | 320 |
| 4 平成15年度税制改正 | 321 |
| 5 小括 | 322 |
| 第3節 住所 | 322 |
| 1 民法における住所 | 322 |
| 2 相続税法における住所 | 325 |
| 3 最高裁平成23年2月18日判決(いわゆる「武富士事件」) | 326 |
| 第4節 国籍 | 331 |
| 1 意義 | 331 |
| 2 日本国籍の得喪 | 331 |
| 3 重国籍 | 333 |
| 第5節 論点と方向性 | 334 |
| 1 住所要件・国籍要件について | 334 |
| 2 今後の方向性 | 338 |
| 第5章 個人以外の主体に対する納税義務者制度 | 340 |
| 第1節 「新たな事例」との関連性 | 340 |
| 第2節 信託制度・非営利法人制度の抜本的見直し | 341 |
| 1 信託制度 | 341 |
| 2 非営利法人制度 | 347 |
| 第3節 信託制度・法人制度の多様化・均一化 | 349 |
| 第4節 信託制度・法人制度に係る課税関係の検証 | 354 |
| 第5節 論点と方向性 | 356 |
| 1 「新たな事例」における本件信託の取扱い | 356 |
| 2 今後の方向性 | 358 |
第6章 相続税・贈与税の納税義務者制度との関連性を有するその他の論点 |
361 |
| 第1節 相続税・贈与税の納税義務者の属性の違い等に基因する税額の加算等 | 361 |
| 1 総説 | 361 |
| 2 税制上の対応方法の類型 | 362 |
| 3 相続税額の加算制度等を巡る課税関係の検証 | 364 |
| 4 納税義務者の属性の違い等に基因する課税の在り方 | 372 |
| 第2節 財産の所在場所の判定 | 376 |
| 第3節 相続税・贈与税の課税方式との関連 | 378 |
| 結びに代えて | 381 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

