相続税法第7条及び第9条の適用範囲に関する一考察
宮脇 義男
税務大学校
研究部教育官
要約
1 研究の目的(問題の所在)
相続税・贈与税の課税対象は、一義的には相続、遺贈又は贈与により取得した財産であるが、一定の生命保険金、信託に関する権利及び債務免除益など、法形式的には相続等により取得した財産に該当するとはいい難いが実質的には相続等と同視できるものも存在する。そこで、我が国の相続税法は、こうした財産を相続等により取得した財産とみなすことにより、相続税等の課税対象に含めている(相税3条〜9条の6)。
相続税法第7条は、こうした「みなし課税」の一つであり、著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には、その対価と時価との差額について贈与等があったとみなすものである。また、相続税法第9条は、みなし課税の対象とされる上記の事由のほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合にも同様に、その対価と利益の価額との差額について贈与等があったとみなすものである。
こうした相続税法第7条及び第9条は、相続税・贈与税の適切な課税を確保する上で、必要かつ基本的な規定の一つとして位置付けることができるが、近年において、これらの規定の適用を巡って国側が敗訴した事例が出現してきている状況にあり、これらの規定の適用範囲の在り方について研究を行うことが必要と考えるところである。
2 研究の概要
(1)相続税法における「みなし規定」について(第1章)
租税法においては、課税の実質的な公平を図る観点から、法形式の如何にかかわらず実体に沿った課税を実現すべく様々な「みなし規定」が存在し、これは相続税法においても同様であるが、同法におけるみなし規定の必要性は、同法に規定する相続税・贈与税の納税義務者の定めに端的に表れているといえる。すなわち、相続税法は、「相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人」(相税1条の3第1号、1条の4第1号)を相続税等の納税義務者として掲げているが、これは、相続税は基本的に相続等という無償の財産移転に担税力を見出して課税する租税である一方、相続によって財産を取得する主体は相続の本質からして自然人である個人に限られること等による。これにより、相続税等においては、課税対象の発生形態とその帰属主体の属性とが限定されることとなるが、遺贈及び贈与については個人以外の主体(法人等)も帰属主体となり得るため、両者の対応関係にズレが存在することとなり、そこに相続税固有の税負担回避が発生し得る要因が生まれることとなる。そこで、現行相続税法では、こうした税負担回避に対応する仕組みの一部について、みなし規定により手当てを講じており、課税対象の発生形態については、実質的に相続等と同視できる特定の移転形態を相続等により取得したものとみなすことにより、また、課税対象の帰属主体の属性については、個人以外の特定の主体(非営利法人等)を個人とみなすことにより、相続税等の課税対象に含めている。そして、本稿にて考察の対象とする相続税法第7条及び第9条は、前者の相続税等の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度に該当する規定であるといえる。
(2)相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度(第2章)
![]() 相続税法第7条等と第9条との関係
相続税法第7条等と第9条との関係
相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係るみなし課税制度は、昭和22年の税制改正において、当時の遺産課税方式による相続税の下、贈与税が相続税から分離して創設された際に併せて創設されたものである。その後、相続税法第7条及び第9条に相当する規定は、昭和25年に、シャウプ勧告の指摘を受けて相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めた際、みなし課税の対象者を贈与者側から受贈与者側に改める等、同課税方式に対応した見直しがなされたものの、その基本的な構造は維持されて現在にまで至っている。
こうした相続税法第7条及び第9条を始めとする同法におけるみなし課税の規定を鳥瞰すると、同法第9条は、第7条等の他のみなし課税の規定を包含する関係にある。すなわち、他のみなし課税の規定では、それぞれ課税すべき対象を特定し、その課税対象の性質に応じて課税すべきタイミングを定めているが、相続税法第9条の規定が資産価値のみの移転を含むあらゆる無償・低額による受益を課税対象とし、相続税・贈与税の課税対象とすべき財産を包括的に捉えるべく、いわばバスケット・クローズとしての構造を有しているがために、他のみなし課税の規定について対象範囲に変更が生ずると、反射的に、同法第9条の対象範囲にも影響を与えることとなる。
● 相続税法における課税対象財産の構成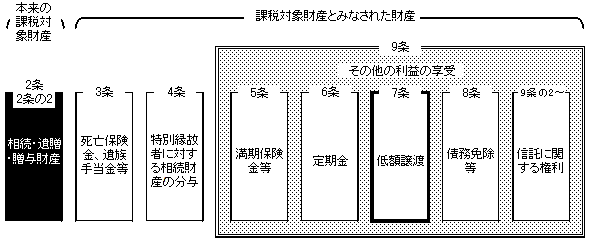
![]() いわゆる「負担付贈与通達」による対応
いわゆる「負担付贈与通達」による対応
負担付贈与通達は、主にバブル期の地価高騰時において、土地家屋等の不動産の通常の取引価額(時価)と相続税評価額(路線価等)との開きに着目しての贈与税の税負担回避行為に対して、税負担の公平を図る観点から、土地家屋等を負担付贈与(財産価額の計算上、贈与財産の価額から負担の額を控除)や個人間の対価を伴う譲渡(法形式上、贈与に該当せず)により取得した場合における時価の解釈(相続税評価額ではなく、通常の取引価額によって評価)を示すとともに、相続税法第7条及び第9条の執行上の取扱いを定めたものであり、今日においてもその解釈や取扱いは維持されているほか、上場株式の評価においても同様の解釈が採用されている。
なお、こうした負担付贈与通達は、相続税法における時価の解釈の在り方からその存在意義が説明されるほか、財産の無償・低額譲渡に係る所得税や法人税をも含めた現行の課税関係からも説得的な存在意義を見出すことができる。すなわち、財産の無償・低額譲渡に係る課税関係を鳥瞰した場合、財産の出し手側及び受け手側の属性が「個人→個人」以外の場合(個人→法人、法人→個人、法人→法人)については、財産の出し手側及び受け手側の双方において所得課税がなされる。これに対して、「個人→個人」の場合においては、現行制度上、財産の出し手側においては、限定承認に係る相続等を除き、みなし譲渡課税がなされることはなく(譲渡損は逆に損益通算される場合あり)、受け手側における贈与税の課税のみとなる場合が生ずるが、負担付贈与や対価を伴う譲渡は、こうした受け手側の課税をも回避することに繋がることとなる。
このように、負担付贈与通達は、財産の移転がなされているにもかかわらず、負担付贈与や個人間の対価を伴う譲渡という手法を利用することによって作出された、財産の出し手側及び受け手側の双方において全く課税がなされないという状態を是正すべく、相続税・贈与税の課税実務として、財産の受け手側における課税を確保すべく実務的な対応を図ったものと捉えることができる。
(3)相続税法第7条及び第9条の適用を巡る裁判事例(第3章)
相続税法第7条及び第9条の適用を巡る近年(平成元年以降)の裁判事例について、国側が勝訴した事例及び敗訴した事例の別に、課税庁及び納税者双方の主張並びにこれらの主張に対する裁判所の判断についての分析・検討を通じて、現行制度上の問題点等の抽出を試みた。
まず、国側勝訴事例については、相続税法第7条及び第9条の適用に際して、贈与意思の有無や租税回避目的の有無を問わないこと、「著しく低い価額の対価」であるか否かの判断に当たっては社会通念に照らして個別に判断することや、これらの規定における「時価」の意義などに関する解釈が示されているが、いずれも、これらの規定に関する従前からの解釈がほぼ維持されている。また、これらの規定と財産評価との関係においては、評価基本通達における財産評価の有する評価基準制度としての性格から、評価基本通達による取扱いを画一的・形式的に適用すると、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害する場合が存するとの判断がなされており、これについても、従前からの解釈や取扱いがほぼ維持されているといえる。
次に、国側敗訴事例については、事実認定の部分で敗訴したものの相続税法第7条及び第9条の適用に関する従前の解釈に変更を来すものではないものがある一方、「著しく低い価額の対価」に関する解釈や財産評価との関係の在り方など、今後、これらの規定に関する従前の解釈や取扱いに変更を来す可能性の含む判断がなされたものも存するところである。
● 国側敗訴事例の概要
○ 東京地裁平成17年10月12日判決
取引相場のない株式の売買について、本件売買における対価を評価基本通達に定められた評価方法によらないことが正当と是認される特別の事情があるとはいえず、その対価は相続税法第7条の「著しく低い価額の対価」に該当しないと判示した事例
○ 東京地裁平成19年8月23日判決
親族間における土地の売買について、本件売買における対価は相続税評価額によっていることから、その対価は相続税法第7条の「著しく低い価額の対価」に該当しないと判示し、負担付贈与通達の適用を否定した事例
○ 東京高裁平成20年3月27日判決
医療法人の跛行増資について、当時の出資1口当たりの評価額は出資金額を上回るものでないことから、増資に伴う経済的利益(出資持分の含み益)の移転は認められず、相続税法第9条所定の要件を欠くものと判示した事例
(4)相続税法第7条及び第9条の適用範囲を巡る論点の検証(第4章)
現行の相続税法第7条及び第9条の構造やこれらの規定の適用を巡る裁判事例の検討・分析などから抽出される以下のような問題点等について、その検証を試みた。
![]() 現行の相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度の構造に基因する批判
現行の相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度の構造に基因する批判
相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る個々のみなし課税の規定を包含し、あらゆる無償・低額による受益を課税対象とする相続税法第9条の規定は、従来から、租税法律主義(課税要件法定主義、課税要件明確主義)に反するとの批判がなされている。
しかし、上記(2)![]() のとおり、相続税法第9条以外の個々のみなし課税制度の対象範囲の変更が反射的に同法第9条の対象範囲に影響することから、こうしたみなし課税制度全体の構造を維持している限り、他のみなし課税制度をその時々の社会・経済状況の変化等に対応して不断の見直しを講じていくこと、場合によっては新たなみなし課税制度を講じていくことを通じて、同法第9条の適用範囲は自ずと限定され、洗練されていくこととなる。したがって、こうした取組みが上記の批判を緩和することに繋がるものと考える。
のとおり、相続税法第9条以外の個々のみなし課税制度の対象範囲の変更が反射的に同法第9条の対象範囲に影響することから、こうしたみなし課税制度全体の構造を維持している限り、他のみなし課税制度をその時々の社会・経済状況の変化等に対応して不断の見直しを講じていくこと、場合によっては新たなみなし課税制度を講じていくことを通じて、同法第9条の適用範囲は自ずと限定され、洗練されていくこととなる。したがって、こうした取組みが上記の批判を緩和することに繋がるものと考える。
![]() 「著しく低い価額の対価」という要件
「著しく低い価額の対価」という要件
上記の東京地裁平成19年8月23日判決は、相続税法第7条について、「時価より『著しく低い価額』の対価で財産の譲渡が行われた場合に課税することとしており、その反対解釈として、時価より単に『低い価額』の対価での譲渡の場合には課税しないものである」、「『著しく』低額でない限り、時価より低額での財産の譲渡が行われることを許容しているのであり、・・・・・(納税者らに)一定の経済的利益を享受させたとしても、それが著しい程度のものと認められない限り、同条は適用されないのである」と判示している。
このような判示に従うと、相続税法第7条の解釈上、「著しく低い価額」、「単に低い価額」及び「適正な価額(時価)」という三つの概念の存在を認め、その何れに該当するかの判断が求められることとなる。そして、「単に低い価額」と時価との差額部分について相続税法第7条の規定が適用されないとなると、相続税等と所得税との二重課税を排除する趣旨から設けられている所得税法上の非課税所得の規定(所税9条1項16号)が適用されないこととなり、所得税の課税対象(一時所得)に該当する可能性が生ずることとなる。
しかし、個人間の対価を伴う譲渡における財産の受け手側においては、基本的には資産の有償取得であるため、そこに課税関係が生ずることはないが、その低い対価の額が看過できない程に顕著な場合には、時価課税という贈与税の適切な課税を図る観点から、その差額部分を贈与税の課税に取り込む規定が相続税法第7条であり、そうした状態を法文上「著しく」という文言で表現したものであると考えると、あくまでも「著しく低い価額」か「適正な価額(時価)」のいずれかに判断されるべきものであって、そこに「単に低い価額」という概念の存在を認めるものではないものと考える。
もし仮に、上記の判示に従って「単に低い価額」という概念の存在を認め、「単に低い価額」に該当する場合における時価との差額部分については所得税の課税対象(一時所得)に該当するとなれば、個人間という同じ属性間における対価を伴う財産の移転でありながら、法人への低額譲渡に係るみなし譲渡課税におけるような形式基準(1/2基準)が存しない中、「著しく低い価額」か「単に低い価額」かの判定をし、そのいずれかによって受け手側における課税関係が異なることとなり、適切ではないと考える。
![]() 財産評価の在り方との関係
財産評価の在り方との関係
相続税法第7条に規定する「当該財産の時価」と同法第9条に規定する「当該利益の価額」との文言は、基本的に、同法第22条に規定する時価の概念と同一との解釈がなされているため、これらの規定は、同法における時価の解釈、財産評価の取扱いやその在り方と密接な関係を有することとなる。相続税法第7条及び第9条の適用を巡る裁判事例においても、対象財産に適用される評価方法の適否を含む財産評価の在り方が主要な争点とされる場合が多く見られるところである。
一方、評価基本通達による財産評価においては、納税者と課税庁との便宜性、課税の公平を意図した統一性、及び一般の相続等を念頭に、偶発的な財産の無償取得であることに配慮した評価の安全性(評価上のしんしゃく)が考慮されているが、このような評価基準制度に基づく評価額は便宜性等に配慮した標準価額であるため、課税時期における個々の対象財産の「時価」と乖離しやすいという構造的ともいえる特質を有しているといえる。
したがって、こうした特質を有する評価基本通達における財産評価と、そもそも一般の相続等を対象としたものとはいえない相続税法第7条及び第9条とのかかわり方については、評価基本通達による取扱いを画一的・形式的に適用すべきではないことを、より一層明確にしていく必要があるものと考える。
![]() 負担付贈与及び低額譲渡の取扱い
負担付贈与及び低額譲渡の取扱い
上記の東京地裁平成19年8月23日判決を踏まえれば、相続税評価額相当額(公示価格等の80%)で譲渡している限り、相続税法第7条及び第9条並びに負担付贈与通達を適用することはできないとも解される。しかし、本事例においては、確かに譲渡対価と相続税評価額とは一致しているものの、親族に対して取得価額の半額程度で譲渡していることや、その土地を親族会社に貸し付けることにより貸宅地としての評価上のしんしゃくを最大限に利用していること、また、土地譲渡損の損益通算が制限される直前の駆け込み的な譲渡であることなど、多分にタックス・プランニング的な要素が含まれている。
こうした要素はいずれも譲渡者側の事情に基づくものであるが、東京地裁判決は譲渡者側の事情を財産の受け手側に対する贈与税の課税の適否に取り込むべきではないと判示しており、これに従えば、取得価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合にはその取得価額による評価を認め、取得価額との比較において相続税法第7条及び第9条の適用の可否判定を認める負担付贈与通達の取扱いと抵触するおそれが生じる。しかし、生前の財産移転による相続税逃れの防止という贈与税の課税趣旨との関係を踏まえれば、こうした負担付贈与通達の取扱いには整合性を見出せることから、将来の被相続人たりうる譲渡者側の事情を全く勘案しないことは適切ではないと考える。したがって、他の要素を勘案することなく、時価の80%という数値のみをもって「著しく低い価額の対価」に該当しないとする判断には疑問が残るところであり、こうした他の要素をも勘案すべきではなかったかと考える。
![]() 利益に相当する金額の算定
利益に相当する金額の算定
例えば、同族会社に対して財産の無償提供があったことにより、既存株主が保有する当該同族会社の株式の価額が増加した場合における相続税法第9条の適用について、同じ価値の財産が同族会社に移転しているのにもかかわらず、会社の規模によって、適用すべき同族会社株式の評価方法(類似業種比準価額方式、純資産価額方式、併用方式)が異なることに基因して、その財産価値の反映度合いに違いが生じ、その結果、同法第9条を適用すべき「利益に相当する金額」に相違が生ずることとなる。
したがって、こうした場合においては、利益に相当する金額の算定方法を、会社の規模にかかわらず、無償提供のあった財産の価額そのものに着目した評価方法である純資産価額方式に統一すべきではないかと考える。
3 結論(今後の方向性)
平成22年度税制改正大綱にあるとおり、相続税については、今後、格差是正の観点から、課税ベースや税率構造の見直しに向けた議論が進められる予定であるが、我が国の相続税制を巡るこうした状況を踏まえると、相続税等の税負担回避に対しては一層厳格に対処していくことが求められる。
こうした観点から、本稿において論点の検証を試みた相続税法第7条及び第9条の適用範囲の在り方についても、上記2(4)において明示した事項を中心に、今後、解釈論及び立法論の双方にわたった一層の考察が必要と考えるが、当然のことながら、これらの規定のみであらゆる相続税等の税負担回避に対処しきれるものではない。したがって、平成22年度税制改正大綱における「法人等を利用した租税回避への対応など、課税の適正化の観点からの見直しを引き続き行っていきます」との指摘にもあるとおり、相続税法第7条及び第9条を始めとしたみなし課税制度のみならず、他の租税回避防止措置との関連をも含め、これらの在り方について、今後とも検討を深めていくことが必要と考えるところである。
目次
| 項目 | ページ |
|---|---|
| はじめに | 220 |
| 1 問題の所在 | 220 |
| 2 本稿の構成 | 221 |
| 第1章 相続税法における「みなし規定」について | 223 |
| 第1節 租税法における「みなし規定」の必要性 | 223 |
| 1 「みなす」という法令用語 | 223 |
| 2 実質課税の原則との関係 | 224 |
| 第2節 相続税法における「みなし規定」の類型 | 226 |
| 1 相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係るもの | 228 |
| 2 相続税・贈与税の課税対象の帰属主体の属性に係るもの | 228 |
| 第2章 相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度 | 230 |
| 第1節 相続税法第7条及び第9条の概要等 | 230 |
| 1 相続税法第7条(低額譲受) | 230 |
| 2 相続税法第9条(その他の利益の享受) | 232 |
| 3 両制度の比較 | 233 |
| (1)「著しく低い価額の対価」 | 234 |
| (2)「財産の譲渡」と「利益を受けた」 | 235 |
| (3)「当該財産の時価」と「当該利益の価額」 | 237 |
| (4)「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」 | 238 |
| 第2節 沿革 | 239 |
| 1 昭和22年 | 239 |
| 2 昭和25年 | 241 |
| 3 小括 | 243 |
| 第3節 その他の「みなし課税」制度 | 244 |
| 1 保険金(相税3条1項1号、5条) | 244 |
| 2 退職手当金(相税3条1項2号) | 246 |
| 3 生命保険に関する権利(相税3条1項3号) | 247 |
| 4 定期金(相税3条1項4号〜6号、6条) | 248 |
| 5 特別縁故者に対する相続財産の分与(相税4条) | 250 |
| 6 債務免除等(相税8条) | 252 |
| 7 信託に関する権利(相税9条の2〜) | 252 |
| 8 小括 | 254 |
| 第4節 相続税法における課税対象財産 | 255 |
| 1 形態別の分類 | 255 |
| 2 相続税法における課税対象財産の構成 | 257 |
| 3 相続税法第7条等と第9条との関係 | 258 |
| 第5節 いわゆる「負担付贈与通達」による対応 | 260 |
| 1 負担付贈与通達 | 261 |
| (1)趣旨 | 261 |
| (2)取扱い | 263 |
| 2 財産の無償・低額譲渡に係る課税関係からみた負担付贈与通達の位置付け | 266 |
| (1)財産の無償・低額譲渡に係る課税関係 | 267 |
| (2)負担付贈与通達の位置付け | 269 |
| 第3章 相続税法第7条及び第9条の適用を巡る裁判事例 | 272 |
| 第1節 検討事例の一覧 | 272 |
| 第2節 国側勝訴事例からの検討 | 278 |
| 1 相続税法第7条及び第9条の趣旨 | 278 |
| 2 相続税法第7条及び第9条の適用の適否 | 280 |
| (1)贈与意思の有無(錯誤)との関係 | 281 |
| (2)租税回避目的の有無との関係 | 282 |
| (3)親族以外の第三者間の取引との関係 | 283 |
| 3 無償の財産移転(価値の移転)に該当するか否か | 284 |
| (1)定期預金 | 284 |
| (2)取引相場のない株式等 | 285 |
| (3)合有不動産権(ジョイント・テナンシー) | 285 |
| 4 「著しく低い価額の対価」に該当するか否か | 286 |
| (1)判定に当たっての基本的な考え方 | 287 |
| (2)具体的な数値等を示して判定した事例 | 287 |
| 5 相続税法第7条及び第9条における「時価」の意義 | 288 |
| 6 財産評価の在り方 | 290 |
| (1)総論(評価基本通達の合理性) | 291 |
| (2)土地(宅地) | 293 |
| (3)上場株式 | 294 |
| (4)取引相場のない株式等 | 296 |
| 7 負担付贈与及び低額譲渡の取扱い | 298 |
| 8 租税法律主義等に反するか否か | 298 |
| (1)租税法律主義 | 299 |
| (2)租税公平主義 | 299 |
| (3)財産権の不可侵等 | 300 |
| (4)禁反言の法理等 | 300 |
| 第3節 国側敗訴事例からの検討 | 300 |
| 1 東京地裁平成17年10月12日判決 | 301 |
| 2 東京地裁平成19年8月23日判決 | 305 |
| 3 東京高裁平成20年3月27日判決 | 312 |
| 第4節 小括 | 319 |
| 第4章 相続税法第7条及び第9条の適用範囲を巡る論点と方向性 | 321 |
| 第1節 論点の検証 | 321 |
| 1 現行の相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度の構造に基因する批判 | 321 |
| 2 贈与意思・租税回避目的の有無と相続税法第7条及び第9条の適用の可否 | 324 |
| 3 第三者間との取引における相続税法7条及び第9条の適用の可否 | 325 |
| 4 相続税法第7条及び第9条の適用が争われた財産 | 328 |
| 5 「著しく低い価額の対価」という要件 | 329 |
| 6 財産評価の在り方との関係 | 335 |
| 7 負担付贈与及び低額譲渡の取扱い | 338 |
| 8 利益に相当する金額の算定 | 343 |
| 9 財産の無償・低額譲渡に係る課税関係 | 346 |
| 第2節 今後の方向性 | 348 |
| 1 我が国の相続税制を巡る状況 | 348 |
| 2 相続税法第7条及び第9条の適用範囲の在り方 | 349 |
| (1)現行の相続税・贈与税の課税対象の発生形態に係る「みなし課税」制度の構造(相続税法第7条等と第9条との関係) | 350 |
| (2)負担付贈与及び低額譲渡への対応の在り方 | 350 |
| (3)相続税の課税方式の見直し等との関連 | 351 |
| 結びに代えて | 353 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

