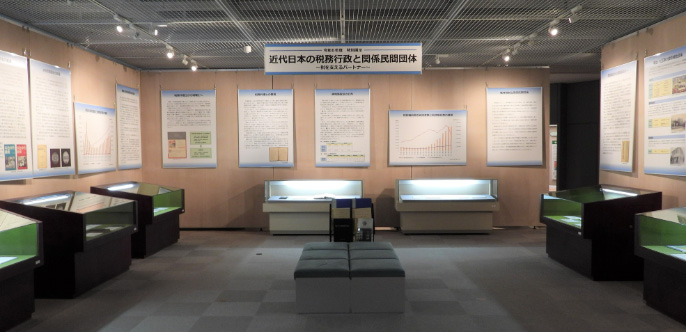令和6年度特別展示「近代日本の税務行政と関係民間団体〜税を支えるパートナー〜」
はじめに
日本の税務行政の特徴の一つに、関係民間団体の協力体制が挙げられます。
現在、納税貯蓄組合、青色申告会、法人会、間税会、納税協会、税理士会等多くの団体により、適正な申告納税制度の実現や税知識の普及、納税意識の向上のためにご協力をいただいています。
このような税をめぐる関係民間団体の協力体制は、明治時代中頃から築かれていました。
近代日本の社会や経済が発達することにより、所得税等の納税者数が増加していく一方で、税務当局は行政整理等による人手不足状態に陥り、事務多端の状況になっていました。この状態を補うため、市町村による一部直接国税の徴収事務や、織物業組合や酒造組合などによる徴収事務の委任が行われました。また、期限内納税の推進のため、明治期から各地で納税組合が自主的に結成されるようになります。
さらに、複雑化していく税法の正しい執行の補助機関として、現在の税理士制度の前身に当たる税務代理士制度も設けられました。
これらの制度は、戦後、申告納税制度の導入やシャウプ勧告と同時期に再整備されていきました。
今回の特別展示では、近代日本の税務行政が様々な関係民間団体に支えられてきた背景と、関係民間団体の変遷についてご紹介いたします。
特別展示の風景