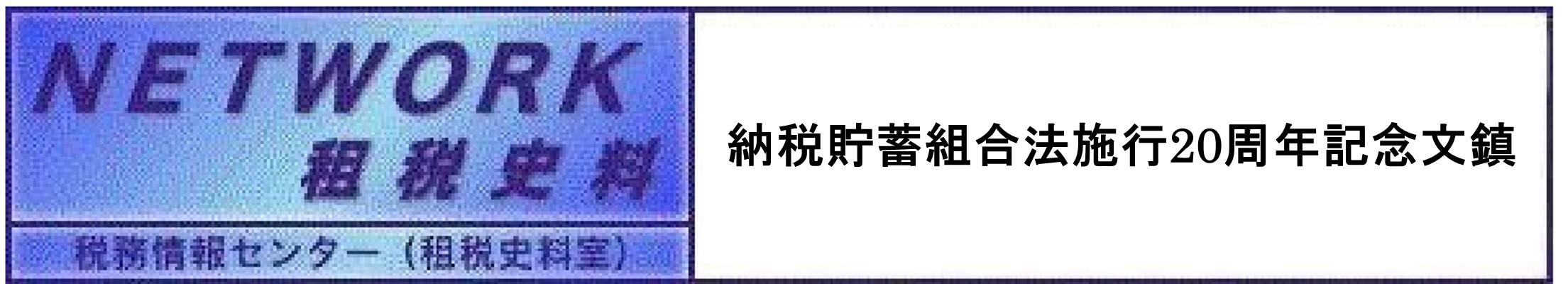
今回ご紹介する史料は、納税貯蓄組合法施行20周年を記念して作成された文鎮です。どちらも「納税貯蓄組合法施行20周年記念」と刻印されていて同じようなデザインですが、よく見ると若干違いがあります。
【写真1】は、全国納税貯蓄組合連合会の名が刻印され、桜の花びらの真ん中にミツバチがあしらわれています。他方、【写真2】は、東住吉税務署と東住吉納税貯蓄組合連合会の名が刻印され、ミツバチはあしらわれていません。今回は、この史料について調べていきましょう。
納税貯蓄組合は、「納税資金の備蓄による各種税金の円滑な納付」を目的として、昭和26年(1951)の納税貯蓄組合法制定により、全国で結成されていきました。
この納税貯蓄組合法制定以前には、さまざまな形態の納税組合が存在していました。納税組合は、日露戦争(明治37年〜明治38年)前後に全国で盛んに結成されていきました。昭和18年(1943)には、納税施設法が制定され、納税組合のほか町内会も納税団体として指定し、納税補助の役割を担わせるようになりました。
この納税施設法は、戦後の民主化政策の一環として、昭和22年(1947)に廃止され、納税団体は解散しました。しかし、戦後の社会や経済が混乱し、税の収納状況が極度に悪化する中、自然発生的に、納税貯蓄組合が結成されていくようになりました。これらの団体の民主的な発展を図るとともに、税の収納状況の向上に資するために、新たな法制化が求められ、昭和26年に議員立法で納税貯蓄組合法が制定されました。
納税貯蓄組合法が制定された直後の昭和26年6月時点の納税貯蓄組合の組合員数は約20万人でしたが、その後、昭和30年(1955)度末には約280万人、昭和36年(1961)度末には約510万人、昭和41年(1966)度末には約830万人と、会員数は着実に増加していきました。また、昭和33年(1958)には、全国組織として全国納税貯蓄組合連合会が結成されました。
昭和30年代、昭和40年代は、納税貯蓄組合が大きく発展していった時期にあたります。そして、納税貯蓄組合法制定20周年を迎えるに際して、昭和46年(1971)10月6日に国会や大蔵省、自治省、国税庁の代表も出席して大々的な式典が開催されたのです。
今回ご紹介した【写真1】の史料は、昭和46年10月6日に、東京都丸の内の東京商工会議所ホールで、納税貯蓄組合法施行20周年記念式典が開催された際に、永年の組合功労者に対して、全国納税貯蓄組合連合会会長表彰の対象者(2,123名)に副賞として授与されたブロンズ製文鎮です。桜の花びらの中にミツバチがあしらわれているデザインは、全国納税貯蓄組合連合会の会章です。
この東京丸の内で開催された全国規模の式典のほかにも、各地でさまざまなイベントが催されていました。【写真2】の史料は、関係文献が残されておらず詳細は不明ですが、東住吉税務署管内で同様の式典が開催されたものと考えられます。
この史料が作成される記念式典直前の昭和45年度末の納税貯蓄組合の会員数は約962万人にまでなっていました。さらに、式典が挙行される昭和46年度に、全国納税貯蓄組合連合会は、会員数1,000万人突破をめざし、特に10月を「1,000万人増強月間」と銘打って組合員増強に取り組んでいます。
今回ご紹介した史料は、納税貯蓄組合の会員数が目覚ましく増加していたこのような時期に作られたのです。
なお、今回ご紹介した【写真1】の史料は、租税史料室の令和6年度特別展示で展示しています。
納税貯蓄組合は、「納税資金の備蓄による各種税金の円滑な納付」を目的として、昭和26年(1951)の納税貯蓄組合法制定により、全国で結成されていきました。
この納税貯蓄組合法制定以前には、さまざまな形態の納税組合が存在していました。納税組合は、日露戦争(明治37年〜明治38年)前後に全国で盛んに結成されていきました。昭和18年(1943)には、納税施設法が制定され、納税組合のほか町内会も納税団体として指定し、納税補助の役割を担わせるようになりました。
この納税施設法は、戦後の民主化政策の一環として、昭和22年(1947)に廃止され、納税団体は解散しました。しかし、戦後の社会や経済が混乱し、税の収納状況が極度に悪化する中、自然発生的に、納税貯蓄組合が結成されていくようになりました。これらの団体の民主的な発展を図るとともに、税の収納状況の向上に資するために、新たな法制化が求められ、昭和26年に議員立法で納税貯蓄組合法が制定されました。
納税貯蓄組合法が制定された直後の昭和26年6月時点の納税貯蓄組合の組合員数は約20万人でしたが、その後、昭和30年(1955)度末には約280万人、昭和36年(1961)度末には約510万人、昭和41年(1966)度末には約830万人と、会員数は着実に増加していきました。また、昭和33年(1958)には、全国組織として全国納税貯蓄組合連合会が結成されました。
昭和30年代、昭和40年代は、納税貯蓄組合が大きく発展していった時期にあたります。そして、納税貯蓄組合法制定20周年を迎えるに際して、昭和46年(1971)10月6日に国会や大蔵省、自治省、国税庁の代表も出席して大々的な式典が開催されたのです。
今回ご紹介した【写真1】の史料は、昭和46年10月6日に、東京都丸の内の東京商工会議所ホールで、納税貯蓄組合法施行20周年記念式典が開催された際に、永年の組合功労者に対して、全国納税貯蓄組合連合会会長表彰の対象者(2,123名)に副賞として授与されたブロンズ製文鎮です。桜の花びらの中にミツバチがあしらわれているデザインは、全国納税貯蓄組合連合会の会章です。
この東京丸の内で開催された全国規模の式典のほかにも、各地でさまざまなイベントが催されていました。【写真2】の史料は、関係文献が残されておらず詳細は不明ですが、東住吉税務署管内で同様の式典が開催されたものと考えられます。
この史料が作成される記念式典直前の昭和45年度末の納税貯蓄組合の会員数は約962万人にまでなっていました。さらに、式典が挙行される昭和46年度に、全国納税貯蓄組合連合会は、会員数1,000万人突破をめざし、特に10月を「1,000万人増強月間」と銘打って組合員増強に取り組んでいます。
今回ご紹介した史料は、納税貯蓄組合の会員数が目覚ましく増加していたこのような時期に作られたのです。
なお、今回ご紹介した【写真1】の史料は、租税史料室の令和6年度特別展示で展示しています。
(2025年1月 研究調査員 今村 千文)



