第1章 組織と管理
第1節 機構と定員
1 機構の概要
-
国税庁は、内国税(国税のうち関税、とん税及び特別とん税を除いたもの)の賦課徴収を担当する行政機関であり、財務省の外局として設置されている。
国税庁の組織としては、中央に国税庁(本庁)、施設等機関、特別の機関、審議会等が置かれ、地方支分部局として全国に11の国税局及び沖縄国税事務所、その下部組織として524の税務署が置かれている(平成30年度)。 - (1) 国税庁(本庁)
-
国税庁(本庁)は、税務行政の執行に関する企画及び立案を行い、これを各国税局、沖縄国税事務所に指示しそれらと税務署の指導監督を行っている。
- イ 最近10年間の機構の変遷
-
国税庁(本庁)における最近10年間の機構の変遷については以下のとおりである。
- 平成21年7月 内部事務一元化のため、管理課が廃止され管理運営課を新設
- 平成22年7月 長官官房国際業務課に国際課税分析官を新設、課税部審理室に国税争訟分析官を新設
- 平成23年7月 長官官房国際業務課相互協議室に相互協議支援官を新設、課税部鑑定企画官に酒類国際技術情報分析官を新設
- 平成24年7月 長官官房企画課に国税企画官を増設、課税部資産評価企画官に財産評価手法研究官を新設、徴収部徴収課に徴収争訟分析官を新設
- 平成25年7月 長官官房企画課に国税企画官を増設、同課に海外税務分析官を新設
- 平成26年7月 長官官房に参事官を増設、長官官房国際業務課に国際企画官を増設、課税部鑑定企画官に分析鑑定技術支援官を新設
- 平成27年10月 長官官房企画課に法人番号管理室を新設
- 平成28年7月 長官官房に参事官を増設、長官官房総務課に広報広聴室を新設、長官官房企画課に国税企画官を増設、課税部課税総括課に課税企画官を増設、消費税軽減税率制度への対応として、同課に消費税軽減税率制度対応室を新設、課税部課税総括課審理室に主任訟務専門官を新設
- 平成29年7月 課税部課税総括課に国際課税企画官を新設
- 平成31年4月 長官官房総務課に公文書監理室を新設
- ロ 機構の内容
-
平成30年度における国税庁(本庁)の機構は、長官官房、課税部、徴収部、調査査察部からなっており、具体的な内容は次のとおりである。
- (イ) 長官官房
-
審議官、参事官、総務課、人事課、会計課、企画課、国際業務課、厚生管理官、首席国税庁監察官、企画官、税務相談官からなる長官官房は、主として一般行政事務を所掌し、また、各部課や施設等機関及び特別の機関を横断的に統合し、調整する役割を果たしている。
審議官は2人置かれており、国際等担当は、国税庁の所掌事務のうち監督評価官室(実績の評価に関することに限る。)、会計課及び国際業務課の所掌事務に関する特に重要な事項等についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括しており、酒税等担当は国税庁の所掌事務のうち企画課、酒税課及び鑑定企画官の所掌事務に関する特に重要な事項等についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括している。参事官は3人置かれており、国税庁の情報システムの整備及び管理に関する重要事項等(法人番号管理室の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案に参画する担当、法人番号管理室の所掌事務に関する重要事項等についての企画及び立案に参画する担当、消費税軽減税率制度対応室の所掌事務に関する重要事項等についての企画及び立案に参画する担当としている。首席国税庁監察官は、国税庁監察官等を総括し、職員の職務に関する非行の防止を図るとともに、非行事件に関して犯罪の捜査を行い必要な行政上又は刑事上の措置をとることにより綱紀の粛正を図っている。企画官は、国税庁の所掌事務のうち重要な事項についての企画及び立案を行っており、広報広聴室の室長を併任している。税務相談官は、税務一般に関する相談や苦情に関する事務を行っている。
なお、総務課には、国税庁の所掌事務の総合調整のうち特に重要な事項についての調整等を行う調整室、監督評価官を総括し、各国税局、沖縄国税事務所及び税務署の事務運営についての一般行政の監察を行っている監督評価官室、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる国税企画官が置かれている。
また、企画課には、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案にあたる国税企画官が置かれている。
あわせて、国際業務課には、外国との租税に関する協定の実施についての協議を行う相互協議室、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる国際企画官、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての調整その他専門的事項を処理する国際企画調整官が置かれている。 - (ロ) 課税部、徴収部
-
課税部の各課(課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課及び酒税課)及び徴収部の各課(管理運営課及び徴収課)は、各国税局、沖縄国税事務所及び税務署の指導監督等に当たっている。
このほか、課税部には、相続税、贈与税などに関し、必要な財産の評価についての企画及び立案に当たる資産評価企画官、間接国税課税物件の分析及び鑑定等についての企画及び立案に当たる鑑定企画官が置かれ、更に、同部課税総括課には消費税の賦課に関する事務の調整等を行う消費税室、内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務を総括する審理室並びに課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(国際課税企画官の所掌を除く。)に当たる課税企画官及び課税総括課の所掌事務のうち国際課税に係るものその他の重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる国際課税企画官が、同部酒税課には酒税課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる酒税企画官が置かれている。
なお、これらの事務を処理するため、課税部及び徴収部に国税実査官が置かれている。 - (ハ) 調査査察部
-
調査査察部には、国税局の行う大規模法人の調査事務の指導監督等を行う調査課と、国税局の行う大口脱税者の査察事務の指導監督等を行う査察課が置かれている。また、調査課には命を受けて上記の調査課の事務のうち海外取引、移転価格取引及び外国法人に係るものを処理する国際調査管理官が置かれている。
なお、これらの事務を処理するため、調査課に国税調査官が、査察課に国税査察官が置かれている。
- (2) 施設等機関及び特別の機関
-
施設等機関としては、税務職員に対し職務の遂行に必要な研修を行っている税務大学校があり、本校のほか、各国税局、沖縄国税事務所単位に地方研修所が置かれている。
特別の機関としては、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う国税不服審判所があり、全国に12の支部及び7の支所が置かれている。
施設等機関及び特別の機関の最近10年間の機構の変遷については、平成22年7月に税務大学校研究部に国際支援室を新設、平成23年7月に税務大学校札幌研修所に主幹を新設、平成26年7月に国税不服審判所に行政救済分析官を新設している。 - (3) 審議会等
- 平成13年1月の中央省庁等改革に関連し、従来の国税審査会、税理士審査会及び中央酒類審議会が統合され、財務省設置法の規定に基づき国税審議会が設置された。国税審議会は20人以内の委員で組織され、国税不服申立事案の処理について学識経験者の公正な意見を反映させる国税審査分科会、税理士試験及び税理士の懲戒処分についての審議等を行う税理士分科会並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律等に定める事項の調査審議等を行う酒類分科会が置かれている。
- (4) 地方支分部局
-
各国税局、沖縄国税事務所は、国税庁の指導監督の下で税務署の賦課徴収事務について指導監督を行うとともに、自らも特定の賦課徴収事務を行っている。
- イ 国税局
-
- (イ) 最近10年間の機構の変遷
-
国税局における最近10年間の機構の変遷については以下のとおりである。
- 平成21年7月 内部事務一元化のため、各国税局の管理課が廃止され管理運営課を新設
- 平成22年7月 札幌・仙台・関東信越・東京・名古屋・大阪・広島・福岡の各国税局の課税第二部法人課税課に源泉所得税事務集中処理センター室を新設
- 平成23年7月 東京国税局の調査第四部に次長を新設、熊本国税局課税部法人課税課に源泉所得税事務集中処理センター室を新設
- 平成24年7月 札幌国税局の課税第二部に次長を増設、東京国税局の査察部に査察広域課を新設
- 平成25年7月 名古屋国税局調査部に国際情報課を新設、大阪国税局査察部に査察広域課を新設
- 平成26年7月 金沢及び高松の各国税局課税部法人課税課に源泉所得税事務集中処理センター室を新設、福岡国税局総務部に総括税務相談官を新設
- 平成27年7月 関東信越国税局徴収部に特別整理総括第一課及び第二課を新設
- 平成28年7月 仙台・広島の各国税局の総務部に総括税務相談官を新設
- 平成30年7月 東京国税局の課税第一部に次長を増設、同局の徴収部に特別機動国税徴収官を新設
- (ロ) 機構の内容
-
平成30年度における国税局の機構は、総務部、課税第一部及び第二部(金沢・高松・熊本の各国税局においては課税部)、徴収部、調査査察部(東京国税局においては調査第一から第四部及び査察部、名古屋国税局においては調査部及び査察部、大阪国税局においては調査第一・第二部及び査察部)の各部からなっており、具体的な内容は次のとおりである。
- A 総務部
-
総務部には、国税局の総合調整事務等を行う総務課、職員の任免等に関する事務を行う人事第一課、職員の任用試験、服務、身分上の特別調査等を行う人事第二課(東京国税局においては、職員の身分上の特別調査等を行う考査課が別に置かれている。)、会計の監査等を行う会計課、長期的な運営方針に関する事務等を行う企画課、職員の衛生、医療その他福利厚生に関する事務等を行う厚生課、情報システムに関する調整等を行う事務管理課(東京国税局においては事務管理第一から第三課)、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務を行う税務相談室(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、広報及び広聴に関する事務等を行う国税広報広聴室が置かれている。
このほか、情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関する事務等を行う情報処理管理官(東京・大阪の各国税局)、税理士制度の運営に関する事務のうち国税局長が指定するものを処理する税理士監理官、人事課の事務のうち国税局長が指定するものを処理する人事調査官(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、税務一般に関する相談等に対応する税務相談官、納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言等を行う納税者支援調整官が置かれている。
なお、部長を補佐する次長が各国税局に各1人(東京国税局においては2人)置かれている。 - B 課税(第一・第二)部
-
金沢、高松及び熊本国税局を除き、各国税局の課税部は、個人に係る課室等の課税第一部と、法人に係る課室等の課税第二部に分かれている。
課税(第一・第二)部には、内国税の賦課に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関する事務等を行う課税総括課、税務署の指導監督等を行う個人課税課、資産課税課、法人課税課、消費税課及び酒税課のほか、所得税、法人税、相続税等、消費税及び印紙税の特に必要があると認められる調査等を行う資料調査課(金沢・高松・熊本の各国税局の課税部及び関東信越・名古屋の各国税局の課税第一・第二部においては資料調査第一・第二課、東京国税局の課税第一部においては資料調査第一から第四課、課税第二部においては資料調査第一から第三課、大阪国税局の課税第一部においては資料調査第一から第三課、課税第二部においては資料調査第一・第二課)が置かれている。
更に、内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務等を行う審理課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、相続税、贈与税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事務等を行う機動課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務を行う国税訟務官室(関東信越・東京・名古屋・大阪・広島の各国税局)、間接国税課税物件の分析及び鑑定その他間接国税の賦課に関する技術的事項等を行う鑑定官室、相続税等の賦課に必要な財産の評価等を行う資産評価官、課税第一部及び課税第二部の事務のうち、国税局長が必要があると認めた特定事項について企画及び立案並びに調整に当たる企画調整官(東京国税局)、国税局長が特に必要と認めた事項に関する事務等を行う統括国税実査官(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、たばこ税等及び酒税の課税標準等の調査等の事務等を行う統括国税調査官(仙台・関東信越・東京・名古屋・大阪・熊本の各国税局)が置かれている。
なお、内国税の賦課に関する法令の適用等に関する事務を行う審理官(関東信越・名古屋の各国税局を除く。)、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務を処理する国税訟務官、間接国税課税物件の分析及び鑑定の事務等を処理する鑑定官、酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する事務等を処理する酒類業調整官、税務署の指導監督に関する事務等を処理する国税実査官、大規模事業者の間接諸税、酒税の調査等を処理する国税調査官が置かれている。
また、部長を補佐する次長が東京国税局に3人、金沢・高松・福岡の各国税局に各1人、その他の国税局に各2人、部長を補佐し酒税課、鑑定官室等の事務を整理する酒類監理官が各国税局に各1人置かれている。 - C 徴収部
-
徴収部には、税務署の指導監督等を行う管理運営課及び徴収課、国税通則法等の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行及び納税の猶予に関する事務(以下「引継ぎに係る滞納処分等の事務」という。)を行う統括国税徴収官が置かれている。
更に、国税局長が特に必要と認めた滞納処分等について税務署の指導等を行う機動課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、引継ぎに係る滞納処分等の事務の管理等を行う特別整理総括(第一・第二)課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、内国税の徴収に関する不服申立てに関する事務等を行う国税訟務官室(東京・名古屋・大阪の各国税局)、国税通則法の規定により国税局長が引継ぎを受けた相続税の延納及び物納に関する事務を行う納税管理官(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、引継ぎに係る滞納処分等の事務のうち特に処理困難なものとして国税局長が指定するものを行う特別国税徴収官(金沢・高松・熊本の各国税局を除く。)、特別国税徴収官の事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を行う特別機動国税徴収官(東京国税局)が置かれている。
なお、内国税の徴収に関する不服申立てに関する事務等を処理する国税訟務官、税務署の指導監督に関する事務等を処理する国税実査官、引継ぎに係る滞納処分等の事務等を処理する国税徴収官が置かれている。
また、部長を補佐する次長が、関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局に各1人置かれている。 - D 調査査察部
-
調査査察部は、原則として資本金1億円以上の内国法人及び外国法人等の法人税等の調査を担当する調査担当(東京国税局においては調査第一から第四部、名古屋国税局においては調査部、大阪国税局においては調査第一・第二部)と内国税の大口脱税者の査察調査、嫌疑者の告発等を行う査察担当(東京・名古屋・大阪の各国税局においては査察部)が置かれている。
調査担当には、各国税局に特別国税調査官、統括国税調査官が置かれているほか、統括国税調査官等の調査方針及び計画の企画・立案等を行う調査管理課並びに調査総括課(東京・名古屋・大阪の各国税局)、連結申告法人等に係る調査の計画及び立案の総括に関する事務等を行う広域情報管理課(東京・名古屋・大阪の各国税局)、調査結果の審理等を行う調査審理課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、海外取引についての調査・指導等を行う国際調査課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、移転価格取引等に係るものの指導等を行う国際情報(第一・第二)課(東京・名古屋・大阪の各国税局)、電子計算組織による企業会計処理に係るものの指導等を行う調査開発課(東京・名古屋・大阪の各国税局)が置かれている。
査察担当には、各国税局に特別国税査察官、統括国税査察官が置かれているほか、統括国税査察官等の調査方針及び計画の企画・立案等を行う査察管理課(金沢・高松・熊本の各国税局を除く。)、並びに査察総括第一・第二課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、広域取引に係るものの指導や情報の収集等を行う査察広域課(東京・大阪の各国税局)、資料情報事務の運営に関する企画等を行う資料情報課(関東信越・東京・名古屋・大阪の各国税局)、国税通則法第11章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理等を行う査察審理課(東京国税局)、機械化会計に係る調査技法の開発等を行う査察開発課(東京・大阪の各国税局)、海外取引に関する犯則事件の調査及び処分等を行う査察国際課(東京・大阪の各国税局)が置かれている。
なお、これらの調査及び査察事務等を処理するため、国税調査官及び国税査察官が置かれている。
また、部長を補佐する次長が、東京国税局に7人(調査第一部2人、第二部、第三及び第四部各1人、査察部2人)、大阪国税局に3人(調査第一部、第二部、査察部に各1人)、名古屋国税局に2人(調査部、査察部に各1人)、関東信越国税局に2人、札幌・仙台・広島・福岡の各国税局に各1人、部長を補佐し国際調査課等の事務を整理する国際監理官が東京国税局に1人置かれている。
- (ハ) 審議会等
- 各国税局には、相続税、贈与税及び地価税の土地等の評価に関して国税局長が意見を求めた事項について調査審議をする土地評価審議会が置かれている。
- ロ 沖縄国税事務所
-
- (イ) 最近10年間の機構の変遷
-
沖縄国税事務所における最近10年間の機構の変遷については以下のとおりである。
- 平成28年7月 総括税務相談官を新設
- (ロ) 機構の内容
-
平成30年度における沖縄国税事務所の機構は、総務課、人事課、会計課、事務管理課、課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課、資料調査課、徴収課、調査課、査察課、統括国税徴収官、税務相談官、納税者支援調整官、国税広報広聴官、国税訟務官、酒類業調整官からなっており、間税課には鑑定官が置かれている。その機構の内容は国税局とほぼ同じであるが、国税局における企画課の事務は総務課で、厚生課の事務は会計課で、酒税課と消費税課の事務は間税課で、管理運営課の事務は徴収課で所掌している。
なお、これらの事務を処理するため、国税実査官、国税調査官、国税徴収官及び国税査察官が置かれている。
また、所長を補佐する次長が3人置かれている。 - (ハ) 審議会等
- 国税局と同様、土地評価審議会が置かれている。
- ハ 税務署
-
税務署は、国税庁、各国税局及び沖縄国税事務所の指導監督の下に内国税の賦課徴収を担当する第一線の機関であり、全国の主要な地に524署が置かれている。
税務署の機構は、署の規模によりいくつかの形態に分かれているが、一般的には、内部事務を担当する総務課及び管理運営部門と外部事務を担当する徴収部門、個人課税部門、資産課税部門、法人課部門及び酒類指導官に分けられており、具体的な内容は次のとおりである。- (イ) 総務課においては、署内の総合調整や庶務、人事、会計、厚生などの事務のほか、対外的な広報広聴事務等を行っている。
- (ロ) 管理運営部門においては、納税証明書の発行、申告書・申請書等の収受、申告・納税等に関する基本情報の処理、租税債権の管理、国税に係る還付金等の還付、相続税の延納、物納の許可等の事務を行っている。
-
(ハ) 徴収部門においては、納付の相談や滞納となった国税の滞納処分等の事務を行っている。
なお、一定額以上の大口滞納については、国税局の徴収部が滞納処分等の事務を行っている。 - (ニ) 個人課税部門においては、所得税及び個人事業者の資産の譲渡等に係る消費税の申告相談、申告書等の処理、調査、不服申し立てに関する事務や、所得計算の基となる収入、支出等に関する資料を収集し整理する資料事務等を行っている。
- (ホ) 資産課税部門においては、相続税及び贈与税等の申告相談、申告書等の処理、調査、不服申し立てに関する事務等を行っている。
-
(ヘ) 法人課税部門においては、法人税・源泉所得税、法人の資産の譲渡等に係る消費税及び間接諸税の申告相談、申告書等の処理、調査、不服申し立てに関する事務等を行っている。
なお、税務署においては、原則として資本金1億円未満の法人について、調査を行っている。 -
(ト) 酒類指導官においては、酒税の申告相談、調査に関する事務や酒類業の発達に係る事務等を行っている。
更に、主要な税務署に、税務に関する広報事務や納税者からの意見を聴く広聴事務を行う税務広報広聴官が置かれている。
なお、規模の小さい税務署では、管理運営部門や徴収部門を置かずに総務課に管理運営及び徴収担当が置かれその事務を行っていたり、個人課税部門、資産課税部門、法人課税部門の事務を合わせて行う調査部門が置かれている場合がある。
これらの事務を円滑に遂行するため、各税務署を通じて、副署長、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官、国税徴収官及び国税調査官が置かれている。
2 定員
-
国税庁の定員は、「行政機関職員定員令」により財務省全体の定員が規定され、これを受けて「財務省定員規則」により国税庁の定員が、更に「財務省定員細則」により国税庁の内部部局等の定員が規定されている。
国税庁の30年度定員は全体で55,724人であり、具体的には、国税庁(本庁)に984人、国税局に11,683人、沖縄国税事務所に168人、税務署に42,094人(内沖縄363人)、その他の機関に795人(税務大学校に324人及び国税不服審判所に471人)が配置されている。
第2節 職員の任用
1 概要
-
昭和20年代前半に、税制の改革や徴税機構の整備に対応するためかなりの増員を行ったが、昭和20年代後半には、予算定員の減少や行政整理により毎年定員が削減され新規採用者数は急激に減少し、昭和35年頃まで少数採用期が続いた。
その後、昭和20年代前半に採用された職員が、昭和50年代後半から退職の時期を迎え相当数の職員が退職するとともに、消費税導入等に伴う定員増により、新規採用者数が増加したが、平成元年をピークに退職者数及び新規採用者数ともに減少傾向に転じた。
その傾向はしばらく続いたが、平成15年以降は退職者数は増加傾向、新規採用者も平成23年度から平成25年度における、政府による国家公務員の新規採用抑制(閣議決定)の期間を除き、基本的に増加傾向にあり、現在、職員の年齢構成は、30歳代後半から40歳前半の職員が少ないといういびつな構成となっている。
このように採用者数の変動は、職員の年齢構成を極めて特異なものとし、世代間の処遇等の公平を図る上で困難な問題を生じさせるとともに、管理者の要員に関する問題や経験年数の浅い職員の育成等の問題を生じさせる原因となっている。
国税庁の人事行政は、このような幾多の難問に対処しながら現在に至っているが、この間、社会経済情勢の変化や行財政改革の推進に的確に対応できる職場体制の確立を図るとともに、職員の士気を向上させるための処遇の改善や職員の資質を向上させるための研修制度の充実など、各種の施策を講じてきた。
2 採用等
- (1) 国家公務員採用総合職試験による採用
-
平成24年度以降、国家公務員採用総合職試験(旧国家公務員採用Ⅰ種試験。以下同じ。)合格者の中から採用を行っている。
令和元年度には、国家公務員採用総合職試験合格者の中から、12人(事務系7人、技術系5人)の採用を行った。 - (2) 国税専門官採用試験による採用
-
昭和45年に始まった大学卒業程度の者を対象とした国税専門官採用試験の採用者数は、大学進学率の上昇に伴い徐々に大卒に依存することとなった結果、平成6年度に税務職員採用試験(旧国家公務員採用Ⅲ種試験(税務)。以下同じ。)の採用者数を上回ることとなった。以降、新規採用者数に占める国税専門官の割合は5割以上を維持している。
平成26年度からは、新規採用抑制が行われなかったことから、平成23年度から平成25年度において生じた大幅な欠員を解消するため、1,000人を超える採用を行っており、令和元年度の採用においては、過去最大となる1,158人の採用を行った。 - (3) 税務職員採用試験による採用
- 高校卒業程度の者を対象とした税務職員採用試験の採用者数は、新規採用抑制の影響により、平成25年度の採用では182人まで減少したが、平成26年度からは、新規採用抑制が行われなかったことから、平成23年度から平成25年度において生じた大幅な欠員を解消するため、700名程度の採用が続いている。
- (4) 経験者採用試験(国税調査官級)による採用
-
公務部門での育成では得られない専門性や多様な経験を有する有為な民間人材の選考採用を推進するため、人事院が各府省の選考採用に協力して、公募や筆記試験、課題討議、人物試験などの能力実証を行うとして、平成18年度に導入され、平成24年度には、採用試験体系の再編に伴い、競争試験に移行した。
国税庁においては、平成22年度から試行的かつ断続的に十数名を採用するところから始め、平成27年度以降継続して本制度を利用し採用することとなった。
なお、平成29年度以降採用規模を大幅に拡大し200名程度の採用を行っている。 - (5) 障害者を対象とした選考による採用
-
「公務部門における障害者雇用に関する基本方針(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議)」において、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を平成30年度より導入することとされた。
国税庁では、同制度を利用し、令和元年度に常勤職員として90人を採用した。 - (6) 女性職員の採用
-
国税専門官採用試験については昭和55年から、税務職員採用試験については昭和56年から、それぞれ女性の受験が可能となった。
「財務省女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画(以下「WLB取組計画」という。)」(平成26年12月財務省)において、女性の採用に係る目標として、「第4次男女共同参画基本計画における『国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を政府全体で30%以上とすること』との目標や、府省全体の女性職員の割合及び採用試験の合格者に占める女性の割合にも留意しつつ、人物本位の選考により、意欲ある有為な女性の採用に努めるものとする。」と規定された。以後、国税庁はこの目標を踏まえた採用活動を行った結果、平成27年度以降、女性職員の採用割合はおおむね30%程度を推移している。
事務職員の採用状況等
| 採用年度 | 総合職 | 国税専門官 | 税務職員 | 経験者 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用者数 | 女性割合 | 採用者数 | 女性割合 | 採用者数 | 女性割合 | 採用者数 | 女性割合 | 採用者数 | 女性割合 | |
| 平成22 | (3) | 23.1% | (228) | 25.2% | (196) | 36.8% | (3) | 33.3% | (430) | 29.5% |
| 13 | 905 | 532 | 9 | 1,459 | ||||||
| 平成23 | (1) | 11.1% | (161) | 21.8% | (126) | 36.4% | - | (288) | 26.3% | |
| 9 | 740 | 346 | - | 1,095 | ||||||
| 平成24 | (4) | 44.4% | (163) | 22.4% | (126) | 34.4% | (8) | 38.1% | (301) | 26.8% |
| 9 | 728 | 366 | 21 | 1,124 | ||||||
| 平成25 | (2) | 20.0% | (151) | 26.7% | (69) | 37.9% | - | (222) | 29.3% | |
| 10 | 566 | 182 | - | 758 | ||||||
| 平成26 | (2) | 16.7% | (248) | 23.2% | (132) | 33.6% | - | (382) | 25.9% | |
| 12 | 1,068 | 393 | - | 1,473 | ||||||
| 平成27 | (7) | 46.7% | (295) | 28.7% | (245) | 35.2% | (7) | 46.7% | (554) | 31.6% |
| 15 | 1,029 | 696 | 15 | 1,755 | ||||||
| 平成28 | (3) | 30.0% | (416) | 36.0% | (245) | 34.9% | (5) | 20.8% | (669) | 35.4% |
| 10 | 1,154 | 703 | 24 | 1,891 | ||||||
| 平成29 | (6) | 50.0% | (262) | 25.1% | (272) | 34.1% | (34) | 18.7% | (574) | 28.2% |
| 12 | 1,043 | 797 | 182 | 2,034 | ||||||
| 平成30 | (4) | 30.8% | (339) | 30.6% | (282) | 36.0% | (31) | 15.5% | (656) | 31.1% |
| 13 | 1,109 | 784 | 200 | 2,106 | ||||||
| 令和元 | (6) | 50.0% | (328) | 28.3% | (300) | 39.2% | (46) | 22.0% | (680) | 31.7% |
| 12 | 1,158 | 765 | 209 | 2,144 | ||||||
(注) カッコ書きは女性の内数を示す。
3 人事配置
-
国税庁が創設された昭和24年以来、職員の異動については、公務の要請に基づき適材を適所に配置し、行政効率を最大限に発揮できるようにという考え方を基に、職員個々に適性、能力、実績等を把握し、これらを総合勘案して適正・公平な人事の確保に努めている。
そして、よく職責を果たした職員については、積極的に上位ポストに登用するなど、職員が意欲と希望をもって職務に精励できるよう配意している。
また、近年においては、再任用職員の活用や「WLB取組計画」を積極的に推進するなど、国税庁を取り巻く環境の変化に応じた各種の取組を行っている。
なお、以上の前提として、職員の能力、実績等を評価するため、人事評価を実施するほか、職員の身上や希望などを的確に把握する目的で、職員自身が身上申告を行う制度を採用している。
4 研修
- 現行の職員研修は、税務大学校における長期研修、短期研修及び通信研修と国税局単位、税務署のブロック単位及び各税務署単位で実施する職場研修から成っている。各研修については、第2章第2節で詳述しているので、ここではその概要について述べる。
- (1) 税務大学校における研修
-
- イ 長期研修
-
- (イ) 普通科
- 税務職員採用試験による採用者、国家公務員中途採用者選考試験(税務)による採用者(平成20年度~平成23年度)及び障害者を対象とした選考による採用者(令和元年度以降)に対し、職務の遂行に必要な基礎的事項を習得させることを目的として、採用直後、1年間全寮制により、地方研修所において実施している。
- (ロ) 初任者基礎研修
- 普通科終了後1年間の実務経験を経た職員に対し、職務の遂行に必要な知識等を習得させることを目的として、3か月間地方研修所において平成25年度まで実施していた。
- (ハ) 中等科
-
平成26年度から普通科終了後3年間の実務経験を経た職員に対し、職務に必要な知識・技能等を習得させることを目的として、3か月間地方研修所において実施している。
なお、平成28年度以降、研修期間を「2か月間」から「3か月間」に延長した。 - (ニ) 専門官基礎研修
-
国税専門官採用試験による採用者に対し、職務の遂行に必要な基礎的事項を習得させることを目的として、採用直後、3か月間和光校舎において実施している。
なお、平成21年度以降、研修期間を「4か月間」から「3か月間」に短縮した。 - (ホ) 専攻税法研修
- 平成22年度から専門官基礎研修終了後1年間の実務経験を経た職員等に対し、職務の遂行に必要な知識・技能等を習得させることを目的として、1か月間地方研修所において実施している。
- (ヘ) 社会人基礎研修
- 平成29年度から経験者採用試験による採用者に対し、職務の遂行に必要な基礎的事項を習得させることを目的として、採用直後、3か月間地方研修所において実施している。
- (ト) 本科
- 税務職員として原則5年(平成28年度までは7年)以上の実務経験を経た職員で、部内の選抜試験により選定された者に対し、幹部職員の養成を目的として、1年間和光校舎において実施している。
- (チ) 専科
-
専門官基礎研修終了後3年間の実務経験を経た職員に対して、専門官として必要な事項を習得させることを目的として、7か月間和光校舎において実施している。
なお、平成24年度以降、実務経験年数を「2年間」から「3年間」に延長した(平成23年度は専科を実施していない。)。 - (リ) 国際科
-
平成25年度から通信研修国際課税Ⅱ修了後2年以上の実務経験を経た職員で、部内の選抜試験により選定された者に対し、国際課税の重要かつ高度な職務に必要な専門的知識を習得させることを目的として、5か月間和光校舎において実施している。
なお、「国際科」の創設に伴い、「国際租税セミナー」基礎コース及び実務コースは平成24年度をもって廃止した。 - (ヌ) 専攻科
-
平成25年度から通信研修審理Ⅱ修了後2年以上の実務経験を経た職員で、部内の選抜試験により選定された者に対し、審理等の重要かつ高度な職務に必要な専門的知識を習得させることを目的として、4か月間和光校舎において実施している(平成25年度以降、研修期間を「6か月間」から「4か月間」に短縮。)。
なお、平成19年度創設時から平成24年度までは、税務職員として14年(国税専門官採用試験による採用者は10年)以上の経験を経た職員で、部内の選抜試験により選定された者に対し、審理・事務管理等の重要かつ高度な職務に必要な知識・技能等を習得させ、税務行政の中核となるにふさわしい職員を育成することを目的として、6か月間和光校舎において実施していた。 - (ル) 研究科
- 研究員として選定された者に対し、租税及び税法の理論と運用に関する高度の研究を行わせることを目的として、1年3か月間和光校舎において実施している。
- (ヲ) 評価特別研修
- 平成25年度から、研修生として選定された職員に対し、不動産その他財産の評価の高度な職務に必要な専門的知識・技能等を習得することを目的として、5か月間和光校舎において実施している。
- (ワ) 酒税行政研修
- 平成25年度から、研修生として選定された職員に対し、酒税行政事務の高度な職務に必要な専門的知識・技能等を習得することを目的として、5か月間和光校舎において実施している。
- (カ) 税務理論研修
- 国家公務員採用総合職試験により採用されて3年の実務経験を経た職員に対し、税務行政に関する高度な知識等を習得させることを目的として、3か月間和光校舎において実施している。
- ロ 短期研修
-
- (イ) 本校短期研修
- 本校における短期研修は、主として各国税局・沖縄国税事務所の職員に対し、職務の遂行に必要な高度な知識・技能を習得させることを目的として、約30コース実施している。
- (ロ) 地方短期研修
- 地方研修所における短期研修は、主として税務署の職員に対し、職務の遂行に必要な専門的知識や技能などを習得させ、その能力・資質の向上を図ることを目的として実施している。
- ハ 通信研修
- 通信研修は、会計学、税務会計及び窓口英語Ⅰ・Ⅱに加え、平成25年度から国際課税Ⅰ・Ⅱ、審理Ⅰ・Ⅱ、韓国語Ⅰ及び中国語Ⅰの科目について、国税局及び税務署等の職員に対して職員自らの研さんによって税務の執行に必要な知識を習得させることを目的として、6か月間~11か月間実施している。
- (2) 職場研修
- 税務行政の複雑化、困難化に対処するため、国税局単位及び税務署のブロック単位で実施する研修並びに税務署主催による集合研修及び実務指導(OJT)により、職務に関する知識、技能の向上を図るとともに、社会人としての豊かな良識のかん養、人格の陶冶に努めるよう、積極的に実施している。
5 その他
- (1) 人事評価
-
平成19年6月の国家公務員法改正により、勤務評定制度が廃止され、全府省において人事評価制度が導入された。人事評価制度は、任用、給与、分限等様々な側面で活用する、能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎と位置づけられ、国税庁においても、平成21年10月から人事評価を実施している。
実施に当たっては、「国税庁職員人事評価実施規程」(平成21年国税庁訓令第20号)を制定し、この規程に基づき実施している。 - (2) 表彰
-
国税庁の職員に対する表彰は、永年勤務者表彰として、財務省表彰規程(昭和49大蔵省訓令特13号)に基づく財務大臣表彰、国税庁永年勤務者表彰準則(昭和37年国税庁訓令特8号)に基づく国税庁長官表彰等があるが、このほか、功績や考案、模範、善行のあった者に対する表彰として国税庁表彰準則(昭和27年国税庁訓令特14号)に基づく表彰を行っている。
永年勤務者表彰については、昭和50年までは、適用される俸給表の種類と等級により、表彰を受ける勤務年数が異なっていた(大臣表彰25年以上又は30年以上、長官表彰20年以上又は25年以上)が、その後、昭和51年6月に大蔵省表彰規程と国税庁永年勤務者表彰準則が改正され、昭和52年4月1日からは、俸給表の種類と等級に関係なく大臣表彰は25年、長官表彰は20年でそれぞれを行うこととし、局長表彰は廃止した。
更に、平成19年6月に財務省永年勤務者表彰準則(昭和37年大蔵省訓令特6号)が改正され、現在、大臣表彰は30年で行われることとなった。
なお、平成21年から平成30年までの永年勤務者表彰受彰者は、次のとおりである。
永年勤務者表彰受彰者数
| 区分 年 |
財務省永年勤務者表彰 | 国税庁永年勤務者表彰 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 財務大臣表彰 | 国税庁長官表彰 | 国税不服審判所長表彰 | ||
| 平成21年 | - | 2,450 | 24 | 2,474 |
| 平成22年 | 1,545 | 2,056 | 15 | 3,616 |
| 平成23年 | - | 2,258 | 19 | 2,277 |
| 平成24年 | 1,316 | 1,839 | 18 | 3,173 |
| 平成25年 | - | 1,756 | 17 | 1,773 |
| 平成26年 | 1,864 | 1,001 | 12 | 2,877 |
| 平成27年 | - | 1,052 | 13 | 1,065 |
| 平成28年 | 1,813 | 1,001 | 11 | 2,825 |
| 平成29年 | 1,753 | 824 | 12 | 2,589 |
| 平成30年 | 1,644 | 806 | 9 | 2,459 |
第3節 給与
1 現行の給与制度
- (1) 俸給
-
国家公務員の給与は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第62条に「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」と定められ、また、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下この節において「給与法」という。)第4条において、「各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。」と定められている。
これらの規定は、職務と責任の度が同じであれば、同一の給与が支給されるという「職務給」が、現行の給与制度の根本基準であることを意味している。
現在、一般職の職員に適用される俸給表は、指定職をはじめ、行政職、専門行政職、税務職、公安職、海事職、教育職、研究職、医療職、福祉職、専門スタッフ職の11種類17表であるが、このうち国税庁の職員は、指定職、行政職、税務職、医療職、専門スタッフ職の5種類8表の適用を受けている。 - (2) 諸手当
-
一般職の職員の給与は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬である俸給と勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められている諸手当に大別される。
現在、国税庁の職員に関係する諸手当には、俸給の調整額、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当等、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当がある。
2 俸給制度及び諸手当制度の改正
-
昭和32年に確立された俸給制度は、その後60年近くにわたり幾多の改正を経て国家公務員の給与制度の根幹をなし運用されてきた。この間、少子高齢化、生活意識の多様性、高度化社会への移行など社会経済情勢の基調の変化は著しく、行政に関しても行政需要の増大及びその多様化、複雑化が年を追って顕著になってきた。
また、公務員不祥事等もあり、国民の公務員に対する批判には極めて厳しいものがあった。中でも公務員給与の在り方については、公務員の給与水準は地域の民間賃金と比較して高いのではないか、また、公務員は勤務実績に関係なく年功的に昇給していくなど民間企業の実態とかい離しているのではないか等の批判が出されていた。
人事院は、こうした国民の批判にこたえるべく、公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し、年功的な給与上昇の抑制と職務・職責に応じた俸給構造への転換及び勤務実績の給与への反映を柱とした改革を行うこととし、平成17年8月に俸給制度、諸手当制度全般にわたる改革について、勧告・報告を行い、給与法が改正され、平成18年4月から段階的に実施された。
その後、平成26年8月に、民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映するための見直し、官民の給与差を踏まえた50歳台後半層の水準の見直し、公務組織の特性、円滑な人事運用の要請等を踏まえた諸手当の見直しといった課題に対応するため、俸給表、諸手当の在り方を含めた「給与制度の総合的見直し」を勧告し、平成27年4月から段階的に実施された。
主な改正点は、以下のとおりである。 - (1) 俸給表
- 地域の民間給与水準を踏まえて俸給表水準の平均2%引下げが行われた。
- (2) 地域手当
- 級地区分が1区分増設された。また、俸給表水準に合わせ支給割合が見直された。
- (3) 広域異動手当
- 円滑な異動及び適切な人材配置の確保のため、異動前後の官署間の距離区分に応じた支給割合の引上げが行われた。
- (4) 単身赴任手当
-
公務が民間を下回っている状況等を踏まえ、基礎額及び加算額の引上げが行われた。
また、遠距離異動に伴う経済的負担の実情等を踏まえ、交通距離の区分が2区分増設された。 - (5) 本府省業務調整手当
- 本府省における人材確保のため、係長級及び係員級の支給月額の引上げが行われた。
- (6) 管理職員特別勤務手当
-
管理職員が平日深夜に及ぶ長時間の勤務を行っている実態を踏まえ、平日深夜勤務も支給対象とされた。
また、平成28年8月に、民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、扶養手当の見直しが勧告され、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額するとともに、本府省課長級の職員は子以外の扶養親族に係る手当を不支給とし、本府省室長級の職員は手当額を引き下げる措置が平成29年4月から段階的に実施されている。
第4節 福利厚生
1 概要
- 国税庁における福利厚生施策は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第71条《能率の根本基準》に基づき、職員の勤務能率の確保・増進を目的に、健康管理、レクリエーション活動の推進、公務員宿舎の整備、福祉事業を4本柱として実施しているが、職場環境等の変化に伴い、国税職員生涯福祉推進計画の策定、バリアフリー化の推進及び子育て育児・介護と仕事の両立支援など、具体的な施策内容も変化してきている。
2 事務所掌
-
国税庁本庁における福利厚生事務については、昭和36年6月から厚生課が所掌してきたが、平成16年度の機構改正に伴い厚生課が廃止され、平成16年7月から厚生管理官が所掌することとなった。
なお、各国税局においては厚生課が、沖縄国税事務所においては会計課が福利厚生事務を所掌している。
3 健康管理
- (1) 生活習慣病対策
-
生活習慣病の職員に対しては、早期かつ適切な保健指導が必要であり、職員の健康状態を把握するための健康診断が有効に実施されることが重要であるとの認識の下、厳しい予算事情ではあるものの、健康診断の水準が低下することのないよう見直しを行っている。特に、生活習慣病予備軍である30歳代の職員に対して、健康診断等の生活習慣の改善に向けた積極的な支援を行っている。
また、人事院規則等の改正等を踏まえ、国税庁では、平成22年度以降、希望する非常勤職員に対して健康診断を実施している。 - (2) 心の健康づくりの推進
-
平成22年7月、人事院は、より円滑な職場復帰支援を実現する観点から、職場復帰支援の各段階において関係者が行うべきことをより明確化する趣旨で、「『円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針指針』の改定について」を発出した。
国税庁では、上記指針の改定を踏まえ、平成22年11月に「『心の健康問題により長期間職場を離れた職員の円滑な職場復帰のための手引き』の改定について(通知)」を発出し、療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤する「試し出勤」制度を導入した。
また、平成26年7月からカウンセリング制度を心の健康づくりにおける対策の一つとして位置付け、平成27年5月、こころの悩みやストレスへの対処法の相談窓口として電話相談ダイヤルを開設するとともに、平成27年7月からカウンセリングを専担とする職員を配置し、部内カウンセリングの充実を図った。 - (3) 感染症対策
-
感染症が疑われる職員が把握された場合には、その職員の健康のみならず、周囲の職員や来署者の健康に配慮する必要があることから、的確に対応することが極めて重要である。
平成22年4月、「感染症の予防と感染の疑いのある職員発生時の対応について(事務運営指針)」を策定し、健康管理監督者による日常の健康状態の把握、確定申告期の健康診断、予防接種の実施等の感染症予防、感染症に関する情報提供等の健康管理意識の向上を図るとともに、感染症が発生した際の具体的な対応を体系的に整理した。
また、平成24年5月、病原性が高い新型インフルエンザ及び同様の危険性のある新型感染症を対象とする新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されるとともに、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が策定された。
国税庁では、上記行動計画に基づき、平成27年6月、「国税庁新型インフルエンザ対策行動計画兼業務継続計画(事務運営指針)」を策定し、正しい知識と適切な予防策を周知するとともに、新型インフルエンザ情報の収集や発生・流行状況に応じて、迅速に対応できる体制を整備した。 - (4) その他の健康管理対策
-
- イ 受動喫煙防止対策
-
平成30年7月、健康増進法が改正され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置等が定められた。また、平成31年2月、その施行に関する関係政省令等が公布され、受動喫煙を防止するための措置に係る規定が令和元年7月及び同2年4月に順次施行されることとなった。
令和元年7月以降、行政機関の庁舎においては、原則敷地内禁煙とされ、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた特定屋外喫煙場所以外の場所での喫煙が禁止され、国税庁においても、令和元年6月30日までに庁舎内喫煙室の撤去の措置を講じるなど、受動喫煙防止対策を推進している。 - ロ ストレスチェック制度
-
平成27年12月の人事院規則改正により、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて心の不健康な状態となることを未然に防止することを目的としたストレスチェック制度が導入された。
国税庁では、平成28年6月、「『ストレスチェック及び面接指導実施規定』の制定について(事務運営指針)」を策定し、全職員を対象としたストレスチェックを実施している。職員に受検義務が課されているものではないが、ストレスチェックを効果的なものとするためには、全ての職員がストレスチェックを受検することが望ましいことから、国税庁WANを活用し、勤務時間内での受検機会を確保するなど、受検しやすい環境整備に努めている。 - ハ 面接指導の実施
-
脳・心臓疾患や精神障害の発症は、長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、平成18年4月以降、長時間勤務により疲労の蓄積が認められる職員で本人が希望する場合に医師による面接指導を実施することとされてきた。
平成31年4月、「人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)」の一部が改正され、一定時間を超える超過勤務を行った者については、本人の希望にかかわらず、医師による面接指導が義務付けられることなどを受けて、国税庁では、平成31年3月、「面接指導等の実施について(事務運営指針)」等の一部を改正し、健康管理医等による適切な面接指導に努めている。
4 レクリエーション活動の推進
-
レクリエーション活動は、職員の心身の健康保持増進及び活力の向上を図るとともに、職場の一体感を醸成するための手段としても有効であることから、国税庁では、従来から共済組合との連携を図りつつ、アウトソーシング化を取り入れるなど、適正かつ効果的なレクリエーション施策の実施に努めている。
なお、平成27年3月に策定・公表された「国税庁特定事業主行動計画(第Ⅲ期安心子育て応援プラン)」では、職員のライフサイクルの各局面における重点的支援策の一つとして、家族の職場への理解を一層深めるため、夏休みに職場見学ツアーを実施している。また、レクリエーション等の福利厚生事業の計画・実施に当たっては、親子で参加・利用できるものも積極的に取り入れることとしている。
5 公務員宿舎の整備
- (1) 公務員宿舎の削減計画等
-
平成23年12月に公表された「国家公務員宿舎の削減計画」において、公務員宿舎は、真に公務のために必要な宿舎に限定し、主として福利厚生(生活支援)目的のものは認めないこととされた。また、職務上公務員宿舎に入居することが認められる職員の類型を五つに分類するとともに、戸数についても、平成28年度末までの5年を目途に、約21.8万戸から5.6万戸程度の削減を行うこととされた。
更に、平成25年12月、公務員宿舎使用料についても、見直しの内容が公表され、平成26年4月から平成30年4月にかけ3回に分けて段階的に引き上げられた。 - (2) 宿舎の確保と質的改善
- 転勤が頻繁に行われる税務の職場において、職員が安心して職務に専念できる環境を整え、職務の能率的な遂行を確保するためにも、公務員宿舎の整備が不可欠であることから、国税庁では、引き続き宿舎の必要戸数の確保及び質的改善に努めている。
6 共済組合による福祉事業
- 共済組合では、医療、出産等に対して支払う短期給付事業及び退職などに対して年金を支払う長期給付事業の二つの給付事業のほか、医療事業、レクリエーション助成、貸付事業、団体定期保険・団体積立終身保険の取扱い等の福祉事業を行っており、組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に努めている。
- (1) 給付事業
-
- イ 短期給付事業
-
民間の健康保険制度の各種給付に相当する組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡、休業、災害等に関する給付や、雇用保険制度における育児休業給付及び介護休業給付に相当する給付を行っている。
平成24年11月、組合員等の利便性の向上を図るため、組合員証をカード化するとともに、組合員証の発行を世帯毎1枚から組合員及び被扶養者に対し各1枚に変更した。
また、平成28年8月、介護休暇の取得時に支給される介護休業手当金の支給率が、40%から67%に引き上げられるとともに、平成29年10月、育児休業給付金の給付期間について、最長で育児休業等に係る子の年齢が1歳6か月に達する日から2歳に達する日までに延長された。 - ロ 長期給付事業
-
平成27年10月、年金制度全体の公平性・安定性確保の観点から、それまでの共済年金制度を民間の厚生年金制度に合わせることを基本とする被用者年金制度の一元化に基づき、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金の給付を行っている。
また、一元化と同時に共済年金の職域年金相当部分が廃止され、新たに民間の企業年金に相当する退職等年金給付が創設されたことにより、退職年金、公務障害年金及び公務遺族年金の給付を行っている。
- (2) 福祉事業
-
- イ 保健事業
-
保健事業として、組合員及び被扶養者の健康増進及びレクリエーション活動を支援している。
財務省共済組合本部においては、平成24年度から「一時保育サービス利用者助成」の助成金額を年間3万円から5万円に引き上げるなど事業内容の充実を図っている。 - ロ 貸付関連事業
- 普通貸付、特別貸付及び住宅貸付のほか、財形貯蓄を行っている組合員を対象とした財形持家融資を行っている。
7 国税職員生涯福祉推進計画
-
平成3年3月に策定された「国家公務員福利厚生基本計画」に基づき、国税庁では、平成6年6月、「ライフプランニング支援策基本計画」を策定し、職員の在職中から退職後にわたる人生において、豊かでゆとりと生きがいのある生活設計を職員の自己責任原則に基づいて対応できるように、ライフプラン通信の発行など各種支援を行ってきた。
少子・高齢化の急速な進行など社会経済情勢が大きく変化する中、平成25年3月、「職員のライフプランニングの支援について(事務運営指針)」を策定し、「ライフプランニング支援策基本計画」を廃止して、ライフプラン研修の実施や通信教育講座の紹介など各種支援を行うとともに、国税庁厚生管理官において、各国税局・沖縄国税事務所の支援策の実施状況を取りまとめ、必要に応じて支援策を見直す体制を整備した。
8 バリアフリー化の推進
-
平成18年12月に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、公共施設のバリアフリー化の推進及び重点整備地区の重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することとなった。
これを受けて、国税庁では、平成19年4月、国税庁ホームページに「庁舎のバリアフリー施設一覧」の掲載を開始した。また、平成26年度に「庁舎のバリアフリー施設一覧」の対象範囲を全局署の庁舎に拡大した上、毎年更新するなど、高齢者・障害者等が利用しやすい庁舎の環境整備を図った。
平成30年10月、官公庁における障害者雇用を巡る問題を受け、政府より「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」が示され、障害者が活躍しやすい職場づくりの推進の一環として、障害者の作業環境を整えるための機器の導入・設備改善に積極的に取り組むこととされた。国税庁では、障害を持つ職員に対応した合理的配慮、備品購入、庁舎修繕又は設備改善、相談員における情報提供等を行う体制整備を図った。
9 育児・介護と仕事の両立支援
- (1) 財務省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画の概要
-
「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)、「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号)及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)を踏まえ、財務省と共同で、平成28年度から令和2年度末までを対象期間とした「財務省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」を策定し、各種取組を実施している。
- イ 働き方の改革
-
育児等を担うなど時間制約のある職員を含む全ての職員が十分な能力を発揮できるよう、男女を問わず全ての職員の「働き方の改革」によるワークライフバランスを実現するため、以下の取組を実施。
- 1 価値観・意識の改革
- 2 職場における仕事改革
- 3 働く時間と場所の柔軟化
- ロ 育児等と両立して活躍できるための改革
-
男女を問わず、職員の育児等に係る状況に応じたきめ細かい対応や配慮を行うこと等により、全ての職員が仕事と育児等を両立して活躍できる職場環境を整備するため、以下の目標を定めるとともに、その達成に向かって取組を実施。
- 1 男性職員の家庭生活への関わり推進
- 2 育児等をしながら活躍できる環境の整備
- 3 保育の確保
- ハ 女性の活躍推進のための改革
-
第4次男女共同参画基本計画における政府全体の目標を踏まえ、女性の採用・登用の拡大を計画的に進めるため、以下の目標を定めるとともに、その達成に向かって取組を実施。
- 1 女性の採用の拡大
- 2 女性の登用の拡大
- ニ その他の次世代育成支援対策
-
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、職場・地域における子育てしやすい環境の整備等に向け、以下の取組を実施。
- 1 子育てバリアフリー
- 2 子どもや家族とふれあう機会の充実
- 3 子ども・子育てに関する地域貢献活動
- (2) 安心子育て応援プラン(特定事業主行動計画)の概要
-
平成15年7月に制定された「次世代育成支援対策推進法」の基本理念の趣旨に基づき、子育てと仕事の両立の推進という視点に立った職場環境を整備するため、「国税庁特定事業主行動計画」を策定し、平成17年4月1日から実施した。
また、本計画にある各種施策の実施状況や職員の意見などを参考に、子育てと仕事の両立を更に推進するため、本計画に明記していた3年目の見直しを行い、変更後の計画「安心子育て応援プラン」を公表するとともに、平成20年4月1日から実施した。
現在は、平成27年4月から令和3年3月までを計画期間とする「第Ⅲ期安心子育て応援プラン」を策定し、実施している。
これまでの具体的取組としては、各種会議、研修等を通じた本計画の周知徹底、育児短時間勤務制導入等に向けた関係機関への積極的な働きかけ、職員の情報交換会の開催、両立支援の重要性等を集中的に啓発する期間として「安心子育て応援プラン推進週間」などを実施している。 - (3) 具体的な子育てと仕事の両立支援策
-
安心子育て応援プランに盛り込まれている、職員のライフサイクルの各局面(結婚・出産、育児休業、職場復帰、子育て期間等)全般に通じた次の支援策を基に、より一層両立支援の推進に努めている。
- イ 職場における子育てと仕事の両立に関する意識の醸成
- ロ 管理者等による職員のニーズの適切な把握、事務計画、事務分担の見直し
- ハ 子育ての状況に応じた人事上の配慮、宿舎の貸与に関する配慮、研修参加への配慮
- ニ 超過勤務の縮減、年次休暇の取得の促進
- ホ テレワークの導入
- ヘ 保育施設や子育てに関する情報提供、情報交換会の実施、地域関係機関への働きかけ等
第5節 規律
1 服務
-
国家公務員法(昭和22年法律第120号)では、第3章第7節を「服務」と題し、第96条から第106条までの規定において公務員の勤務に服する場合の在り方を定めているが、服務の根本基準として同法第96条第1項は、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定し、公務員の服務に関する根本的な考え方を示している。
租税の賦課徴収に関する事務に携わる税務職員は、その職務の公正な執行により、申告納税制度の趣旨に沿った課税の公平を実現していくという重責を担っているだけに、常に厳正な服務規律の維持に努め、公共の利益のため、誠実に職務に専念し、税務行政に対する納税者の信頼を高めていくよう不断の努力をしていくことが要請されている。
国税庁では、このような趣旨に沿い、職員の厳正な服務規律の確保について従来から鋭意配意してきている。昭和28年度に、税務行政運営の基本的方針である「税務運営方針」が定められたのを機会に、各税事務共通の重要事項の一つとして、綱紀の粛正と職場秩序の維持を取り上げ、全職員に直接その趣旨を徹底させることとし、更に、昭和36年度以降は、基本的な考え方の三本柱の一つにも「綱紀を正し、明るい執務体制を作ること」(昭和46年度から「綱紀を正し、明るく、能率的な職場をつくること」に変更)を掲げ、職員に対し、税務職員としての職責を自覚し、服務規律を遵守して良識ある行動をとるよう努めさせているとともに、管理者には、自らを律し、非行の未然防止に努めるよう措置している。
また、従来から、公務の適正な運営、綱紀の厳正な保持及び倫理法令等の遵守について、通達を発遣するほか、会議などあらゆる機会を通じて職員に対し注意を喚起しており、服務規律違反の根絶に向けて、綱紀の厳正な保持等について、引き続き、その徹底に努力しているところである。
2 懲戒
-
公務員に服務規律違反があった場合は、綱紀を粛正し、公務員の勤務についての秩序を維持するため、その公務員に対し、国家公務員法第82条などに基づき、懲戒処分が行われる。
懲戒処分は、職員にとって重大な不利益処分であるため、同法第74条では、懲戒の根本基準として、特に公正に行うことを規定し、また、同法第90条では、職員が著しく不利益な処分を受けた場合には、その不利益処分に関して、人事院に対し、審査請求をすることができると規定されている。
国税庁では、職員のごく一部の限られた非行事件であっても、その職務の執行の公正さと税務行政に対する国民の信頼を著しく損なうおそれがあることに鑑み、服務規律に違反した職員に対してはもとより、指導監督が不十分であったため、非行を未然に防止することができなかった監督者に対しても、厳正な措置をもって臨んできている。
また、平成25年には、国税庁職員矯正措置規程(国税庁訓令第19号)を制定し(同時に昭和28年に制定された国税庁職員訓告規程は廃止)、職員に懲戒処分にまでは至らない非違の行為が認められた場合にも、その職員やその職員の監督者に対して、注意を喚起し、その職務遂行に関する行為を矯正する措置として、「訓告」や「厳重注意」、「注意」を行っている。
3 公務員倫理
- (1) 倫理法令の概要
-
国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止することにより、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として制定され、平成12年4月に施行された。
倫理法令では、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則、利害関係者等との具体的な行為規範、贈与等の報告制度などについて定められている。 - (2) 行動規範
-
行動のルールとして、利害関係者との間の禁止行為、利害関係者でない者との間でも許されない行為等が定められている。
- イ 利害関係者
- 利害関係者とは、職員の職務遂行によって直接に利益又は不利益を受ける者で、具体的には、許認可等、補助金等、立入検査、監査、監察、不利益処分、行政指導、契約などの相手方が利害関係者に該当する。
- ロ 利害関係者との間の禁止行為
-
職員は、利害関係者との間で行う一定の行為が、一部の例外を除き禁止されている。
具体的には、金銭を受けること、物品又は不動産の贈与を受けること、金銭の貸付けを受けること、無償による物品又は不動産の貸付けを受けること、無償による役務の提供を受けること、未公開株式を譲り受けること、供応接待、共に遊技、ゴルフ又は旅行をすることは禁止されている。 - ハ 利害関係者でない者との間でも許されない行為
- 利害関係者でない者から、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待を受けること又は財産上の利益を受けることや、飲食等の場に居合わせない者に対し本人の知らないままに代金を負担させる、いわゆる「つけ回し」を行うことは禁止されている。
- (3) 報告制度
-
- イ 贈与等の報告
-
本省課長補佐級以上の職員が、事業者等から1件につき5,000円を超える贈与、供応接待、報酬の支払を受けた場合、四半期ごとのその状況について報告することとされている。
なお、報告書は、翌四半期の初日から14日以内に提出しなければならない。 - ロ 株取引等及び所得等の報告
- 本省審議官級以上の職員は、前年の株券等の取得又は譲渡について株取引等報告書を、前年の所得について所得等報告書を、毎年3月31日までに提出しなければならない。
4 監察
- (1) 国税庁監察官制度
-
国税庁の監察官制度は、昭和24年6月1日の国税庁発足時に、旧大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第91条の規定により創設された。
当時の監察官の職務権限は、国税庁の所属職員について身分上の監察(行政処分を前提とした非行調査)を実施するのみで、犯罪捜査権までは付与されていなかったことから、証拠収集等が困難で事務処理上支障をきたすことが多かった。
その後、前記問題解決のため、昭和25年5月大蔵省設置法の一部が改正され、監察官制度が大蔵省設置法で規定されるとともに、国税庁の所属職員が行った職務に関連する犯罪について任意の捜査権が付与されることとなった。
なお、国税庁監察官及び国税庁監察官補(以下「監察官等」という。)の定数は、発足当初は60名(監察官のみ)であったが、その後、数次の改正を経て、現在158名である。
国税庁(本庁)及び各派遣別国税庁監察官等の定数(平成30年度)
| 区分 派遣名 |
監察官 | 監察官補 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首席 | 次席 | 主任 | 監察官 | 小計 | |||
| 国税庁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 札幌 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 仙台 | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 関東信越 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 15 |
| 東京 | 1 | 1 | 10 | 14 | 26 | 12 | 38 |
| 金沢 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 名古屋 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 5 | 18 |
| 大阪 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 広島 | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 高松 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 福岡 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 熊本 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 沖縄 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 合計 | 12 | 5 | 40 | 63 | 120 | 38 | 158 |
- (2) 国税庁監察官の職務
-
国税庁監察官の職務範囲等については、財務省設置法(平成11年法律第95号)第26条第1項において、「国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。以下同じ。)についてその職務上必要な監察を行わせる。」とし、同法第4条第21号において、「法令の定めるところに従い、第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること。」とした上で、同法第27条第1項において、各号に掲げる犯罪(職務犯罪)があると思料するときは、国税庁監察官が、犯人及び証拠を捜査すると規定されており、具体的には、国税庁監察官事務規程や国税庁監察官職務規範に基づき実施される。
したがって、国税庁監察官には、その職務を遂行する上で必要な監察権限と犯罪捜査権限(特別司法警察職員に準ずる職員としての扱い)の二つの職務権限が与えられている。- イ 監察
-
国税庁監察官が行う監察とは、行政上の監督の立場から職員の行為について調査して服務上の適否を判断するとともに、非行の防止及び発見並びにその処理を行う手続である。また、非行とは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条各号に掲げる懲戒の事由に該当する全ての行為(情状によって懲戒処分が免除される場合を含む。)とされ、犯罪はもちろん犯罪に至らない違法又は不当な行為も全て含まれる。
現在、監察官等は、職員の非行の未然防止及び早期発見並びに必要な措置を講ずるため、監察事務を予防監察、資料監察及び非行監察の三つに区分して実施している。 - ロ 犯罪捜査
-
国税庁監察官が捜査する犯罪とは、
- (イ) 国税庁の所属職員がしたその職務に関する犯罪
- (ロ) 国税庁の所属職員がその職務を行う際にした犯罪
- (ハ) (イ)及び(ロ)に掲げる犯罪の共犯
- (ニ) 国税庁の所属職員に対する刑法第198条(贈賄)の犯罪
-
をいい、上記(ハ)及び(ニ)に掲げる犯罪については、国税庁の所属職員だけでなく一般民間人に対しても捜査権の行使が認められているが、上記以外の犯罪については、国税庁の所属職員でも捜査権は及ばないこととされている。
国税庁監察官に付与されている捜査権は、いわゆる任意捜査権であり、強制捜査の権限は有しておらず、逮捕、差押え、捜索等をすることはできない。このように国税庁監察官は、限られた捜査権を有していることなどから特別司法警察職員に準ずる職員の扱いとされている。
なお、国税庁監察官が犯罪の捜査をした場合には、刑事訴訟法第246条の規定に基づき事件を検察官に送致しなければならないこととされている。
また、非行事件は、国税庁監察官制度が創設された当時は、第二次世界大戦後の混乱期という影響もあって、職務に関連した非行事件が多発し、その態様も様々なものが見受けられたが、昭和40年以降は、税務行政の安定、職員の資質の向上並びに非行防止策の浸透や、監察官等による地道でたゆまぬ幅広い予防監察などの結果、非行事件の発生は激減したものの、現在まで非行の根絶には至っていない。 - ハ 監察事務の運営
-
最近の社会経済が多様に変化している中で、国民の税務行政、特に、執行面に対する適正・公平の確保の要請が一段と高まっていることに鑑み、従来にも増して信頼される税務行政の確立を図る必要がある。そこで、監察事務の運営に当たっては、綱紀を粛正し、公正な税務行政の運営に資するため、非行防止を最重点事項と定め、国税庁、国税局(所)及び税務署が一体となって創意工夫を凝らし、非行の未然防止と早期発見に鋭意努めている。
平成21事務年度からは、非行の根絶に向け、組織運営面からの非行発生誘因や職場の健全化・活性化の阻害要因の把握等にも積極的に取り組み、監察官等が担当部署を数次にわたり巡回している。
また、今後も、職場の実情や社会情勢の変化に沿って必要な監察事務の改善を実施し、職場秩序の確立と予防監察の一層の充実に努めていくこととしている。
第6節 事務の管理・企画
1 「税務行政の将来像」の公表
- (1) 概要
-
税務行政を取り巻く環境が大きく変化する中で、国税庁が今後とも納税者の理解と信頼を得て適正な申告・納税を確保していくためには、税務行政の透明性の観点から目指すべき将来像を明らかにし、それに向けて着実に取り組んでいくことが重要であるとの問題意識の下、「税務行政の将来像~スマート化を目指して~」を取りまとめ、平成29年6月に公表した。
「税務行政の将来像」では、ICTやマイナンバーなどの積極的な活用を通じて、「納税者の利便性の向上」と、「課税・徴収の効率化・高度化」を2本柱とした、税務行政のスマート化を目指すこととしている。
なお、この将来像は、情報システムの高度化と外部機関の協力を前提としたもので、おおむね10年後のイメージを示したものである。 - (2) 納税者の利便性の向上
- 第1の柱である「納税者の利便性の向上」については、カスタマイズ型の情報の発信、税務相談の自動化、申告・納付のデジタル化の推進に取り組むことで、申告から納付までの税務手続を抜本的にデジタル化し、税務署に出向くことなく、スムーズかつスピーディに手続が完了する環境の構築を目指すこととしている。
- (3) 課税・徴収の効率化・高度化
- 第2の柱である「課税・徴収の効率化・高度化」については、申告内容の自動チェック、軽微な誤りのオフサイト処理、調査・徴収でのAI活用に取り組むことにより、課税・徴収の効率化・高度化を進め、創出したマンパワーも活用しつつ、国際的租税回避への対応、富裕層に対する適正課税の確保、大口・悪質事案への対応といった重点課題に的確に取り組み、適正・公平な課税・徴収の実現を図っていくこととしている。
- (4) 最近の取組状況の公表
-
令和元年6月には、「税務行政の将来像」公表から約2年が経過したことを踏まえ、これまでの間に具体的に実現した取組の紹介に加え、施策のイメージが具体化したものを、「『税務行政の将来像』に関する最近の取組状況~スマート税務行政の実現に向けて~」として公表した。
この「最近の取組状況」では、スマートフォン等による電子申告など、申告・納付手続のデジタル化・ペーパレス化に向けた取組のほか、チャットボットの導入などによる税務相談の効率化・高度化に向けた取組を紹介している。この他、マイナンバーや法人番号をキーにした各種資料情報データの有効活用といった、調査・徴収事務でのICT・AIの活用に向けた取組やCRSに基づく非居住者金融口座情報の自動的情報交換による情報収集領域の拡大といった国際的な取組を紹介している。
さらに、「納税者の利便性向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」に向けて、国税情報システムの高度化を目指すこととし、そのイメージも掲載している。
2 デジタルガバメントの実現
-
税務行政を取り巻く環境は、経済取引の複雑化・広域化や経済社会の国際化・高度情報化の急速な進展に伴い、事務が複雑・困難化するなど、大きく変化しており、引き続き国税庁の使命を果たしていくためには、納税者サービスの充実、適正かつ公平な課税及び徴収の実現に向けて、ICT及びデータの一層の活用が重要となっている。こうした状況の下、国税庁においては、各種政府方針に基づき、国民の目線に立った利便性の向上や行政運営の効率化・高度化を図るために、税務行政のシステムインフラである国税情報システムのうち、主なシステムである国税申告・納税システム(以下「e-Tax」という。)と、国税総合管理システム(以下「KSKシステム」という。)を中心に見直しを行ってきた。
e-Taxとは、所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税(地方消費税を含む。)等の申告手続のほか、青色申告の承認申請、納税地の異動届、納税証明書の交付請求及び法定調書の提出などの申請・届出等の各種手続について、税務署に出向くことなく、書面の提出に代えてインターネット等を利用して電子的に行うことを可能としたシステムである。
納税者や税理士は、e-Taxに対応した税務・会計ソフトを利用すれば、会計処理や申告などのデータ作成から提出までの一連の作業を電子的に行うことができるので、事務の省力化やペーパーレス化につながる。また、国税当局にとっても、窓口・郵送での申告書収受事務やデータ入力事務の削減、文書管理コストの低減などの効果が期待され、税務行政の効率化が図られる。
国税庁では、政府全体で推進する電子政府の構築に向けた取組の一環として、納税者の利便性の向上及び税務行政の効率化を図る観点から、平成16年6月からe-Taxの全国での運用を開始した。
KSKシステムは、全国の国税局(所)と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピュータシステムである。
KSKシステム導入以前、東京、名古屋、大阪の各国税局及び関東信越国税局管内の埼玉県南8税務署(その後、署の分割に伴い10署となる。)については、税務署の内部事務を中心にバッチ処理を主体にした都市局システムを、 その他の各国税局(所)については、オンライン処理を主体にした地方局システム(総合オンラインシステム)を導入していた。その後、①都市局と地方局で異なったシステムにより運用されていること、②経済取引の複雑・広域化、情報化の急速な進展など、税務行政を取り巻く環境が大きく変化する中、更に高度なシステムを構築する必要性が認められるようになってきたこと、③情報処理技術は飛躍的な進歩を遂げてきており、国税事務のより高度なコンピュータの活用が可能な状況になってきたことなどから、更に各種情報を有効活用して、効果的な税務調査や的確な滞納整理を実施するなどの税務行政の効率化・高度化を図るため、昭和63年度に発展性のある新しいコンピュータシステムであるKSKシステムの開発が決定され、検討期間を経て、平成2年度から本格的な開発・テスト作業が進められた。その後、平成13年11月に全国12国税局(所)及び524税務署への導入が完了した。
今後も、これらe-Tax、KSKシステムをはじめとした国税情報システムの見直しを行うことで、納税者の利便性向上と、課税・徴収の効率化・高度化を図る必要があるところ、これまでに実施した具体的な取組内容は、以下のとおりとなっている。 - (1) 税務手続のオンライン化
-
- イ e-Taxの普及及び定着に向けた取組
-
e-Taxについては、上述したように、納税者の利便性向上と税務行政の効率化につながるものであることから、その普及及び定着を国税庁における当面の最重要課題の一つと位置付け、国税庁ではオンライン利用に関する計画等を作成し、計画に基づき各種施策に取り組んできた。
- (イ) 平成21~23事務年度の主な取組
- 平成20年9月に政府のIT戦略本部において、オンライン利用促進の対象手続として国民に広く利用されている手続1に重点化して絞り込み(国税関係手続としては、15手続を対象としている。)、重点分野ごとに平成25年度末時点の目標値(65%以上)を設定2するとともに、この新たなオンライン利用促進の取組を強力に推進するため、平成21年度から平成23年度までの間に集中的に講ずる措置を定めた「オンライン利用拡大行動計画」(以下「行動計画」という。)が決定された。これに基づき、国税庁では、以下のような取組を実施した。
- A e-Taxの受付時間については、これまでも順次拡大してきており、平成20年度までは、平日は8時30分から21時まで、所得税の確定申告期は休日も含め24時間受付を行っていたところであるが、平成21年度には、法人税等の申告が集中する5月末(4日間)の受付時間を22時30分(通常期は21時)まで延長した(その後、平成24年度には、法人税等の申告が集中する5月末の受付に加えて、8月末及び11月末の受付日を、平成25年度には、平日の通常時の受付時間を24時まで、平成28年度には、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日の代わりに翌月の最初の日曜日とする。)へと、受付時間の拡大を実施してきた。)。
- B e-Taxにより申告書等を提出した後、納税者の本人名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続であるダイレクト納付のサービスを開始した。
- C e-Taxを利用して還付申告を行った場合、支払予定日等、還付金の処理状況を、税務署に問い合わせることなく、e-Taxにログインすることにより確認できる機能を追加した。
- D 地方団体による所得税申告書等の閲覧については、従来、書面申告の場合は、複写式の申告書の回付により、e-Tax申告の場合は、税務署において紙出力した申告書の交付により行ってきたが、地方税法の改正により、国税庁と地方団体との間で所得税申告書等のデータ提供が可能となったことを受け、所得税申告書等について、地方団体に対するデータによる提供等を開始した。
- (ロ) 平成24~26事務年度の主な取組
-
国税庁におけるオンライン利用については、これまで「行動計画」に基づき、重点手続の分野ごとに利用率目標を設定し、利用率の向上に取り組んできた。しかし、「行動計画」については、利用者の満足度は必ずしも高くないこと、計画の対象期間が平成22年度に終了すること、我が国のオンライン利用の現状等を踏まえ、
- ① 費用対効果等を検討し、オンライン利用の範囲の見直しを更に進める必要性
- ② 利用者の視点に立った業務の分析・見直し
- ③ 申請システムの設計等が不十分であり、利用者がオンライン利用の利便性を実感できる改善の必要性
- といった観点から見直しが行われることとなった。平成23年8月にIT戦略本部において決定された「新たなオンライン利用に関する計画」を受け、従来の「オンライン利用率」の向上に加え、新たに「e-Taxの利用満足度」や「申請受付1件当たりの費用」など、国民の利便性の向上や行政運営の効率化といった視点も取り入れ、平成23年度から平成25年度までの3年間を対象期間にした「業務プロセス改革計画」(以下「改革計画」という。)を平成24年5月に策定した。改革計画においては、「行動計画」と同様に、重点手続として、公的個人認証の普及割合等に左右される3手続とその他の12手続の合計15手続が対象とされた。国税庁では、「改革計画」に基づき、以下のような施策に取り組んだ。
- A 贈与税申告手続をe-Tax利用可能手続に追加した。
- B 納税証明書をオンライン請求し、税務署窓口で書面にて受け取る場合の電子署名を省略した。
- C タブレット端末等のスマートデバイスの急速な普及が進んでいることから、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Taxのサービスのうち、納税手続等について、スマートデバイス向けのサービスを開始し、その後順次手続を拡大した。
- D 個人の自宅等からのe-Taxの還付申告のうち、早期提出分(1月・2月提出分)については、処理期間を2~3週間程度で処理する等を実施した。
- なお、「改革計画」では、政府全体の方針を踏まえ、費用対効果等を考慮し、オンライン利用の範囲を判断することとされたことから、平成24年9月には、国税庁におけるオンライン利用の範囲の見直しを行い、オンライン利用が可能な国税関係の888手続のうち、オンラインだけでなく書面も含めて利用のない等の528手続について、オンラインの利用を停止した。また、平成25年3月には、「改革計画」について、行政運営の効率化に関する指標として「事務処理(削減)時間」を新たに設定するとともに、法人税申告等12手続のオンライン利用率の平成25年度における目標を72%から76%へ引き上げるなどの改定を行った。
- (ハ) 平成26~28事務年度の主な取組
- 平成26年度以降のオンライン利用に関する政府全体の取組方針として、「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月閣議決定)に基づき、平成26年4月に各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議において「新たなオンライン利用に関する計画」が決定され、「オンライン手続の利便性向上に向けた改善方針」が策定された。本方針ではオンライン手続のうち、「利用頻度が高い年間申請等件数が100万件以上のもの及び主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続」であってオンライン手続の利用率の向上を引き続き図るべきものを、「改善促進手続」と位置づけ、社会保障・税番号制度の導入を勘案しつつ、利便性の向上とオンライン利用の拡充・定着に重点的に取り組むこととされた。これを受け、平成26年度から平成28年度までの3年間を対象期間に、公的個人認証の普及割合等に左右される2手続、その他の国税申告4手続及び申請・届出等9手続の合計15手続を対象とした「財務省改善取組計画」を平成26年9月に策定し、従前の「改革計画」で設定した、e-Taxの利用満足度やオンライン利用率等の目標その他評価指標(成果指標)等についても、引き続き設定することとした。また、「改革計画」との連続性・継続性にも配慮しつつ、e-Taxの一層の普及及び定着を図るため、平成26年度から平成28年度までの間において措置する改善事項等が定められ、国税庁では、以下のような施策に取り組んだ。
- A 従来、e-Taxソフト(WEB版)によりCSVファイルを利用して提出できる法定調書の合計枚数の上限が、各法定調書(6種類)につき100枚であったが、6種類の法定調書の合計枚数の上限を、5,000枚かつデータサイズ10MBまで拡大した。
- B 納税証明書の交付請求(署名省略分)をe-Taxソフト(SP版)でも利用できる手続に追加した。
- C 税務・会計ソフトで作成した法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書に係るデータのうち、e-Taxで受付可能なデータ形式で作成されていないものは、別途、書面による提出が必要であったが、税務・会計ソフトで持つこれらの帳票のデータをe-Taxで送信できるように、e-Taxで受付可能なデータ形式に変換するプログラムを税務・会計ソフトの開発業者に提供した。
- D これまでe-Taxで申告や申請などを行った場合でも、別途、書面による提出が必要だった出資関係図など、法人税法等による添付書類について、イメージデータ(PDF形式)による提出を可能とした。
- E マイナンバーカードでマイナポータルにログインすることで、これまで入力が必要であったe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力することなくe-Taxにログインし、メッセージボックスの情報を確認できるほか、納税証明書、源泉所得税、法定調書などに関する手続が利用できるようマイナポータルとのシングルサインオンを開始した。
- (ニ) 平成29~30事務年度の主な取組
-
平成28年12月に制定された官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第10条において、「行政機関等・・・に係る申請、届出、処分の通知その他の手続に関し、電子情報処理組織・・・を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことを原則とするよう、必要な措置を講ずる」旨が示されているが、e-Taxによる電子申告の利用率(平成28年度)は法人税申告が79.3%、所得税申告が53.5%となっていた。
特に法人税の申告については、企業活動におけるICTの利用が広がる一方で、ICTで作成された申告データが必ずしもデータのまま国税当局に提出されていない状況等が課題とされていたところであり、「行政手続部会取りまとめ(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会決定)」において、「電子申告の義務化が実現されることを前提として、大法人の法人税・消費税の申告について、電子申告(e-Tax)の利用率100%」との数値目標が設定された後、「未来投資戦略2017」及び「規制改革実施計画」(いずれも同年6月9日 閣議決定)において、この「行政手続部会取りまとめに沿って行政手続コストの削減を進める」旨の指摘がなされた。
また、「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告②(平成29年11月20日政府税制調査会)」においても、「法人の基本的な手続は原則としてe-Taxで行われるという姿(法人税等の電子申告利用率100%)の実現を目指すべき」とされるとともに、併せて、法人側のニーズも踏まえ、「e-Taxシステム自体の機能改善、提出書類の見直し、認証手続(電子署名)の簡便化等を行うほか、法人がICTで作成・管理するデータが円滑にe-Taxで提出できるよう、情報セキュリティ等にも配意しつつe-Taxに提出可能なファイル形式の多様化等も検討すべき」との指摘もされた。
そこで、平成30年度税制改正においては、経済社会のICT化等が進展する中、こうした政府税制調査会等の議論を踏まえ、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点から、「法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務」を創設するとともに、法人税等の電子申告の添付書類の光ディスク等による提出の可能化、法人の認証手続の簡便化等の「申告データの円滑な電子提出のための環境整備」を行った。
具体的には、法人税等の申告書のe-Taxによる提出義務の対象となる特定法人(令和2年4月1日以後に開始する事業年度において資本金等の額が1億円を超える法人並びに相互会社、投資法人及び特定目的会社をいう。)である内国法人又は事業者の法人税、地方法人税及び消費税の申告書の提出については、これらの申告書に記載すべきものとされている事項(申告書記載事項)又はその添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(添付書類記載事項)を、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供することにより、行わなければならないこととした。また、国又は地方公共団体が公的な主体であり、また、一般会計に係る業務としての事業又は特別会計を設けて事業を行う場合には消費税が課されることを踏まえ、国又は地方公共団体も特定法人に該当し、e-Taxによる提出義務の対象とされた。
そのほか、平成29年5月に、IT戦略本部において、国民・事業者の利便性向上に重点を置き、行政のあり方そのものをデジタル前提で見直す「デジタル・ガバメント推進方針」が決定され、さらに、平成30年1月には、具体的な取組や実行の主体等を明確にするため、「デジタル・ガバメント実行計画」が策定された(平成30年7月改定)。これらを踏まえ、財務省においては、平成30年6月に、平成30年度から令和4年度までの5年間を対象期間として、「財務省デジタル・ガバメント中長期計画」(平成30年6月29日財務省行政情報化推進委員会決定・令和元年6月25日改定)が策定された。本計画では、オンライン化を進めるための各種施策のうち、3つの手続(所得税、法人税及び相続税)のe-Tax利用率をKPI(主要業績指標)とするとともに、それぞれ適宜の時期における目指すべき利用率を設定した。また、この計画等に基づき、以下のような施策に取り組んだ。 - A 法人税申告書等に添付が必要であった収用証明書等の添付書類について、その添付を省略し法人等において保存しておけばよいこととした(当該取扱いについては、書面による申告書等の場合にも適用される。)。
- B 法人税申告等における代表者及び経理担当者の自署押印制度が廃止され、法人納税者がe-Taxを利用して申告手続を行う際、当該法人納税者の経理責任者の電子署名及び電子証明書の送信を不要とするとともに、当該法人納税者の代表者から委任を受けた者(当該法人納税者の役員及び職員に限る。)の電子署名及び電子証明書を送信する場合に、代表者の電子署名等の送信を不要にする等の法人納税者のe-Tax利用の電子認証の簡便化を実施した。
- C マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を可能とした「マイナンバーカード方式」、マイナンバーカード及びICカードリーダライタを所有していない納税者については、税務署で職員との対面による本人確認に基づいて発行されたe-Tax用のID・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信を可能とした「ID・パスワード方式」といった個人納税者のe-Tax利用の認証手続の簡便化を実施した。
- D 年末調整済の給与所得者で、医療費控除や寄附金控除の適用を受ける方について、確定申告書等作成コーナーで、スマートフォンなどに最適化された専用の画面を利用して所得税の確定申告書の作成を可能とした。
-
E これまでイメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類について、税務署がその内容を確認する必要があるときは提出又は提示を求めることがあるため、納税者において一定期間保存しておく必要があったが、当該イメージデータを原本として取り扱うこととしたため、納税者において当該イメージデータの送信を行った添付書類を税務署へ提出又は提示するため、原本の保存を不要とした。
上記の「法人税等の申告書の電子情報処理組織による提出義務」が創設されたことや、「財務省デジタル・ガバメント中長期計画」に基づいた施策などを行うことで、国税庁としては、今後も①提出情報等のスリム化、②データ形式の柔軟化、③提出方法の拡充、④提出先の一元化、⑤認証手続の簡便化等の環境整備を実施し、利便性の向上をより一層図っていくこととしている。
- ロ e-Taxの利用率の推移
-
上記イの主な取組以外にも、納税者や税理士等の要望を聞きつつ、納税者の利便性向上のためのシステム及び運用の改善や制度の改正に積極的に取り組んできた。また、税理士会等の関係民間団体への協力要請、納税者に対する個別勧奨などを重点的に行うとともに、あらゆる機会を通じて広報・周知を実施してきた。
その結果、e-Taxの利用率は増加しており、「改革計画」における①公的個人認証の普及割合に左右される3手続については、平成24年度の46.9%から平成25年度では48.6%となり、②法人税申告等①以外の12手続については、平成24年度の75.7%から平成25年度の77.8%となっている。
また、平成26年度から平成28年度までについては、「財務省改善取組計画」における①マイナンバーカードの普及割合等に左右される国税申告2手続(所得税申告、消費税申告(個人))の利用率については、平成26年度の53.0%から、平成28年度では54.0%となっている。次に、②他の国税申告4手続(法人税申告、消費税申告(法人)、酒税申告、印紙税申告)の利用率については、平成26年度の71.0%から、平成28年度では78.0%となっている。③申請・届出等9手続(給与所得の源泉徴収表等(6手続)、利子等の支払調書、納税証明書の交付請求書、電子申告・納税等開始(変更等)届出書)については、平成26年度の58.4%から、平成28年度では64.3%となっている。
なお、平成29年度、30年度のデータについても、同じ手続区分で算出している。表にあるように大部分の申告・手続のe-Taxの利用率については、毎年増加してきている。
e-Taxに関するこれまでの計画の概要と利用率の実績
| 年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画 | オンライン利用拡大行動計画 (平成20年9月IT戦略本部決定) |
業務プロセス改革計画 (平成24年5月財務省決定) |
財務省改善取組計画 (平成26年9月財務省決定) |
- | 財務省デジタル・ガバメント中長期計画 (平成30年6月財務省決定) |
|||||||||
| 対象手続 | ・所得税、印紙税申告、納税証明書交付請求等4手続 ・法人税申告等先行11手続 全15手続 |
・所得税申告、納税証明書交付請求等3手続 ・法人税申告等12手続 全15手続 |
・所得税申告等2手続 ・法人税、印紙税、酒税申告等4手続 ・申請・届出等9手続 全15手続 |
- | ・所得税申告 ・法人税申告 ・相続税申告 全3手続 |
|||||||||
| 目標値 | ○オンライン利用率 ①平成25年度までに65%以上 ②上記①のうち、先行11手続については、平成23年度までに70%以上 |
○オンライン利用率等 ①所得税申告等3手続:50% ②法人税申告等12手続:76% ③ICT活用率(※):65% ○オンライン利用率等以外の目標値 ④e-Taxの利用満足度 ⑤確定申告書等作成コーナーの利用満足度 ⑥オンライン申請の受付1件当たりの費用 ⑦事務処理(削減)時間 |
○オンライン利用率等 ①所得税申告等2手続:58% ②法人税申告等4手続:72% ③申請・届出等9手続:62% ④ICT活用率:72% ○オンライン利用率等以外の目標値 ⑤e-Taxの利用満足度 ⑥確定申告書等作成コーナーの利用満足度 ⑦オンライン申請の受付1件当たりの費用 ⑧事務処理(削減)時間 |
- | ○オンライン利用率 【令和元年度まで】 ①所得税申告:61% ②法人税申告:85% 【令和2年度まで】 ③相続税申告:25% 【令和3年度まで】 ④石油ガス税申告及び揮発油税・地方揮発油税申告:25% |
|||||||||
| 実績 | ○平成23年度のオンライン利用率 先行11手続:79.3%(70%) ※かっこ書きは目標値 (注)本計画は平成23年度で終了したため、平成24年度以降の利用率については未集計。 |
○平成25年度のオンライン利用率等 ①所得税申告等3手続:48.6%(50%) ②法人税申告等12手続:77.8%(76%) ③ICT活用率:68.8%(65%) ※かっこ書きは目標値 |
○平成28年度のオンライン利用率等 ①所得税申告等2手続:54.0%(58%) ②法人税申告等4手続:78.0%(72%) ③申請・届出等9手続:64.3%(62%) ④ICT活用率:76.8%(72%) ※かっこ書きは目標値 |
- | 〇平成30年度のオンライン利用率等 ①所得税申告等2手続:58.5% 内、所得税申告:57.9%(61%) ②法人税申告等4手続:82.9% 内、法人税申告:84.3%(85%) ③申請・届出等9手続:76.9% ④ICT活用率:82.7% ※かっこ書きは目標値 |
|||||||||
- ※所得税申告及び消費税申告(個人)の総件数のうち、 所得税申告及び消費税申告(個人)の総件数のうち、
-
- ① e-Tax利用件数
- ② 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した申告書を印刷して書面により税務署に提出した件数の合計件数が占める割合。
- (2) 業務・システムの最適化と業務改革(BPR)の推進
-
- イ 平成21~26事務年度の主な取組
-
- (イ) 事務処理の簡素化・効率化
- A KSKシステムが保有する情報を活用し、大規模法人に係る調査関連資料の作成事務を簡素化するためのシステム開発を段階的に行った。
- B 所得税の確定申告書について地方公共団体への連絡方法を書面からデータ送信に変更した(再掲)。
- C 株主・役員情報の入力事務の効率化を図るために、e-Taxにより提出された株主・役員情報をKSKシステムへデータ連絡を行うほか、株主の異動がないものについては、法人事業概況説明書の株主情報から一括で複写処理を行うためのシステム開発を行った。
- D 地方税当局との間で相互提供している税務情報のうち、利子・配当等の支払調書及び給与所得・公的年金等の源泉徴収表(地方税当局へ提供)並びに扶養控除の適用誤り等に関する情報(地方税当局から受領)について、オンラインでの提供を可能とするためのシステム開発を行った。
- E 所得税及び消費税の申告書に係る一連の事務全体の進行状況について、KSKシステムでの管理を可能とするためのシステム開発を行った。
- F 税務署間又は局署間で更正決定及び減額更正等の連絡を行う際に使用している「各課部門事務連絡せん」等について、その作成から処理までを進捗管理するためのシステム開発を行った。
- (ロ) 納税者利便性の向上
- 平成21年7月からの、内部事務の一元化と併せて、税務署への来署者が短時間で目的を達成できるよう、各部署の窓口事務に係る業務システムを集約するとともに、納税者窓口の一本化を図った。
- (ハ) システムの高度化
- A 各国税局が保有する間接諸税に係る情報を共有化することや、各システムで管理していた酒類関係の情報を一元化し、各種データの連携を実施した。
- B 財務データ等を高度に活用することにより、調査対象を的確に選定するためのシステム開発を行った。
- C 効果的・効率的な滞納整理事務を行うため、個々の滞納事案に対する整理状況の把握や進捗管理など、段階的にシステム整備を行うとともに、これまでメインフレームで稼働していた徴収システムのオープンシステム化を図り運用を開始した。
- D 株式等譲渡所得事案に係る調査事績の入力をKSKシステムへ一元化し、それに伴う多角的な分析に基づく調査事案の選定を実現するためのシステム開発を行った。
- ロ 平成27~30事務年度の主な施策
-
「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月閣議決定)や、それに基づく「政府情報システム改革ロードマップ」(平成25年12月CIO連絡会議決定、平成27年3月改定)、各年度の「政府情報システム投資計画」を踏まえ、国税関係システムについて、令和3年度を目途に運用コストの3割削減に向けた取組を着実に進めるとともに、より付加価値の高いシステムへと再構築するための戦略的な取組を推進してきた。
なお、具体的には以下のような取組を実施した。- (イ) クレジットカード納付制度の創設、加算税制度の見直し等に対応するためのシステム改修を行った。
- (ロ) 納付手続のデジタル化の推進として、ダイレクト納付において複数の金融機関の預貯金口座を登録し、納税者が引き落とし口座の選択を可能とするためのシステム改修を実施した。
- (ハ) 徴収システムと資料情報システム等との連携を行い、資料情報を有効に活用した滞納整理を可能とした。
- (ニ) 国税庁LANシステムのリプレースにおいて、各国税局で整備していたLANシステムを国税庁LANシステムに統合することにより、運用コストの削減を図るとともに、各国税局で重複していたLAN構築・運用に伴う事務処理の削減、業務継続性の確保などのセキュリティ対策の強化に取り組んだ。
本計画において、「これまでもe-Taxの整備等により電子申告を推進してきたが、経済社会のデジタル化が一段と進展する中、納税者が簡便・正確に手続を行うことができるよう利便性を高めるとともに、社会全体のコスト削減や企業の生産性向上を図る観点から、税務手続のデジタル化を一層推進する。併せて、経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応した税務行政を実現するため、手続オンライン化の徹底や添付書類の撤廃、ワンストップサービスの実現など『納税者の利便性の向上』を図るとともに、組織内では書面中心からデータ中心の事務処理へと転換しつつ内部事務を集約処理するなど、『課税・徴収の効率化・高度化』を図る必要があり、そのために税務行政のインフラである国税情報システムの見直しを行う。その見直しに当たっては、納税者の権利・義務に直結する税務行政の基幹となる極めて重要なシステムであることから、システムのセキュリティや安定運用に十分に配慮した上で、既存のメインフレーム中心の構成からオープンシステム化された構成への最適化を図り、運用コストや機能追加経費の低減と『納税者の利便性の向上』、『課税・徴収の効率化・高度化』を実現するための基盤づくりを目指す。」こととしている。
脚注
- 1 具体的には、①国民や企業による利用頻度が高い年間申請等件数が100万件以上の手続、②100万件未満であっても主として企業等が反復的又は継続的に利用する手続をいう。
- 2 一部手続については、早期に効果が現れやすい手続であるとして、平成23年度末までに目標値を70%以上と設定した。
3 内部事務の一元化等の取組
- (1) 管理運営部門の設置
-
内部事務の一元化は、これまで税務署内の複数の部署で税目別に行っていた内部事務を可能な限り一つの部署(管理運営部門)で一体的に処理することにより事務の効率化を目指すとともに、納税者に対する受付窓口を一本化することにより納税者の利便性向上を目的とする施策である。
平成21年7月から全国の税務署に管理運営部門を設置し、これまで、税務署内の複数の部署で税目別に行っていた同種の内部事務のうち、質問検査権等調査権限を行使しない事務を統合し、管理運営部門で一体的に処理を行っている。 - (2) 内部事務の集中化
-
小規模な税務署は、広い管轄区域を抱える中で、限られた人員により、納税者への賦課・徴収事務を適切かつ効果的・効率的に実施する必要がある。
こうした中で、平成27事務年度から、一部の税務署において、小規模な税務署の内部事務を近隣の税務署に集中化することにより、事務処理の一層の効率化・高度化を図るという施策を実施している(令和元年6月現在9局24署)。 - (3) 内部事務のセンター化
-
経済社会の国際化・ICT化など、税務行政を取り巻く環境が大きく変化する中、国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現」する観点から平成29年6月に「税務行政の将来像~スマート化を目指して~」を公表し、その実現に向けた業務改革に取り組んでいる。
こうした中、平成29事務年度から、一部の国税局において、複数の税務署の内部事務を専担部署(センター)で集約処理することにより、内部事務のより一層の正確性の向上と効率化を図るという施策を試行している(令和元年6月現在12局28センター)。
令和元事務年度からは、当該内部事務のセンター化の試行を国税庁試行と位置づけ、全国的に取り組むこととし、令和3事務年度においては、組織面での体制整備を目指し、更に令和8事務年度においては、全税務署を対象とするセンター化の実施を目指すことについて、平成31年3月18日に職員への伝達を行った。
4 事務の監察
- (1) 監督評価官制度の変遷
-
監督評価官制度は、従来、財務局の所掌とされていた税務監督の事務について、昭和24年6月1日の国税庁発足と同時に、その直属の機関として、事務運営についての総合的監督を行う監督官の制度として創設された。
平成12年6月30日の旧大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)の改正により、平成12年7月10日に旧監督官室が改組され新たに監督評価官室が創設されるとともに、実績の評価(中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号に規定する実績の評価をいう。以下同じ。)の実施事務についても所掌することとされた。
監督評価官室は、創設以来現在まで一貫して全監督評価官の身分を国税庁の職員とし、このうち国税庁本室の監督評価官を除いて各国税局・沖縄国税事務所に派遣する派遣制度が採られている。
国税庁には監督評価官等を指揮監督するために監督評価官室長が置かれ、各国税局には派遣監督評価官等を指揮監督するために派遣監督評価官室長が置かれている。
なお、監督評価官等の定数は、創設当時監督官60人であったが、その後数次の改正を経て、令和元年6月末時点では監督評価官39人、監督評価官補19人となっている。 - (2) 監督評価官の職務
-
監督評価官の職務は、国税庁の所掌事務の監察であり(財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)第384条、第405条)、具体的には監督評価官事務規程(平成12年国税庁訓令第8号)第7条に次のように定めている。
- イ 国税局総合視閲規程(昭和27年国税庁訓令特第29号)に基づく事務
- ロ 国税庁、各国税局・沖縄国税事務所、税務署、税務大学校、税務大学校地方研修所(沖縄研修支所を含む。)、国税不服審判所及び国税不服審判所支部(国税不服審判所沖縄事務所を含む。)の事務運営等を客観的見地から検討するために必要な事務監察(以下「一般監督」という。)に関する事務
- ハ 一般監督のうち、特定事項に限定して、国税庁の事務運営等を機動的に検討するために必要な事務監察(以下「特別監督」という。)に関する事務
- ニ 国税庁の保有する行政文書等の管理の状況の適否について検討するために必要な事務監察(以下「行政文書等の事務監察」という。)に関する業務
- ホ 実績の評価に関する事務の実施に関する事務(総務課調整第一係の所掌に属するものを除く。)
- (3) 監督の状況
-
監督事務については、限られた人員を効果的かつ効率的に活用する観点から、随時、監督体制等を見直している。
平成23事務年度には、それまで対象部署別に「局務視閲」及び「署務視閲」としていた事務監察の区分を「一般監督」に統一した。
また、平成23年4月の「公文書等の管理に関する法律」の施行を踏まえ、平成23事務年度以降は、全国で統一的に「行政文書等の事務監察」を実施している。
なお、「一般監督」及び「特別監督」については、令和元年6月末現在、監督事務の態様によってそれぞれ以下のとおり区分して実施している。- イ 一般監督
- 監督評価官室長が、自らの判断で国税庁の事務運営等を客観的見地から検討するために行う監督事務として、①年間を通じて計画的に行う「計画的一般監督」と②不適切事案等を契機として機動的に行う「機動的一般監督」に区分している。
- ロ 特別監督
-
監督対象を特定の事項に限定し、国税庁の事務運営等を機動的に検討するために行う監督事務として、①長官の命を受けて国税庁全体を対象にする「長官特命特別監督」と②国税局長から要請を受けて国税局及び税務署を対象にする「局長要請特別監督」に区分している。
なお、平成27事務年度以降は、「局長要請特別監督」の実施方法を見直し、全国の派遣監督評価官室を東京及び大阪派遣室を中心とした東西2ブロックに分け、各派遣室が行う監督事務について、実地の事務監察や取りまとめ等をブロックごとに合同で行う「合同運営体制」を実施している。
・東ブロック:札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、沖縄
・西ブロック:名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本
長官特命特別監督テーマ一覧
| 事務年度 | 監督テーマ |
|---|---|
| 21 | 職員研修の現状と今後の在り方(若手・中堅職員の調査・徴収能力(審理能力を含む)の育成を中心として) |
| 22 | 課税内部事務の現状と今後の在り方 |
| 23 | 災害等非常時の対応状況の現状と今後の在り方~通常の勤務体制がとれない状況となった場合の対応マニュアル作成を目指して~ |
| 24 | 事務の集中化の現状と今後の在り方 |
| 25 | 内部事務一元化の現状と今後の在り方 |
| 26 | 署の調査事務運営の現状と今後の在り方 |
| 27 | 署の統括国税調査官・審理専門官(審理担当者を含む)による調査審理の現状と課題 |
| 28 | 署の資料情報事務の現状と課題 |
| 29 | 署の統括国税調査(徴収)官の管理事務の現状と課題 |
| 30 | 署の相談・窓口事務の現状と課題 |
-
- ハ 行政文書等の事務監察
- 国税庁における行政文書等の管理・取扱の状況について、訓令等に従って適切に実施されているかを確認し、「国税庁行政文書管理規則」(平成23年国税庁訓令第1号)に定める総括文書管理者等に行政文書の管理状況等の事務監察の結果を報告している。
- (4) 実績の評価
-
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6号第2号では、主として政策の実施に関する機能を担う庁(以下「実施庁」という。)について、その業務の効率化を図る観点等から、府省の長(当庁では財務大臣)は、実施庁の長(国税庁長官)にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、実施庁(国税庁)が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価・公表することとされている。
実績の評価に当たっては、評価の客観性を確保するとともにその質を高めるため、有識者からなる「財務省政策評価懇談会(第48回(平成25年6月18日開催)以前は、「財務省の政策評価の在り方に関する懇談会」)において議論され、講評を得ており、この評価結果を踏まえ、税務行政の改善に取り組んでいる。
なお、国税庁の実績の評価の目的は、おおむね次の三つに整理される。- ① 国税庁の使命、目標等を明らかにし、納税者に対する説明責任を果たすこと。
- ② 国税庁の行政全般について、客観的な評価の実施を確保することにより、常により効果的で質が高く時代の要請に合った成果重視の行政を目指し続けること。
- ③ 国税庁の仕事の進め方を改善し、職員の意欲の向上、組織の活性化を図ること。
-
国税庁の実績の評価については、平成12事務年度における試行を経て、平成13事務年度から本格実施した。
その後、平成25年12月20日に、各行政機関における取組の標準的な指針として「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」(政策評価各府省連絡会議了承)が示され、これに基づき平成26事務年度から実施計画と併せて事前分析表を作成している。
事前分析表においては、過年分の各測定指標の目標値や各目標に関係する予算等を明示するなど、より適切な目標の設定・管理を行うとともに、これまで設定していた定量的測定指標に加え、定性的測定指標を設定することで、実績の評価の充実を図ったほか、評定方法をより明確にすることにより、評価の質的向上及び評価作業の効率化を図った。
各事務年度の実施計画及び実績の評価書については、財務省ホームページにおいて公表している。 - (5) 監督事務及び実績の評価における今後の展望
-
現在、国税庁では「税務行政の将来像」を掲げ、経済社会の急激な変化に税務行政が的確に対応できるよう、ICTの活用による「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を柱とした「スマート税務行政」の実現に向け、必要なインフラ整備や業務改革等に取り組んでいるところであり、今後、国税庁、国税局及び税務署における事務運営のあり方も大きな変革を迎えることになる。
このような環境の中、監督事務及び実績の評価事務においても、常に時代の要請にあったものとなるよう、その手法や基準について随時見直していく。
5 提案制度
-
提案制度は、職員それぞれによる日常の職務及び職場の改善を通じて、税務行政に対する国民の理解と信頼が得られるよう、行政文書、電子データ、個人情報等の厳正な管理及び職務を遂行するに当たっての法令遵守の徹底など適正な事務の管理を図るほか、職員の職務への積極的な参加意識の醸成、職員の能力向上及び事務の効率化を図り、より効率的な税務行政を推進するとともに、納税者利便の向上及び職員の働きやすい職場環境の整備を図ることを目的として設けられている。
本制度は、昭和25年に「献策制度」として発足し、昭和38年には、「提案制度」と改称するとともに、提案方法、審査方法及び報賞規定を改定している。その後数次の改正を経ながら、税務行政の効率的運営を図る施策の一つとして定着しているところである。
平成27年には、提案制度のさらなる活用に向けて、事務の適正化・効率化や納税者利便の向上等につながる提案の重要性を周知するため、国税広報の広報内容の見直しを行った。
庁入賞提案については、提案審査委員会(次長を委員長とし、審議官、各部長、官房3課長及び監督評価官室長を委員として構成されている。)が、提案を実施した場合に期待できる効果、実現性、着想、努力・研究の程度などを総合的に審査して決定している。
制度発足時の昭和25年度から平成30年度までの提案件数は合計約23万3,000件、庁入賞件数は合計約1,200件に達している。
活用された庁入賞提案の例
| 提案の題名等 |
|---|
| 「国税還付金振込通知書(はがき)」の様式変更 |
| 個人の各種届出書(開廃業等届出書、納税地の変更届出書、納税地の異動届出書、青色承認申請書など)の様式改訂について |
| レコードスケジュール(RS)設定作業に係るシステム開発 |
| 国税庁ホームページにおける「個人事業の開業・廃業等届出書」のマイナンバー対応様式の提供 |
| 国外送金等調書の効率的な分析のためのOAシステム(隼Ⅱ及び隼EZ)の開発・活用 |
| KSK(連結)研修における「KSK(連結)バーチャルSYS」の開発・活用 |
6 行政文書の適切な管理
- (1) 公文書管理法の制定
-
適切な公文書等の管理体制確立の必要性から、平成23年4月1日に「公文書等の管理に関する法律」(以下「公文書管理法」という。)が施行(平成21年7月1日公布)され、同日付で、「公文書等の管理に関する法律施行令」も施行(平成22年12月22日公布)されるとともに、「行政文書の管理に関するガイドライン(内閣総理大臣決定)」が決定された。
これら法令等により、公文書等の作成・取得、整理・保存、移管・廃棄と特定歴史公文書等の保存・利用を統一したルールで規律し、歴史的に重要な公文書が保存・利用される枠組みが構築された。
国税庁においては、それまで「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」により行政文書の管理方法のほか、決裁、文書の収受・発送の手順等について規定していたところ、公文書管理法等の制定に伴い、平成23年4月1日付で当該訓令を廃止の上、新たに「国税庁行政文書管理規則」(行政文書の作成から廃棄までの一連の手続のほか、点検・監査、紛失等への対応等、行政文書の管理に係るルールを規定)、「国税庁行政文書管理規則細則」(行政文書の保存期間の設定方法、保存・廃棄方法等に係る具体的な手順を規定)、「国税庁行政文書取扱規則」(行政文書の収受・発送、部内決裁等に係るルールを規定)及び「標準文書保存期間基準」(行政文書の分類ごとの名称例及び保存期間等について全庁的なルールを規定)を整備し、公文書管理法等に準拠した行政文書管理を行うこととした。 - (2) 一元的な文書管理システムの整備・運用
-
文書管理については、「総合的な文書管理システムの整備について」(平成12年3月29日各省庁事務連絡会議了承、行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づいて、各府省がそれぞれの文書管理業務の実態に即した個別の文書管理システムで整備・管理することとされ、国税庁においても平成16年2月に「総合的文書管理システム」を導入した。
しかし、個別の文書管理システムにおいては、システムへの登録作業や電子決裁の操作が煩雑との状況が見られたことから、「文書管理業務の業務・システム見直し方針」(平成18年3月31日各府省情報化総括責任者(CIO)連絡会議幹事会決定)に基づいて策定された、「文書管理業務の業務・システム最適化計画」(平成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定、平成21年8月28日改定)において、文書管理業務・システムの効率化・高度化を図る観点から、政府全体で利用可能な各府省共通の「一元的な文書管理システム」を総務省が整備・管理することとされた。
これを受け、平成21年3月以降、各府省において、行政文書の登録・保存・収受・発遣等、電子決裁・供覧等の機能を実装した「一元的な文書管理システム」の運用が段階的に開始され、国税庁においても、平成25年1月に「総合的文書管理システム」から「一元的な文書管理システム」へ移行し、電子決裁の利用促進を含め、文書管理業務の効率化を図った。 - (3) 行政文書管理の適正を確保するための取組
-
公文書管理法に基づく文書管理の徹底を図る観点から、平成29年12月26日に「行政文書の管理に関するガイドライン」が改正され、文書の作成範囲の明確化・正確性の確保・保存期間の適正化等の新たなルールが設けられた。また、「公文書管理の適正の確保のための取組について」(平成30年7月20日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定)において、新たなルールの遵守を徹底するとともに、更なる公文書管理の適正を確保するための取組として、①公文書に関するコンプライアンス意識改革を促す取組の推進、②行政文書をより体系的・効率的に管理するための電子的な行政文書管理の充実、③決裁文書の管理の在り方の見直し、電子決裁システムへの移行の加速を推進することとされた。
国税庁においては、これらの状況を踏まえ、「国税庁行政文書管理規則」等を改正するとともに、公文書監理室を設置し(平成31年4月)、監査体制の整備等を行った。また、今後においても、内閣府をはじめとする関係府省と連携・協調しつつ、行政文書の電子的管理への対応を含め、行政文書管理の適正を確保するための取組を推進していくこととした。
第7節 会計と営繕
1 概要
-
国の財政が厳しい状況にあることを踏まえ、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進する等という基本方針の下、予算編成が行われている。
このような状況の中、国税庁としても、国税庁が実施する各施策について必要性・有効性・効率性等の視点から見直しを行う一方、国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。」を果たすため、指導・調査の充実を図るために必要な予算や国民に対する情報提供等を実施するために必要な予算の確保に努めてきた。
併せて、予算の執行に当たっては、経費の経済的・効率的な使用、調達の透明性の確保に努めてきた。
また、庁舎については、耐震性能が不足する庁舎の耐震化を行うとともに、老朽化の改善や狭あい化の解消に対応するため、建替や大規模改修を継続している。
2 予算の推移
-
平成21年度から平成30年度においては、前述のとおり、国の厳しい財政事情を反映して、予算編成が行われている。
なお、平成10年度以来となる暫定予算が平成24年度に加え、平成25年度及び平成27年度において成立している。
また、平成24年度及び平成25年度には、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するために設けられた、東日本大震災復興特別会計に、庁舎が被災した場合の業務継続体制の強化及び防災機能の強化を図ることを目的とした庁舎の耐震改修経費等が計上された。
このような状況の中、国税庁においては、経済取引の複雑化・国際化、ICT化の進展など、税務行政を取り巻く環境の変化に適切に対応し、国税庁の任務である「適正・公平な賦課及び徴収の実現」を果たすために必要な予算の確保に努めてきた。
その結果、事務の合理化・効率化の推進、納税者利便の向上、税制改正への対応並びに社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応などに必要な予算が措置されている。- (1) 事務の合理化・効率化の推進
-
厳しい定員事情の下で、税務行政の適正な執行を確保するため、事務処理のICT化を一層推進するとともに電子政府の実現に向けて、KSKシステム、国税情報ネットワークの整備等を行った。
なお、その整備等に当たっては、システムの効率的運用を図るとともに、調達の透明性を確保することにより、経費削減に努めた。
また、税務署等における内部事務の効率化による調査・徴収事務の充実を図るため非常勤職員の積極的な活用に努めた。 - (2) 納税者利便の向上
-
国税庁では、e-Taxの普及及び定着を最重要課題の一つに位置付け、オンライン利用に関する累次の計画を策定し、e-Taxの普及及び定着に向けた各種施策を実施した。
e-Taxは、広範な納税者が利用するシステムであるとともに、納税者の権利・義務に関わる重要なデータを扱うことなどから、安全確実なサービスが求められており、システムの安定的な稼動を確保するために必要な整備等予算の確保を図ってきた。
なお、その整備等に当たっては、システムの効率的運用を図るとともに、調達の透明性を確保することにより、経費削減に努めた。 - (3) 税制改正への対応
- 平成21年度から平成30年度においては、国税通則法の改正や消費税の税率改定、国際観光旅客税の創設などの大規模な改正が行われたことから、これらの改正に的確に対応し、制度の執行が円滑に行われるよう、周知、指導、システム改修等に必要な予算の確保を図った。
- (4) 社会保障・税番号制度への対応
-
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月公布)」において、国税庁は、法人番号の付番機関、マイナンバー(個人番号)及び法人番号の利活用機関とされており、平成25年度以降、法人番号を指定・通知・公表するためのシステム開発、共通番号と部内整理番号を紐付けるためのシステム開発、KSKシステムやe-Tax等の既存システムをマイナンバー制度に対応させるためのシステム改修を実施するとともに、これらのシステムに係る運用に必要な予算の確保を図った。
また、国税庁においては、平成27年10月から法人番号の通知を開始するとともに、社会保障分野、税務分野等で利用するため、平成28年1月以降に提出される申告書等(所得税申告書は平成28年分から、法人税申告書は平成28年1月以降に開始する事業年度から)に番号の記載を求めており、法人番号の通知等に必要な予算のほか、番号の利活用機関として、番号制度導入に伴う効果を発揮するために必要なシステム改修及び平成29年11月に本格運用が開始された、マイナポータルの利便性向上に資するシステム改修の予算の確保を図った。
3 徴税コストの推移
-
徴税コストとは、徴税費の租税及び印紙収入(国税庁扱い)に対する割合であり、通常、租税及び印紙収入100円当たりの徴税費として示される。
徴税費とは、国税庁の経費の中で、直接徴税活動に必要な事業費的な経費で、具体的には、国税庁の決算額から、独立行政法人酒類総合研究所運営費交付金及び単式蒸留焼酎製造業近代化事業費等補助金(平成30年度は清酒製造業近代化事業費等補助金)を除いたものである。
徴税コストの推移を見ると国税庁発足時の昭和24年度では、2円47銭であったものが、平成2年度には90銭まで低下したが、平成3年度以降は遂次増加し平成21年度には1円93銭となった。
平成22年度以降は、再び、低下傾向となり、平成30年度は1円22銭となっている。
なお、国税庁関係の徴税費、租税及び印紙収入及び徴税コストの平成21年度以降の推移は統計編1-2の表のとおりである。
4 庁舎整備
- (1) 庁舎の状況
- 税務署庁舎は、昭和30年代から昭和40年代にかけて集中的に整備されたことから、近年、その老朽化が顕著となるとともに、事務の機械化等に伴う狭あい化への対応のほか、耐震性能の低い庁舎の耐震化など、庁舎整備の必要性が高まってきている。
- (2) 庁舎整備への取組
-
庁舎の老朽・狭あい・耐震などへの対応のため、庁舎整備を進める必要があるところ、平成21年度からの10年間においては、次の(3)の建替などによる庁舎整備を行ってきた。
また、庁舎の建替や耐震化のほか、増築や大規模改修による老朽・狭あい対策も進めてきている。 - (3) 庁舎整備の状況
-
- イ 国税局等の庁舎
-
平成26年度には、熊本地方合同庁舎B棟が新築され、熊本国税局、熊本国税不服審判所及び熊本西税務署が入居した。
平成27年度には、東京国税局が新築された。 - ロ 税務署の庁舎
- 平成21年度から平成30年度までに、老朽・狭あい・耐震などへの対応のため、4署の建替と49署の増築を行ったほか、26署が合同庁舎に入居した。
第8節 職員団体
-
現在、国税職員の組織する職員団体の全国組織としては、国税労働組合総連合(以下この節において「国税労組」という。)と全国税労働組合(以下この節において「全国税」という。)の二つがある。このほか、沖縄の国税職員と税関職員とで組織する沖縄非現業国家公務員労働組合全税支部(以下この節において「沖縄国公労全税支部」という。)がある。
なお、全国税と沖縄国公労全税支部は、全国税労働組合・沖縄国公労全税支部国税部門連合会協議会を結成している。- (1) 国税労組
-
国税労組は、各国税局・沖縄国税事務所毎に組織されている12の単位組合が構成する協議体組織である。
なお、平成24年4月に国税庁職員労働組合(庁職組)が設立され、国税労組にオブザーバーとして加盟している。
上部団体との関係については、日本労働組合総連合(連合)系の国公関連労働組合連合会(国公連合)及び全大蔵労働組合連絡協議会(全大蔵労連)に加盟している。 - (2) 全国税
-
全国税は、全国単一組織であり、地方組織としておおむね各国税局単位で9の地方連合会(地連)を組織している。
上部団体との関係については、全国労働組合総連合(全労連)系の日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)に加盟している。各国税局・沖縄国税事務所の職員団体
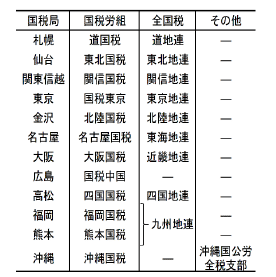
(注) 名称はいずれも略称

