国庫金制度
租税金の地方から中央への送納など国庫金の取扱いは、明治元年(1868)に、三井組・小野組・島田組の官金為替方がはじめで、廃藩置県後は、これら三組が府県為替方に、第一国立銀行が大蔵省為替方となり、取り行いました。
明治7年に小野組・島田組が倒産した後は、大蔵省が直接に国庫金を取り扱い、各地に直轄の金庫を設けました。しかし明治12年には、国税金領収順序にもとづき、各府県に税金預り所を設け、そこで税金預り人が国庫金を取り扱う仕事をしました。
松方財政のもとで成立した日本銀行は、明治16年(1883)年から、国庫金を取り扱うことになり、全国に国庫金取扱所を設けました。また明治20年には、現金の支払い事務も日本銀行が取り行うことになり、国庫金取扱所は国庫金出納所と改称しました。
明治22年(1889)には、中央金庫−本金庫−支金庫の金庫制度を導入し、金庫の事務を日本銀行に委託したことから、日本銀行は全国に支店・代理店を設けて、本金庫・支金庫にあて、金庫事務の一切を取り行うことになり、国庫金の制度が確立しました。

日本銀行
| 国庫金取扱所一覧 明治十七年 一八八四 |
道県府名 | 東京 | 京都 | 大坂 | 神奈川 | 兵庫 | 長崎 | 新潟 | 埼玉 | ||||||||||||||
| 地 名 | 武蔵国日本橋区駿河町 | 山城国下京区三組六角町 | 丹波国天田郡呉服町 | 摂津国東区高麗橋 | 大和国添上郡角振町 | 和泉国堺区熊野町 | 武蔵国横浜区本町 | 武蔵国南多摩郡八王子八幡町 | 相模国足柄下郡幸町 | 摂津国神戸栄町 | 播磨国飾東郡本町 | 播磨国明石郡明石西本町 | 但馬国出石郡出石田結庄町 | 丹波国多紀郡篠山二階町 | 淡路国津名郡洲本大工町 | 肥前国長崎区東浜町 | 対馬国下県郡大手橋町 | 越後国新潟区東堀前通 | 越後国古志郡長岡表三ノ町 | 越後国中頸城郡高田呉服町 | 武蔵国北足立郡浦和宿 | 武蔵国入間郡川越南町 | |
| 取扱所 | 東 京 | 京 都 | 福知山 | 大 坂 | 奈 良 | 堺 | 横 浜 | 八王子 | 小田原 | 神 戸 | 姫 路 | 明 石 | 出 石 | 篠 山 | 洲 本 | 長 崎 | 厳 原 | 新 潟 | 長 岡 | 高 田 | 浦 和 | 川 越 | |
| 代理店名 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第百三十四国立銀行 | 三井銀行 | 第六十八国立銀行 | 第三十二国立銀行 | 三井銀行 | 三井銀行 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第三十八国立銀行 | 第五十六国立銀行 | 第五十五国立銀行 | 第百三十七国立銀行 | 久次米銀行 | 第十八国立銀行 | 第十八国立銀行 | 第四国立銀行 | 第六十九国立銀行 | 第百三十九国立銀行 | 中井銀行 | 第八十五国立銀行 | |
| 国庫金取扱所一 覧明治十七年 |
道県府名 | 群馬 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | ||||||||||||||
| 地 名 | 上野国東群馬郡前橋本町 | 上野国山田郡桐生新町 | 上野国北甘楽郡富岡町 | 下総国千葉郡千葉町 | 下総国香取郡佐原村 | 上総国望陀郡木更津村 | 常陸国東茨城郡水戸上市泉町 | 常陸国新治郡土浦川口町 | 下総国豊田郡本宗通町 | 下野国下都賀郡栃木万町 | 下野国河内郡宇都宮杉原町 | 下野国足利郡足利町 | 伊勢国安濃郡津大門町 | 伊勢国度会郡山田岡本町 | 伊賀国阿拝郡上野中町 | 尾張国名古屋区伝馬町 | 三河国額田郡岡崎連尺町 | 三河国渥美郡豊橋八町 | 駿河国安倍郡静岡呉服町 | 遠江国敷知郡浜松伝馬町 | 伊豆国田方郡韮山町 | 甲斐国西山梨郡常磐町 | |
| 取扱所 | 前 橋 | 桐 生 | 富 岡 | 千 葉 | 佐 原 | 木更津 | 水 戸 | 土 浦 | 本宗道 | 栃 木 | 宇都宮 | 足 利 | 津 | 山 田 | 上 野 | 名古屋 | 岡 崎 | 豊 橋 | 静 岡 | 浜 松 | 韮 山 | 甲 府 | |
| 代理店名 | 第二国立銀行 | 第二国立銀行 | 第二国立銀行 | 川崎銀行 | 川崎銀行 | 川崎銀行 | 川崎銀行 | 第五十国立銀行 | 川崎銀行 | 安田銀行 | 安田銀行 | 安田銀行 | 三井銀行 | 第百五国立銀行 | 第八十三国立銀行 | 三井銀行 | 第百三十四国立銀行 | 第百三十四国立銀行 | 第三十五国立銀行 | 第二十八国立銀行 | 伊豆銀行 | 第十国立銀行 | |
| 国庫金取扱所 一覧明治十七年 |
道県府名 | 滋賀 | 岐阜 | 長野 | 福島 | 宮城 | 岩手 | 青森 | |||||||||||||||
| 地 名 | 近江国滋賀郡大津上小辛崎町 | 近江国蒲生郡八幡池田町 | 近江国犬上郡彦根本町 | 美濃国厚見郡国小熊町 | 飛騨国大野郡高山町 | 美濃国可児郡御嵩村 | 信濃国上水内郡長野町 | 信濃国東筑摩郡松本南渥志町 | 信濃国小県郡上田町 | 岩代国信夫郡福島本通 | 岩城国田村郡三春町 | 岩代国岩瀬郡須賀川村 | 岩代国北会津郡若松大町 | 陸前国仙台区大町 | 陸前国牡鹿郡石巻村 | 陸前国志田郡大柿村 | 陸中国南岩手郡志家村 | 陸中国西磐井郡一関村 | 陸中国東閉伊郡宮古村 | 陸奥国東津軽郡青森米町 | 陸奥国津軽郡本町 | 陸奥国三戸郡八戸八日町 | |
| 取扱所 | 大 津 | 八 幡 | 彦 根 | 岐 阜 | 高 山 | 御 嵩 | 長 野 | 松 本 | 上 田 | 福 島 | 三 春 | 須賀川 | 若 松 | 仙 台 | 石 巻 | 古 川 | 盛 岡 | 一 関 | 宮 古 | 青 森 | 弘 前 | 八 戸 | |
| 代理店名 | 三井銀行 | 第六十四国立銀行 | 第百三十三国立銀行 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第十六国立銀行 | 田中銀行 | 田中銀行 | 第十九国立銀行 | 安田銀行 | 第九十三国立銀行 | 久次米銀行 | 第六十国立銀行 | 第七十七国立銀行 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 三井銀行 | 第五十九国立銀行 | 第百五十国立銀行 | |
| 国庫金取扱所一覧明治十七年
|
道県府名 | 秋田 | 山形 | 石川 | 富山 | 福井 | 島根 | 鳥取 | 岡山 | 広島 | 山口 | ||||||||||||
| 地 名 | 羽後国南秋田郡大町 | 羽後国由利郡本荘中町 | 羽後国平鹿郡横手大町 | 羽前国南村山郡山形七日町 | 羽前国西田川郡鶴岡三日町 | 加賀国金沢区尾張町 | 能登国鹿島郡七尾府中町 | 越中国上新川郡富山袋町 | 越中国足羽郡佐久良中町 | 若狭国速敷小浜広峯町 | 出雲国島根郡松江本町 | 石見国那賀郡新町 | 因幡国邑美郡二階町 | 伯耆国会見郡岩宮町 | 備前国岡山区船著町 | 美作国西北条郡津山伏見町 | 備中国上房郡高梁下町 | 安芸国広島区大手町 | 備後国御調郡尾道久保町 | 備後国三次郡上里村 | 周防国吉敷郡山口田町 | 周防国都濃郡徳山村 | |
| 取扱所 | 秋 田 | 本 荘 | 横 手 | 山 形 | 鶴 岡 | 金 沢 | 七 尾 | 富 山 | 福 井 | 小 浜 | 松 江 | 浜 田 | 鳥 取 | 米 子 | 岡 山 | 津 山 | 高 梁 | 広 島 | 尾 道 | 三 次 | 山 口 | 徳 山 | |
| 代理店名 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 第一国立銀行 | 第八十一国立銀行 | 第六十七国立銀行 | 第十二国立銀行 | 第十二国立銀行 | 第十二国立銀行 | 第九十二国立銀行 | 第二十五国立銀行 | 第三国立銀行 | 第五十三国立銀行 | 第八十二国立銀行 | 第八十二国立銀行 | 第二十二国立銀行 | 津山銀行 | 第八十六国立銀行 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第六十六国立銀行 | 第百十国立銀行 | 第百十国立銀行 | |
| 国庫金取扱所一覧明治十七年 |
道県府名 | 山口 | 和歌山 | 徳島 | 高知 | 愛媛 | 福岡 | 大分 | 佐賀 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | |||||||||||
| 地 名 | 長門国赤間関区西南部町 | 紀伊国和歌山区本町 | 紀伊国西牟婁郡田辺栄町 | 阿波国名東郡徳島通町 | 土佐国土佐郡種崎町 | 土佐国高岡郡須崎村中町 | 讃岐国香川郡丸亀町 | 伊予国温泉郡三番町 | 伊予国北宇和郡横新町 | 筑前国福岡区福岡橋口町 | 豊前国企救郡室町 | 筑後国御井郡片原町 | 豊後国大分郡大分町 | 豊前国下毛郡諸町 | 肥前国佐賀郡水ヶ江村 | 肥前国西松浦郡伊万里町 | 肥後国熊本区米屋町 | 肥後国八代郡八代町広横町 | 日向国宮崎郡川原町 | 薩摩国鹿児島郡築町 | 大隈国姶良郡加治木反士村 | 大隈国大島郡金久村 | |
| 取扱所 | 赤間関 | 和歌山 | 田 辺 | 徳 島 | 高 知 | 須 崎 | 高 松 | 松 山 | 宇和島 | 福 岡 | 小 倉 | 久留米 | 大 分 | 中 津 | 佐 賀 | 伊万里 | 熊 本 | 八 代 | 宮 崎 | 鹿児島 | 加治木 | 金 久 | |
| 代理店名 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第四十三国立銀行 | 第三十四国立銀行 | 第七国立銀行ほか | 第三十七国立銀行 | 第百十四国立銀行 | 第九十二国立銀行 | 第二十九国立銀行 | 第十七国立銀行 | 第八十七国立銀行 | 第六十一国立銀行ほか | 第二十三国立銀行 | 第七十八国立銀行 | 第百六国立銀行 | 伊万里銀行 | 第九国立銀行 | 第百三十五国立銀行 | 第百四十七国立銀行 | 第五国立銀行 | 第五国立銀行 | 第五国立銀行 | |
| 国庫金取扱所一覧明治十七年 一八八四 |
道県府名 | 沖縄 | 北海道 | ||
| 地 名 | 琉球国 | 石狩国札幌郡 | 根室国根室郡 | 渡島国函館区 | |
| 取扱所 | 那 覇 | 札 幌 | 根 室 | 函 館 | |
| 代理店名 | 川崎正蔵 | 三井銀行 | 三井銀行 | 第三十三国立銀行 | |
※松尾家文書第14・47号より作成、税関の部10箇所は省略
明治15年(1882)に日本銀行が創設され、翌年から国税金など国庫金を取り扱うようになり、明治17年の段階で、全国の国立銀行などに置かれた国庫金取扱所は、合わせて114ヵ所でした。
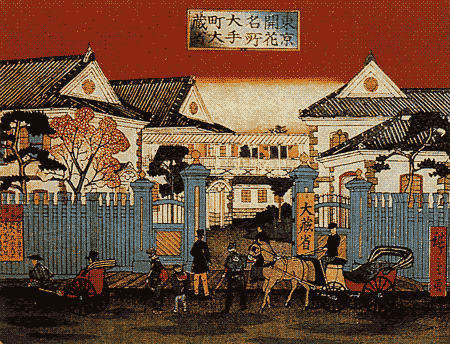
※大蔵財務協会撮影
大蔵省の錦絵
大蔵省は、明治2年(1869)7月8日に設けられました。庁舎は東京城内などを転々としましたが、この錦絵の大蔵省庁舎は、明治10年に大手町に創建されました。
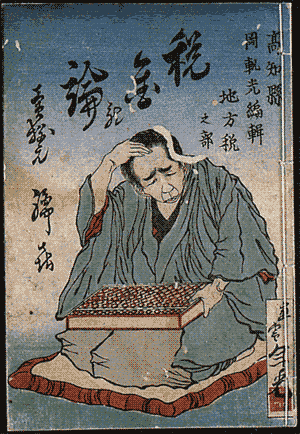
税金の論 明治11年(1878)
高知県士族・岡軌光の編集による、地方税規則に関する解説書です。表紙の、そろばんを持った商人が頭をかいている姿が印象的です。
明治11年には、地方三新法(郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則)が公布され、また同年に「国税金領収順序」も定められたことで、国税と地方税の取り扱いが明確になりました。
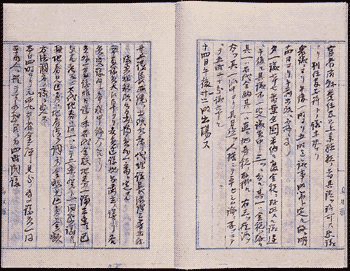
議事日録 明治6年(1873) ―初期の大蔵省金庫―
大蔵省は、明治6年4月、全国の府県官を一堂に会して、地租改正について話し合いました。「議事日録」は、鳥取県参事の関義臣が、議事などを記した日誌で、会議の様子を知る貴重な記録です。
明治6年4月14日には、「本日四時ヨリ、元西丸本省金庫見分ノ為メ、議員一同案内人二従テ、可相赴筈二付四時閉議、四時後、各員一同金庫見分二赴ク」と、出席した府県官らが大蔵省の金庫を見学しました。
その後、この金庫は出納に不便であることから、大手町の大蔵省内に、石造りの金庫を設けました。
江戸幕府は、金納年貢を江戸城の「金蔵」に納めました。明治新政府は、この「金蔵」を引き継ぎ、大蔵省の金庫とし、税金をここに納めました。
金庫を管理していたのは、大蔵省の出納寮でした。その職務規定のなかからは、次のように、金庫を厳重に管理している様子がうかがえます。
「金庫は二重の扉と鎖で、外扉は監督司が緘封(かん ぽう)し、内扉は出納司が印封(いん ぷう)する。開鎖(かい さ)するごとに、両司が立ち会って、出納する金額を詳細に記録し、翌日に金庫帳とつき合わせて、正しければ検印する」(『大蔵省沿革志』)