3 適正・公平な税務行政の推進
国税庁は、適正かつ公平な課税を実現するため、限られた人員等をバランスよく配分し、大口・悪質な納税者に対しては組織力を最大限に活かした的確な調査を行う一方で、簡単な誤りの是正などは簡易な接触を組み合わせて行うなど、メリハリのある事務運営を心掛けています。
特に不正に税金の負担を逃れようとする納税者に対しては、様々な角度から厳正な調査を実施することとしています。
具体的には、KSKシステムを活用して、データベースに蓄積された所得税や法人税の申告内容や各種資料情報などを基に、業種・業態・事業規模といった観点から分析して、調査対象を選定しています。
このように、資料情報は、適正・公平な課税を実現する上で重要であることから、調査において活用効果の高い資料情報を効率的に収集するための体制を整備しています。
税務調査等の件数
| 事務年度 | 平成17事務年度 | 平成18事務年度 | 平成19事務年度 |
|---|---|---|---|
| 調査の件数 | 439 | 474 | 466 |
| 簡易な接触の件数 | 687 | 658 | 698 |
税務調査は、納税者の申告内容を帳簿などで確認し、申告内容に誤りがあれば是正を求めるものです。特に悪質な納税者に対する税務調査には日数を十分かけるなど重点的に取り組んでいます。
実地調査で把握した1件当たりの申告漏れ所得金額は、平成19事務年度においては、申告所得税は965万円1、法人税は1,107万円となっています。
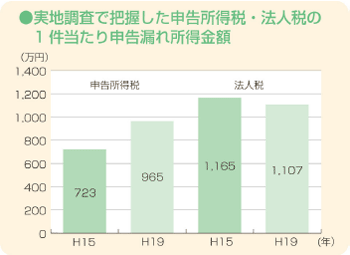
注釈
- 1 実地調査のうち、特別・一般調査に係る金額です。
(1) 調査において重点的に取り組んでいる事項
-
イ 資産運用の多様化・国際化に対する取組
高額な所得が見込まれるが申告額が少なかったり、そもそも申告を行っていない者などについては、資産運用の多様化・国際化も念頭に置いた上で調査等に取り組んでいます。特に高額所得者が、海外投資や外国為替証拠金取引(以下「FX取引」といいます。)により得た収入の申告を行わないケースも把握されているため、様々な切り口により調査選定を行い、調査を充実させています。
また、昨今の活発なFX取引を反映して、平成20年度の税制改正により、先物取引に関する調書に係る整備が行われ、平成21年1月1日以後に店頭で取引される金融商品先物取引の差金決済についても、取引所取引と同様に支払調書の提出が義務付けられました。提出された支払調書は申告内容の確認等に利用し、必要に応じて適正課税のために活用することとなります。 -
ロ 消費税の不正還付申告に対する取組
消費税は、主要な税目の一つであり、預り金的性格を有するため、国民の関心が極めて高く、一層の適正な執行が求められています。特に、消費税について虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられるため、還付の原因となる事実関係について十分な審査を行うとともに、還付原因が不明な場合には、調査等により接触し、不正還付防止に努めています。 - ハ 審理の充実
税務行政に対する信頼を確保するために、課税がきちんとした事実認定の下、適切な法令解釈あるいは法令の適用がなされていることが重要です。
このため、あらゆる事案において、常に、納税者の主張を正確に把握し、的確な事実認定に基づいて十分に法令面の検討を行った上で、適正な課税処理を行うよう努めています。その際、確実に法令要件が満たされているかなどを確認するための手続・手順の遵守を徹底しています。FX取引に係る実地調査の事績
○ 平成18事務年度において、FX取引を行っている者のうち、申告漏れあるいは無申告が想定される者に対して、重点的に実地調査を行いました(調査件数 1,030件)。
申告漏れ所得金額は、224億円にも上り、1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,176万円となっています。
平成18事務年度の所得税の実地調査(特別・一般)の状況は、1件当たりの申告漏れ所得金額が846万円となっており、FX取引に係る実地調査事績と比較すると、1件当たりの申告漏れ所得金額は2.6倍となっています。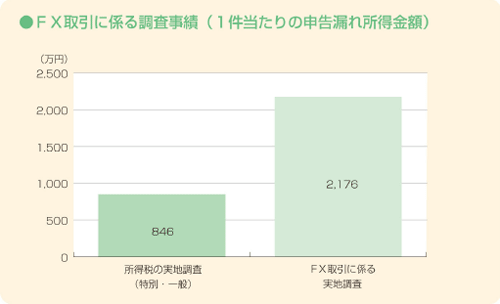
消費税調査の取組み
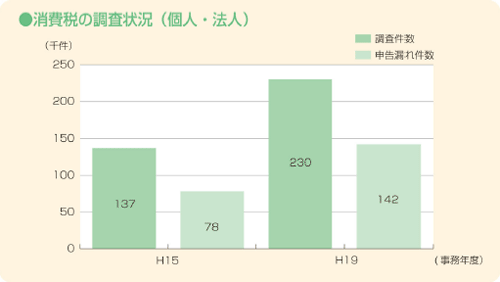
○ 悪質な消費税不正の例
- ・ 架空の契約により、不動産や機械設備などの固定資産を取得したように仮装し、不正に消費税の還付を受けていた。
- ・ 事業者が支払う人件費は非課税であるが、関係会社(人材派遣会社など)からの派遣であると偽ることにより、課税取引である外注費に仮装して不正に消費税の還付を受けていた。
(2) 適正な源泉徴収制度の運営
源泉徴収制度は、年末調整を行うことにより、5,000万人を超える給与所得者のうち多くが確定申告の手続を要することなく課税関係を完結できる制度であり、申告納税制度の円滑な運営と並び、税務行政上極めて重要な制度です。
国税庁では、源泉徴収義務者に適正に源泉徴収や納付を行っていただくため、年末調整説明会や各種手引・パンフレットの配布等により、源泉徴収制度の周知・広報を行っています。
また、預り金である源泉所得税を納期限まで納付していない源泉徴収義務者に対しては、文書や電話照会により効率的な納付指導を実施しています。特に、大口、悪質・処理困難事案に対しては、厳正・的確に対応しています。
(3) 資料情報
国税庁では、税法などの規定により提出が義務付けられている給与所得の源泉徴収票や利子等の支払調書のほか、調査などの際に把握した裏取引や偽装取引に関する情報など、様々な資料情報の収集を行っています。
国税庁で収集した資料情報は、現在、年間1億9,000万枚にも上り、これらの情報と申告に関するデータを一元的にKSKシステムで管理し、的確な指導や税務調査に活用しています。
また、近年の経済社会の広域化、国際化、高度情報化などに対応するため、新しい取引形態に関する資料情報を積極的に収集しており、海外の企業との取引、海外投資に関する情報、インターネットを利用した電子商取引などの資料情報の収集に取り組んでいます。
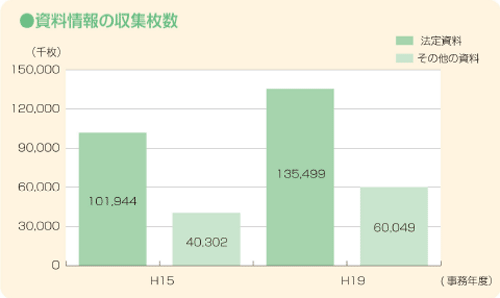
(4) 査察
一般の税務調査とは別に、偽りその他不正の行為により故意に税を免れた納税者には、正しい税を課すほかに、反社会的行為に対して刑事責任を追及するため、強制的権限を行使するなどして犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づき検察官に告発し、公訴することを求めます。これを査察制度といいます。査察制度は、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じ、適正・公平な課税の実現と申告納税制度を維持するという重要な使命を担っています。
全国の国税局等の査察部門では、関係各部及び検察当局等との連携の強化を図り、従来の所得税・法人税事案に加え、国際化事案をはじめとする社会・経済状況の変化に即した社会的波及効果の高い事案についても積極的に対応するよう努めています。
平成20年度においては、211件の査察調査に着手する一方で、前年度から引き続き査察調査を行っていた事件も含めて208件を処理し、そのうち153件を検察官に告発しました。脱税総額は351億円、告発事件1件当たりの脱税額は1億6,300万円となっています。
脱税の手口としては、売上を故意に隠したり、原価を不当に高く計上したりといったものが目立っていました。また、海外取引に関連した脱税、金融・証券取引に関連した脱税、無申告の脱税事例なども見られました。
なお、平成20年度中に一審判決が言い渡された事件は154件で、すべての事件について有罪判決が出されました。平均の懲役月数は16.1か月、罰金額は2,200万円となっています。また、実刑判決は9人に出されました。実刑判決は昭和55年以降毎年言い渡されています。
査察調査の状況
| 年度 | 着手件数 | 処理件数 | 告発件数 | 脱税総額 (うち告発分) |
1件当たり脱税額 (うち告発分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 件 220 |
件 218 |
件 158 |
百万円 35,340 (30,888) |
百万円 162 (195) |
| 20 | 211 | 208 | 153 | 35,070 (24,942) |
169 (163) |
- ※ 脱税額には、加算税を含みます。
査察事件の判決の状況
| 年度 | 判決件数 |
有罪件数 |
有罪率 / / |
実刑判決人数 |
1件当たり犯則税額 |
1人当たり懲役月数 |
1人(社)当たり罰金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 件 189 |
件 189 |
% 100.0 |
人 22 |
百万円 127 |
月 16.1 |
百万円 31 |
| 20 | 154 | 154 | 100.0 | 9 | 79 | 16.1 | 22 |
- ※
 〜
〜 は、他の犯罪との併合事件を除いてカウントしています。
は、他の犯罪との併合事件を除いてカウントしています。 - 犯則税額とは、偽りその他不正の行為により免れた税額をいいます。
≪コラム≫査察制度60周年
査察制度は、昭和23年7月に大蔵省(現、財務省)主税局と財務局に査察部が設置されたことに始まり、平成20年7月に60周年を迎えました。
創設当初には、終戦直後のインフレに伴う利得者の所得の徹底的な捕捉による税収の確保に重点が置かれていましたが、その後の経済・社会の安定とともに、査察制度についての様々な議論を経て、今日に至る「大口・悪質な脱税者の摘発」という理念を確立し、法務・検察当局との緊密な連携の下、わが国における申告納税制度の「最後の砦」として、その定着に大きな役割を果たしてきました。
この60年間は、その時々の経済・社会状況の変化に的確に対応しながら、悪質性が著しく高く、納税秩序の維持に多大な影響を与える事案など、社会的に意義のある事件を幅広く摘発して、期待される査察の役割を果たしてきました。
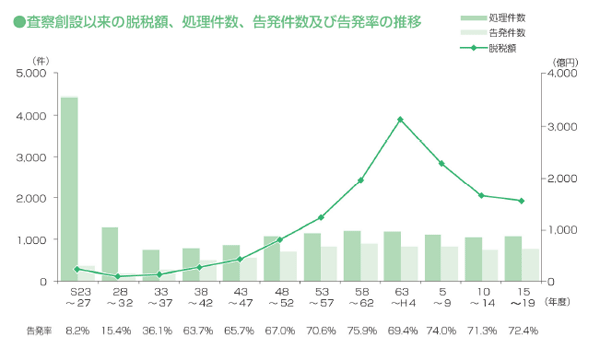

[参考]税務調査について
国税庁においては、適正申告の実現を図るため、納税者に対して、的確な調査・指導を実施することとしています。
(1) 調査の事前通知
調査に際しては、納税者の都合を伺うため、原則として、調査日時などをあらかじめ電話により通知しています。ただし、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前に通知は行っていません。
なお、事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施しています。
(2) 調査の進め方
税務調査のため、職員が納税者の住居や事務所に伺う際には、写真入りの身分証明書などを提示して職員の身分と氏名を明らかにしています。
税務調査の際、調査担当者に日々の取引を記帳している帳簿書類などを提示していただき、申告内容や帳簿書類などに関する質問に対して正確に説明していただければ、税務調査は迅速かつ円滑に進みます。
また、調査を開始した場合は、納税者にかかる負担を少なくするため、できるだけ迅速に進めることとしています。
税務調査は、原則として、納税者本人の立会いの下に行います。
なお、納税者は、税務代理を委嘱した税理士を税務調査に立ち会わせることができます。
(3) 調査終了後の対応
税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容などについて説明することとしています。
申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧める際には、「修正申告等について」という書面を用いて、修正申告に係る異議申立てや審査請求ができないことや延滞税及び加算税について説明をしています。また、今後の申告や帳簿書類の記帳などに関して指導事項があるときは、その内容についても説明を行い、税務調査を契機に納税者が税務知識を深め、将来にわたって自主的に適正な申告と納税ができるよう図っています。
なお、納税者が修正申告などの勧めに応じない場合には、税務署長が更正又は決定を行い、納税者のもとに更正通知書や決定通知書を送付しています。
税務調査の結果、申告内容に誤りが認められなかった場合、次のような対応をとっています。
 申告内容に誤りが認められず、かつ、指導事項もないときには、納税者に対して、「調査結果についてのお知らせ」という書面を送付しています。
申告内容に誤りが認められず、かつ、指導事項もないときには、納税者に対して、「調査結果についてのお知らせ」という書面を送付しています。 修正申告などには至らないが、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項があるときには、その内容について説明を行っています。また、税務調査が終了したことを明確に伝えています。
修正申告などには至らないが、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項があるときには、その内容について説明を行っています。また、税務調査が終了したことを明確に伝えています。
[参考]情報の厳正な管理
税金の計算においては、収入や売上、経費の支払いなど納税者のプライバシーに触れる情報が必要となります。また、税務調査では、取引先に関する情報なども必要となる場合があります。こうした納税者のプライバシーや情報が簡単に漏れるようでは、納税者の国税庁への協力は期待できなくなり、円滑な調査に支障が生じかねません。
このため、税務職員が税務調査などで知った秘密を漏らした場合には、国家公務員法上の刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い税法上の刑事罰(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることとなっています。こうした罰則規定の趣旨を徹底するため、定期的に職員に対する研修を行っています。また、お話を伺う場所についても、プライバシーを配慮し、店舗先や玄関先はなるべく避けるようにしています。
また、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨などを踏まえ、行政文書の管理状況を定期的に点検するなどにより、国税庁の保有する納税者情報を厳正に管理するよう努めています。
[参考]加算税・延滞税の取扱いと免除
適正な申告や納税を確保するため、期限内に正しい申告や納税をしていない場合、申告所得税や法人税などのほかに延滞税がかかる場合があります。更に、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
| 延滞税 | 納期限の翌日から2か月を経過する日まで | 年4.5%(平成21年の場合)※ |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2か月を経過した日以後 | 年14.6% |
- ※ 金融情勢により年ごとに変動します。
| 加算税 | 通常の場合 | 仮装隠ぺいがあった場合 | |
|---|---|---|---|
| 期限内に申告したが税額が少なかった場合 | 過少申告加算税 (10%又は15%) |
重加算税(35%) | |
| 期限内の申告がない場合 | 無申告加算税 (15%又は20%) |
重加算税(40%) |
なお、納税者の責めに帰すべき事由のない、正当な理由があると認められる場合は、過少申告加算税又は無申告加算税は課されません。
また、災害による納税の猶予を受けた場合、国税職員の誤った申告指導などによって納税者が申告又は納付することができなかったなど一定の要件に該当する場合には、延滞税の全部又は一部が免除されます。国税庁では、こうした加算税などが課されない場合の取扱いを定め、国税庁ホームページで公表しています。

