別紙
相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について
1 事前照会の趣旨
下記2の事実関係に基づき、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対する遺留分減殺請求の提訴に基づく判決とは異なる内容の相続財産を再配分する旨の書類を作成して合理的な再配分を行った場合、相続人間で贈与又は交換等その態様に応じて贈与税又は所得税の課税関係が生ずることとなると解してよろしいか、ご照会申し上げます。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
被相続人Aと被相続人Bは、婚姻関係にあり、その実子としてC及びDがいます。
昭和Ⅹ年に、CはEと、DはFとそれぞれ結婚し、EとFは、婚姻と同時にA及びBと養子縁組を行いました。
Aは、平成3年に死亡しましたが、Aの全遺産をB、C及びEに包括遺贈する内容の遺言があり、B、C及びEは、Aの遺言に基づき、申告期限内に被相続人Aに係る相続税の申告を行いました。
また、Bは平成4年に死亡しましたが、Bの相続においても、Bの全遺産をEに包括遺贈する内容の遺言があり、Eは、Bの遺言に基づき、申告期限内に被相続人Bに係る相続税の申告を行いました。
D及びFは、A及びBに係る遺言に基づく包括遺贈について、B、C及びEを相手方として遺留分減殺請求権の行使に基づく相続財産の持分移転登記手続及び持分確認等の訴え(以下「本件訴え」といいます。)を提起しました。なお、Eは、平成7年に死亡しました。
平成21年2月、本件訴えに対し、A及びBのほぼ全ての相続財産のそれぞれについて、個別具体的な割合でのD及びFへの遺留分減殺請求権の行使に基づく共有持分移転登記又は共有持分を認める旨の判決(以下「本件判決」といいます。)があり、その後確定したため、本件判決に基づき、Bの相続人、C及びEの相続人は、被相続人A及び被相続人Bに係る相続税の更正の請求を行いました。
ところで、C、D、F及びEの相続人は、本件判決の内容では相続財産の管理処分が困難となり、利用価値も損なわれることから、本件判決とは異なる内容の相続財産の合理的な再配分を行うこととしています。
【相続関係図】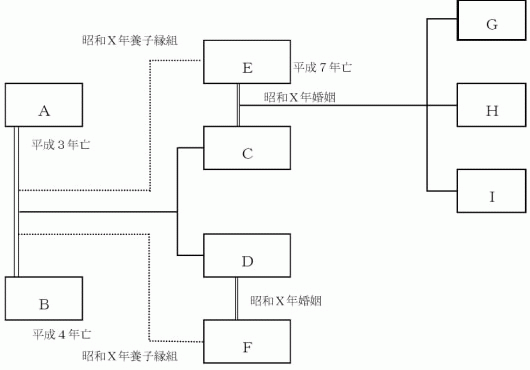
3 事前照会者の求める見解となることの理由
(1)遺留分減殺請求権
イ 遺留分減殺請求権の法的性質
- (イ)遺留分については、民法第1028条において「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける」と規定しています。すなわち、遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合であるとされています。
- (ロ)一方、遺留分減殺請求権については、民法第1031条において「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる」と規定しています。すなわち、遺留分減殺請求権とは、現存の積極的相続財産から贈与や遺贈を差し引くと遺留分の額に達しない場合には、遺留分が侵害されたことになるから、遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するため、贈与や遺贈の履行を拒絶し、さらに、既に給付された財産の返還を請求することができる権利とされています。
遺留分減殺請求権については、「一般に遺留分減殺請求権は形成権であると解されるから(最高裁判所昭和41年7月14日第一小法廷判決)、同請求権の行使により、贈与又は遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利はその限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に物権的に帰属するものと解するのが相当である。」旨判示されています(平成15年9月12日東京地裁判決)。
ロ 遺留分減殺請求と遺産分割の関係
遺留分減殺請求と遺産分割の関係について、最高裁判所は、「遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。特定遺贈が効力を生ずると、特定遺贈の目的とされた特定の財産は何らの行為を要せずして直ちに受遺者に帰属し、遺産分割の対象となることはなく、また、民法は、遺留分減殺請求を減殺請求をした者の遺留分を保全するに必要な限度で認め(1031条)、遺留分減殺請求権を行使するか否か、これを放棄するか否かを遺留分権利者の意思にゆだね(1031条、1043条参照)、減殺の結果生ずる法律関係を、相続財産との関係としてではなく、請求者と受贈者、受遺者等との個別的な関係として規定する(1036条、1037条、1039条、1040条、1041条参照)など、遺留分減殺請求権行使の効果が減殺請求をした遺留分権利者と受贈者、受遺者等との関係で個別的に生ずるものとしていることがうかがえるから、特定遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解される。そして、遺言者の財産全部についての包括遺贈は、遺贈の対象となる財産を個々的に掲記する代わりにこれを包括的に表示する実質を有するもので、その限りで特定遺贈とその性質を異にするものではないからである。」旨判示しています(平成8年1月26日最高裁判所第二小法廷判決)。
すなわち、遺留分減殺請求と遺産分割の関係について、最高裁判所は、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求により取り戻した財産は、取り戻した遺留分権利者の固有の財産であるとの考えを明らかにしていると考えます。
(2)相続税の課税財産
- イ 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが(民法896)、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し(同法898)、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することとなります(同法899)。
このように、相続開始により、相続財産は、遺産共有の状態になり、遺産の分割が行われた場合、その効力は相続開始の時に遡ることとなります(同法909)。 - ロ 相続税の課税財産は、相続又は遺贈により取得した財産であり(相法2)、この場合の相続により取得した財産とは、遺産の分割の遡及効により、一般的には遺産の分割により取得した財産となります。
そして、協議による遺産の分割は被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でもすることができるところ(民法907)、相続税法基本通達19の2-8は「法第19条の2第2項に規定する『分割』とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。」ことを明らかにしています。
このため、当初の遺産分割などにより取得した財産について、各人に具体的に帰属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、一般的には、共同相続人間の自由な意思に基づく贈与又は交換等を意図して行われるものであることから、その意思に従って贈与又は交換等その態様に応じて贈与税又は譲渡所得等の所得税の課税関係が生ずることとなります。
ただし、共同相続人間の意思に従いその態様に応じた課税を行う以上、当初の遺産分割協議後に生じたやむを得ない事情によって当該遺産分割協議が合意解除された場合などについては、合意解除に至った諸事情から贈与又は交換の有無について総合的に判断する必要があると考えます。
また、当初の遺産分割による財産の取得について無効又は取消し得べき原因がある場合には、財産の帰属そのものに問題があるので、これについての分割のやり直しはまだ(当初の)遺産の分割の範ちゅうとして考えるべきであると思われます。
(3)照会の場合の課税関係
上記(1)のとおり、遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解されています。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により取得した資産の共有持分権は、遺産分割が行われるまでの遺産共有としての持分の割合ではなく、遺留分減殺請求権の行使により遺留分権利者に物権的に帰属し、その資産に遺留分権利者固有の財産としての共有持分を有したものであるから、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないと解されており、遺留分減殺請求権の行使により取得した資産の共有持分権が遺留分権利者の相続税の課税財産となります。また、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したことは、相続税法特有の更正の請求事由として規定されています(相法32三)。
以上のことからすると、遺言者AとBの財産全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求権の行使に基づく相続財産の共有持分移転登記又は共有持分を認める旨の判決である本件判決とは異なる内容の相続財産の再配分を行った場合、その再配分は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない共有持分権を有する共有物の再配分であると考えられますから、上記(2)でいうところの「当初の遺産分割協議後に生じたやむを得ない事情によって当該遺産分割協議が合意解除された場合など」及び「当初の遺産分割による財産の取得について無効又は取消し得べき原因がある場合」の遺産の分割の範ちゅうとして考えるべき場合には該当しないと考えます。
したがって、相続人間で本件判決とは異なる内容の相続財産の再配分を行った場合には、原則として、相続人間で贈与又は交換等その態様に応じて贈与税又は所得税の課税関係が生ずることとなると考えます。

