�C���\�������������ꍇ�̒ʎZ�@�l�̉ߔN�x�̌������z�̑����Z���z�̌v�Z���@
�i��55�j
�o�ЁA�r�P�Ћy�тr�Q�Ёi����̒ʎZ�O���[�v���̒ʎZ�@�l�ŁA��������R�����Z�ł��B�j�́A�O���ɂ����Đ��������̌������z��L���Ă���A�܂��A�����̊������\���ɂ����錇�����z���T������O�̏����̋��z�i�@57![]() �A�ȉ��u�������z�v�Ƃ����܂��B�j�͎��̂Ƃ���ł��B
�A�ȉ��u�������z�v�Ƃ����܂��B�j�͎��̂Ƃ���ł��B
| �O�� | ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���茇�����z | ���茇�����z�ȊO�̌������z | �������z�̍��v | �������\���̏������z | �C���\����̏������z | �������\���ɂ�����ߔN�x�̌������z�̑����Z���z | |
| �o�� | 0 | 150 | 150 | 220 | 600 | 104 |
| �r�P�� | 50 | 70 | 120 | 80 | 180 | 50 |
| �r�Q�� | 0 | 300 | 300 | 180 | - | 86 |
| ���v | 50 | 520 | 570 | 480 | - | 240 |
���̌�A�Ŗ������ɂ��o�Ћy�тr�P�Ђ̏������z�����ꂼ��600�y��180�ƂȂ������߁A�o�Ћy�тr�P�Ђ͏C���\�����s�����ƂƂȂ�܂����B
���̏ꍇ�̂o�Ћy�тr�P�Ђ̌������z�̑����Z���z�̌v�Z�͂��ꂼ��ǂ̂悤�ɍs���܂����B�܂��A�r�Q�Ђ́A�o�Ћy�тr�P�Ђ̏C���\���ɔ����A�����Z���z���Čv�Z����K�v�͂���܂����B
�Ȃ��A�o�ЁA�r�P�Ћy�тr�Q�Ђ́A�����@�l���Ȃǂ̖@�l�ɂ͊Y�����܂���B
�y�z
�������\���ɂ����ĒʎZ�O���[�v���̑��̒ʎZ�@�l�Ƃ̊ԂŌ������z���Œ肷�钲����������ŁA�o�Ћy�тr�P�Ђ͂��ꂼ��̖@�l�݂̂ő����Z���z���v�Z���邱�ƂƂȂ�܂��B
�{���ɂ��ẮA�o�Ћy�тr�P�Ђ̊������\���ɂ����鑹���Z���z�́A���ꂼ��104�y��50�ł����A�C���\���ɔ������ꂼ��200�y��94�ƂȂ�܂��B
����A�r�Q�Ђɂ����đ����Z���z�̍Čv�Z���s���K�v�͂���܂���B
�y����z
- �P ���̒ʎZ�@�l�̏C���\�����ɂ��ʎZ�@�l�i���Ёj�ւ̉e���̎Ւf
���̒ʎZ�@�l�̎���(1)����(6)�̋��z���C���\�����ɂ��������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ���z�ƈقȂ邱�ƂƂȂ����ꍇ�ɂ́A�ʎZ�@�l�̌������̒ʎZ�̋K��i�@64�̂V �j�ɂ�鑹���Z���z�̌v�Z��́A���̏��ނɋL�ڂ��ꂽ���z������(1)����(6)�܂ł̋��z�Ƃ݂Ȃ����ƂƂ���Ă��܂��i�@64�̂V
�j�ɂ�鑹���Z���z�̌v�Z��́A���̏��ނɋL�ڂ��ꂽ���z������(1)����(6)�܂ł̋��z�Ƃ݂Ȃ����ƂƂ���Ă��܂��i�@64�̂V �j�B
�j�B
���Ȃ킿�A�C���\�����ɂ��ʎZ�O���[�v���̑��̒ʎZ�@�l�̑����Z�����x�z�������������Ƃ��Ă��A���̑������Ȃ������ʎZ�@�l�́A���Y���̒ʎZ�@�l�̑����Z�����x�z�����������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ���z�ɌŒ肵�đ����Z���z���Z�o���邱�Ƃɂ��A���̒ʎZ�@�l�̏C���\�����ɂ��e�����Ւf���邱�ƂƂ��Ă��܂��B- (1) ���̒ʎZ�@�l�̑����Z�����x�z(���P)
- (2) ���̒ʎZ�@�l�ɂ����Đ������������z
- (3) ���̒ʎZ�@�l�ɂ����Đ��������茇�����z
- (4) ��L(2)�̂������̒ʎZ�@�l�̑����̊z�ɎZ���������z
- (5) ��L(3)�̂������̒ʎZ�@�l�̑����̊z�ɎZ���������z
- (6) ���̒ʎZ�@�l�̏������z
�{���ɂ��ẮA�o�Ћy�тr�P�Ђ̏C���\���ɂ�肻�ꂼ��̏������z���������邱�Ƃɔ����A�o�Ћy�тr�P�Ђ̑����Z�����x�z�����ϓ����邱�ƂƂȂ�܂����A�r�Q�Ђ́A���̑����Z�����x�z�����o�Ћy�тr�P�Ђ̊������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ���z�ɌŒ肵�đ����Z���z���Z�o���邽�߁A�����Ƃ��āA�����̏C���\���ɂ��r�Q�Ђ̑����Z���z���ϓ����邱�Ƃ͂���܂���B���̂��߁A�r�Q�Ђɂ����đ����Z���z�̍Čv�Z���s���K�v�͂���܂���B
- �i���P�j �����Z�����x�z�Ƃ́A�@�l�Ŗ@��57���P�����������ɋK�肷�鑹���Z�����x�z�A���Ȃ킿�A���̒ʎZ�@�l�̏������z��50���ɑ���������z�i�����@�l���A�X���@�l���y�ѐV�ݖ@�l�ɂ��ẮA�������z�j�������܂��i�@64�̂V
 ��n(2)�j�B
��n(2)�j�B
- �Q �C���\�������s�����ʎZ�@�l�̉ߔN�x�̌������z�̑����Z���z�̌v�Z
1�ʎZ�@�l�̏C���\�����ɂ�葹���Z�����x�z���̋��z���������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ���z�ƈقȂ邱�ƂƂȂ����ꍇ�ɂ́A���̒ʎZ�@�l�̑����̊z�ɎZ�������ߔN�x�̌������z�́A����(1)�y��(2)�̋��z�̍��v�z�Ƃ���܂��i�@64�̂V �j�B
�j�B
- (1) �������\�����ɓY�t�������ނɎ��̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ���z���C���\������̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ݂Ȃ����ꍇ�ɂ������z���������T���z(���Q)�i�@64�̂V
 ��j�B
��j�B
���Ȃ킿�A�����\���ɂ����đ��̒ʎZ�@�l����z�����ꂽ�������z�ŒʎZ�@�l�̏������z����T���������z�́A�����̊z�ɎZ���������z�ƂȂ�܂��B- �C �ʎZ�@�l�̑����Z�����x�z
- �� �ʎZ�@�l�ɂ����Đ������������z
- �n �ʎZ�@�l�ɂ����Đ��������茇�����z
- �j �ʎZ�@�l�̓��葹���Z�����x�z
- �z �ʎZ�@�l�̔���葹���Z�����x�z
- (2) ���̒ʎZ�@�l�̉ߔN�x�̌������z�̂������̃C�̋��z���Ȃ����̂Ƃ��A���̒ʎZ�@�l�̑����Z�����x�z�����̃��̋��z�Ƃ��A���A�������̒ʎZ�̋K��i�@64�̂V
 ��E�O�j��K�p���Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�Ɍ������̌J�z���̋K��i�@57
��E�O�j��K�p���Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�Ɍ������̌J�z���̋K��i�@57 �j�ɂ�葹���̊z�ɎZ���������z�i�@64�̂V
�j�ɂ�葹���̊z�ɎZ���������z�i�@64�̂V ��j�B
��j�B
���Ȃ킿�A�ʎZ�@�l�̉ߔN�x�̌������z�̂����A�����\���ɂ����đ��̒ʎZ�@�l�ɔz�������������z�ő��̒ʎZ�@�l�̏������z����T���������z�i���̃C�̋��z�j���A���̒ʎZ�@�l�̉ߔN�x�̌������z����T�����������ŁA���̍T����̌������z�̂��������Z�����x�z�Ƃ������z�i���̃��̋��z�j�ɒB����܂ł̋��z���A�����̊z�ɎZ���������z�ƂȂ�܂��B- �C �ߔN�x�̌������z�̂����A�Ȃ����̂Ƃ������z
���̒ʎZ�@�l�ɂ����Đ������������z�̂����A�������\�����ɓY�t�������ނɏ�L(1)�̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ���z���C���\������̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ݂Ȃ����ꍇ�ɂ�����z���������T���z�i���R�j�i�@64�̂V ��C�j�B
��C�j�B - �� �����Z�����x�z�Ƃ������z
�ʎZ�@�l�̏C���\������̑����Z�����x�z�ɁA���� �̋��z������ꍇ�ɂ͂��̋��z�����Z���A����
�̋��z������ꍇ�ɂ͂��̋��z�����Z���A���� �̋��z������ꍇ�ɂ͂��̋��z���T���������z����A��L(1)�̋��z�i��z���������T���z�j���T���������z(�@64�̂V
�̋��z������ꍇ�ɂ͂��̋��z���T���������z����A��L(1)�̋��z�i��z���������T���z�j���T���������z(�@64�̂V ��)�B
��)�B
���Ȃ킿�A�C���\������̑����Z�����x�z�ɁA�������\�����ő��̒ʎZ�@�l����z�����������Z�����x�z�i���� �̋��z�j������ꍇ�ɂ͂��̋��z�����Z���A���̒ʎZ�@�l�ɔz�������������Z�����x�z�i����
�̋��z�j������ꍇ�ɂ͂��̋��z�����Z���A���̒ʎZ�@�l�ɔz�������������Z�����x�z�i���� �̋��z�j������ꍇ�ɂ͂��̋��z���T�����A�X�ɏ�L(1)�ő����̊z�ɎZ���������z���T���������z���A�����Z�����x�z�Ƃ������z�ƂȂ�܂��B
�̋��z�j������ꍇ�ɂ͂��̋��z���T�����A�X�ɏ�L(1)�ő����̊z�ɎZ���������z���T���������z���A�����Z�����x�z�Ƃ������z�ƂȂ�܂��B
 ���������Z�����ߊz�i���S�j�i�@64�̂V
���������Z�����ߊz�i���S�j�i�@64�̂V ��(1)�j
��(1)�j
- (�@) �������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɖ@�l�Ŗ@��57���P���̋K��ɂ�葹���̊z�ɎZ���������z�Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ���z
- (�A) ���̒ʎZ�@�l�̊������\�����ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�����Z�����x�z
 ���������Z���s���z�i���T�j�ɑ����Z���s�������i���U�j���悶�Čv�Z�������z�i�@64�̂V
���������Z���s���z�i���T�j�ɑ����Z���s�������i���U�j���悶�Čv�Z�������z�i�@64�̂V ��(2)�j
��(2)�j
- �C �ߔN�x�̌������z�̂����A�Ȃ����̂Ƃ������z
- �i���Q�j ��z���������T���z�Ƃ́A����茇�����z���z�����茇�����z�ȊO�̌������z����ꍇ�̂��̒����镔���̋��z�i�@64�̂V
 ��n�A�ȉ��u��z���������z�v�Ƃ����܂��B�j�ɔ���葹���Z�������i�@64�̂V
��n�A�ȉ��u��z���������z�v�Ƃ����܂��B�j�ɔ���葹���Z�������i�@64�̂V �O���j���悶�Čv�Z�������z�������܂��B
�O���j���悶�Čv�Z�������z�������܂��B - �i���R�j �z���������T���z�Ƃ́A����茇�����z���z�����茇�����z�ȊO�̌������z�ɖ����Ȃ��ꍇ�̂��̖����Ȃ������̋��z�i�@64�̂V
 ��j�A�ȉ��u�z���������z�v�Ƃ����܂��B�j�ɔ���葹���Z���������悶�Čv�Z�������z�������܂��B
��j�A�ȉ��u�z���������z�v�Ƃ����܂��B�j�ɔ���葹���Z���������悶�Čv�Z�������z�������܂��B - �i���S�j ���������Z�����ߊz�Ƃ́A(2)��
 (�@)�̋��z��(�A)�̋��z����ꍇ�ɂ����邻�̒����镔���̋��z�������܂��B
(�@)�̋��z��(�A)�̋��z����ꍇ�ɂ����邻�̒����镔���̋��z�������܂��B - �i���T�j ���������Z���s���z�Ƃ́A(2)��
 (�@)�̋��z��(�A)�̋��z�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ����邻�̖����Ȃ������̋��z�������܂��B
(�@)�̋��z��(�A)�̋��z�ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ����邻�̖����Ȃ������̋��z�������܂��B - �i���U�j �����Z���s�������Ƃ́A���̎Z���ɂ��v�Z���������������܂��B
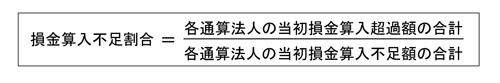
- (1) �������\�����ɓY�t�������ނɎ��̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ���z���C���\������̃C����z�܂ł̋��z�Ƃ݂Ȃ����ꍇ�ɂ������z���������T���z(���Q)�i�@64�̂V
- �R �o�Ћy�тr�P�Ђ̏C���\���ɂ�����ߔN�x�̌������z�̑����Z���z�̌v�Z
- (1) �������\���ɂ�����ߔN�x�̌������z�̑����Z���z�̌v�Z
�o�� �r�P�� �r�Q�� ���v �J�z�������z
�y�� ���茇�����z�z150�y0�z 120�y50�z 300�y0�z 570�y50�z �����Z�����x�z
�i�����~50%�j110 40 90 240 �����Z�������
���茇�����z�\ 50 �\ 50 �����Z�����茇�����z
�T����̑����Z�����x�z110 0 90 200 ���茇�����z�ȊO�̌������z 150 70 300 520 ����茇�����z���z 520�~110�^200��
286520�~0�^200��
0520�~90�^200��
234520 ��z���������z 286�|150
��136�\ �\ 136 �z���������z �\ 70�|0��70 300�|234��66 136 ����葹���Z������ 36.5%���i240�|50�j�^520 ����葹���Z�����x�z 104
��286�~36.5%0 86
��234�~36.5%190 �������z�̑����Z���z
�y���@���茇�����z�z104 50�y50�z 86 240�y50�z - (2) �C���\���ɂ�����o�Ђ̑����Z���z�̌v�Z
�o�� �r�P�� �r�Q�� ���v ��z���������T���z�i�w�j��L�Q(1) 50
��136�~36.5%�\ �z���������T���z
��L�Q(2)�C�\ ���������Z�����ߊz
��L�Q(2)��
�\ 10
��50�|40�\ 10 ���������Z���s���z
��L�Q(2)��
6
��110�|104�\ 4
��90�|8610 �����Z���s������ 100%��10�^10 �����Z���s���z�~�����Z���s������
�i��L�Q(2)�� �j
�j6 �\ �z���������T���z�T����̌J�z�������z
�i��L�Q(2)�j150
��150�|0�����Z�����x�z�Ƃ������z�i��L�Q(2)���j 244
��300�|6�|50��L�Q(2)�̑����Z���z(�x) 150
150��244�o�Ђ̑����Z���z
�i�w�{�x�j200 - (3) �C���\���ɂ�����r�P�Ђ̑����Z���z�̌v�Z
�o�� �r�P�� �r�Q�� ���v ��z���������T���z�i�w�j��L�Q(1) �\ �\ �\ �z���������T���z
��L�Q(2)�C26
��70�~36.5%���������Z�����ߊz
��L�Q(2)��
�\ 10
��50�|40�\ 10 ���������Z���s���z
��L�Q(2)��
6
��110�|104�\ 4
��90�|8610 �����Z���s������ 100%��10�^10 �����Z���s���z�~�����Z���s�������i��L�Q(2)��  �j
�j�\ �\ �\ �z���������T���z�T����̌J�z�������z
�i��L�Q(2)�j94
��120�|26�����Z�����x�z�Ƃ������z�i��L�Q(2)���j 100
��90�{10��L�Q(2)�̑����Z���z(�x) 94
100��94�r�P�Ђ̑����Z���z
�i�w�{�x�j94
�i�Q�l�j
�@�ߔN�x�̌������z�̓����\���ɂ����鑹���Z���z�̌v�Z���@�ɂ��ẮA���̂p���`���Q�Ƃ��Ă��������B - (1) �������\���ɂ�����ߔN�x�̌������z�̑����Z���z�̌v�Z