【新設】(特定適格合併等に係る特定資本関係法人が2以上ある場合の特定資本関係が生じた日の判定)
12の2−2−5 法人が2以上の特定資本関係法人との間で当該法人を合併法人等とする法第62条の7第1項に規定する特定適格合併等を行った場合における同項の規定の適用上、同項に規定する特定資本関係の生じた日がいつであるかは、当該法人と各特定資本関係法人(当該法人との間において令第123条の8第4項《共同で事業を営むための適格合併等》に規定する要件を満たしている場合の当該特定資本関係法人を除く。)との間において特定資本関係が生じた日のうち最も遅い日をいうことに留意する。
【解説】
- (1) 法人と特定資本関係法人(当該法人との間に特定資本関係がある法人をいう。)との間で当該法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする特定適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資のうち、共同で事業を営むためのものに該当しないものをいう。)が行われた場合において、当該特定資本関係が当該法人の特定適格合併等事業年度(特定適格合併等の日の属する事業年度をいう。)開始の日の5年前の日以後に生じているときは、当該法人の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、損金の額に算入しない(法62の7
 )。
)。
また、この適用期間とは、合併法人等の特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間をいうが、当該経過する日が当該特定資本関係が生じた日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、その5年を経過する日までの期間とされている(法62の7 )。
)。 - (2) ところで、法人と2社以上の特定資本関係法人との間で特定適格合併等が行われた場合において、当該法人と各特定資本関係法人との特定資本関係が生じた日が異なるときは、当該適用期間の基準日となる特定資本関係が生じた日がいつであるかが問題となる。
例えば、次の事例のようにA社を合併法人として、B社、C社及びD社の3社を被合併法人とする適格合併が行われた場合に、AB間、AC間及びAD間のそれぞれにおいて、それぞれ特定資本関係を有し、また、いずれも共同で事業を営むためのものに該当しないときは、A社において損金不算入期間となる適用期間はいつまでかという問題である。
[事例]
3月決算法人
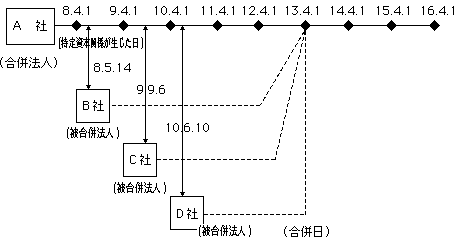
この点、合併法人A社とそれぞれの特定資本関係法人(B社、C社及びD社)との間を個々にみると、![]() A社とB社間では、特定資本関係が生じた日は平成8年5月14日で、適用期間は平成13年4月1日から平成13年5月13日まで、
A社とB社間では、特定資本関係が生じた日は平成8年5月14日で、適用期間は平成13年4月1日から平成13年5月13日まで、![]() A社とC社間では、特定資本関係が生じた日が平成9年9月6日で、適用期間は平成13年4月1日から平成14年9月5日まで、
A社とC社間では、特定資本関係が生じた日が平成9年9月6日で、適用期間は平成13年4月1日から平成14年9月5日まで、![]() A社とD社間では、特定資本関係の生じた日が平成10年6月10日で、適用期間はは平成13年4月1日から平成15年6月9日までということになる。
A社とD社間では、特定資本関係の生じた日が平成10年6月10日で、適用期間はは平成13年4月1日から平成15年6月9日までということになる。
しかし、上記事例のような合併が行われた場合、例えば、平成15年2月に生じた特定資産譲渡等損失額が損金算入できるかどうかという点については、同条の規定は、合併法人Aの適用期間において生じた特定資産譲渡等損失額の損金算入を認めないというものであるところ、A社にとってみれば、D社との関係において適用期間が平成15年6月9日までとなる以上、法令上、平成15年2月に生じた特定資産譲渡等損失額は、結局、損金算入が認められないことになる。
そこで、本通達において、法人が2社以上の特定資本関係法人との間で特定適格合併等を行った場合には、適用期間の基準日となる特定資本関係が生じた日は、各特定資本関係法人との間において特定資本関係が生じた日のうち最も遅い日ということになることを明らかにしている。
なお、仮に、上記の事例において、AD間が共同で事業を営むための適格合併等に該当する場合には、特定資本関係が生じた日の判定上、D社を除くことは当然であり、このような場合には、AC間の平成9年9月6日を基準として平成14年9月5日までが適用期間となる。本通達の本文かっこ書においてこのことを明らかにしている。