第2章 公売財産の評価
第2節 試算価格の具体的な算定方法
公売財産の試算価格は、原則として、次に掲げる評価方法のうち財産の種類等からみて適当と認められる一又は複数の方法により算定する。この場合においては、いずれの評価方法によっても、公売財産の価格形成要因に基づき、市場性を適切に考慮する必要があることに留意する。
また、公売財産が不動産である場合は、公売財産の属する地域又は類似地域にある標準地の公示価格又は基準地の標準価格との比較検討を行った上、試算価格を算定するものとする。
1 取引事例比較法の適用方法
(1) 取引事例の選択の基準
不動産の取引事例については、次のいずれにも該当するものを選択するよう努めるものとする。
なお、最終的には取引が成立しなかった売買の交渉に関する事例であっても、その具体的事情を考慮の上、適正に補正できるものについては、取引事例に準ずるものとして取り扱って差し支えない。
また、不動産以外の財産についても、これに準ずるものとする。
- イ 公売財産の近隣地域に属するものであること。
なお、この取引事例が少ない場合には、公売財産の類似地域に属するものでも差し支えない。 - ロ その取引が正常なものと認められるものであること又は事情補正が可能なものであること。
- ハ 時点修正が可能なものであること。
- ニ 個別的要因の比較が可能なものであること。
(2) 対象取引事例価格に対する事情補正
事情補正は、上記(1)により選択した対象取引事例が、おおむね次に掲げるような正常な取引事情以外の事情を含んでおり、これが対象取引事例価格に影響していると認められるときに行い、対象取引事例価格を正常な取引価格に修正する。
なお、この修正に当たっては、精通者の意見(第2章第3節2(4)参照)、取引当事者の申立て、標準地の公示価格又は基準地の標準価格と当該地域の取引価格との格差割合等を参考にして行うことに留意する。
- イ 特殊な使用方法を前提として取引が行われたとき。
- ロ 極端な供給不足又は景気等の先行きに対する過度に楽観的な見通し等、特殊な市場条件の下に取引が行われたとき。
- ハ 業者等の中間利益の取得を目的として取引が行われたとき。
- ニ 買手又は売主の知識や情報量が明らかに不足している状態において取引が行われたとき。
- ホ 買急ぎ又は売急ぎにより取引が行われたとき。
- へ 知人、親戚間等の人的関係により恩恵的な取引が行われたとき。
- ト 割賦払いによる金利相当額が含まれるなど、対価以外のものが含まれて取引が行われたとき。
- チ 不相応な造成費、修繕費等を考慮して取引が行われたとき。
(3) 対象取引事例価格に対する時点修正
時点修正は、対象取引事例に係る取引時点が見積価額の決定時点と異なることにより、価格水準の変動があると認められるときに行い、次により対象取引事例価格を見積価額の決定時点における価格に修正する。
- イ 不動産以外の財産については、取引時点と見積価額の決定時点の間における当該財産の価格変動率を乗じて修正する。
-
ロ 不動産については、対象取引事例に係る不動産の属する近隣地域又は類似地域における不動産の価格変動率を求め、これにより、対象取引事例価格を修正する。
なお、この場合には、 標準地の公示価格及び基準地の標準価格の変動率、
標準地の公示価格及び基準地の標準価格の変動率、 日本不動産研究所発表の全国市街地価格指数、全国木造建築費指数、
日本不動産研究所発表の全国市街地価格指数、全国木造建築費指数、 消費者物価指数及び卸売物価指数、
消費者物価指数及び卸売物価指数、 路線価等の変動率及び固定資産評価額における変動率、
路線価等の変動率及び固定資産評価額における変動率、 精通者の意見による地価変動率及び建築費指数等を参考として変動率を求めて差し支えない。
精通者の意見による地価変動率及び建築費指数等を参考として変動率を求めて差し支えない。
(4) 不動産の個別的要因の比較
取引価格は、不動産の個別的要因(例えば、土地については、地積、形状、日照、地勢等がある。)を反映しているものであるから、公売財産と対象取引事例に係る財産の個別的要因を比較し、価格水準格差の是正を行う(第3章第1節4《比較表による調整》参照)。
なお、対象取引事例が類似地域のものである場合には、下記(5)の地域要因の比較後にこの調整を行うことに留意する。
(5) 不動産の地域要因の比較
対象取引事例が、公売財産の属する地域の類似地域のものである場合には、公売財産が属する地域と当該事例が属する地域のそれぞれの標準的な不動産に係る地域要因を比較し、価格水準格差の是正を行う(第3章第1節4《比較表による調整》参照)。
2 収益還元法の適用方法
(1) 純収益
- イ 純収益とは、公売財産に帰属する適正な収益をいい、一般には年間を単位とする総収益から総費用を差し引いて求める。例えば、賃貸用不動産にあっては、その賃貸収入及び敷金等の運用益から維持管理費、公租公課(固定資産税、都市計画税等)、損害保険料等の諸経費を差し引いて求める。
なお、純収益には、永続的なものと非永続的なもの、減価償却前のものと償却後のものがあり、それぞれ還元利回り又は割引率の選択と整合がとれていなければならないこと(例えば、減価償却費を控除した償却後の純収益を用いる場合には還元利回りも償却後の純収益に対応するものを用いらなければならない。)、また、賃貸収入は、いわゆる実質賃料であり、共益費等の名目で支払を受けているものでも、実質的に賃料と認められるものはこれに含まれることに留意する。 - ロ 純収益の算定に当たっては、公売財産からの総収益及びこれに係る総費用を把握し、かつ、それぞれの項目の細部について過去及び将来の推移動向等を分析して、適正な純収益を求める。
- ハ 公売に係る不動産の純収益を公売財産と類似の不動産の純収益によって間接的に求める場合には、それぞれの地域要因の比較及び個別的要因の比較を行い(本節1(4)及び(5)参照)、採用した純収益について適正な補正を行う必要があることに留意する。
- ニ 純収益が建物及びその敷地に係るものである場合において、建物(又は敷地)に係る部分が特定できるときは、純収益から建物(又は敷地)に係る部分を控除することによって敷地(又は建物)に係る純収益を求めて差し支えない(この方法を「土地残余法」又は「建物残余法」という。)。
(2) 還元利回り及び割引率
還元利回り及び割引率は、公売財産の収益性を表すものであり、比較可能な他の資産の収益性や金融市場における運用利回りと密接な関連性を持っている。還元利回りの算定に当たっては、 公売財産と類似の財産の取引事例から求められる利回りを基に、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じて補正を行う方法や、
公売財産と類似の財産の取引事例から求められる利回りを基に、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じて補正を行う方法や、 割引率から純収益の変動率を控除する方法などにより求める。また、割引率の算定に当たっては、
割引率から純収益の変動率を控除する方法などにより求める。また、割引率の算定に当たっては、 のほか、
のほか、 債券等の金融資産の利回りを基に、その投資対象との関連において有する当該公売財産の個別性、すなわち投資対象としての危険性、流動性、管理の困難性、資産としての安全性等を加味する方法などによっても求めることができる。
債券等の金融資産の利回りを基に、その投資対象との関連において有する当該公売財産の個別性、すなわち投資対象としての危険性、流動性、管理の困難性、資産としての安全性等を加味する方法などによっても求めることができる。
(3) 収益価格を求める方法
公売に係る不動産について収益価格を求める基本的方法は、次の計算式によるものとする。なお、直接還元法又はDCF法の選択は、収集可能な資料の範囲及び対象不動産の類型に即して適切に適用し、また、両方法の適用が可能な場合には併用して得られた二つの価格を比較検討して、最終的な収益価格を求める。
なお、不動産以外の財産についても、これに準ずるものとする。
イ 直接還元法
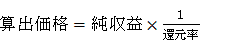
ロ DCF法
算出価格=毎期の純収益の現在価値の合計 + 保有期間満了時の売却予想額の現在価値
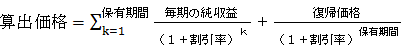
3 原価法の適用方法
(1) 再調達原価を求める方法
不動産についての再調達原価を求める方法には、直接法と間接法の二つがあるが、必要に応じてこれらを併用するものとする。ただし、これらの方法により求めることが困難である場合には、下記ハに掲げる方法によることとして差し支えない。
なお、不動産以外の財産についても、これに準ずるものとする。
おって、再調達原価を求めるに当たっては、例えば、建物については、建設請負や自己建設を問わず、全て建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費に、発注者が直接負担すべき通常の附帯費用を加算して求める。
(注) 発注者が直接負担すべき通常の附帯費用とは、設計監理費、請負者に前渡した資金の金利、測量費、分筆、合筆等の費用をいい、その他契約の内容、地域的慣行などにより、通常必要と認められるものも含まれる。
イ 直接法
直接法とは、公売財産の基礎、屋根、壁等の各構成部分別又は全体について、使用資材の種別、品等及び数量並びに所要労働の種別、時間等を調査し、公売財産の属する地域の見積価額の決定時点におけるそれぞれの単価を基礎とした直接工事費を積算し、これに間接工事費及び請負者の適正な利潤を加えて標準的な建設費を求め、更に発注者が直接負担すべき通常の附帯費用を加算して再調達原価を求める方法である。
なお、公売財産の実際の建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の利潤及び発注者が直接負担した附帯費用の額並びにこれらの明細(種別、品等、数量、工事期間、単価等)が工事見積書などによって判明している場合には、これらの明細を分析して適正に補正し、かつ、必要に応じて時点修正を施し、再調達原価を求めることとして差し支えない。
ロ 間接法
間接法とは、近隣地域又は類似地域に属する公売財産と類似した財産について、その実際の建設に要した直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利潤及び発注者が直接負担した附帯費用の額並びにこれらの明細(種別、品等、数量、時間、単価等)を明確に把握できる場合には、これらの明細を分析して公売財産の再調達原価を求め、それが標準的でない場合には、適正に補正してその再調達原価を求めた上で、これと公売財産とを比較して公売財産の再調達原価を求める方法である。
なお、この方法による場合には、必要に応じて時点修正を行うとともに、類似財産と公売財産について地域要因の比較及び個別的要因の比較を行う(本節1(4)及び(5)参照)。
ハ その他の方法
公売財産の種類及び構造等を基に、建設に要する標準的な費用を建設業者等の精通者の意見を聴取した上で、この価格又は所要の調整を行った価格をもって再調達原価としても差し支えないものとする。
(2) 減価修正の方法
減価額については、原則として財産の耐用年数に基づく方法により求めるものとするが、必要に応じて観察減価法を併用するものとする。
イ 耐用年数に基づく方法
耐用年数に基づく方法には、定額法、定率法があり、公売財産に応じて適当と認められる方法を採用する。
なお、これらの方法による場合の耐用年数については、原則として実際耐用年数によることとする。実際耐用年数を求める場合には、法定耐用年数及び精通者の意見を参考とする。また、公売財産の経過年数が1年未満であるときは、1年に切り上げ、経過年数に1年未満の端数があるときは、これを五捨六入して計算する。
(イ) 定額法
定額法とは、物の耐用年数中の毎年の減価額が一定額であるという前提に基づいて減価償却額を算定する方法であり、平均的に減価する財産(例えば、建物)について適当な方法である。
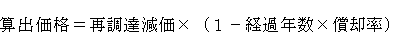
(ロ) 定率法
定率法とは、物の耐用年数中における毎年の減価額が一定の割合であるという前提に基づいて減価償却額を算定する方法であり、経過年数当初において著しく減価する財産(例えば、機械類)について適当な方法である。
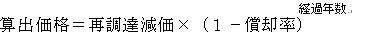
ロ 観察減価法
観察減価法とは、耐用年数に基づく方法のような算式を直接に用いるのではなく、公売財産について各構成部分に減価の要因である物理的要因(腐朽、破損、亀裂、沈下等)、機能的要因(設計の不良、型式の旧式化等)及び経済的要因(近隣地域の衰退等)による実態を調査して減価額を直接求める方法である。