特定民間再開発事業の共同化要件について(照会)
(別紙)
国都制第1号
平成23年7月1日
国税庁課税部審理室長
飯島 信幸 殿
国土交通省都市局
市街地整備課長 望月 明彦
Ⅰ 事実関係等
1 本特例制度における共同化要件
租税特別措置法第37条の5《既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例》第1項第1号の制度(以下「本特例制度」といいます。)の適用対象となる特定民間再開発事業の要件として、事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとする要件(以下「共同化要件」といいます。措令25の4![]() 三)があり、その詳細は次のとおり定められています。
三)があり、その詳細は次のとおり定められています。
[共同化要件](措置法規則18の6![]() )
)
施行令第二十五条の四第二項第三号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
上記の共同化要件を分解すれば、
 譲渡資産の所有権等に係る要件
譲渡資産の所有権等に係る要件
施行地区内の土地(借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権をいいます。)が設定されている土地を除きます。)の所有権を有する者又は施行地区内の借地権が設定された土地に係る借地権を有する者(以下これらの者を「施行前判定対象者」といいます。)の数が2以上であるという事業施行前の所有者が複数であることを必要とする要件(上記の太字前半部分) 買換資産の所有権等に係る要件
買換資産の所有権等に係る要件
事業施行後の施行地区内の土地に係る所有権又は借地権が、施行前判定対象者又は施行前判定対象者及び事業施行により建築された中高層耐火建築物を所有することとなる者の2以上の者により共有されるものであるという事業施行後の所有者が施行前判定対象者を含む複数であり、これらの者に共有されることを必要とする要件(上記の太字後半部分)
という2つの要件から構成されていることが分かります。
2 照会の事実関係
照会の施行地区内には地下鉄が通っているため、施行地区内の土地の一部について地下鉄会社が民法第269条の2《地下又は空間を目的とする地上権》の地上権(以下「区分地上権」といいます。)を設定しており、その区分地上権が特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物の建築に影響しない地下の深部を対象とする区分地上権である場合においては、地下鉄会社がその区分地上権を譲渡することなく、区分地上権が設定されている土地の所有者(以下「底地権者」といいます。)が土地を譲渡すれば、その区分地上権の設定された土地の利用の共同化を図ることができることとなります(次のイメージ参照)。
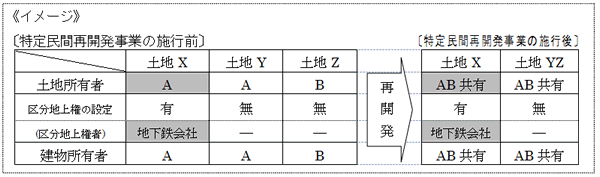
この事実関係により、譲渡資産の所有権等に係る要件を判定する場合、土地Xについては区分地上権という借地権が設定されているため、底地権者であるAではなく、借地権を有する者(以下「借地権者」といいます。)である地下鉄会社を施行前判定対象者として、その判定を行うものと考えることができます。
一方、上記の事実関係からすれば、地下鉄会社が有する借地権は事業の施行による中高層耐火建築物の建築に影響しない地下の深部を対象とするものであることから、たとえ土地Xに借地権が設定されていたとしても、譲渡資産の所有権等に係る要件の判定に当たっては、所有する土地の譲渡により土地の利用の共同化に資することができる底地権者であるAを施行前判定対象者として、その判定を行うべきではないかとの疑問が生じます。
Ⅱ 事前照会の趣旨
上記Ⅰの「2 照会の事実関係」を前提とすれば、譲渡資産の所有権等に係る要件の判定に当たっては、土地Xに係る施行前判定対象者は、借地権者である地下鉄会社ではなく、底地権者であるAとして、その判定を行うものとして差し支えないかお伺いいたします。
結果として、この場合の施行前判定対象者は、土地Xの底地権者であり土地Yの所有者であるAと土地Zの所有者であるBの2者となり、譲渡資産の所有権等に係る要件を満たすことになると考えております。
また、上記のとおり解することを前提とすれば、買換資産の所有権等に係る要件も施行前判定対象者により判定することとなるところ、その判定においても、借地権者である地下鉄会社ではなく、底地権者であるAを土地Xに係る施行前判定対象者とすることとなります。
結果として、事業施行後においては、施行前判定対象者であるA及びBという2者により、区分地上権が設定される土地Xの所有権と土地YZの所有権がいずれも共有されていることから、買換資産の所有権等に係る要件も満たすことになると考えております。
Ⅲ 照会者の求める見解となることの理由
1 本特例制度の概要
個人が、既成市街地等(これに準ずる一定の地区を含みます。)内にある土地等、建物又は構築物(当該個人の事業の用に供しているものを除きます。)を特定民間再開発事業の用に供するために譲渡し、一定期間内に、イ その譲渡をした土地等(譲渡した資産が建物又は構築物である場合にはその敷地の用に供されている土地等)の上に当該特定民間再開発事業により建築された地上階数4以上の中高層耐火建築物(その敷地を含みます。)又はロ 当該特定民間再開発事業の施行される地区内で行われる他の特定民間再開発事業等の施行により当該地区内に建築された中高層耐火建築物(その敷地を含みます。)の全部又は一部を取得して、その取得の日から1年以内に居住の用に供した場合には、
 その譲渡資産の収入金額が取得した資産(買換資産)の取得価額以下である場合には、その譲渡資産の譲渡がなかったものとし、
その譲渡資産の収入金額が取得した資産(買換資産)の取得価額以下である場合には、その譲渡資産の譲渡がなかったものとし、 その譲渡資産の収入金額が買換資産の取得価額を超える場合には、その超える部分に相当する土地建物等のみの譲渡があったものとして、
その譲渡資産の収入金額が買換資産の取得価額を超える場合には、その超える部分に相当する土地建物等のみの譲渡があったものとして、
譲渡所得の計算をすることができることとされています(措法37の5![]() 一)。
一)。
2 特定民間再開発事業について
上記1の特定民間再開発事業とは、地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、その事業が一定の区域又は地区内において施行されるものであること及び次に掲げる要件のすべてを満たすものであることつき、中高層耐火建築物の建築主の申請に基づき、都道府県知事(一定の場合には、国土交通大臣)が認定したものとされています(措令25の4![]() )。
)。
 事業の施行される土地の区域(施行地区)の面積が1,000
事業の施行される土地の区域(施行地区)の面積が1,000 以上であること。
以上であること。 事業の施行地区内において都市施設の用に供される土地又は建築基準法の定めによる規模の空地が確保されていること。
事業の施行地区内において都市施設の用に供される土地又は建築基準法の定めによる規模の空地が確保されていること。 事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして、財務省令で定める要件
事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして、財務省令で定める要件
上記![]() から
から![]() までの要件のうち
までの要件のうち![]() の「財務省令で定める要件」が、今回の照会の対象となる共同化要件ということになります。
の「財務省令で定める要件」が、今回の照会の対象となる共同化要件ということになります。
この共同化要件の内容については、上記Ⅰの「1 本特例制度における共同化要件」に記載したとおりですが、この要件が設けられた趣旨は、細分化された土地の利用の共同化を促進しようとする観点からのものとされています(「昭和59年改正税法のすべて」102頁)。
3 借地権が設定されている土地における共同化要件の判定について
一般に、特定民間再開発事業の施行地区内の土地に借地権が設定されている場合には、事業の施行前(譲渡資産)、事業の施行後(買換資産)のいずれにおいても、借地権が設定されている土地の所有権者である底地権者は判定対象者に該当せず、譲渡資産の所有権等に係る要件及び買換資産の所有権等に係る要件のいずれの判定においても、その借地権者を判定対象者として、その判定を行うこととなります(昭和59年6月20日付建設省都市局長・建設省住宅局長通知「特定民間再開発事業認定事務等の実施について」第一の二の(四))。
このことから、上記Ⅰの「2 照会の事実関係」の土地Xについては、借地権(区分地上権)が設定されていることから、借地権(区分地上権)を有する地下鉄会社を土地Xに係る施行前判定対象者として共同化要件を判定することとした場合、譲渡資産については土地Xに係る借地権者である地下鉄会社、土地Yの所有権を有するA及び土地Zの所有権を有するBという3者が施行前判定対象者として存することから、譲渡資産の所有権等に係る要件を満たすこととなります。
一方、買換資産については、土地Xに係る借地権が地下鉄会社の単独所有となることから、買換資産の所有権等に係る要件を満たさないこととなってしまいます。
しかしながら、次の理由から、土地Xについては、借地権者である地下鉄会社ではなく、底地権者であるAを施行前判定対象者として、共同化要件を判定することが相当と考えています。
[理由]
共同化要件のうち、譲渡資産の所有権等に係る要件については、その判定の対象となる土地の所有権者から、借地権が設定されている土地の所有権者である底地権者が除かれています。
したがって、共同化要件は、事業の施行地区内の土地の所有者のすべてが、その権利を譲渡することまでを求めていないこととなるものと考えます。
一方、借地権については上記の底地権者のような除外規定は存在しないため、事業の施行地区内の借地権者のすべてが借地権を譲渡していなければ、譲渡資産の所有権等に係る要件を満たしていないことになるとも考えられます
しかしながら、施行地区内の土地に借地権を設定している土地(以下「底地」といいます。)が含まれる場合において、その借地権が事業の施行による中高層耐火建築物の建築に影響しない区分地上権のような借地権であるときには、その借地権を譲渡することなく、その底地を譲渡し、施行地区内の他の土地が譲渡されれば、その施行地区内の土地の利用の共同化を図ることができることとなります。
この点、法令上、「その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして、財務省令で定める要件」(措令25の4![]() 三)との政令を受け、財務省令で定める要件として共同化要件(措規18の6
三)との政令を受け、財務省令で定める要件として共同化要件(措規18の6![]() )が定められていることからすれば、この共同化要件にいう「借地権」は、土地の利用の共同化に影響する借地権に限定されることになると解されます。
)が定められていることからすれば、この共同化要件にいう「借地権」は、土地の利用の共同化に影響する借地権に限定されることになると解されます。
したがって、土地の利用の共同化に影響する借地権が設定されている場合(共同化に借地権の譲渡が必要な場合)にはその借地権者を施行前判定対象者とし、土地の利用の共同化に影響しない借地権が設定されている場合(共同化に借地権の譲渡が必要でない場合)には底地権者を施行前判定対象者として、共同化要件の判定を行うとすることが相当と考えます。
結果として、上記Ⅰの「2 照会の事実関係」の場合、地下鉄会社の有する土地Xに対する借地権(区分地上権)は、事業の施行による中高層耐火建築物の建築に影響しない借地権ですから、共同化要件の判定に当たっては、借地権者である地下鉄会社ではなく、底地権者であるAを土地Xに係る施行前判定対象者として、その判定を行うこととなるものと考えているところです。
(注) 上記Ⅰの「2 照会の事実関係」の場合、買換資産は1筆の土地ではなく土地Xと土地YZの2筆になりますが、特に1筆とすることは本特例制度の適用要件とされていませんので、このことが本特例制度の適用に影響を与えることはありません。
Ⅳ 参考(法人税について)
法人税に関しても、本特例制度と同様の措置(旧措法65の7![]() 十二)が講じられていましたが、平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(以下「平成23年6月改正法」といいます。)により、この同様の措置(以下「旧措置」といいます。)が廃止されました。
十二)が講じられていましたが、平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(以下「平成23年6月改正法」といいます。)により、この同様の措置(以下「旧措置」といいます。)が廃止されました。
この旧措置においても、その適用要件に本特例制度における共同化要件と同一の文言による要件(以下「旧措置における共同化要件」といいます。)が定められていたところです(旧措規22の7![]() )。
)。
このため、本件の照会は所得税に係るものではありますが、法人税に係る旧措置における共同化要件についても、所得税と同様に解することとなると考えております。
なお、旧措置については、平成23年6月改正法の施行日(平成23年6月30日)前に法人が行った資産の譲渡に係る法人税に適用があることとされていますので(平成23年6月改正法附則56![]() )、同日前に資産の譲渡を行った法人が今後、法人税の申告を行うケースも考えられることから、念のため旧措置についても付言した次第です。
)、同日前に資産の譲渡を行った法人が今後、法人税の申告を行うケースも考えられることから、念のため旧措置についても付言した次第です。