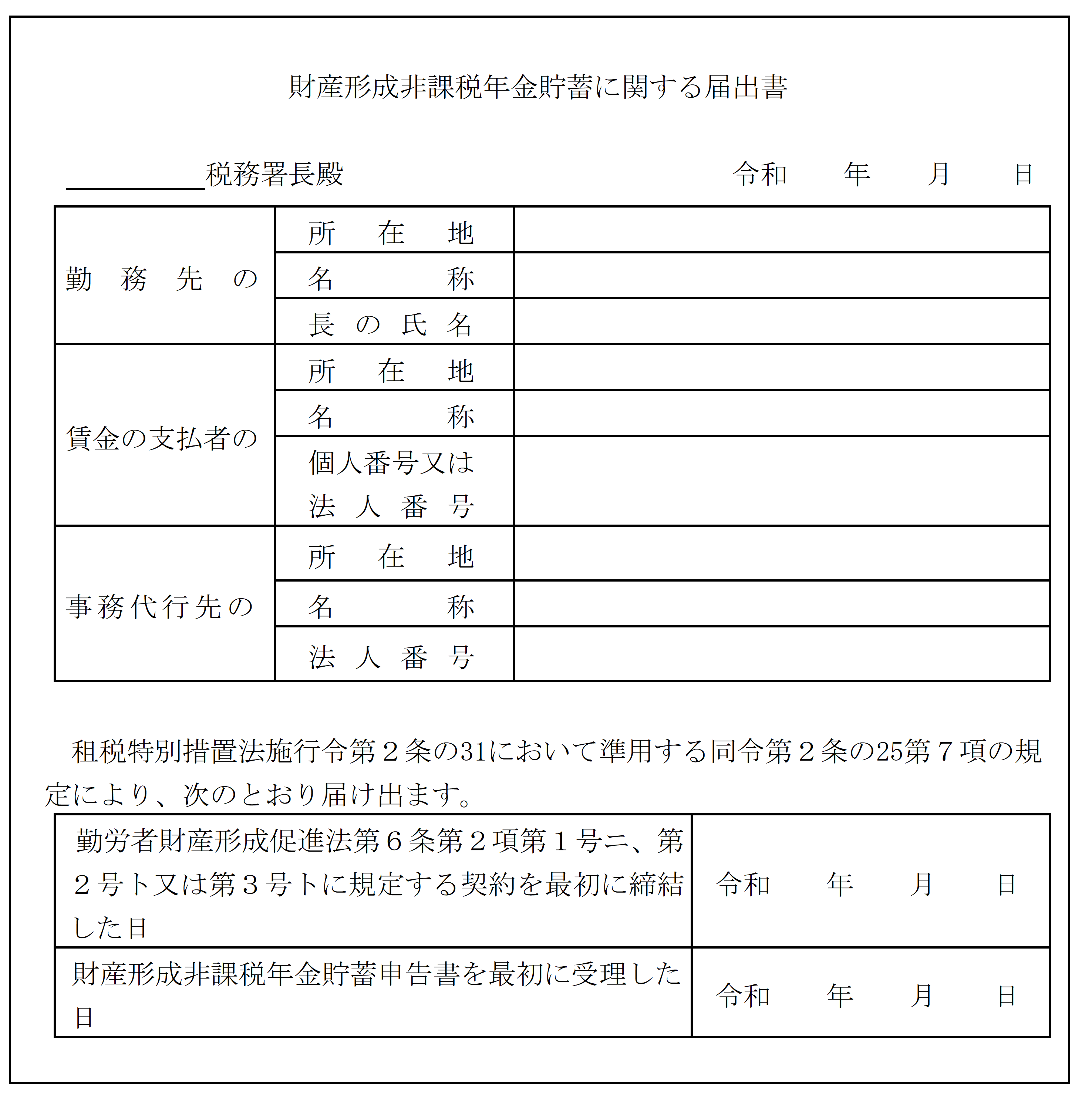第4条の3《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税》関係
(昭63直法6−8、直所3−9)
(用語の意義)
4の3−1 この措置法第4条の3関係において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平3直法6−2、平9課法8−2、課所4−2、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34、平19課法9−18、課個2−29、課審4−42、平27課法10−1、課審5−1、令3課法11-23、課審5-3、令7課法12-7、課審5-13改正)
(1) 財形年金貯蓄申告書 措置法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をいう。
(2) 財形年金貯蓄限度額変更申告書 措置法第4条の3第5項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書をいう。
(3) 財形年金貯蓄異動申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の18第3項《財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書》に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書をいう。
(4) 財形年金貯蓄勤務先異動申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の19第1項《財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書》に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書をいう。
(5) 転職者等の財形年金貯蓄継続適用申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の20第3項《転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書》に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書をいう。
(6) 海外転勤者の財形年金貯蓄継続適用申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の21第1項《海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等》に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書をいう。
(7) 海外転勤者の特別国内勤務申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の21第4項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書をいう。
(8) 育児休業等をする者の財形年金貯蓄継続適用申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の21の2第1項((育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等))に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書をいう。
(9) 育児休業等期間変更申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の21の2第3項に規定する育児休業等期間変更申告書をいう。
(10) 財形年金貯蓄廃止申告書 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の23第1項《財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書》に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。
(11) 財形年金貯蓄の確認申告書 措置法令第2条の32第1項《財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等》に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。
(12) 財形年金貯蓄者の退職等申告書 措置法令第2条の32第2項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書をいう。
(13) 勤労者 財形法第2条第1号《定義》に規定する勤労者をいう。
(14) 財形年金貯蓄契約 財形法第6条第2項《勤労者財産形成貯蓄契約等》に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。
(15) 金融機関の営業所等又は預入等 それぞれ措置法第4条の2第1項《勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税》に規定する金融機関の営業所等又は預入等をいう。
(16) 財形年金貯蓄、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体 それぞれ措置法第4条の3第1項に規定する財産形成年金貯蓄、勤務先、特定賃金支払者又は事務代行団体をいう。
(17) 事務代行先 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の6第1項第1号に規定する事務代行先をいう。
(18) 生命保険契約等又は差益 それぞれ措置法第4条の3第1項第4号に規定する生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約、又は差益をいう。
(19) 利子等 措置法令第2条の27《財産形成年金貯蓄の範囲》に規定する定期預金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権若しくは公社債投資信託以外の公募証券投資信託の受益権に係る利子若しくは収益の分配又は措置法第4条の3第1項第4号に規定する差益をいう。
(20) 積立期間の末日 措置法令第2条の32第5項に規定する積立期間の末日をいう。
(21) 不適格事由 措置法令第2条の31において準用する同令第2条の12第1項《退職等により財産形成年金貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合》に規定する不適格事由をいう。
(22) 個人番号又は法人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項又は第16項((定義))に規定する個人番号又は法人番号をいう。
(財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用)
4の3−2 措置法第4条の3の規定の適用に当たっては、次の表に掲げる項目については、それぞれ次の表の「準用する項」に掲げる措置法第4条の2関係の取扱いに準ずる。(平5課法8−3、課所4−7、平9課法8−2、課所4−2、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平27課法10−1、課審5−1、平28課法10-7、課審5-16、平29課法10-1、課審5-1、令3課法11-23、課審5-3改正)
| 項目 | 準用する項 | |
|---|---|---|
| (1) | 財形年金貯蓄申告書を提出できる勤労者 | 4の2−2 |
| (2) | 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用 | 4の2−4 |
| (3) | 最高限度額の合計額が550万円を超える財形年金貯蓄申告書の効力 | 4の2−5 |
| (4) | 財形年金貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形年金貯蓄申告書の効力 | 4の2−6 |
| (5) | 財形年金貯蓄申告書の効力 | 4の2−7 |
| (6) | 郵便等により財形年金貯蓄申告書等の提出があった場合 | 4の2−8 |
| (7) | 財形年金貯蓄申込書を提出できない場合 | 4の2−9 |
| (8) | 退職に含まれないもの | 4の2−12 |
| (9) | 退職、転任その他の理由に含まれるもの | 4の2−13 |
| (10) | 最後の払込日から2年を経過する日 | 4の2−14 |
| (11) | 海外転勤者の特別国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定 | 4の2−15 |
| (12) | 育児休業等をする者の財形年金貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定 | 4の2−15の2 |
| (13) | 退職等に関する通知の効力 | 4の2−16 |
| (14) | 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い | 4の2−17 |
| (15) | 事務代行団体に財形年金貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合 | 4の2−18の2 |
| (16) | 住所等の変更と財形年金貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続 | 4の2−19 |
| (17) | 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形年金貯蓄の移管が同時に行われた場合の手続 | 4の2−20 |
| (18) | 海外事業所等の意義 | 4の2−22 |
| (19) | 国内払賃金の意義 | 4の2−23 |
| (20) | 国外勤務期間内における限度額の変更等 | 4の2−24 |
| (21) | 国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合 | 4の2−25 |
| (22) | 国内勤務をすることとなった日の意義 | 4の2−26 |
| (23) | 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形年金貯蓄異動申告書の提出 | 4の2−27 |
| (24) | 国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形年金貯蓄異動申告書の提出の省略 | 4の2−28 |
| (25) | 出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合 | 4の2−29 |
| (26) | 海外転勤者の特別国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合(国外勤務期間中に財形年金貯蓄の積立期間の末日が到来した者を除く。) | 4の2−31 |
| (27) | 育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合 | 4の2−31の2 |
| (28) | 育児休業等をする者の財形年金貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合 | 4の2−32 |
| (29) | 転任があった場合の書類の送付 | 4の2−34 |
| (30) | 退職があった場合の書類の写しの送付 | 4の2−35 |
| (31) | そ及課税の対象となる利子等 | 4の2−36 |
| (32) | 転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等 | 4の2−37 |
| (33) | 財形年金貯蓄の払出し等の管理(年金の支払状況等の管理を含む。) | 4の2−38 |
| (34) | 財形年金貯蓄者が死亡した場合 | 4の2−39 |
| (35) | 要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期 | 4の2−41 |
| (36) | 違反の財形年金貯蓄が発見された場合 | 4の2−42 |
| (37) | 居住の用に供している家屋 | 4の2−44 |
| (38) | 医療費の範囲等 | 4の2−45 |
(財形年金養老保険に係る還付金)
4の3−3 財形年金養老保険の簡易生命保険契約に係る還付金は、措置法令第2条の28第1項《財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益》に規定する「解約返戻金」に該当するものとする。
(生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等)
4の3−4 生命保険契約等が失効したことに伴い返戻金又は還付金(以下4の3−12までにおいて「返戻金等」という。)の支払請求が行われた場合には、当該支払請求の行われた日において当該契約等が解約されたものとして、措置法令第2条の28の規定を適用する。(平3直法6−2、直所3−4改正)
4の3−5 削除(平3直法6-2、直所3-4改正、平29課法10-1、課審5-1削除)
(生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分)
4の3−6 財形年金貯蓄契約である生命保険契約等が解約された場合(4の3−4の支払請求が行われた場合を含む。)に支払われる返戻金等(措置法令第2条の28第1項に規定する災害等の事由が生じたことにより、生命保険契約等が解約された場合に支払われるものを除く。)は、一時所得に該当することに留意する。(平29課法10-1、課審5-1改正)
(注) 一時所得の収入すべき時期については、所得税基本通達36−13による。
(財形年金貯蓄の確認申告書の不提出)
4の3−7 財形年金貯蓄申告書を提出して財形年金貯蓄の預入等をしている勤労者が、財形年金貯蓄の確認申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その財形年金貯蓄契約に係る積立期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日(積立期間の末日において次に掲げる申告書を提出している者にあっては、それぞれ次に定める日)後に支払われる利子等については、措置法第4条の3第1項の規定の適用はないことに留意する。(平27課法10−1、課審5−1追加)
(1) 海外転勤者の財形年金貯蓄継続適用申告書 海外転勤者の特別国内勤務申告書を提出する日
(2) 育児休業等をする者の財形年金貯蓄継続適用申告書 その申告書(当該申告書に係る育児休業等期間変更申告書を提出している場合にあっては、当該申告書)に記載された育児休業等の期間の終了の日の翌日
(財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更)
4の3−8 財形年金貯蓄申告書又は財形年金貯蓄限度額変更申告書に記載した最高限度額については、財形年金貯蓄契約において定められている積立期間の末日後であっても、財形年金貯蓄申告書を提出した勤労者が不適格事由に該当することとなる日までは変更できることに留意する。
(財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続 )
4の3−9 財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者につき、その提出後当該申告書に記載した住所又は氏名の変更と当該申告書に係る財形年金貯蓄の措置法令第2条の31において準用する同令第2条の18第2項に規定する移管とが同時に行われた場合において、当該移管に係る財形年金貯蓄異動申告書に住所又は氏名の異動事項を記載し、当該申告書を同項に規定する移管前の営業所等に経由してその者の異動前の住所地の所轄税務署長に提出したときは、措置法令第2条の32第3項の規定による届出書の提出は要しないものとする。
4の3−10 削除(平24課法9−8、課審5-42削除)
4の3−11 削除(平9課法8-2、課所4-2、平19課法9-3、課審4-13改正、平24課法9−8、課審5-42削除)
(差益の収入すべき時期)
4の3−12 財形年金貯蓄契約である生命保険契約等に係る差益の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。
(1) 当該契約等に基づき支払われる年金に係る差益(措置法第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。) 当該契約等において定められている年金の支払日
(2) 当該契約等が解約された場合に支払われる返戻金等に係る差益 当該契約等が解約された日
(3) 当該契約等が失効したことに伴い支払われる返戻金等に係る差益 当該返戻金等の支払請求が行われた日
4の3−13 削除(平9課法8-2、課所4-2改正、平24課法9−8、課審5-42削除)
(財形年金貯蓄申告書の受理届)
4の3−14 勤務先の長が、措置法令第2条の31において準用する同令第2条の25第7項の規定により当該勤務先の所在地の所轄税務署長に提出する同項の届出書の標準的な様式は、次に定める様式とする。(平2直法6−6、直所3−7、平9課法8−2、課所4−2、平10課法8−3、課所4−6、平27課法10−1、課審5−1、令元課法11-7、令3課法11-23、課審5-3改正)