直所3−1
昭和47年1月21日
国税局長 殿
国税庁長官
農業協同組合受託農業経営事業等から生ずる収益に対する所得税の取扱いについて
農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和45年法律第55号)の施行に伴い、農業協同組合が行なう受託農業経営事業(以下「受託経営事業」という。)等から生ずる収益の所得の種類等については、下記により取り扱うこととしたから、通達する。
(理由)
受託経営事業は、「農業協同組合農業経営受託規程例」(別添参照)に基づき、昭和46年分から実施されており、その損益は委託者に帰属することになるので、この取扱いについて統一するためである。
記
1 受託経営事業の場合
(1) 所得の種類
- イ 受託経営事業から生ずる収益は、委託者の事業所得(農業所得)に該当する。
(注) 受託経営事業を行なう場合には、当該農地について農地法第3条第1項の規定による使用収益権が設定されるが、受託者は、その使用収益の対価を支払うことはなく、受託経営事業から生ずる損益は、委託者に帰属するものである。
- ロ 委託者(後記(2)により所得者を判定した場合は、その者。以下この項において同じ。)およびその者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「家族」という。)が、受託経営事業にかかる農耕に従事したことにより、受託者から受ける報酬は、委託者が負担する受託経費のうちの作業費(農業協同組合農業経営受託規程例第14条第2号参照)に相当する部分は、委託者の事業所得に該当するものとし、当該部分をこえる金額は、委託者または家族の給与所得として取り扱うものとする。
(注) この場合において、委託者が受ける報酬からさきに事業所得に該当するものとして計算する。
(2) 所得者の判定
受託経営事業から生ずる収益にかかる所得者は、原則として委託者であるが、所得税基本通達12−3(夫婦間における農業の事業主の判定)および12−4(親子間における農業の事業主の判定)により推定した農業の事業主が委託者と異なる場合には、その推定した事業主を、受託経営事業から生ずる収益にかかる所得者とする。
(注) 受託経営事業の委託者は、原則として、農業協同組合の組合員であり、かつ、当該委託にかかる農地の所有権を有する者である。
(3) 収入金額および必要経費の計算
受託経営事業にかかるその年分の農業所得の計算については、収入金額および必要経費の計算を省略して、受託者がその年の12月
31日 現在で損益の計算(仮決算)をした結果により、委託者に通知された受託経営事業からの配分見込額を、農業所得の収入金額とし、当該委託農地にかかる固定資産税および受託経営事業の用に供された減価償却資産の償却費等を必要経費として計算してもさしつかえない。
(注)
- 受託者から通知された配分見込額は、受託者において当該受託経営事業の損益について、税務計算に従つて計算されるものである。
- 配分見込額と、受託経営事業にかかる精算額との差額はその精算時の年分の収入金額または必要経費として調整されるものである。
2 1以外のいわゆる委託耕作の場合
農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)の規定による農業委員会の許可を受けないで、他人に農地の耕作をさせている場合の、当該農地にかかる所得の種類は、次による。
- (1) 他人に農地を耕作させ、その対価を受ける者(いわゆる委託者)の当該農地から生ずる収益は、原則として事業所得(農業所得)に該当する。
- (2) 他人の農地を耕作している者(いわゆる受託者)の当該農地から生ずる収益(当該農地の受託耕作により委託者から受ける報酬を含む。)は、事業所得(農業所得)に該当する。
○○農業協同組合農業経営受託規程例 (水稲作の場合)
(目的)
第1条 この規程は、○○農業協同組合定款第○○条の規定に基づき、この組合が組合員の委託を受けて行なう農業の経営(以下「受託農業経営」という。)の事業について必要な事項を定め、受託農業経営の事業の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(受託農業経営の種類)
第2条 この組合の受託農業経営の事業は、水稲作について行なうものとする。
(委託者)
第3条 この組合の組合員のほか、次の各号の一に該当する者は、この組合に対し、農業の経営を委託することができる。
一 この組合の組合員と同一の世帯に属する者
二 この組合の地区内に住所を有する者
2 この組合は、組合員、前項各号に掲げる者、この組合に農業の経営を委託した後にこの組合の地区外に住所を移転した者又は農業の経営を委託する際に組合員と同一の世帯に属していた者以外の者については、契約の更新をしないものとする。
3 この組合に農業の経営を委託しようとする者は、当該委託に係る農地の所有権を有する者でなければならない。
(委託の申込み)
第4条 この組合に農業の経営を委託しようとする者は、別に定める様式による農業経営委託申込書を毎年○月○日までにこの組合に提出しなければならない。
(契約の締結)
第5条 この組合は、前条の申込みがあつた場合において、農業経営委託申込書の内容を審査し委託の申込みを相当と認めたときは、別に定める様式による農業経営委託契約書により契約を締結するものとする。
(契約の期間)
第6条 契約の期間は、○年以上であつて契約において定める間とする。
(受託の制限)
第7条 この組合は、委託申込みに係る農地の圃場条件等が機械作業等に適しないと認められる場合においては、農業の経営を受託しないことができる。
(解約の制限)
第8条 この組合及び委託者は、契約の期間中は、解約の申入れをしないものとする。ただし、正当な理由がある場合であつて、この組合及び委託者が合意したときはこの限りではない。
(契約の更新)
第9条 委託者が契約の期間の満了の一年前から三月前までの間にこの組合に対して契約を更新しない旨の通知をしないときは、契約の期間満了時において、従前の契約と同一の条件(期間を含む。)でさらに契約したものとみなす。
(善管注意義務)
第10条 この組合は、受託農業経営を行なうに当たつては、委託契約の本旨に基づき、善良なる管理者の注意をもつて委託者の利益に最も適合するように配慮しなければならない。
(主宰権)
第11条 受託農業経営の運営に関する事項については、農業経営委託契約書に定めるもののほか、この組合が決定する。
(収穫物の所有権)
第12条 受託農業経営の事業により生ずる収穫物の所有権は、組合に帰属するものとする。
(受託農業経営に係る損益の帰属及び損益の委託者ごとの算出方法)
第13条 受託農業経営に係る損益は委託者に帰属するものとし、この組合は受託農業経営に係る損益を次に掲げる算式により計算するものとする。
総販売額(共済金等を含む)
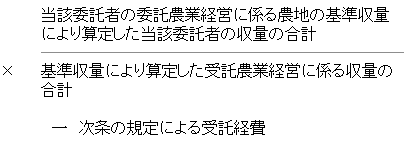
2 前項に規定する基準収量は、受託農業経営に係る農地の自然条件その他の諸条件を勘案して、毎年受託農業経営事業運営協議会の議を経てこの組合が決定する。
(受託経費の計算)
第14条 受託農業経営に係る委託者ごとの受託経費は、次の各号に掲げるところにより算出して得た額の合計額とする。
一 資材費及び共済掛金
この組合の受託農業経営に係る資材費及び共済掛金の総額
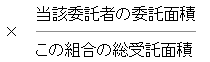
二 作業費
単位面積当たりの別に定める作業費 × 当該委託者の委託面積 × 作業の難易度
三 事務管理費
単位面積当たりの別に定める事務管理費 × 当該委託者の委託面積
四 水利費その他の負担金
委託農地の負担額
五 カントリーエレベーターその他の乾燥調製施設の利用料及び販売経費
総利用料及び販売経費
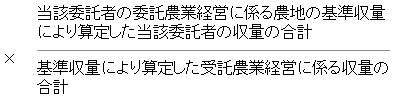
2 受託農業経営の運営に伴い臨時の必要費が生じたときは、委託者とこの組合が協議して決定する。
(損害賠償)
第15条 この組合は、異常気象、水害その他の災害による受託農業経営の収量の減少、受託農業経営の事業の用に供した農地等の損壊、滅失等この組合の故意又は過失によらない損害についての責を負わないものとする。
(運営協議会)
第16条 この組合は、受託農業経営の事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、委託者、農業改良普及所、市町村、農業委員会、土地改良区等からなる受託農業経営事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会においては、受託農業経営の事業の運営に関する基本方針、受託の条件、受託の経費その他受託農業経営の事業の運営に関する重要事項について、毎年協議するものとする。
(作業委託)
第17条 この組合は、受託農業経営の事業を効率的に行なうために必要があると認めるときは、受託農業経営に係る一部の作業を農業者等に委託することができる。
(経理の区分)
第18条 この組合は、受託農業経営の事業と他の事業を区分して経理するものとする。
2 この組合は、委託者又はその一般承継人から請求があつたときは、経理の内容を明らかにした書類を閲覧させ、又はこれらの書類につき説明を行なうものとする。
(受託農業経営の事業の運営に必要な事項の委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、受託農業経営の事業の運営上必要な事項については、この組合が別に定めるところによる。
附則
この規程は、 年 月 日から施行する。