附則
(施行期日)
1 法人税基本通達(以下「基本通達」という。)は、昭和44年7月1日から施行する。
(適用時期の原則)
2 基本通達は、別段の定めのあるものを除き、基本通達の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する法人税について適用する。
(適用時期の特例-1)
3 基本通達のうち、次に掲げる事項の適用については、それぞれ次による。
- (1) 2-3-1(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)は、施行日以後の建設工事等につき新たにその用に供する仮設材料について適用し、同日前に建設工事等の用に供されている仮設材料については、なお従前の例による。
- (2) 4-3-1及び4-3-2(広告宣伝用資産の受贈益等)は、施行日以後に取得する広告宣伝用資産について適用し、同日前に取得した広告宣伝用資産については、なお従前の例による。
- (3) 8-1-2、8-2-3及び8-2-4(共同的施設の設置又は改良のために支出する費用等)は、施行日以後に設置される施設等につき同日以後に支出する負担金について適用し、同日前の設置に係る施設等につき支出する負担金については、なお従前の例による。
- (4) 10-7-7(特定出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)の割増償却の適用に関する部分は、施行日以後の特定出資に係る新築貸家住宅の割増償却等について適用し、同日前の特定出資に係る新築貸家住宅の割増償却等については、なお従前の例による。
- (5) 11-5-21(退職年金を支給する場合の取崩しの方法)は、施行日以後の退職に係る退職給与引当金勘定の金額の取崩しについて適用し、同日前の退職に係る退職給与引当金勘定の金額の取崩しについては、なお従前の例による。
(適用時期の特例-2)
4 7-1-2(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)並びに15-2-4、15-2-8、15-2-15及び15-2-16(金銭貸付業の範囲等)は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(適用時期の特例-3)
5 11-3-2(売掛金の範囲)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の法人税については、なお従前の例による。
(無形減価償却資産としていたノーハウに関する経過的取扱い)
6 ノーハウの設定契約をするために要した費用で特許権に準じて取り扱っていたものは、施行日以後に終了する事業年度においては、8-1-4(令第14条第1項第9号ハに規定する繰延資産)に定める繰延資産に該当するものとし、8-2-3(繰延資産の償却期間)に定める償却期間により償却するものとする。
(金融機関における貸倒引当金の対象となる貸金の額の計算に関する経過的取扱い)
7 削除(昭和49年10月1日以後終了する事業年度から適用)(昭49年直法2-71「29」により改正)
改正法人税法(昭和45年4月改正)等の施行に伴う法人税の取扱いについて
直審(法)58(例規)
昭和45年7月16日
法人税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第37号)及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第106号)の施行に伴い、法人税基本通達(昭和44年5月1日付直審(法)25)の一部を改正するとともに、その経過的取扱いを下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、法人税基本通達の改正部分は、法人の昭和45年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用する。
記
第1 法人税基本通達の改正 (略)
第2 経過的取扱い
(少額の減価償却資産の基準引上げの適用)
8 令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の少額の減価償却資産の基準の引上げは、昭和45年4月1日前に開始した事業年度に取得し、同日以後開始する事業年度に事業の用に供した減価償却資産についても適用があることに留意する。
(減価償却資産に計上しているものの一時償却)
9 昭和45年4月1日前に開始した事業年度において事業の用に供した減価償却資産で資産として計上しているものについては、その取得価額が5万円未満であっても、昭和45年4月1日以後開始する事業年度においてその帳簿価額の全部を一時に償却することはできないことに留意する。
法人税基本通達の一部改正について
直審(法)20(例規)
昭和46年6月15日
法人税基本通達(昭和44年5月1日付直審(法)25)の一部を下記のとおり改正したから、通達する。
(趣旨) 法人税基本通達制定後、通達事項に疑義があったため個別通達により解釈の統一を図って処理してきたもの等を法人税基本通達として整理するものである。
記
(略)
改正法人税法(昭和46年3月改正)等の施行に伴う法人税基本通達の一部改正について
直審(法)21(例規)
昭和46年6月15日
法人税法の一部を改正する法律(昭和46年法律第19号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第71号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和46年大蔵省令第16号)の施行に伴い、法人税基本通達(昭和44年5月1日付直審(法)25)の一部を下記のとおり改正し、法人の昭和46年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用することとしたから、通達する。
記
(略)
昭和48年法人税関係法令の改正等に伴う法人税(土地譲渡重課関係を除く。)の取扱いについて
直法2-81(例規)
昭和48年9月10日
標題のことについて、下記のとおり定めたから、通達する
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される法人税について、その他の部分については今後処理する法人税について、適用する。
- 法人税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第15号)
- 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第93号)
- 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第31号)
- 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第94号)
- 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第25号)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和48年大蔵省令第32号)32号)
記
第1 法人税基本通達の改正 (略)
第2 経過的取扱い等
(経過的取扱い………償却方法の変更の承認)
27 法人が、昭和48年3月31日現在において2以上の船舶を有する場合において、改正後の法人税法施行令第51条第1項(償却方法の変更)の規定により船舶ごとに償却の方法を選定するため、昭和49年3月31日までに、同令第52条第2項(償却方法の変更承認申請書の提出)の規定により船舶について償却方法の変更承認申請書の提出をしたときは、これを承認するものとする。
昭和49年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税(租税特別措置法関係を除く。)の取扱いについて
直法2-71(例規)
昭和49年9月30日
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については、別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。
- 法人税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第16号)
- 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第42号及び第77号)
- 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和49年大蔵省令第8号及び第26号)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和49年大蔵省令第35号)
記
第1 法人税基本通達の改正
一〜十四 (略)
十五 経過的取扱い
(旧少額減価償却資産の範囲)
30 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第77号。以下「昭和49年改正政令」という。)附則第7条に規定する旧少額減価償却資産(以下「旧少額減価償却資産」という。)には、昭和49年改正政令による改正前の法人税法施行令第133条に規定するその内国法人の業務の性質上基本的に重要なもので昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日において帳簿価額のあるものを含むことに留意する。
(圧縮記帳をした減価償却資産等の取得価額の判定)
31 圧縮記帳の適用を受けた資産又は特定現物出資により受け入れた資産につき昭和49年改正政令附則第7条の規定を適用する場合において、その取得価額が5万円未満であるかどうかの判定については、その圧縮記帳後の金額又は受入価額による。
(帳簿価額が5万円以上のものの令附則第7条の不適用)
32 事業の用に供した日における取得価額が5万円未満である減価償却資産であっても、その後における資本的支出等により昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額が5万円以上となっているものについては、昭和49年改正政令附則第7条の適用はないものとする。
(旧少額減価償却資産の損金算入額の原価性)
33 旧少額減価償却資産でその償却費の額を製造原価に算入すべきものとされていたものにつき、昭和49年改正政令附則第7条の規定により損金の額に算入した金額がある場合には、当該金額についても製造原価に算入することに留意する。
(旧少額減価償却資産に係る償却超過額の損金算入)
34 旧少額減価償却資産につき、昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度に繰り越された償却超過額がある場合において、その償却超過額の全部又は一部を当該最初に開始する事業年度開始の日以後3年以内の日を含む各事業年度において申告調整により損金の額に算入したときは、その損金算入額を当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入するものとする。
(取得価額5万円以上の少額の減価償却資産等の減価償却)
35 昭和49年4月1日前に開始した各事業年度において事業の用に供した減価償却資産で取得価額が5万円以上10万円未満のものについては、昭和49年4月1日以後開始する各事業年度においても通常の減価償却の方法により償却することに留意する。
旧少額減価償却資産で昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後3年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度開始の日において帳簿価額があるものに係る当該翌事業年度以後の各事業年度における償却についても、同様とする。
第2 耐用年数の適用等に関する取扱通達の改正 (略)
第3 個別通達の改廃
41 次に掲げる通達は、廃止とする。
- (1) 昭和43年6月29日付直法4-47ほか1課共同「旅館業における少額重要資産の具体的区分について」
- (2) 昭和44年2月19日付直法4-5ほか1課共同「土木建築業における少額重要資産に該当する仮設資材の取扱いについて」
- (3) 昭和44年8月14日付直法4-28「パン製造業及び菓子製造業におけるパン箱及び通箱の取扱いについて」
42 昭和48年3月16日付直法2-16、査調4-5「資本的支出と修繕費の区分等にかかる法人税の取扱いについて」通達の第1の2中「5万円」を「10万円」に改め、昭和49年4月1日以後開始する事業年度から適用する。
昭和50年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税の取扱いについて
直法2-21(例規)
昭和50年10月6日
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。
- 法人税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第14号)
- 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第58号及び第188号)
- 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第9号及び第25号)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第12号)
- 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)
- 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号及び第33号)
おって、法人税基本通達(昭和44年直審(法)25)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年直法4-25)中、昭和49年1月4日付官総1-1「「公用文の書き方」の全部改正について」通達に定める用字、用語等に抵触するものについては、当該通達に定める用字、用語等に改める。
記
第1 法人税基本通達関係
一〜三 (略)
四 割戻し
4 2-5-3中(1)を次のように改め、この通達の日付の日以後の割戻しについて適用する。
五〜十一 (略)
十二 信用取引等による株式の取得価額
18 第6章に、次の1節を加え、6-4-3については、昭和50年4月1日以後終了する事業年度から適用する。
十三〜二十二 (略)
二十三 外貨建債権債務の換算等
33 第13章の次に、次の1章を加え、13の2-2-9については、この通達の日付の日以後終了する事業年度から適用する。
二十四〜二十七 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 既往通達の改廃
次に掲げる通達は、廃止する。
- 1 昭和46年10月21日付直法2-13(例規) 「外国為替相場の変動幅制限停止に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」
- 2 昭和47年3月10日付直法2-14(例規) 「基準外国為替相場の変更に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」
- 3 昭和47年10月25日付直法2-48(例規) 「現行の基準外国為替相場制のもとにおける外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」
- 4 昭和50年4月25日付直法2-9(例規) 「商法の一部を改正する法律の施行等に伴う法人税の取扱いについて」
昭和51年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税の取扱いについて
直法2-39(例規)
昭和51年10月14日
標題のことについて下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。
- 1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第53号)
- 2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年大蔵省令第8号)
- 3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)
- 4 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第54号)
- 5 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年大蔵省令第9号)
記
第1 法人税基本通達関係
一〜三 (略)
四 償却費の計算
4 8-3-2を次のように改め、この通達の日付の日以後支払の確定するものについて適用する。
五〜十 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
昭和52年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税の取扱いについて
直法2-33(例規)
昭和52年10月31日
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。
- 1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第53号)
- 2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第8号)
- 3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第9号)
- 4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号)
- 5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第54号)
- 6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第10号)
記
第1 法人税基本通達関係
一〜十二 (略)
十三 外貨建債権債務の換算
19 13の2-1-1中「法人が発行する外貨建社債」を「法人が発行する外貨建社債(転換期間満了前の転換社債を除く。)」に改め、この通達の日付の日以後終了する事業年度から適用する。
十四〜十五 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
昭和53年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税の取扱いについて
直法2-24(例規)
昭和53年10月31日
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については今後処理する法人税について適用する。
- 1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第78号)
- 2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第16号)
- 3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第37号)
- 4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)
- 5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)
- 6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第18号)
記
第1 法人税基本通達関係 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 その他
-
1 昭和41年8月30日付直法4-23ほか2課共同「減価償却資産に関する諸申請書および届出書ならびに特別修繕費の額等の認定に関する申請書の様式の改正および制定について」通達の一部を、次のように改正する。
- (1) 目次中「様式14開発研究用減価償却資産の耐用年数の適用の届出書」及び「様式15租税特別措置法第44条による開発研究機械等の特別償却の適用を受けるための明細書」を削り、「様式16」を「様式14」に、「様式17」を「様式15」に改める。
- (2) 様式14及び様式15を削る。
- (3) 様式16中「国税局長」を「税務署長」に改め、同記載の方法の二中「を経由して国税局長」を削り、様式16を様式14に改める。
- 2 昭和45年7月27日付直法2-7ほか3課共同「法人税に関する申請書等の様式の一部改正について」通達の様式8中「国税局長」を「税務署長」に改め、同記載要領の2中「を経由して所轄国税局長」を削る。
- 3 昭和50年7月15日付直法2-18「外貨建債権債務の換算制度に関する申請書等の様式の制定について」通達の様式2中「国税局長」を「税務署長」に改め、同記載要領の2中「を経由して所轄国税局長」を削る。
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-31(例規)
昭和54年10月18日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これらによられたい。
なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分のうち別に定めるものの適用時期については別に定めるところによる。
- 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第70号)
- 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第15号)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第16号)
- 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
- 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
おって、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十 (略)
十一 (経過的取扱い………外貨建債権債務の換算及び外貨建取引に係る会計処理等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の13の2-1-3、13の2-1-4、13の2-1-6の2、13の2-2-1、13の2-2-1の2、13の2-2-5及び13の2-2-8により法人がその経理基準を変更する必要が生ずる場合には、当該法人の昭和54年10月1日以後最初に開始する事業年度の法人税からこれらの取扱いを適用することができる。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-8(例規)
昭和55年5月15日
標題のことについては、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三十八 (略)
三十九(経過的取扱い……商品引換券等の発行に係る収益の帰属時期に関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の2-1-33及び2-2-11の取扱いは、法人の昭和55年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「通達適用初年度」という。)の法人税から適用する。この場合において、通達適用初年度開始の時において未引換券2-2-11に定める未引換券をいう。)があるときにおける当該未引換券に係る対価の額等の処理についてはおおむね次に定めるところによる。
- (1) 当該未引換券に係る対価の額の全部又は一部が通達適用初年度の直前事業年度終了の時までに益金の額に算入されていない場合 次の区分に応じそれぞれ次による。
- イ 通達適用初年度以後の各事業年度における商品引換券等の収益の計上方法につき2-1-33の本文によるとき 当該未引換券に係る対価の額で益金の額に算入されていないものの合計額(以下「繰越未計上額」という。)のうち通達適用初年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額が当該各事業年度において回収された商品引換券等に係る対価の額の合計額を超える場合のその超える部分の金額に相当する部分の金額を通達適用初年度の益金の額に算入するとともに、当該繰越未計上額のうち当該益金の額に算入される金額以外の金額については、通達適用初年度開始の日以後4年以内に開始する各事業年度(以下「経過措置適用年度」という。)において均等額以上の金額を益金の額に算入する。
- ロ 通達適用初年度以後の各事業年度における商品引換券等の収益の計上方法につき2-1-33のただし書によるとき 繰越未計上額のうち通達適用初年度開始の日前3年以内に開始した事業年度前の各事業年度において発行した商品引換券等に係るものについては、通達適用初年度の益金の額に算入する。
- (2) (1)以外の場合 通達適用初年度の直前事業年度において当該未引換券に係る費用の額として損金の額に算入した金額のうち当該直前事業年度において2-2-11を適用するとした場合に損金の額に算入される金額を超える部分の金額は、経過措置適用年度において均等額以上の金額を益金の額に算入する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 既往通達の改廃
次に掲げる通達は、廃止する。
| 1 | 昭和42年9月30日付 |
査調4-9(例規) 直法1-278 直審(法)82 |
「特定の期間損益事項にかかる法人税の取扱いについて」 |
| 2 | 昭和48年3月16日付 |
直法2-16(例規) 査調4-5 |
「資本的支出と修繕費の区分等にかかる法人税の取扱いについて」 |
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-15(例規)
昭和55年12月25日
〔本文〕(略・昭和55年5月15日付 直法2-8の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三十八 (略)
三十九 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)……棚卸資産の評価に関する改正通達の適用時期)
法人税基本通達第5章のうち次に掲げる事項の適用については、次による。
- (1) この通達による改正後の5-2-8の2、5-2-13のただし書及び5-2-14の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後開始する事業年度の法人税について適用する。
- (2) この通達による改正後の5-3-9の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後終了する事業年度の法人税について適用する。
(経過的取扱い(2)……有価証券の評価に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の6-3-5の後段の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後終了する事業年度の法人税について適用する。
(経過的取扱い(3)……生命保険の保険料に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の9-3-4及び9-3-6の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後開始する事業年度において支払う保険料の額について適用するものとし、同日前に開始した各事業年度において支払った保険料の額については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(4)……事業税の損金算入に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の9-5-1のうち事業税の損金算入の時期に関する部分の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後開始する事業年度の法人税について適用する。
(経過的取扱い(5)……債権償却特別勘定の設定等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の9-6-4、9-6-5及び9-6-7の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後終了する事業年度の法人税について適用する。
(経過的取扱い(6)……特別修繕引当金の繰入れに関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の11-6-4の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後開始する事業年度の法人税について適用する。この場合において、当該事業年度に係る令第112条第1項第1号ロ《特別修繕引当金の繰入れの基礎となる期間》に規定する期間のうちに長期にわたる稼動休止期間があり、かつ、当該稼動休止期間の属する各事業年度において、当該稼動休止期間につき特別修繕引当金勘定への繰入れを行っていたときは、その繰入れに係る稼動休止期間については11-6-4の(注)の取扱いの適用はないものとする。
(経過的取扱い(7)……製品保証等引当金の繰入れに関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の11-7-9、11-7-10の2及び11-7-14の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後終了する事業年度の法人税について適用する。ただし、同日前に終了した各事業年度において行った延払条件付請負又は延払条件付譲渡に係る収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法により経理している法人が、この通達による改正前の11-7-14の取扱いにより、その目的物の引渡しをした日の属する事業年度においてその請負又は譲渡に係る収益の額の全部を対象として法第56条の2第1項《製品保証等引当金》の規定の適用を受けた場合における当該延払条件付請負又は延払条件付譲渡については、この通達による改正後の11-7-14の取扱いは適用しない。
(経過的取扱い(8)……借地権の設定等に伴う所得の計算に関する改正通達の適用時期等)
法人税基本通達第13章のうち次に掲げる事項の適用については、次による。
- (1) この通達による改正後の13-1-7の取扱いは、法人が、この通達の日付の日以後に借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合の法人税について適用するものとし、同日前に行った借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合の法人税については、なお従前の例による。ただし、法人が、同日前に行った借地権の設定等(既に13-1-3により権利金の認定課税が行われたものを除く。)により他人に土地を使用させている場合において、これにつき同日以後13-1-7の取扱いの適用を受けることとして遅滞なく13-1-7に定める届出をしたときは、これを認める。
- (2) 法人が、この通達の日付の日前に行った借地権の設定等により他人に土地を使用させている場合において、これにつき令第137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》に規定する相当の地代を収受しているときは、同日以後遅滞なくこの通達による改正後の13-1-8に定める届出をするよう指導するものとする。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 その他の通達関係
| 昭和46年10月18日付 | 査調4-2 直法2-12 |
「特別分担金にかかる協会等の調査、指導等について」通達のうち4(特別分担金の範囲等)の部分を削除する。 |
第4 既往通達の改廃
昭和53年5月10日付直法2-12「外貨建公社債につき評価損の計上ができる事実について」通達は、廃止する。
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-16(例規)
昭和56年11月20日
〔本文〕(略・昭和55年5月15日付直法2-8の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-11(例規)
昭和57年12月24日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
おって、法人税基本通達(昭和44年直審(法)25)、租税特別措置法関係通達(法人税編)(昭和50年直法2-2)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年直法4-25)の全文を、昭和49年1月4日付官総1-1「「公用文の書き方」の全部改正について」通達の別冊「公用文の書き方」(昭和56年12月18日付官総1-63による改正後のもの)に基づいた用字、用語等に改める。
(注) 太字を付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-3(例規)
昭和58年6月3日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十 (略)
十一 経過的取扱い
(経過的取扱い……販売費、一般管理費等の配賦方法に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の16-3-10から16-3-15まで又は20-3-5により法人が販売費、一般管理費その他の費用の額又は損失の額の国外業務又は国内業務への配分方法を変更する必要が生ずる場合には、当該法人の昭和58年4月1日以後に開始する各事業年度の法人税についてこれらの取扱いを適用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-11(例規)
昭和58年12月12日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-3(例規)
昭和59年12月17日
〔本文〕(略・昭和58年12月12日付直法2-11の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-11(例規)
昭和60年12月9日
〔本文〕(略・昭和58年12月12日付直法2-11の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-12(例規)
昭和61年12月22日
〔本文〕(略・昭和58年12月12日付直法2-11の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-1(例規)
昭和63年1月21日
〔本文〕(略・昭和58年12月12日付直法2-11の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-14(例規)
昭和63年11月18日
〔本文〕(略・昭和58年12月12日付直法2-11の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-7(例規)
平成元年8月28日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその新設した通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い金額基準等を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注)
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)の目次については、本通達において改正を行った第2章及び第8章から第13章までを掲げた。
- 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜七 (略)
八 経過的取扱い
(経過的取扱い……広告宣伝用資産等の受贈益等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の4-3-1、7-1-1、7-5-1、7-7-9、7-8-3、7-8-4及び7-9-5の取扱いは、この通達の日付の日以後に取得等をする資産又は支出する費用について適用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-1(例規)
平成2年1月23日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十五 (略)
十六 経過的取扱い
(経過的取扱い……旧法の適用を受けた外国法人税の額が減額された場合における納付控除対象外国法人税額からの控除等)
所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第2条《法人税法の一部改正》の規定による改正前の法第69条第1項から第3項まで《外国税額の控除》の規定の適用を受けた同条第5項に規定する外国法人税の額が平成元年4月1日以後に開始する事業年度(以下「改正事業年度」という。)以後の各事業年度において減額された場合には、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第2条《法人税法施行令の一部改正》の規定による改正前の令第150条第1項又は第3項《外国法人税の額が減額された場合における納付外国税額からの控除》に規定する減額されることとなった部分の金額又は減額があったものとみなされる部分の金額については、当該金額の全額が令第150条第1項又は第150条の2第1項《外国法人税の額が減額された場合における納付控除対象外国法人税額からの控除》に規定する減額控除対象外国法人税額であるものとして、令第150条又は第150条の2《外国法人税が減額された場合の特例》の規定を適用する。
(注)
- 改正前の法第69条第1項《外国税額の控除》の規定の適用を受けた外国法人税の額が改正事業年度以後の各事業年度において増額された場合には、当該増額された部分の金額については、当該金額の全額が法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額であるものとして、同項の規定を適用する。
- 改正前の法第69条第4項《外国税額の間接控除》の規定の適用を受けた外国法人税の額が改正事業年度以後の各事業年度において増額された場合には、改正前の令第147条第1項《納付する外国法人税の額とみなされる金額》の規定により納付する外国法人税の額とみなされる金額については、当該金額の全額が法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額であるものとして、令第149条《2以上の外国法人税が課された場合の特例》の規定を適用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
直法2-6(例規)
平成2年11月29日
〔本文〕(略・平成2年1月23日付直法2-1の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十一 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-4(例規)
平成3年12月25日
〔本文〕(略・平成2年1月23日付直法2-1の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十六 (略)
十七 経過的取扱
(経過的取扱い(1)……改正前の法人税法施行令の規定の適用がある場合)
改正法令(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第87号)をいう。)による改正前の令(改正法令の附則により適用される改正前の令を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の法人税基本通達の取扱いの例による。
(経過的取扱い(2)……現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の10-7-1の注書き及び10-7-6の取扱いは、平成4年1月1日以後に行う金銭以外の資産(土地又は土地の上に存する権利を含む場合に限る。)の譲渡について適用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 その他の通達関係
平成元年3月30日付直法2-2「法人税の借地権課税における相当の地代の取扱いについて」通達中、「相続税財産評価に関する基本通達」を「財産評価基本通達」に改める。
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-1(例規)
平成5年3月15日
〔本文〕(略・平成2年1月23日付直法2-1の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十一 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-1(例規)
平成6年3月16日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十一 (略)
十二 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)……改正前の法人税法施行令の規定の適用がある場合)
改正法令(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第86号)及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号)をいう。)による改正前の令(改正法令の附則により適用される改正前の令を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の法人税基本通達の取扱いの例による。
(経過的取扱い(2)……新たに有価証券とされた証券又は証書の評価方法の届出)
法人の平成5年4月1日において有する令第11条第2号《有価証券に準ずるものの範囲》に掲げる証券又は証書については、同日において取得したものとみなして、令第35条第2項《有価証券の評価の方法の選定》の規定が適用されるのであるから、その評価の方法の届出は同日の属する事業年度に係る法第74条第1項《確定申告》の規定による申告書の提出期限(法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定によりその提出期限が延長されている場合には、その延長された期限)までに行うことに留意する。
(経過的取扱い(3)……施行日前に先物外国為替契約等を締結している場合の取扱い)
施行日(平成5年4月1日をいう。以下同じ。)前に取得又は発生をした令第139条の8第1項《先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例》に規定する外貨建債権及び外貨建債務(以下「長期外貨建債権債務」という。)に係る同日前に締結された同項に規定する先物外国為替契約等(以下「先物外国為替契約等」という。)の履行の日につき施行日以後に繰延べがあった場合(履行の日の繰延べに伴い当該長期外貨建債権債務の円換算額に変更があった場合を含む。)には、当該長期外貨建債権債務につき同条の規定の適用はないものとする。
(注) 同条の規定は、法人が施行日以後に締結する先物外国為替契約等により円換算額が確定する長期外貨建債権債務について適用されるのであるから、同日前に締結された先物外国為替契約等により長期外貨建債権債務の円換算額が確定する場合には、同条の規定の適用がないことに留意する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 その他の通達関係
昭和56年4月6日付直法2-2「借地権の設定等に係る届出書等の様式について」通達中、「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和_年_月_日」を「平成_年_月_日」に、「昭和_年_月〜昭和_年_月」を「平成_年_月〜平成_年_月」に、![]() に、「相続税評価額」を「財産評価額」に改め、昭和56年5月28日付直法2-5「債権償却特別勘定への繰入額の認定申請書等の様式について」通達中、「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和××年以降債務超過」を「平成××年以降債務超過」に、「昭和××年×月××日更生手続の開始の申立て」を「平成××年×月××日更生手続の開始の申立て」に改め、平成元年3月1日付直法2-1「消費税法の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達中、「令第139条の9第5項」を「令第139条の10第5項」に、「令第139条の9の」を「同条の」に、「令第139条の9第1項」を「令第139条の10第1項」に改める。
に、「相続税評価額」を「財産評価額」に改め、昭和56年5月28日付直法2-5「債権償却特別勘定への繰入額の認定申請書等の様式について」通達中、「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和××年以降債務超過」を「平成××年以降債務超過」に、「昭和××年×月××日更生手続の開始の申立て」を「平成××年×月××日更生手続の開始の申立て」に改め、平成元年3月1日付直法2-1「消費税法の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達中、「令第139条の9第5項」を「令第139条の10第5項」に、「令第139条の9の」を「同条の」に、「令第139条の9第1項」を「令第139条の10第1項」に改める。
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-5(例規)
平成6年12月19日
〔本文〕(略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-7(例規)
平成7年12月8日
〔本文〕(略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十一 (略)
十二 経過的取扱い
(経過的取扱い……有価証券の評価に関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の通達のうち次に掲げる事項の適用については、次による。
-
(1) この通達による改正後の6-3-3の取扱いは、この通達の日付の日以後に提出する「有価証券の評価方法の届出書」又は「有価証券の評価方法の変更承認申請書」に基づく有価証券の評価について適用する。
(注) 法人が、この通達の日付の日に現に有する有価証券のうち、改正後の6-3-3により新たな種類の有価証券として区分するものについては、同日の属する事業年度において新たに取得したものとみなして「有価証券の評価方法の届出書」を提出することができる。
- (2) この通達による改正後の6-3-3の3、7-8-2、7-8-5、7-8-6、9-4-6の2、9-4-6の3、9-4-6-の4、9-7-15の4及び16-2-8の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後に終了する事業年度から適用する
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係 (略)
法人税基本通達の一部改正について
課法2-6(例規)
平成8年9月30日
〔本文〕(略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達の一部改正について
課法2-7(例規)
平成8年12月26日
〔本文〕(略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-6(例規)
平成10年6月1日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
(注) 太字を付した箇所が改正した箇所である。
(趣旨)
法人が子会社等の整理や再建に伴って当該子会社等に対して行う債権放棄等の利益供与が寄附金に該当しない旨の現行の取扱いにつき一層の明確化を図ることとしたものである。
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について
課法2-7(例規)
平成10年6月23日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜二十五(略)
二十六 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)……改正前の法人税法等の適用がある場合)
改正法令(法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第105号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第45号)をいう。)による改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、第21章の取扱いがあるものを除き、この通達の改正前の法人税基本通達の取扱いの例による。
(経過的取扱い(2)……送金が許可されない利子、配当等の帰属時期の特例に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の2-1-31の取扱いは、平成10年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3)……旧債権償却特別勘定に関する適用時期)
平成10年4月1日前に開始した事業年度分の法人税については、この通達による改正前の9-6-4から9-6-11までの取扱いの適用があるものとする。
(経過的取扱い(4)……9-6-4(3)による債権償却特別勘定を取崩した場合の損金算入の特例)
法人が、平成10年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において債権償却特別勘定の金額を有している場合には、当該最初に開始する事業年度においてその全額を取り崩して益金の額に算入するのであるが、当該債権償却特別勘定の金額のうちにこの通達による改正前の9-6-4(3)によるものがある場合において、当該金額(この通達による改正前の9-6-10(1)から(3)に該当する金額及び法第52条第1項第1号《貸倒引当金》に掲げる金額の計算の基礎となったものを除く。)に相当する金額を当該最初に開始する事業年度の損金の額に算入したときはこれを認める。
この場合において、当該損金の額に算入した金額の明細を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならないものとする。
(経過的取扱い(5)……現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の10-7-1及び20-3-15の取扱いは、平成10年4月1日以後に行う金銭以外の資産の譲渡について適用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
第4 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係 (略)
第5 既往通達の廃止
次に掲げる通達を廃止する。
- 昭和56年5月28日付直法2-5「債権償却特別勘定への繰入額の認定申請書等の様式について」
- 昭和63年3月1日付直法2-4「外国の公的債権に対する債権償却特別勘定の設定について」
法人税基本通達の一部改正等について
課法2-15(例規)
平成10年12月3日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」を別紙のとおり改めるとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
- 昭和53年7月20日付直法2-19他1課共同「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」
- 昭和63年3月30日付直法2-7他2課共同「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」
- 昭和63年4月26日付直法2-8他2課共同「「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」通達の運用について」
- 平成4年9月18日付課法2-4他1課共同「認定による債権償却特別勘定の設定に関する運用上の留意点について」
別紙 (略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
平成10年12月22日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係 (略)
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 「共有持分を有する法人が共有持分の追加取得をした場合の耐用年数の適用について」通達関係
昭和54年5月7日付直法2-17「共有持分を有する法人が共有持分の追加取得をした場合の耐用年数の適用について」通達のうち「改正前」欄に掲げるものを「改正後」欄のように改める。〔編注「改正後」の算式のみを掲載した。〕
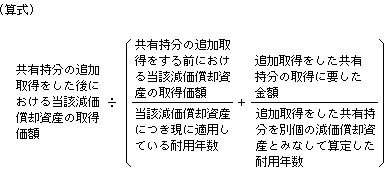
(注)
- 算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切捨て、その年数が2年に満たない場合には、2年とする。
- 算式の適用上、追加取得をした共有持分について耐用年数を算定する場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項第2号《中古資産の耐用年数の簡便法》の規定を準用することができる。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-9
平成11年12月1日
〔本文〕(略・平成10年12月22日付課法2-17の本文に同じ。)
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜二十六 (略)
二十七 経過的取扱い
(経過的取扱い……有価証券の評価に関する改正通達の適用時期等)
この通達による改正後の通達の適用に関し、次に掲げる事項については次による。
-
(1) この通達による改正後の6-3-3の取扱いは、この通達の日付の日以後に提出する「有価証券の評価方法の届出書」又は「有価証券の評価方法の変更承認申請書」に基づく有価証券の評価について適用する。
(注) 法人が、この通達の日付の日に現に有する有価証券のうち、改正後の6-3-3により新たな種類の有価証券として区分するものについては、同日の属する事業年度において新たに取得したものとみなして「有価証券の評価方法の届出書」を提出することができる。
- (2) 法人が、内航海運組合法の規定により平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得したいわゆる建造引当権については、この通達による改正前の7-1-5の取扱いの例による。
- (3) この通達による改正後の13-1-11の取扱いは、平成11年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-7
平成12年6月28日
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
おって、平成10年10月30日付課法2-11「金融商品に関する法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)は、廃止する。
別紙
一〜二十五 (略)
二十六 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…金融商品会計等に関する改正通達の適用時期)
この通達による改正後の取扱いは、法人税法の一部を改正する法律(平成12年法律第14号。以下「改正法」という。)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第145号。以下「改正政令」という。)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成12年大蔵省令第29号。以下「改正規則」という。)において特に定められているもの又は次に掲げる経過的取扱いを除き、平成12年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)…附則適用年度後の譲渡損益の計上時期)
改正法附則第3条第2項《有価証券の譲渡損益の計上時期に関する経過措置》の適用を受けた最後の事業年度の翌事業年度における有価証券の譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額の計上に当たっては、同条第1項本文の規定を準用する。
(経過的取扱い(3)…ローン・パーティシペーション及びデット・アサンプションの取扱い)
平成11年1月22日付「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」の「実施時期等」の「2 経過措置(1)」に定められているいわゆるローン・パーティシペーション及びデット・アサンプション(信託契約による場合には、債務の履行を引き受ける者が受益者となっているものに限る。)については、原則として当該経過措置に定められた会計基準による処理を認めるものとする。
(経過的取扱い(4)…複合有価証券等を有する場合の取扱い)
2-3-42《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める複合有価証券等を平成12年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「改正事業年度」という。)開始の時に有している場合には、改正事業年度開始の日に当該複合有価証券等を取得し、又は発生させたものとして同通達を適用する。
この場合において、次のことは次による。
- (1) 改正事業年度開始の時における当該複合有価証券等の帳簿価額は、改正事業年度の直前の事業年度終了の時における当該複合有価証券等の帳簿価額(2-3-42に定める組込デリバティブ取引(以下この取扱いにおいて「組込デリバティブ取引」という。)について受領し、又は支払うオプション料、キャップ料等(以下この取扱いにおいて「オプション料等」という。)の額を区分して計上していた場合には、有価証券等の帳簿価額と当該オプション料等の帳簿価額との合計額)とする。
- (2) 改正事業年度において2-3-42本文により当該複合有価証券等に係る取引を区分する場合には、次の場合の区分に応じ、次による。
- イ 改正事業年度前の事業年度において当該複合有価証券等を区分していた場合には、当該区分していた金額に基づき区分する。
- ロ 改正事業年度前の事業年度において当該複合有価証券等を区分していなかった場合には、合理的に区分するものとするが、これが困難であると認められるときは、組込デリバティブ取引の帳簿価額はないものとして区分して差し支えない。
- (3) 改正事業年度において2-3-42本文により当該複合有価証券等に係る取引を区分しない場合であっても、改正事業年度前の事業年度において区分していたオプション料については、(1)にかかわらず、この通達による廃止前の平成10年10月30日付課法2-11「金融商品に関する法人税の取扱いについて」の例により処理して差し支えない。
(経過的取扱い(5)…有価証券の保有目的等の帳簿書類への記載等)
改正事業年度における次に掲げるものに係るそれぞれ次に掲げる帳簿書類への記載については、改正事業年度の開始の時期等も勘案し、当該事業年度開始後遅滞なくこれを行っているときは、課税上弊害がない限り、これを認めて差し支えないものとする。この場合、令第119条の11《有価証券の区分変更によるみなし譲渡》の規定は適用しない。
- (1) 改正政令附則第8条第2号《満期保有目的有価証券》に規定する有価証券 規則第27条の2《満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法》に規定する事項の記載
- (2) 改正政令附則第11条第3号《売買目的有価証券》に規定する有価証券 規則第27条の5第1項《短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法》に規定する事項の記載
- (3) 改正政令附則第11条第4号《金銭の信託に係る売買目的有価証券》に規定する有価証券 規則第27条の5第2項《金銭の信託に係る売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法》に規定する事項の記載
- (4) 改正規則附則第2項《金利スワップ取引等の特例処理》の規定の適用を受ける同項に規定する取引 規則第27条の7第2項第2号《金利スワップ取引等に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する事項の記載
- (5) 改正法附則第4条《ヘッジ処理に関する経過措置》の規定の適用を受けるデリバティブ取引等 次に掲げる事項の記載
- イ 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する事項
- ロ 規則第27条の8第3項及び第4項《繰延ヘッジ処理に係る特定事由の記載》に規定する事項
- ハ 規則第27条の8第5項《繰延ヘッジ処理に係る超過差額の処理の記載》に規定する事項
- ニ 規則第27条の9第1項及び第2項《時価ヘッジ処理に係るヘッジ対象等の明細の記載》に規定する事項
- ホ 規則第27条の9第3項《時価ヘッジ処理に係る特定事由の記載》に規定する事項
- ヘ 2-3-59《繰延ヘッジ処理の表示》に定める事項(2-3-61《時価ヘッジ処理に係る取扱い》で準用する事項を含む。)
- (6) 改正政令附則第14条《改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置》の規定の適用を受ける先物外国為替契約 規則第27条の10第2項《先物外国為替契約による取引発生時の円換算額の確定の記載》に規定する事項の記載
- (7) 改正政令附則第15条《改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置》の規定の適用を受ける先物外国為替契約等 規則第27条の11第2項《先物外国為替契約等により円換算額が確定している旨の記載の方法》に規定する事項の記載
(経過的取扱い(6)…上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定)
この通達による改正後の9-1-9の(1)ハの取扱いは、平成12年4月1日以後にされる民事再生法の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条《和議法及び特別和議法の廃止》の規定による廃止前の和議法の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-19
平成12年11月20日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通他関係
一〜二十一 (略)
二十二 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の9-1-5の(2)、9-1-16の(2)及び9-6-1の(1)(2)の取扱いは、平成12年4月1日以後にされる民事再生法の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条《和議法及び特別和議法の廃止》の規定による廃止前の和議法の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正後の2-1-27、16-2-4及び17の2-1-1の取扱いは、平成12年11月30日から適用する。
(経過的取扱い(2)…施行日前に製作を開始したソフトウエアの取得価額)
法人が平成12年4月1日以後に取得したソフトウエアのうち、同日前に製作を開始したものの取得価額については、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第145号)附則第3条の規定により、平成12年3月31日までに損金の額に算入されるべき原材料費、労務費及び経費の額を控除した金額となることに留意する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-1
課審4-25
平成14年2月15日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜四十七 (略)
四十八 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…自己株式の評価方法の区分に関する適用時期等)
法人の平成13年10月1日前に開始した事業年度については、この法令解釈通達による改正前の2-3-17の取扱いは、なお従前の例による。
(注) 法人が、同日以後最初に開始する事業年度開始の時において自己株式を有する場合には、その時にその自己株式を取得したものとみなして、令第119条の2の規定を適用する。
(経過的取扱い(2)…複利の方法による現在価値に相当する金額の計算)
この法令解釈通達による改正後の13-1-11の取扱いは、平成13年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-7
課審4-9
平成15年2月28日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜六十二 (略)
六十三 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)……転換社債又は新株引受権に関する改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前の1-5-1(3)、(4)、1-5-5、2-1-33(4)、(7)イ、2-3-5、2-3-6、2-3-12、2-3-13、2-3-15、2-3-30、2-3-31、3-1-5、3-1-6、3-2-14、3-2-14の2、13の2-2-13、16-2-10及び16-2-10の2の取扱いは、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)……退職給与引当金の取崩し)
法人が平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時において有する旧法人税法第54条第6項《退職給与引当金勘定の取崩し》に規定する退職給与引当金勘定の金額につき、平成14年改正法(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年7月法律第79号)をいう。以下同じ。)附則第8条第2項又は第3項《退職給与引当金に関する経過措置》の規定により取り崩すべき金額を超えて取り崩した場合には、その超える部分の金額は、その取崩しを行った日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(経過的取扱い(3)……複利の方法による現在価値に相当する金額の計算)
この法令解釈通達による改正後の13-1-11の取扱いは、平成14年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(4)……金銭貸付業に該当しない共済貸付け)
この法令解釈通達による改正後の15-1-15の取扱いは、平成16年1月1日以後の契約による貸付けについて適用し、同日前の契約による貸付けについては、なお従前の例による。
(経過的取扱い(5)……外国税額の控除における退職給与引当金の取崩額の国外所得金額への配賦)
平成15年3月31日前に終了する事業年度については、この法令解釈通達による改正前の16-3-16の取扱いは、なお従前の例による。
また、法人が、平成15年3月31日以後に終了する各事業年度において、平成14年改正法附則第8条第2項又は第3項《退職給与引当金に関する経過措置》の規定の適用により取り崩す退職給与引当金勘定の金額の国外所得金額に係るものの計算について、平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)開始の時における国内の在職者と国外の在職者の退職給与引当金の要支給額の比により計算しているときは、これを認める。
(経過的取扱い(6)……特別修繕引当金の取崩し)
- (1) 平成10年改正法(法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)をいう。以下同じ。)附則第7条第1項《特別修繕引当金に関する経過措置》の規定により特別修繕引当金の取崩しを行う場合の取扱いについては、この法令解釈通達による廃止前の21-4-4及び21-4-6の取扱いの例による。
- (2) 法人が平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)終了の日において有する平成10年改正法附則第7条第2項に規定する取崩対象特別修繕引当金額につき、同項の規定により取り崩すべき金額を超えて取り崩した場合には、その超える部分の金額は、その取崩しを行った日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係 (略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-22
課審5-22
平成15年12月16日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十九 (略)
二十 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・平成10年改正法令による経過措置に係る取扱い)
平成15年3月31日以前に開始した事業年度分の法人税については、この法令解釈通達による改正前の第21章の取扱いは、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-14
課審5-33
平成16年12月20日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十七 (略)
十八 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の1-5-1の(1)の取扱いは、平成16年10月1日から適用する。
- (2) この法令解釈通達による改正後の9-1-9の(1)のロ、9-6-1の(2)及び9-7-12の(注)の取扱いは、平成17年1月1日以後にされる破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は職権でされる破産手続開始の決定に係る破産事件について適用し、同日前にされた同法附則第2条《旧法の廃止》の規定による廃止前の破産法の規定による破産の申立て又は職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正後の12-4-1の取扱いは、連結法人の平成13年4月1日以後に開始した連結事業年度(法人税法第81条の9第2項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
- (4) この法令解釈通達による改正後の13-1-11の取扱いは、平成16年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-14
課審5-212
平成17年12月26日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜二十一 (略)
二十二 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の3-1-1及び3-2-5の取扱いは、平成17年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-3
課審5-11
平成19年3月13日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜五十 (略)
五十一 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…合併、分割、株式交換又は株式移転に関する改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前の1-2-3、1-4-1、2-1-22(3)ロ、ハ、ホ、2-1-27(4)イ、ロ及び2-6-2の2の取扱いは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第36条《合併等に関する経過措置》、第72条《合名会社等の合併に関する経過措置》又は第105条《株式会社の合併等に関する経過措置》の規定によりなお従前の例によることとされた合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)…資本金の増加の日に関する改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の1-5-1の取扱いは、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日以後に行われる資本金又は出資金の増加について適用し、同日前に行われた資本又は出資の増加については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(3)…役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当)
法人が次に掲げる事業年度及び期間において役員に対して支給した歩合給又は能率給のうち、この法令解釈通達による改正前の9-2-15の取扱いにより定期の給与とされるものは、法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期同額給与に該当するものとする《2)に掲げる期間については、(1)に掲げる事業年度についてこの経過的取扱いを受ける場合に限る。)。
- (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度
- (2) (1)に掲げる事業年度のうち最も新しい事業年度終了の日の翌日から同日以後に行われる役員給与の改定までの期間(同日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日)までの期間に限る。)
(経過的取扱い(4)…出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い)
法人が次に掲げる事業年度及び期間において支出した給与負担金の額については、この法令解釈通達による改正後の9-2-46に定める出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていない場合であっても、同通達の取扱いによることができるものとする。
- (1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度
- (2) (1)に掲げる事業年度のうち最も新しい事業年度終了の日の翌日から同日以後に行われる役員給与の改定までの期間(同日から3月を経過する日(保険会社にあっては、4月を経過する日)までの期間に限る。)
(注) 法人がこの法令解釈通達による改正後の9-2-46及び本文の取扱いの適用を受けない場合において、(1)及び(2)に掲げる事業年度及び期間において支出した給与負担金の額のうち、この法令解釈通達による改正前の9-2-34の取扱いにより報酬とされるものの額は、法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期同額給与に該当するものとする《2)に掲げる期間については、(1)に掲げる事業年度についてこの取扱いを受ける場合に限る。)。
(経過的取扱い(5)…自社発行の新株予約権証券及び転換社債型新株予約権付社債)
この法令解釈通達による改正前の13の2-2-13の取扱いは、法人が平成18年5月1日前にその発行に係る決議をした外貨建ての転換社債型新株予約権付社債については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)
信託に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-5
課審5-22
平成19年6月22日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち信託に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙(略)
減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-7
課審5-23
平成19年6月22日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち減価償却に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係(略)
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
一〜九 (略)
十 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・・・・減価償却に関する改正通達の適用時期等)
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第37号》による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審5-31
平成19年12月7日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三十四 (略)
三十五 経過的取扱い
(経過的取扱い…リース取引に係る改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の2-4-2の2、2-4-8から2-4-11まで、3-2-3、7-6の2-1から7-6の2-16まで、11-2-19の2、12の5-1-1から12の5-1-3まで及び12の5-2-1から12の5-2-4までの取扱いは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法第64条の2第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引について適用し、同日前に締結された契約に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の令第136条の3第3項《リース取引の範囲》に規定するリース取引については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-5
課審5-181
平成20年7月2日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三十四 (略)
三十五 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…特例民法法人が公益社団法人等に移行した場合の事業年度)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下経過的取扱い(2)までにおいて「整備法」という。)第40条第1項《社団法人及び財団法人の存続》の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項《移行の登記》(同法第121条第1項《認定に関する規定の準用》において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)(以下経過的取扱い(3)までにおいて「平成20年改正法」という。)附則第10条第1項《公益法人等の範囲に関する経過措置》に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)が、行政庁の認定を受けて公益社団法人若しくは公益財団法人への移行をした場合又は行政庁の認可を受けて一般社団法人若しくは一般財団法人への移行をした場合の事業年度は、次に掲げる期間となることに留意する。
- (1) その事業年度開始の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則第2条第1項《計算書類等の作成に係る期間》ただし書の移行の登記をした日の前日までの期間
- (2) その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間
(経過的取扱い(2)…旧有限責任中間法人及び特例無限責任中間法人に係る事業年度)
平成20年改正法附則第10条第2項《公益法人等の範囲に関する経過措置》に規定する旧有限責任中間法人又は同条第3項に規定する特例無限責任中間法人に係る事業年度は、整備法の施行及び整備法第33条第1項《移行の登記》に規定する設立の登記によっては区分されず継続することに留意する。
ただし、旧有限責任中間法人が整備法施行の日以後、令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のすべてに該当することとなった場合の当該旧有限責任中間法人に係る事業年度は、次に掲げる期間となることに留意する。
- (1) その事業年度開始の日から、その要件のすべてに該当することとなった日の前日までの期間
- (2) その要件のすべてに該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間
(経過的取扱い(3)…長期大規模工事以外の工事の取扱い)
平成20年4月1日前に開始した事業年度において着手した平成20年改正法による改正前の法(以下経過的取扱い(3)において「旧法」という。)第64条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(旧法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の旧法第64条第2項の規定を含む。以下経過的取扱い(3)において同じ。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用している長期大規模工事以外の工事(平成20年改正法附則第19条第2項《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置》に規定する経過措置工事のうち旧法第64条第2項の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき工事進行基準の方法を適用しているものを含む。)については、この法令解釈通達による改正前の2-4-19の取扱いは、なお従前の例による。
(経過的取扱い(4)…事業税及び地方法人特別税の取扱い)
この法令解釈通達による改正後の5-1-4の(7)、9-5-2、9-5-2の2及び20-3-8の取扱いは、平成20年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-5
課審5-41
平成21年12月28日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十七 (略)
十八 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正前の法人税法等の適用がある場合)
改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第18号)をいう。)による改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の法人税法、法人税法施行令及び法人税法施行規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の法人税基本通達の取扱いの例による。
(経過的取扱い(2)…特例民法法人が一般社団法人等に移行した場合における非営利型法人の要件判定)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条第1項《社団法人及び財団法人の存続》の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第121条第1項《認定に関する規定の準用》により読み替えて準用する同法第106条第1項《移行の登記》の登記をしていないもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第10条第1項《公益法人等の範囲に関する経過措置》に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)が、行政庁の認可を受けて一般社団法人又は一般財団法人(以下経過的取扱い(2)において「一般社団法人等」という。)への移行をした場合において、当該一般社団法人等がその移行の日を含む期間について15-1-28の取扱いによる実費弁償の確認を受けたことにより収益事業としないものとされた業務があるときには、当該業務は当該一般社団法人等の収益事業に該当しないものとして令第3条第2項第3号《非営利型法人の範囲》の要件に該当するかどうかの判定を行うこととする。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-1
課審5-25
平成22年6月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜四十六 (略)
四十七 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正前の1-1-6、12の6-2-2及び第19章の取扱いは、平成22年10月1日前に解散が行われた場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正前の1-2-5、1-4-13、1-4-14、12-4-1、12の2-1-2、12の4-1-4及び12の4-3-7の取扱いは、平成22年10月1日前に行われた分割、事後設立又は譲渡損益調整額の計算については、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正後の1-1-7、12-3-2及び12の3-2-4の取扱いは、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用し、同日前に解散が行われた場合については、なお従前の例による。
- (4) この法令解釈通達による改正後の1-2-4、1-4-1、1-4-11、1-6-1、1-6-3、2-1-39、2-2-2、2-3-51、7-4-15、8-1-14、8-1-15、9-1-6の5、9-1-6の6、9-1-6の11、9-6-8、10-1-2、10-1-4、11-2-14、12-1-4、12の2-1-1、12の2-2-2、12の2-2-3、12の3-2-3、12の3-2-5、12の3-2-6、12の4-1-1、12の4-1-2、12の4-2-1から12の4-3-2まで、12の4-3-4から12の4-3-6まで、12の4-3-8から12の4-3-10まで、13の2-2-10、14-3-2、16-3-16、16-3-20、16-3-23、16-3-25、16-3-26及び17-1-5の取扱いは、平成22年10月1日以後に行われる合併、分割、現物分配(残余財産の分配にあっては、同日以後の解散によるものに限る。)又は譲渡損益調整資産の譲渡について適用し、同日前に行われた合併、分割、事後設立又は譲渡損益調整資産の譲渡については、なお従前の例による。
- (5) この法令解釈通達による改正後の3-1-8、3-3-4、4-2-4から4-2-6まで、9-4-2の5、9-4-2の6、12-1-5、12-1-6、12-3-7から12-3-9まで、12の2-2-5、12の2-2-7及び12の3-3-1の取扱いは、平成22年10月1日から適用する。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審5-21
平成23年12月21日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等による税制改正をいう。)に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三十八(略)
三十九 経過的取扱い
(改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正前の5-2-9の取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、同年6月30日前に終了する事業年度を含む。)における期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正後の7-3-20の2、7-3-21の2の取扱いは、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に令第57条第1項《耐用年数の短縮》の承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用する。
- (3) この法令解釈通達による改正前の7-4-8から7-4-13までの取扱いは、平成23年3月31日以前に開始した事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)による改正前の令第60条の2第1項《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の承認を受けた場合(同年4月1日以後に開始した事業年度において同年6月30日前に同項の承認を受けた場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審6-15
平成24年9月12日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜七(略)
八 経過的取扱い
(改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の11-2-1の3及び12-3-2の取扱いは、平成24年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (2) 平成24年4月1日前に開始した事業年度分の法人税については、この法令解釈通達による改正前の16-3-2及び16-3-3の取扱いは、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正後の16-3-10の2の取扱いは、平成23年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-4
課審6-16
平成25年6月27日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-6
課審6-11
平成26年6月27日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-9
課審6-13
査調6-6
平成26年7月9日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十二 (略)
十三 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、次に掲げる経過的取扱いを除き、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)…欠損金の繰戻しによる還付)
この法令解釈通達による改正後の20-8-2の取扱いは、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-12
課審6-22
平成26年12月19日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
- (趣旨)
- 減価償却資産の範囲の取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一 (略)
二 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等については、なお従前の例による。ただし、法人が、平成27年1月1日前に取得をした美術品等(この法令解釈通達により減価償却資産とされるもので、かつ、同日以後最初に開始する事業年度(以下「適用初年度」という。)において事業の用に供しているものに限る。)について、適用初年度から減価償却資産に該当するものとしている場合には、これを認める。
(注) ただし書の取扱いにより減価償却資産に該当するものとしている場合における減価償却に関する規定(措置法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》の規定を含む。)の適用に当たっては、当該減価償却資産を適用初年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができる。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-8
課審6-3
平成27年6月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十四 (略)
十五 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の3-3-5及び16-3-36の2の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度において法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
- (2) この法令解釈通達による改正後の16-2-5及び16-2-8の取扱いは、平成28年1月1日以後に支払を受ける法第68条第1項《法人税額から控除する所得税額の計算》に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される所得税について適用し、同日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正前の16-2-1、16-2-6、16-2-6の2及び16-2-9の取扱いは、平成28年1月1日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
- (4) この法令解釈通達による改正後の2-3-60、20-2-6、20-2-7及び20-5-4の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-26
課審6-103
査調7-28
平成27年12月16日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜三 (略)
四 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審6-6
平成29年6月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜二十八 (略)
二十九 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の1−4−4(法第2条第12の11ニ((適格分割))の分割及び株式分配に係る部分に限る。)、1−4−5(株式分配に係る部分に限る。)、1−4−8から1−4−10まで、1−6−1及び2−1−27の取扱いは、平成29年4月1日以後に行われる同号ニの分割又は株式分配について適用する。
- (2) この法令解釈通達による改正後の1−4−1、1−4−2、1−4−4(株式交換等に係る部分に限る。)及び1−4−5(株式交換等に係る部分に限る。)の取扱いは、平成29年10月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
- (3) この法令解釈通達による改正後の9−2−14、9−2−15の2から9−2−15の5まで及び9−2−17の2から9−2−20の2まで(退職給与及び新株予約権による給与に係る部分を除く。)の取扱いは、法人が平成29年4月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
- (4) この法令解釈通達による改正後の9−2−14、9−2−15の2から9−2−15の5まで及び9−2−17の2から9−2−20の2まで(退職給与及び新株予約権による給与に係る部分に限る。)並びに9−2−27の2の取扱いは、法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
- (5) この法令解釈通達による改正前の9−2−15の取扱いは、法人が平成29年4月1日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
- (6) この法令解釈通達による改正後の9−2−16の2の取扱いは、法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。
- (7) この法令解釈通達による改正前の9−2−53の取扱いは、法人が平成29年10月1日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る承継新株予約権については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-8
課審6-1
平成30年5月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜二十四 (略)
二十五 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)
別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)…収益の計上の単位の通則等に関する改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の2−1−1から2−1−1の9まで、2−1−21の2から2−1−21の11まで、2−1−29から2−1−30の5まで、2−1−39から2−1−39の3まで、2−1−40の2、2−1−41、2−2−9、2−2−11、2−4−14、2−4−15、2−4−18の2及び9−7−1から9−7−3までの取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する事業年度において契約する取引について適用し、同日前に終了した事業年度において契約した取引に係るこの法令解釈通達による改正前の2−1−5、2−1−6、2−1−9、2−1−10、2−1−12、2−1−13、2−1−17、2−1−29、2−1−30、2−1−39、2−1−41、2−2−9、2−2−11、2−4−14、2−4−15及び9−7−1から9−7−3までの取扱いは、なお従前の例による。
経過的取扱い(3)…相手方に支払われる対価)
2−1−1の16の場合において、相手方に支払われる対価についてその支払をした日の属する事業年度の費用として損金の額に算入しているときは、当分の間これを認める。
(経過的取扱い(4)…知的財産のライセンスの供与に係る売上高等に基づく使用料に係る収益の帰属の時期)
2−1−30の4の適用上、工業所有権等又はノウハウを他の者に使用させたことにより支払を受ける使用料の額は、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、当分の間これを認める。
(経過的取扱い(5)…送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)
この法令解釈通達による改正後の2−1−31の取扱いは、措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社又は措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額及び課税対象金額、部分適用対象金額及び部分課税対象金額、金融子会社等部分適用対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額並びに金融関係法人部分適用対象金額及び金融関係法人部分課税対象金額について適用し、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等又は措置法第66条の9の2第1項に規定する特定外国法人の同日前に開始した事業年度に係る適用対象金額及び当該適用対象金額に係る課税対象金額並びに部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(6)…商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)
法人が平成30年4月1日前に終了した事業年度において発行した商品引換券等につきこの法令解釈通達による改正前の2−1−39本文の適用を受けている場合又はこの法令解釈通達による改正前の2−1−39ただし書の確認を受けている場合(同日以後に終了する事業年度においてこの法令解釈通達による改正後の2−1−39(3)の基準を定めていない場合に限る。)において、同日以後に終了する事業年度において発行した商品引換券等のうち未引換となっている対価の額を次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合(当該事業年度の確定申告書において益金算入に関する申告の記載をした場合を含む。)には、新たに当該基準を定める日までの間は「次に定める日の属する事業年度終了の日が到来すること」を法人が継続して収益を計上することとしている基準として予め定めているものとしてこの法令解釈通達による改正後の2−1−39(3)を取扱うことができる。
(1) この法令解釈通達による改正前の2−1−39本文の適用を受けている場合 その発行日
(2) この法令解釈通達による改正前の2−1−39ただし書の確認を受けている場合 その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日
(経過的取扱い(7)…長期割賦販売等)
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の2−4−1から2−4−2の2まで、2−4−4から2−4−11まで、11−2−19、12の3−2−3、12の3−3−1の2、12の3−3−3、13の2−1−6及び13の2−1−7の例による。
(経過的取扱い(8)…返品調整引当金)
改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第53条(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の11−1−1、11−3−1から11−3−8まで、14−3−5及び20−5−2の例による。
(経過的取扱い(9)…譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)
この法令解釈通達による改正前の12の4−2−2の取扱いは、法人が平成30年4月1日前に行った改正法第15条の規定による改正前の措置法第65条の12第1項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2−28
課審6−11
査調5−9
平成30年12月12日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜七 (略)
八 経過的取扱い
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正後の20−1−1から20−1−10まで及び20−5−7の取扱いは、平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-10
課審6-9
査調9-117
令和元年6月28日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十二 (略)
十三 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の2−1−21の12、2−1−21の14、2−1−29、2−1−49及び2−3−62から2−3−65までの取扱いは、平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正後の5−1−4(7)、9−5−2及び20−5−8の2の取扱いは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日以後に開始する事業年度分の特別法人事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の地方法人特別税については、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正後の9−5−5の取扱いは、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の施行の日から適用する。
- (4) この法令解釈通達による改正後の20−2−4及び20−5−21の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)
課法2-13
課審6-10
査調5-3
令和元年6月28日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
- 1 平成24年4月27日付課法2−5他1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」
- 2 平成13年8月10日付課審4−100他1課共同「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
- 3 平成元年12月16日付直審4−52他1課共同「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」
- 4 昭和62年6月16日付直法2−2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
- 5 昭和54年6月8日付直審4−18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」
(趣旨)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについて、所要の見直しを行うために改正を行ったものである。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一 (略)
二 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは令和元年7月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(9−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険を除く。)の保険料及び令和元年10月8日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険(9−3−5に定める解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険に限る。)の保険料について適用し、それぞれの日前の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料については、この法令解釈通達による改正前の取扱い並びにこの法令解釈通達による廃止前の昭和54年6月8日付直審4―18「法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて」、昭和62年6月16日付直法2―2「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」、平成元年12月16日付直審4―52「法人又は個人事業者が支払う介護費用保険の保険料の取扱いについて」、平成13年8月10日付課審4―100「法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」及び平成24年4月27日付課法2―5ほか1課共同「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)」の取扱いの例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-33
課審6-19
査調5-6
令和元年12月18日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜五 (略)
六 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の16−2−2の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払を受ける法第68条第1項《所得税額の控除》に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される16−2−2に定める所得税の額(以下「所得税の額」という。)について適用し、同日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税の額については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正後の16−2−11((1)に係る部分に限る。)及び16−3の2−5((1)に係る部分に限る。)の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払われる措置法第9条の3の2第1項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》に規定する上場株式等の配当等について適用する。
- (3) この法令解釈通達による改正後の16−2−11((2)から(5)までに係る部分に限る。)及び16−3の2−5((2)から(5)までに係る部分に限る。)の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払われる措置法第9条の6第1項《特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定目的会社の同項に規定する利益の配当、措置法第9条の6の2第1項《投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例》に規定する投資法人の同項に規定する配当等、資産の流動化に関する法律第2条第13項《定義》に規定する特定目的信託の剰余金の配当又は措置法第9条の6の4第1項《特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例》に規定する特定投資信託の剰余金の配当について適用する。
- (4) この法令解釈通達による改正後の16−3−23の取扱いは、令和2年1月1日から適用する。
- (5) この法令解釈通達による改正後の第16章第3節の2(16−3の2−5を除く。)並びに20−7−3及び20−7−4の取扱いは、令和2年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る法第69条の2第1項《分配時調整外国税相当額の控除》又は第144条の2の2第1項《外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審6-9
令和2年6月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十三 (略)
十四 経過的取扱い
(経過的取扱い)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の2−3−4の2、2−3−4の3、2−3−22から2−3−22の9まで、2−3−29から2−3−34まで、2−3−40、2−3−68から2−3−70まで及び9−1−12の2の取扱いは、令和2年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (2) 法人の令和2年4月1日以後に終了する事業年度(令和3年3月31日以前に開始するものに限る。)において改正令(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第112号)をいう。以下同じ。)附則第6条第2項《売買目的有価証券の時価評価金額に関する経過措置》の規定の適用を受ける場合の売買目的有価証券の時価評価金額の計算に当たっては、この法令解釈通達による改正前の2−3−29から2−3−34までの取扱いの例による。
- (3) 法人の令和2年4月1日以後に終了する事業年度(令和3年3月31日以前に開始するものに限る。)において改正令附則第4条第2項《短期売買商品等の時価評価金額に関する経過措置》の規定の適用を受ける場合の短期売買商品等の時価評価金額の計算に当たっては、この法令解釈通達による改正前の2−3−68の取扱いの例による。
- (4) この法令解釈通達による改正後の2−3−4、2−3−19、2−3−39、4−1−4、9−1−7、9−1−8、9−1−11及び9−1−15の2の取扱いは、令和2年4月1日以後に終了する事業年度(令和3年3月31日以前に開始した事業年度で令和元年7月4日付改正前の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「旧金融商品会計基準」という。)を適用する事業年度を除く。)分の法人税について適用し、令和2年4月1日前に終了した事業年度(令和3年3月31 日以前に開始した事業年度で旧金融商品会計基準を適用する事業年度を含む。)分の法人税については、この法令解釈通達による改正前の2−3−4、2−3−19、2−3−39から2−3−41まで、4−1−4、9−1―7、9−1−8、9−1−11及び9−1−15の2の取扱いの例による。ただし、令和2年4月1日以後に終了する事業年度(令和3年3月31日以前に開始した事業年度に限る。)で令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び同日付改正後の企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びに旧金融商品会計基準のいずれも適用しない事業年度については、この法令解釈通達による改正前の2−3−4、2−3−19、2−3−39から2−3−41まで、4−1−4、9−1―7、9−1−8、9−1−11及び9−1−15の2の取扱いの例によることができる。
- (5) この法令解釈通達による改正後の15−1−15の取扱いは、令和3年1月1日から適用する。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-21
課審6-3
令和3年6月25日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十六 (略)
十七 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の7−3−15の2、7−3−15の3及び7−8−6の2の取扱いは、令和3年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
- (2) この法令解釈通達による改正後の9−2−27の2の取扱いは、法人がこの法令解釈通達の日付の日以後に開始する会計期間においてその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前に開始した会計期間においてその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
- (3) この法令解釈通達による改正後の9−5−2の取扱いは、この法令解釈通達の日付の日以後に当該事業年度(その直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度。以下「直前年度」という。)が令和2年4月1日以後に開始するものに限る。)の法人税について更正又は決定をする場合について適用し、この法令解釈通達の日付の日前に当該事業年度の法人税について更正又は決定をした場合(この法令解釈通達の日付の日以後に当該事業年度(その直前年度が令和2年4月1日前に開始したものに限る。)の法人税について更正又は決定をする場合を含む。)については、なお従前の例による。
第2 連結納税基本通達関係(略)
第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)
第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係(略)
第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係(略)
第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-14
課審6-5
令和4年6月24日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙の第1から第6までのとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。
1 平成15年2月28日付課法2−3ほか1課共同「連結納税基本通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「連結納税基本通達」という。)
2 平成15年2月28日付課法2−5ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(連結納税編)の制定について」(法令解釈通達)(以下「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」という。)
3 令和2年9月30日付課法2−33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)
なお、連結納税基本通達及び租税特別措置法関係通達(連結納税編)の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第7による。
おって、別紙の第1から第6までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜六十五 (略)
六十六 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正前の法等の適用がある場合)
連結改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)のうち同法第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)に係る部分、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)及び法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)をいう。)及び4年改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第137号)及び法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第14号)をいう。)による改正前の法、令及び規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の法人税基本通達の取扱いの例による。
(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項についてはそれぞれ次による。
- (1) この法令解釈通達による改正後の1−2−6((1)へ及び(2)チに係る部分に限る。)の取扱いは、令和4年10月1日以後に1−2−6(1)へ及び(2)チに掲げる場合に該当する事実が生じた場合について適用する。
- (2) この法令解釈通達による改正後の2−3−22の6の取扱いは、法人が令和2年4月1日以後に開始した事業年度において受ける対象配当等の額について適用する。
- (3) この法令解釈通達による改正後の7−1−11の2及び7−1−11の3の取扱いは、法人が令和4年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする減価償却資産について適用する。
- (4) この法令解釈通達による改正後の9−5−8から9−5−11までの取扱いは、法人の令和5年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(経過的取扱い(3)…労働者協同組合への組織変更により特定非営利活動法人又は企業組合が普通法人又は公益法人等に該当することとなった事実が生じた日)
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項《定義》に規定する特定非営利活動法人をいう。以下経過的取扱い(3)において同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号《種類》に掲げる企業組合をいう。以下経過的取扱い(3)において同じ。)が労働者協同組合法附則第4条《組織変更》の規定による労働者協同組合への組織変更(以下経過的取扱い(3)において「組織変更」という。)をしたことにより法第14条第1項第4号《事業年度の特例》に掲げる事実が生じた場合の同号に規定する「その事実が生じた日」は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日をいう。
- (1) 特定非営利活動法人が組織変更をした場合(労働者協同組合法附則第16条第4項《特定非営利活動法人の組織変更計画の承認等》において準用する同法附則第5条第4項第7号《企業組合の組織変更計画の承認等》に規定する効力発生日において、同法第94条の3第2号《認定の基準》に規定する特定労働者協同組合(以下経過的取扱い(3)において「特定労働者協同組合」という。)に該当しない場合に限る。) 当該効力発生日
- (2) 企業組合が組織変更をした場合(労働者協同組合法附則第5条第4項第7号に規定する効力発生日において、特定労働者協同組合に該当する場合に限る。) 当該効力発生日
(経過的取扱い(4)…企業組合又は特定非営利活動法人が労働者協同組合に組織変更をした場合の該当することとなる日等)
経過的取扱い(3)の(1)及び(2)に掲げる場合において、法第14条《事業年度の特例》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、経過的取扱い(3)の取扱いを準用する。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
第4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
第5 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)
第6 「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一部改正について」通達関係(略)
第7 経過的取扱い関係(略)
法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-17
課審6-7
査調13-1
令和5年9月21日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
別紙
一〜十一 (略)
十二 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、経過的取扱い(2)を除き、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度分の法第82条の2第1項《国際最低課税額》に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。
(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))
この法令解釈通達による改正後の目次から17−2−8まで及び第19章の取扱いは、令和6年4月1日から適用する。
(経過的取扱い(3)…特定会計処理に準ずる会計処理)
法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第47号。以下「改正規則」という。)附則第3条第13項《国際最低課税額の計算に関する経過措置》の「これに準ずる会計処理」とは、法第82条第1号ハ《定義》に規定する会社等が同条第2号に規定する企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る同条第10号に規定する最終親会社等の同条第1号イに掲げる連結等財務諸表における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を用いて当該最終親会社等の連結財務諸表を作成するための一連の基礎資料(いわゆる連結パッケージ)を作成する会計処理をいうことに留意する。(令6年課法2−21により追加)
(経過的取扱い(4)…収入金額及び税引前当期利益の額の円換算)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号。以下「改正法」という。)附則第14条第1項第1号イ及びロ《国際最低課税額の計算に関する経過措置》の「財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額」に満たないかどうかの判定に当たり、同号イに規定する収入金額及び同号ロに規定する税引前当期利益の額(以下経過的取扱い(4)において「収入金額等」という。)が外国通貨で表示される場合には、当該収入金額等を当該判定に係る対象会計年度開始の日(改正規則附則第3条第3項《国際最低課税額の計算に関する経過措置》に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2−21により追加)
(注) 本文の取扱いは、法人税法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第208号)附則第4条第2項《国際最低課税額の計算に関する経過措置》に係る判定を行う場合についても、同様とする。
(経過的取扱い(5)…その他これに準ずる金額の例示)
改正規則附則第3条第14項第1号ロ(1)《国際最低課税額の計算に関する経過措置》の「その他これに準ずる金額」には、例えば、措置法第66条の5の3第1項又は第2項《対象純支払利子等に係る課税の特例》の規定により、同号に規定する資金供与会社等の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下経過的取扱い(5)において同じ。)に相当する金額又は調整対象超過利子額(同条第2項に規定する調整対象超過利子額をいう。以下経過的取扱い(5)において同じ。)に相当する金額(外国におけるこれらに相当するものを含む。)として損金の額に算入される金額(当該超過利子額又は当該調整対象超過利子額が生じた法第82条の2第2項第1号ロ《国際最低課税額》に規定する過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等(改正規則附則第3条第4項に規定する法人税等をいう。以下経過的取扱い(5)において同じ。)の額を減少させることが見込まれないこと(令和4年12月16日以後に行われる改正規則附則第3条第14項第1号の資金の供与がないものとした場合に、当該過去対象会計年度後の各対象会計年度における法人税等の額を減少させることが見込まれないことを含む。)により当該超過利子額又は当該調整対象超過利子額に係る改正規則附則第3条第5項に規定する繰延税金資産が計上されていないものに限る。)に対応する部分の金額が含まれることに留意する。(令6年課法2−21により追加)
(経過的取扱い(6)…国際最低課税額の計算に関する経過措置における国別グループ純所得の金額から控除する金額の取扱い)
改正法附則第14条第1項第3号《国際最低課税額の計算に関する経過措置》の「同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額」は、改正法附則第14条第5項及び第6項の規定を適用して計算した金額となることに留意する。(令6年課法2−21により改正)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-14
課審6-5
令和6年6月21日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が改正した箇所であり、「……」とした箇所は記載を省略した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十 (略)
十一 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正前又は改正後の法令解釈通達の適用に関し、次に掲げる事項については、それぞれ次による。
(1) この法令解釈通達による改正前の1−4−12の取扱いは、令和6年10月1日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
(2) この法令解釈通達による改正後の1−4−12の取扱いは、令和6年10月1日以後に行われる現物出資について適用する。
(3) この法令解釈通達による改正後の1−4−13の取扱いは、令和6年10月1日以後に行われる現物出資について適用し、同日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)
第4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2-7
課審6-1
令和7年6月30日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
別紙
第1 法人税基本通達関係
一〜十九 (略)
二十 経過的取扱い
(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)
別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、令和7年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経過的取扱い(2)…リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)
所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号。以下「改正法」という。)附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第63条(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の2−4−2から2−4−11まで、12の7−2−7、12の7−3−2、12の7−3−3、12の7−3−13、13の2−1−6及び13の2−1−7の例による。
(経過的取扱い(3)…所有権移転外リース取引に関する改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の7−6の2−2及び7−6の2−10の取扱いは、令和7年4月1日以後に締結する令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、同日前に締結した法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第121号)第1条の規定による改正前の令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。
第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係(略)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
課法2−14
調審6−3
査調14−6
令和7年9月26日
昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
(注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
別紙
第一 法人税基本通達関係
一、二 (略)
三 経過的取扱い
(経過的取扱い…改正通達の適用時期)
この法令解釈通達による改正後の取扱いは、18−1−53、18−1−70の2、18−2−1、18−2−5の2及び18−2−5の7を除き、令和7年4月1日以後に開始する対象会計年度分の法第82条の2第1項《国際最低課税額》に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。