同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
【照会要旨】
B社は、令和7年に以下のとおり、役員Aに対し、使用人としての退職金と役員退職金を支給しました。
Aには、使用人として勤続した期間と役員として勤続した期間に重複する期間がありますが、この場合、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」には、どのように記載することとなりますか。
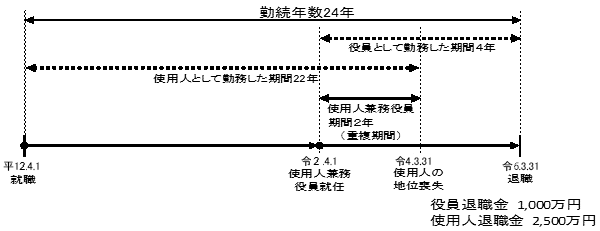
【回答要旨】
下記の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のとおりとなります。
照会の場合、Aが役員として勤務した期間は令3.4.1から令7.3.31までの4年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この期間に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等(※)に該当します。
※ 特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
Aは、令3.4.1に使用人兼務役員に就任しましたが、令5.3.31に使用人としての地位を喪失し、令5.4.1から専任の役員となっていますので、特定役員等勤続期間(※)(令3.4.1〜令7.3.31)と一般勤続期間(平13.4.1〜令5.3.31)とが重複している機関は、使用人兼務役員期間であった令3.4.1から令5.3.31までの期間となり、重複勤続年数は2年となります。
※ 特定役員等勤続期間とは、特定役員退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいいます。
また、使用人としての退職金(2,500万円)は特定役員退職手当等には該当しませんので一般退職手当等に該当します。
(退職所得控除額等の金額の計算)
- 退職手当等 3,500万円(一般退職手当等 2,500万円、特定役員退職手当等1,000万円)
- 勤続年数 24年(内特定役員等勤続年数 4年、重複勤続年数 2年)
- 退職所得控除額 1,080万円(一般退職所得控除額 960万円、特定役員退職所得控除額 120万円)
- 源泉徴収税額 3,991,089円
- 特別徴収税額 (市町村民税990,000円、道府県民税660,000円)
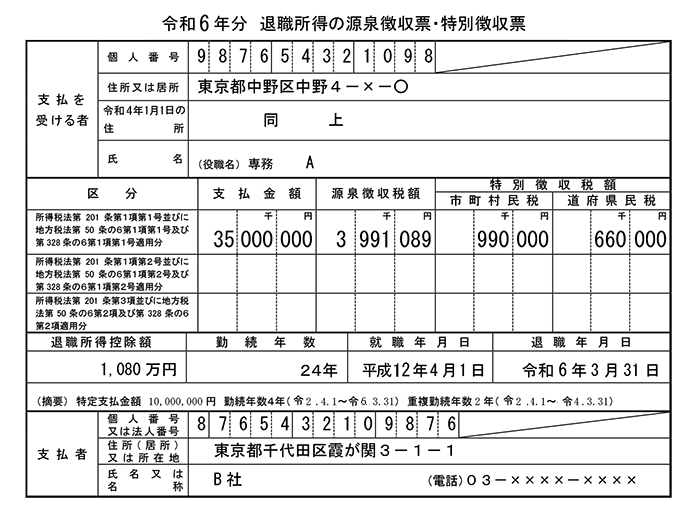
○ 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成における留意点
・ 上記太字部分の特定役員退職手当等の支払金額、特定役員等勤続年数及びその計算の基礎、重複勤続年数を「摘要欄」に記入します。
※ 「短期退職手当等及び特定役員退職手当等がある方の『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』について(令和4年1月)」(PDF/648KB)についても併せてご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
【関係法令通達】
所得税法第30条、第201条、所得税法施行令第69条、第69条の2、第71条の2、所得税法施行規則第94条、別表第六(二)
注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。