グループ通算制度に加入する法人に対する時価評価の適用免除要件について(従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性について)
【照会要旨】
当社の発行済株式の50%超を有するP社は、通算親法人であり、P社の通算子法人としてS社がおり、××事業を行っています。また、当社は、S社と同じ××事業を行う法人であり、当社の100%子会社としてⅩ社がいます(資本関係図参照)。
今般、××事業を行う当社とS社との間でのシナジー効果を見込み、××事業の経営の見直しを図ることを予定しています。具体的には、当社はP社の100%子会社となり、当該事業の人的資源をグループ内で再配分をすることを以下の手順により行うことを計画しています。
1 P社は、相対取引により他の当社株主から当社株式の取得(以下「本件取得」といいます。)をします。
2 当社及びX社は、本件取得によってP社(通算親法人)との間にP社による完全支配関係を有することとなることから、本件取得の日に通算承認の効力が生じてP社の通算グループに加入します。
3 本件取得直後に、当社の従業者の総数100人のうち40人について当社からS社に異動(以下「本件人事異動」といいます。)をさせ、S社の業務に従事させることを予定しています。残りの60人の当社の従業者は、引き続き当社の業務に従事することを予定しています。
この場合において、当社は、P社の通算グループへの加入に伴い保有資産等の時価評価を行う必要があるか検討することとなりますが、通算親法人と加入する法人との間に通算親法人による支配関係があるときには、時価評価の適用対象外となるための要件の一つに従業者継続要件があります。この要件は、通算グループに加入する法人の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれていることが要件とされています。
本件取得によって当社はP社の通算グループに加入し、その直後の本件人事異動によって当社の従業者100人のうち40人が、本件取得前から完全支配関係のあるX社ではなく、本件取得によって完全支配関係が生ずることとなったS社に移転して、S社の業務に従事することを予定していますが、S社が上記の括弧書の「完全支配関係がある法人」に該当するとして、この従業者継続要件を満たすと解して差し支えないでしょうか。
なお、当社及びX社は、通算除外法人(※)及び外国法人のいずれにも該当しません。
※ 法人税法第127条第2項の規定により青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人等一定の法人をいいます。
【資本関係図】
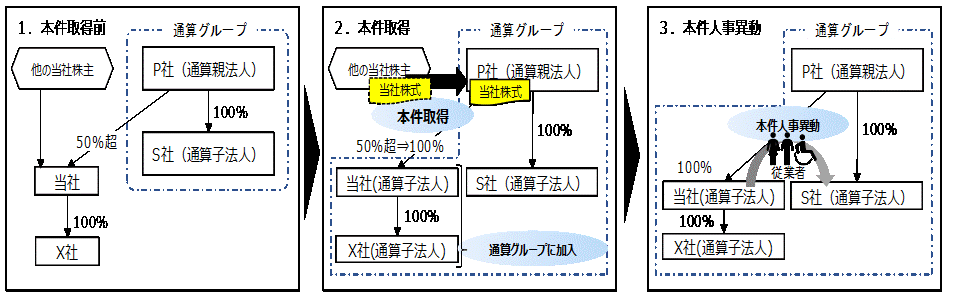
【回答要旨】
貴見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
1 通算グループに加入する内国法人が通算グループへの加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その加入直前の事業年度において、益金の額又は損金の額に算入する必要がありますが、一定の要件に該当する法人は、時価評価資産の時価評価を要しないこととされています(法法64の12 )。この時価評価を要しない法人(以下「時価評価除外法人」といいます。)に該当するための一定の要件の一つに、下記2の要件があります。
)。この時価評価を要しない法人(以下「時価評価除外法人」といいます。)に該当するための一定の要件の一つに、下記2の要件があります。
2 通算親法人が法人との間にその通算親法人による完全支配関係(通算除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下2において同じです。)を有することとなった場合(その有することとなった時の直前においてその通算親法人とその法人との間にその通算親法人による支配関係がある場合に限ります。)で、かつ、次の(1)及び(2)の要件の全てに該当する場合におけるその法人(通算制度の承認の効力が生じた後にその法人とその通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合に限るものとし、適格株式交換等の要件のうち、対価要件以外の適格要件に該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなったその株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除きます。)は、時価評価除外法人に該当することとされています(法法64の12 三)。
三)。
(1) その法人の完全支配関係を有することとなる時の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれていること【従業者継続要件】。
(2) その法人の完全支配関係を有することとなる前に行う主要な事業がその法人(その法人との間に完全支配関係がある法人を含みます。)において引き続き行われることが見込まれていること。
3 ところで、本照会のように、通算除外法人及び外国法人が介在しない通算親法人による完全支配関係が構築されたことにより通算グループに加入する法人が、通算グループの加入前から完全支配関係がある法人に従業者を移転させるのではなく、加入した通算グループ内の通算法人に従業者を移転させる場合において、上記2(1)の従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」とは、通算親法人による完全支配関係が生ずる前の資本関係下の法人をいうのか(本件ではX社がこれに該当するのか)、それとも、通算親法人による完全支配関係が生じた後の資本関係下の法人をいうのか(本件ではP社、S社及びX社の3社がこれに該当するのか)疑義が生ずるところです。
4 この点、上記2(1)の従業者継続要件については、支配関係がある法人間で行われる組織再編成(特に株式交換等)の要件(下記≪参考≫。以下「適格要件」といいます。)と同様の要件とする趣旨で設けられたものと解され、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がないと考えられる場合には課税関係を継続させることが適当であるという上記適格要件の趣旨を踏まえると、その完全支配関係が構築されているグループ全体からすれば、そのグループ内で一定数の従業者の従事が継続している場合には経済実態に実質的な変更がないと考えられるため、上記2(1)の従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」とは通算親法人による完全支配関係が生じた後の資本関係下の法人をいうと解することが合理的であると考えられます。
≪参考≫
組織再編税制では、上記2の従業者継続要件と同様の要件として、例えば、支配関係がある法人間の株式交換等が適格株式交換等に該当するための要件の一つに従業者継続要件があります。これは、株式交換等完全子法人の株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその株式交換等完全子法人の業務(その株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務及び一定の法人の業務を含みます。)に従事することが見込まれていることが要件とされています(法法2十二の十七ロ(1))。この組織再編税制の従業者継続要件における「完全支配関係がある法人」については、多段階型再編等多様な手法による事業再編の円滑な実施を可能とするため、平成30年度税制改正における従業者継続要件の見直しにより追加されたものであり、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者を移転することが見込まれている場合にも、当初の組織再編成の従業者継続要件に該当することとされました。例えば、株式交換等で株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に完全支配関係が生じ、その株式交換等直後に株式交換等完全子法人から株式交換等完全親法人及びその株式交換等完全親法人との間に完全支配関係があるグループ法人に株式交換等完全子法人の従業者を異動させ、その従業者がそのグループ法人等の業務に従事することが見込まれている場合には、従業者継続要件の80%の計算の分子に含めて計算することが認められています。そうすると、この組織再編税制の従業者継続要件における「完全支配関係がある法人」とは、組織再編成後の資本関係下の法人をいうものと解されます。
5 このため、本照会では本件取得によって貴社とP社との間にP社による完全支配関係が生じた後の資本関係下で上記2(1)の従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」に該当するか判断すると、S社はこの「完全支配関係がある法人」に該当することとなります。本件取得直後の本件人事異動によって、貴社の従業者の総数100人のうち40人が貴社からS社に異動し、S社の業務に従事することを予定し、残りの60人の貴社の従業者は、引き続き貴社の業務に従事することを予定しているため、法人(貴社)の完全支配関係を有することとなる時の直前の従業者(100人)のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者(貴社:60人+S社:40人=100人:100%)がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人(S社)の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれているといえることから、上記2(1)の従業者継続要件を満たすと考えられます。
6 なお、本件において、貴社はP社との間にP社による完全支配関係を有することとなった日(本件取得の日)に通算承認の効力が生じ(法法64の9 )、通算完全支配関係を有することとなり、P社の通算グループに加入していますが、これとは別に、貴社が加入時期の特例(法法14
)、通算完全支配関係を有することとなり、P社の通算グループに加入していますが、これとは別に、貴社が加入時期の特例(法法14 )を適用する場合には、P社による完全支配関係を有することとなった日(本件取得の日)ではなく、同日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日に通算承認の効力が生ずることとなります(法法64の9
)を適用する場合には、P社による完全支配関係を有することとなった日(本件取得の日)ではなく、同日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日に通算承認の効力が生ずることとなります(法法64の9 )。そのため、貴社は、その特例決算期間の末日の翌日にP社との間に通算完全支配関係を有することとなり、P社の通算グループに加入することとなります。本照会では、
)。そのため、貴社は、その特例決算期間の末日の翌日にP社との間に通算完全支配関係を有することとなり、P社の通算グループに加入することとなります。本照会では、 本件取得(貴社とP社との間で完全支配関係発生)⇒
本件取得(貴社とP社との間で完全支配関係発生)⇒ 通算グループへの加入(通算承認の効力発生・貴社とP社との間で通算完全支配関係の発生)⇒
通算グループへの加入(通算承認の効力発生・貴社とP社との間で通算完全支配関係の発生)⇒ 本件人事異動(貴社の従業者の異動)の順序ですが、加入時期の特例を適用する場合には、
本件人事異動(貴社の従業者の異動)の順序ですが、加入時期の特例を適用する場合には、 ’本件取得⇒
’本件取得⇒ ’本件人事異動⇒
’本件人事異動⇒ ’通算グループへの加入という順序となることも考えられます。この加入時期の特例を貴社が適用して上記
’通算グループへの加入という順序となることも考えられます。この加入時期の特例を貴社が適用して上記 ’から
’から ’までの順序でP社の通算グループに加入した場合において、上記2(1)の従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性に影響があるかどうかについては、“通算完全支配関係がある法人”とは規定されていないことから、加入時期の特例の適用の有無は「完全支配関係がある法人」の該当性に影響はありません。
’までの順序でP社の通算グループに加入した場合において、上記2(1)の従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性に影響があるかどうかについては、“通算完全支配関係がある法人”とは規定されていないことから、加入時期の特例の適用の有無は「完全支配関係がある法人」の該当性に影響はありません。
【関係法令通達】
法人税法第2条第12号の17、第14条第8項、第64条の9第11項、第64条の12第1項
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。