合併法人と被合併法人の特定役員を兼務している場合の特定役員引継要件について
【照会要旨】
当社は、〇〇県で〇〇事業を行う法人であり、××県で同事業を行い業績拡大中であった甲社の代表取締役社長であるA氏の経営手腕を見込み、約5年前にA氏を当社の代表取締役副社長に招へいし、以降、A氏は当社の経営に参画しています。
今般、当社の唯一の株主であり代表取締役社長であるX氏が一身上の都合により、当社の経営から退くこととなり、これに伴い、当社と甲社を統合し、その経営をA氏に委ねることを計画しています。
具体的には、当社を合併法人とし、甲社を被合併法人とする合併(以下「本件合併」といいます。)を行い、本件合併前に当社の代表取締役社長であったX氏が本件合併に伴い退任し、以降は株主として当社に携わることとなり、A氏以外の役員は退任することを予定しています。また、本件合併前に、甲社の代表取締役社長であり、当社の代表取締役副社長であったA氏は、本件合併後に合併法人である当社の代表取締役社長に就任することを予定しています。
ところで、当社と甲社は資本関係もなく、両社の個人株主の間には血縁関係はなく、法人株主の間にも資本関係がないことから、当社と甲社との間には(完全)支配関係がなく、本件合併が適格合併に該当するためには、いわゆる共同事業要件を満たす必要があります。この共同事業要件の1つに特定役員引継要件があり、「合併前の被合併法人の特定役員(・・・)のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること」がその要件とされていますが、本件合併は、特定役員引継要件を満たすと解して差し支えないでしょうか。
〔資本関係図〕
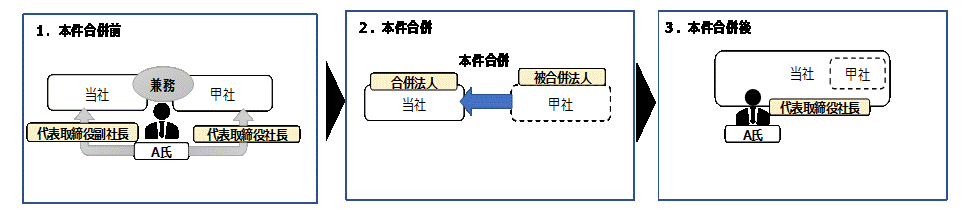
【回答要旨】
貴見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
1 合併において被合併法人と合併法人との間に50%超の保有関係がない場合に金銭等不交付要件及び共同事業要件に該当すれば適格合併に該当することとなりますが、この共同事業要件のうちの一つとして、事業規模要件又は特定役員引継要件が規定されています。この「事業規模要件又は特定役員引継要件」のうちの特定役員引継要件は、合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれていることと規定されています(法令4の3 二)。
二)。
この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいうと規定されています(法令4の3 二括弧書)。
二括弧書)。
この特定役員引継要件は、合併時点において、被合併法人の特定役員が合併後の合併法人で特定役員となり、かつ、合併法人の特定役員も合併後に合併法人の特定役員となることが見込まれているのであれば、経営面からみて共同事業が担保されることから、事業規模が5倍を超えているような法人間での合併であっても事業規模要件に代わる要件として認められているものと考えられます。
したがって、この要件の基本的な考え方としては、被合併法人で経営参画していた者のいずれかと合併法人で経営参画していた者のいずれかとが合併後の合併法人において共同して経営参画することが見込まれることが要求されているものと考えられます。
2 ご照会は、この特定役員引継要件の「合併前の被合併法人の特定役員のいずれかと合併法人の特定役員のいずれかとが・・・」とされていることから、合併前の被合併法人の特定役員と合併法人の特定役員とが別の者である必要があるのではないかという点を確認するものでありますが、この点、特定役員引継要件を定めた規定では、合併前の被合併法人の特定役員と合併法人の特定役員が別の者であることまで要件としているものではありません。このため、同一人物が両法人の特定役員であってもその適用を妨げられるものではありません。
本件では、合併前において被合併法人である甲社の代表取締役社長を貴社の代表取締役副社長であるA氏が兼務して両社の経営に参画していることから、A氏は、両社の特定役員に該当することとなります。そして、合併後は、合併法人である貴社の代表取締役社長に就任することが予定されていますので、特定役員引継要件を満たすこととなります。
3 なお、合併法人及び被合併法人の特定役員として兼務はしたものの、実際にはその一方又は双方の職務を遂行していない場合(名目的な特定役員である場合)などには、適格要件を形式的に満たすためだけに兼務させたのではないかと見る余地もありますので注意が必要です。
【関係法令通達】
法人税法施行令第4条の3第4項第2号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。