独立して事業を行うための分割に係る適格要件(非支配要件)の判定について
【照会要旨】
法人税法第2条第12号の11ニに規定する分割(いわゆるスピンオフ)が適格分割に該当するためには、分割の直前にその分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、その分割後にその分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないことが要件とされています。
以下の取引関係図において、他の者による支配関係はどのように判定することとなるのでしょうか。
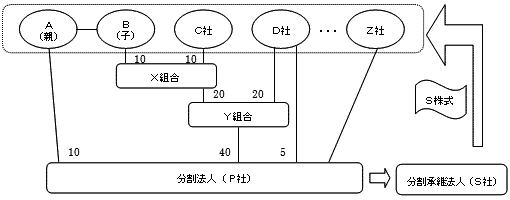
(※)Y組合に帰属する資産は、組合員であるX組合とD社が持分割合(50:50)に応じて保有し、X組合に帰属する資産は、組合員であるBとC社が持分割合(50:50)に応じて保有しています。したがって、P社の発行済株式のうち、Bは10%、C社は10%、D社は25%を保有することを前提とします。
【回答要旨】
分割法人(P社)の株主であるAからZ社までをそれぞれ「他の者」とした場合に、分割法人との間に当該他の者による支配関係があるかを判定します。上記取引図において、A又はBを他の者とした場合には、その保有する分割法人の株式は分割法人の発行済株式の50%超となりますので、分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなります。したがって、上記の取引関係図に係る分割については、C社以下の株主を他の者として判定を行うまでもなく、法人税法施行令第4条の3第9項第1号の要件を満たさないこととなります。
(理由)
1 法人税法第2条第12号の11ニに規定する分割(いわゆるスピンオフ)が適格分割に該当するためには、分割の直前にその分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、その分割後にその分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないことが要件とされています。ここで、「他の者」が個人である場合には、その個人との間に法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある者(親族等)がこの「他の者」に含まれます。また、「他の者」には、その者が締結している民法第667条第1項に規定する組合契約等及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含むこととされています(法令4の3 一)。
一)。
- イ その者が締結している組合契約による組合が締結している組合契約
- ロ 上記イ又は下記ハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
- ハ 上記ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
2 分割法人に複数の株主がいる場合には、それぞれの株主を「他の者」とした場合に、その分割法人との間に当該他の者による支配関係があるかを判定することとなります。上記の取引関係図においては、AからZ社までをそれぞれ「他の者」として判定を行うこととなりますが、そのうち、A又はBを「他の者」とした場合の支配関係については、次のとおりとなります。
- (1) 個人Aを「他の者」とした場合
Aは、分割法人の発行済株式の10%を直接保有しています。BはAの親族に該当しますので、「他の者」であるAに含まれます。次に、BはAに含まれますので、Bが締結しているX組合契約に係る他の組合員であるC社及びBが締結しているX組合契約による組合(X組合)が締結しているY組合契約に係る他の組合員であるD社も「他の者」であるAに含まれます。
したがって、Aを「他の者」とした場合には、B、C社及びD社がこれに含まれ、分割法人の発行済株式の55%(50%超)を保有することとなりますので、分割法人と他の者との間には当該他の者による支配関係があることとなります。 - (2) 個人Bを「他の者」とした場合
Bは、X組合及びY組合を通じて分割法人の発行済株式の10%を保有しています。AはBの親族に該当しますので、「他の者」であるBに含まれます。次に、Bが締結しているX組合契約に係る他の組合員であるC社及びBが締結しているX組合契約による組合(X組合)が締結しているY組合契約に係る他の組合員であるD社も「他の者」であるBに含まれます。
したがって、Bを「他の者」とした場合には、A、C社及びD社がこれに含まれ、分割法人の発行済株式の55%(50%超)を保有することとなりますので、分割法人と他の者との間には当該他の者による支配関係があることとなります。
3 上記2のとおり、A又はBを「他の者」とした場合には、分割法人と他の者との間には当該他の者による支配関係があることとなります。したがって、上記の取引関係図に係る分割については、C社以下の株主を他の者として判定を行うまでもなく、法人税法施行令第4条の3第9項第1号の要件を満たさないこととなります。
(参考)
- 1 C社を「他の者」とした場合
C社は、X組合及びY組合を通じて分割法人の発行済株式の10%を保有しています。C社が締結しているX組合契約に係る他の組合員であるB及びC社が締結しているX組合契約による組合(X組合)が締結しているY組合契約に係る他の組合員であるD社は、「他の者」であるC社に含まれます。なお、Aは「他の者」であるC社には含まれません。
したがって、C社を「他の者」とした場合には、B及びD社がこれに含まれ、分割法人の発行済株式の45%(50%以下)を保有することとなりますので、分割法人と他の者との間には当該他の者による支配関係がないこととなります。 - 2 D社を「他の者」とした場合
D社は、分割法人の発行済株式の5%を直接保有するとともに、Y組合を通じて20%保有しています。なお、A、B及びC社は「他の者」であるD社には含まれません。
したがって、D社を「他の者」とした場合には、分割法人の発行済株式の25%(50%以下)を保有することとなりますので、分割法人と他の者との間には当該他の者による支配関係がないこととなります。
【関係法令通達】
法人税法第2条第12号の11ニ
法人税法施行令第4条の3第9項第1号
注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。