いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
【照会要旨】
外国法人A社の100%子会社であるB社と、B社と出資関係を有しないE社(内国法人であるC社と外国法人であるD社がその発行済株式の全てを保有しています。)との間で、B社を合併法人、E社を被合併法人とする適格合併を予定しています(B・C・E社はいずれも株式会社で、A・D社は日本の株式会社に相当する法人です。また、A・D社が所在する外国と日本との間に租税条約は締結されていません。)。
この合併は、E社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の100%親法人である外国法人A社の株式とするいわゆる「クロスボーダーの三角合併」により行うことを予定しています。被合併法人E社の株主であるC社及びD社に対しては、B社の100%親法人である外国法人A社の株式以外の資産は交付されません。
この場合、C社及びD社が保有するE社株式の譲渡に係る課税関係は生じないと解してよろしいでしょうか。
なお、D社は、日本に恒久的施設を有していません。また、D社は、昨年にE社の発行済株式の30%を取得し、現在まで継続して保有しています。
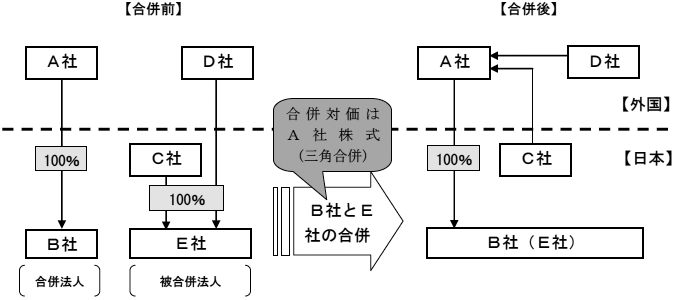
【回答要旨】
C社については、E社株式の譲渡に係る課税関係は生じません。
D社については、E社株式の譲渡に係る譲渡損益は課税の対象となります。
(理由)
-
Ⅰ C社(内国法人である被合併法人株主)の課税関係
- 1 合併に伴い被合併法人の株主である法人が、合併により消滅する被合併法人の株式を有しないこととなった場合には、原則として、その合併の日の属する事業年度に当該被合併法人の株式の譲渡に係る譲渡損益を計上することとなります(法法61の2
 、法規27の3十)。
、法規27の3十)。 - 2 ただし、その合併により、被合併法人の株主に合併法人の株式又は合併親法人の株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)のいずれか一方の株式のみが交付された場合には、上記1の譲渡損益の算定に際し、被合併法人の株主は被合併法人の株式の譲渡対価の額を当該合併直前の被合併法人の株式の帳簿価額に相当する金額として計算することとされていますので(法法61の2
 )、譲渡対価の額と譲渡原価の額が同額(いずれも合併の直前の被合併法人の株式の帳簿価額)となり、譲渡損益は生じません。この取扱いは、被合併法人の株主に交付される合併親法人の株式が外国法人の株式であっても同様となります。
)、譲渡対価の額と譲渡原価の額が同額(いずれも合併の直前の被合併法人の株式の帳簿価額)となり、譲渡損益は生じません。この取扱いは、被合併法人の株主に交付される合併親法人の株式が外国法人の株式であっても同様となります。 - 3 したがって、内国法人である被合併法人株主については、いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国法人である合併親法人の株式が交付された場合においても、被合併法人の株式の譲渡損益は生じないこととなりますので、ご照会の合併については、E社の株主であるC社においてE社株式の譲渡に係る課税関係は生じないこととなります。
- 1 合併に伴い被合併法人の株主である法人が、合併により消滅する被合併法人の株式を有しないこととなった場合には、原則として、その合併の日の属する事業年度に当該被合併法人の株式の譲渡に係る譲渡損益を計上することとなります(法法61の2
-
Ⅱ D社(外国法人である被合併法人株主)の課税関係
- 1 外国法人が株式を譲渡した場合の課税関係は、国内に恒久的施設を有するかどうかによって異なります。恒久的施設を有しない外国法人については、いわゆる事業譲渡類似株式の譲渡(※)など一定の株式の譲渡に限って課税の対象とされています(法法141二、法令178
 四)。
四)。
また、恒久的施設を有しない外国法人が、その保有する株式の発行法人である内国法人を被合併法人とする合併により、その保有する株式(被合併法人株式)を有しないこととなった場合で、その合併により交付される合併親法人株式が外国法人の株式であるときには、その株式の譲渡損益は繰り延べられないこととされています(法法61の2 、142、142の10、法令184
、142、142の10、法令184 十九、191)。これは、外国法人である被合併法人株主に外国法人の株式が交付され、その再編時に課税の繰延べを行うと、日本での課税機会が失われることとなるため、国際課税を適正化するという観点によるものです。
十九、191)。これは、外国法人である被合併法人株主に外国法人の株式が交付され、その再編時に課税の繰延べを行うと、日本での課税機会が失われることとなるため、国際課税を適正化するという観点によるものです。 - 2 ご照会によれば、E社の発行済株式の30%を保有する外国法人D社は、日本に恒久的施設を有しておらず、また、D社は、E社を被合併法人とする合併により、その保有するE社株式の全部を譲渡したこととなりますので、いわゆる事業譲渡類似株式の譲渡をしたこととなります。この場合、D社が当該合併により交付を受ける合併親法人の株式(A社株式)は外国法人の株式に該当しますので、E社株式の譲渡損益は繰り延べられません。したがって、D社については、E社株式の譲渡に係る譲渡損益は課税の対象となります。
- ※ 事業譲渡類似株式の譲渡とは、
 内国法人の特殊関係株主等(内国法人の一の株主及びその同族関係者等)が、譲渡事業年度終了の日以前3年以内のいずれかの時において、その内国法人の発行済株式等の総数の25%以上を所有していたこと(所有株数要件)、及び
内国法人の特殊関係株主等(内国法人の一の株主及びその同族関係者等)が、譲渡事業年度終了の日以前3年以内のいずれかの時において、その内国法人の発行済株式等の総数の25%以上を所有していたこと(所有株数要件)、及び 内国法人の株式等の譲渡を行った外国法人を含むその法人の特殊関係株主等がその発行済株式等の総数の5%以上の譲渡をしたこと(譲渡株数要件)の2つの要件を満たす譲渡のことをいいます(法令178
内国法人の株式等の譲渡を行った外国法人を含むその法人の特殊関係株主等がその発行済株式等の総数の5%以上の譲渡をしたこと(譲渡株数要件)の2つの要件を満たす譲渡のことをいいます(法令178 四ロ、
四ロ、 、
、 )。
)。
- 1 外国法人が株式を譲渡した場合の課税関係は、国内に恒久的施設を有するかどうかによって異なります。恒久的施設を有しない外国法人については、いわゆる事業譲渡類似株式の譲渡(※)など一定の株式の譲渡に限って課税の対象とされています(法法141二、法令178
【関係法令通達】
法人税法第61条の2第1項、第2項、第141条第2号、第142条、第142条の10
法人税法施行令第178条第1項第4号ロ、第4項、第6項、第184条第1項第19号、第191条
法人税法施行規則第27条の3第10号
注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。