いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
【照会要旨】
A社の100%子会社であるB社と特に出資関係を有しないC社との間で、B社を株式交換完全親法人とする株式交換を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
この株式交換は、C社の株主に交付する株式交換の対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角株式交換」により行うことを予定していますが、株式交換の対価をB社株式とする通常の株式交換の場合と「三角株式交換」の場合とでは、適格株式交換等に該当するための要件に異なる点はあるのでしょうか。
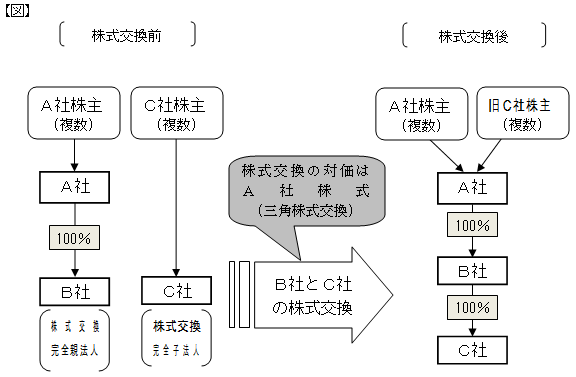
【回答要旨】
株式交換の対価は異りますが、適格株式交換等に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
(理由)
1 株式会社が行う株式交換が適格株式交換等に該当するためには、株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十七イ〜ハ)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十七柱書)を満たす必要があります。
このうち、これらの関係に共通して定められた要件は、株式交換完全子法人の株主に、次に掲げる株式のいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十七柱書)、いわゆる「三角株式交換」の場合には、 の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
 株式交換完全親法人の株式
株式交換完全親法人の株式
又は 株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とされる一定の関係がある法人をいいます。)の株式
株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係とされる一定の関係がある法人をいいます。)の株式
2 これに対して、株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との関係ごとに定められた要件は、いわゆる「三角株式交換」であるか、それ以外の株式交換であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角株式交換」であることをもって異なる要件が定められているわけではありません。
3 したがって、いわゆる「三角株式交換」の場合には、株式交換の対価が株式交換完全支配親法人の株式に限られる点は異なりますが、いわゆる「三角株式交換」とそれ以外の株式交換の間で適格株式交換等に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
4 なお、参考までに適格株式交換等に該当するための要件を定めた規定は、次のとおりです(法法2十二の十七)。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一〜十二の十六 (省略)
十二の十七 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
- イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
- ロ その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
- (1) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
- (2) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
- ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
- (以降省略)
【関係法令通達】
法人税法第2条第12号の17
注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。