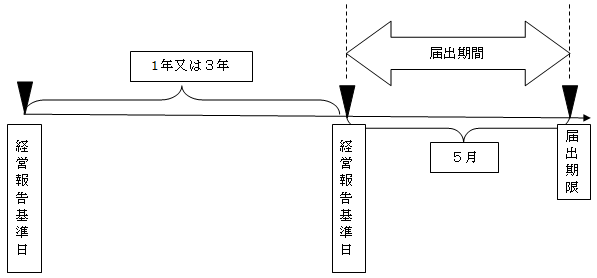【措置法第70条の6の4((山林についての相続税の納税猶予))関係】
- (申告期限前に総収入金額がゼロとなった場合)
- 70の6の4-9 措置法第70条の6の4第1項に規定する被相続人に相続が開始した日から当該被相続人に係る相続税の申告期限までの間に12月31日がある場合において、林業経営相続人の当該12月31日の属する年分の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となった場合であっても、措置法第70条の6の4第3項第4号の規定の適用はないことに留意する。
(新設)
(説明)
措置法第70条の6の4第3項第4号においては、同条第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人のその年分の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となった場合には、収入金額が零となった年の12月31日から2月を経過する日に納税の猶予に係る期限が到来することとされている。
措置法第70条の6の4第3項は、相続税の申告期限以降に適用される規定であり、かつ、同条第1項の適用要件として、同条第3項第4号に該当しないことといった要件はないことから、被相続人の相続が開始した日から当該被相続人に係る相続税の申告期限までの間に12月31日がある場合において、林業経営相続人の当該12月31日の属する年分の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となった場合の取扱いに疑義があるところである。本通達は、措置法第70条の6の4第1項の適用を受けた(る)場合において、林業経営相続人の当該12月31日の属する年の所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となったときであっても、措置法第70条の6の4第3項第4号の規定の適用はないことを留意的に明らかにした。また、この場合には、措置法第70条の6の4第1項の要件を満たしていれば、同項の規定の適用があることとなる。
(参考)
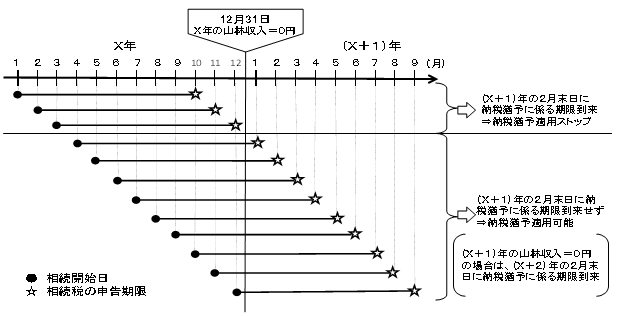
- (相次相続控除の算式)
- 70の6の4-10 第2次相続に係る被相続人が措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受けていた場合又は第2次相続により財産を取得した者のうちに同項の規定の適用を受ける者がある場合における相次相続控除額は、相続税法基本通達20-3((相次相続控除の算式))に準じて算出することに留意する。
この場合において、相続税法基本通達20-3中のAは、当該被相続人が当該納税猶予の適用を受けていた場合には、同条第15項の規定により免除された相続税額以外の税額に限ることに留意する。
(新設)
(説明)
相続税法においては、10年以内に2回以上相次いで相続が発生した場合には、相続税負担が過重となることからその調整を図るため、相次相続控除の制度を設けている(相法20)。
この控除は、相続税の納税猶予の適用を受けたものについても適用されるのであるが、控除する相続税額に免除を受けた税額が含まれない点が一般の場合とは異なっている。本通達は、その旨を留意的に明らかにしたものである。
なお、相続人又は受遺者のうちに措置法第70条の6の4の適用を受けた者がいたとしても、同条には農地の納税猶予における措置法令第40条の7第10項に相当する読み替え規定はないため、相続税法第20条第1項第2号の割合を算定する際の財産の価額は、相続の開始の時の時価を基に算定することとなる。農地の納税猶予の場合は、当該財産の価額は、農業投資価格を基に算定している(70の6-38)ことから、この点は農地の納税猶予における取扱いと異なっている。
- (納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予の期限が確定する場合)
- 70の6の4-11 措置法第70条の6の4第3項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合における納税猶予の期限は、農林水産大臣等(同項第1号に規定する農林水産大臣等をいう。)から納税地の所轄税務署長に対する同項第1号又は第2号の通知があった日から2月を経過する日であることに留意する。したがって、措置法令第40条の7の4第11項各号のいずれかに該当する場合又は措置法第70条の6の4第3項第2号に掲げる場合に該当する場合であっても、当該通知が所轄税務署長に到達しなければ、納税猶予の期限が確定することはないことに留意する。
ただし、措置法令第40条の7の4第11項各号に該当する場合又は措置法第70条の6の4第3項第2号に掲げる場合に該当する場合において、その該当することとなった日以後これらの号に定める日までの間に林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の死亡の日の前日から2月を経過する日が納税猶予の期限となることに留意する。 - (注) 措置法第70条の6の4第4項の場合に該当する場合においても上記と同様であることに留意する(ただし書きを除く。)。
(新設)
(説明)
措置法第70条の6の4第3項第1号においては、同号に掲げる場合に該当する場合には、農林水産大臣等から林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に同号に掲げる場合に該当する旨の通知があった日から2月を経過する日に納税猶予に係る期限が到来するとされ、同項第2号においては、同号に掲げる場合に該当する場合には、農林水産大臣等から林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に同号の100分の20を超えることとなった同号に規定する譲渡等又は同号に規定する路網未整備等に係る通知があった日から2月を経過する日に納税猶予に係る期限が到来することとされている。本通達では、納税猶予に係る期限は、これらの通知が税務署に到達しない限り到来しないことからその旨を留意的に明らかにした。
なお、農地等についての相続税・贈与税の納税猶予(措法70の4、70の6)や非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(措法70の7、70の7の2)においては、税務署長への通知とは関係なく通知を行うべき事実が生じた日の翌日から2月を経過する日に納税猶予に係る期限が到来することからこの点で異なっている。
また、上記の第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合において、その該当することとなった日以後通知が到達する日までの間にその林業経営相続人が死亡した場合には、上記の納税猶予に係る期限はその林業経営相続人の死亡の日の前日から2月を経過する日に到来することとなる(措令40の7の4![]() )。これは、通知を行うべき事実の発生から通知があった日までの間に林業経営相続人が死亡した場合には、本来納付すべき納税猶予税額がその死亡により免除されてしまうことから規定されているもので、ただし書きにおいては、このことを留意的に明らかにした。
)。これは、通知を行うべき事実の発生から通知があった日までの間に林業経営相続人が死亡した場合には、本来納付すべき納税猶予税額がその死亡により免除されてしまうことから規定されているもので、ただし書きにおいては、このことを留意的に明らかにした。
さらに、(注)においては、措置法第70条の6の4第4項に該当する場合においても上記と同様であることからその旨を留意的に明らかにした。
なお、措置法令第40条の7の4第13項のような読み替え規定は、措置法第70条の6の4第4項に関してはないことから(注)のカッコ書きにおいてそのことを留意的に明らかにした。
(参考)
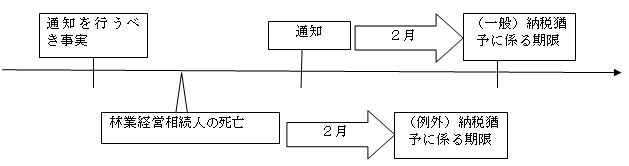
- (譲渡をした特例山林の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
- 70の6の4-12 措置法第70条の6の4第3項第2号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる算式により行うことに留意する。

(注)
- 1 算式中の符号は次のとおりである。
Aは、相続又は遺贈により取得した特例山林の土地の面積をいう。
Bは、今回、譲渡等(措置法第70条の6の4第3項第2号に規定する譲渡等をいう。以下同じ。)をした又は路網未整備等(同号に規定する路網未整備等をいう。以下同じ。)に該当することとなった特例山林の土地の面積をいい、Cは、既往において譲渡等をした又は路網未整備等に該当した特例山林の土地の面積をいうことに留意する。この場合のB又はCの譲渡等には、措置法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡は含まないことに留意する。 - 2 特例山林の面積が100ヘクタールを下回った場合で措置法第70条の6の4第3項第2号の通知があったときには、上記の算式の割合が100分の20を超えないときであっても猶予中相続税額(同条第2項第7号ロに規定する猶予中相続税額をいう。以下70の6の4-15までにおいて同じ。)の全部につき納税の猶予に係る期限が到来することに留意する。
- 1 算式中の符号は次のとおりである。
(新設)
(説明)
特例の対象となる山林のうち、譲渡等があった又は路網未整備等があった部分の面積の合計が、特例の対象となる山林の面積の20%を超えることとなった場合で措置法70条の6の4第3項第2号の通知があったときには、原則としてその通知があった日から2月を経過する日に納税猶予税額の全部について納税猶予に係る期限が到来することとなる(措法70の6の4![]() 二)。本通達は、その20%を超えるか否かの計算を計算式で示したものである。
二)。本通達は、その20%を超えるか否かの計算を計算式で示したものである。
また、措置法令第40条の7の4第11項第7号においては、特例山林の面積の合計が100ヘクタールを下回ることとなった場合において、その旨の農林水産大臣等の通知が林業経営相続人の納税地の所轄税務署長にあったときには、上記の20%を超えるか否かにかかわらず、原則としてその通知があった日から2月を経過する日に納税猶予税額の全部について納税猶予に係る期限が到来することとされていることから、通達の(注)2においてはそのことを留意的に明らかにした。
- (納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の相続税額の計算)
- 70の6の4-13 措置法第70条の6の4第4項の規定により納税猶予税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合における相続税の額の計算は、同項の規定に該当する直前の猶予中相続税額に次に定める割合を乗ずることにより行うことに留意する。
なお、これにより算出した金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予税額として残ることに留意する。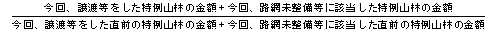
- (注) 特例山林のうち立木のみ又は立木の生育の用に供される土地のみについて譲渡等があった場合には、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても譲渡等があったものとみなして上記算式の分子の特例山林に含めて分子の金額を算定することに留意する。
(新設)
(説明)
措置法第70条の6の4第4項においては、納税猶予期間中に林業経営相続人が特例山林の一部を同条第3項第2号に規定する譲渡等をした場合又は当該特例山林が同号に規定する路網未整備等に該当することとなった場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなった特例山林の金額に対応する部分の額として「一定の額」については、農林水産大臣等から林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があった旨の通知があった日から2月を経過する日(当該通知があった日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)に納税猶予に係る期限が到来することとされている。
また、その「一定の額」については、措置法令第40条の7の4第15項においてその計算方法が規定されている。本通達では、この計算方法を算式により示したものである。
なお、措置法第70条の6の4第5項においては、納税猶予税額の一部について納税猶予に係る期限が到来する場合において、特例山林のうち立木のみ又は立木の生育の用に供されている土地のみについて譲渡等があったときには、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても当該譲渡等があった日において譲渡等があったものとみなすと規定されていることから、そのことを通達の(注)で留意的に明らかにした。
- (林業経営相続人が特例山林についての納税猶予の適用を取りやめる場合の期限)
- 70の6の4-14 措置法第70条の6の4第3項第5号の規定に該当することによる納税の猶予に係る期限は、同条第1項の規定の適用を受けている林業経営相続人から同項の規定の適用を受けることをやめる旨の届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)となることから、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関わらず、当該2月を経過する日に到来することに留意する。
(新設)
(説明)
措置法第70条の6の4第3項第5号においては、林業経営相続人が同条第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出があった日から2月を経過する日(当該届出書の提出があった日から当該2月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日をいう。)に納税の猶予に係る期限が到来することとされている。したがって、当該届出書の提出があった場合には、当該納税猶予に係る相続税の額及び当該相続税の額に係る利子税の額の納付の有無に関らず当該届出書の提出があった日から2月を経過する日に納税の猶予に係る期限が到来することになる。本通達は、その旨を留意的に明らかにしたものである。
- (増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
- 70の6の4-15 措置法第70条の6の4第12項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、担保不足に対応する納税猶予に係る税額だけでなく、猶予中相続税額の全額について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。
(新設)
(説明)
増担保命令等に応じないため納税の猶予に係る期限を繰り上げる場合の納税猶予税額の取扱いについて留意的に明らかにしたものである。
- (継続届出書の提出期間)
- 70の6の4-16 措置法第70条の6の4第9項に規定する届出書は、措置法第70条の6の4第2項第7号に規定する経営報告基準日の翌日から5月を経過するごとの日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、当該経営報告基準日の翌日から当該5月を経過するごとの日までの期間として取り扱う。
(新設)
(説明)
措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、申告期限の翌日から猶予中相続税額の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から5月を経過する日をいう。)までに、引き続いてこの特例の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項等の措置法令第40条の7の4第16項及び措置法規則第23条の8の4第21項の規定による記載事項を記載した届出書(以下「継続届出書」という。)並びに同条第20項に規定する添付書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(措法70の6の4![]() 、措令40の7の4
、措令40の7の4![]() 、措規23の8の4
、措規23の8の4![]() 、
、![]() )。
)。
そして、この継続届出書の提出がない場合には、原則として納税猶予が打ち切られ、当該届出期限の翌日から2月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があったことを知った日の翌日から6月を経過する日)に納税に係る期限が到来することとされている(措法70の6の4![]() )。
)。
この継続届出書の提出期限については、その期限(終期)は明らかであるが、いつから提出できるのか(始期)は必ずしも明らかではない。そこで、継続届出書が直近の経営報告基準日間の特定森林経営計画に従った適正かつ確実な林業経営を確認するものであることから、本通達では、当該直近の経営報告基準日を提出期間の始期として取り扱うこととしたものである。
(参考)