2 被相続人の共有する土地が被相続人等の居住の用と貸付事業の用に供されていた場合
問 被相続人甲は、配偶者乙と共有する土地の上に建物2棟を所有し、1棟(A建物)は甲と乙の居住の用に供し、他の1棟(B建物)は甲の貸付事業の用に供していた。
乙は、甲が所有する土地の共有持分、A建物及びB建物を相続により取得し、A建物は引き続き居住の用に供し、B建物は、甲の貸付事業を引き継ぎ、引き続き貸付事業の用に供している。
この場合に特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等に該当する部分はどの部分となるか。
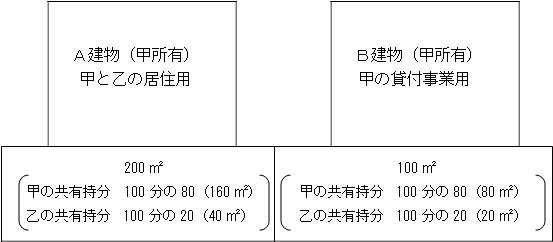
甲と乙の居住の用に供されていた部分に相当する宅地の相続税評価額 30,000,000円
甲の貸付事業の用に供されていた部分に相当する宅地の相続税評価額 11,000,000円
答
一般的に、土地の共有持分権者がその土地に有する権利は、その土地のすべてに均等に及ぶと解されている。そうすると、本件の場合は、土地に係る甲の共有持分は、A建物の敷地とB建物の敷地に均等に及んでいると考えるのが相当である。
したがって、乙が取得した甲の共有持分のうち、A建物の敷地部分に相当する部分(160![]() )が特定居住用宅地等として、B建物の敷地部分に相当する部分(80
)が特定居住用宅地等として、B建物の敷地部分に相当する部分(80![]() )が貸付事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を選択することができる。
)が貸付事業用宅地等として、小規模宅地等の特例の適用を選択することができる。
ただし、小規模宅地等の特例の適用に当っては、限度面積要件があるため、乙が取得した特例の選択が可能な部分のすべてを小規模宅地等の特例の適用対象として選択することはできない。
仮に、特定居住用宅地等(160![]() )のすべてと貸付事業用宅地等(80
)のすべてと貸付事業用宅地等(80![]() )のうち(66.66
)のうち(66.66![]() )を選択して、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))及び第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))の記載は次頁のとおり。
)を選択して、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の相続税の申告書第11・11の2表の付表2の1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その1))及び第11・11の2表の付表2の2(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その2))の記載は次頁のとおり。
なお、相続税の申告書第11・11の2表の付表2の3(小規模宅地等についての課税価格の計算明細(その3))は、次の![]() 又は
又は![]() に該当する場合に作成することとされていることから、本件の場合はその作成を要しない。
に該当する場合に作成することとされていることから、本件の場合はその作成を要しない。
![]() 相続又は遺贈により一の宅地等を2以上の相続人又は受遺者が取得している場合
相続又は遺贈により一の宅地等を2以上の相続人又は受遺者が取得している場合
![]() 一の宅地等の全部又は一部が、貸家建付地である場合において、貸家建付地の評価額の計算上「賃貸割合」が「1」でない場合
一の宅地等の全部又は一部が、貸家建付地である場合において、貸家建付地の評価額の計算上「賃貸割合」が「1」でない場合
※ 一の宅地等とは、一棟の建物又は構築物の敷地をいう。ただし、マンションなどの区分所有建物の場合には、区分所有された建物の部分に係る敷地をいう。
〔甲の共有持分の利用状況〕
A建物(居住用)の敷地部分 ![]()
B建物(貸付事業用)の敷地部分 ![]()
〔甲の共有持分の価額〕
A建物の敷地部分 ![]()
B建物の敷地部分 ![]()
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。