「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
○ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
措置法第36条の2《特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
※ アンダーラインを付した部分が改正関係部分である。
【新設】
(譲渡に係る対価の額が2億円を超えるかどうかの判定)
36の2−6の2 措置法第36条の2第1項に規定する譲渡資産の譲渡に係る対価の額(以下この項において「譲渡対価」という。)が2億円を超えるかどうかの判定は、次により行うものとする。
(1) 譲渡資産が共有である場合は、各所有者ごとの譲渡対価により判定する。
(2) 譲渡資産が店舗兼住宅等及びその敷地の用に供されている土地等である場合は、その居住の用に供している部分に対応する譲渡対価により判定し、この場合の譲渡対価の計算については、次の算式により行う。
イ 当該家屋のうち居住の用に供している部分の譲渡対価の計算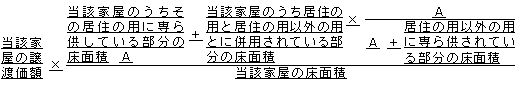
ロ 当該土地等のうち居住の用に供している部分の譲渡対価の計算
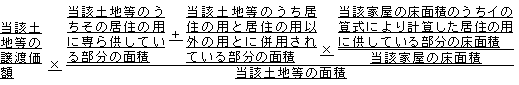
ただし、これにより計算したその居住の用に供している部分がそれぞれ当該家屋又は当該土地等のおおむね90%以上である場合において、31の3−8に準じて当該家屋又は当該土地等の全部をその居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うときは、当該家屋又は当該土地等の全体の譲渡価額により判定する。
(3) 災害により滅失したその居住の用に供している家屋の敷地の用に供されていた土地等に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合において、所得税基本通達33−4《固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》及び33−5《極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得》により譲渡所得となる部分について措置法第36条の2第1項の規定を適用する場合は、その譲渡に係る対価の額のうち譲渡所得となる部分の対価の額により判定する。
(4) 家屋の所有者と当該家屋の敷地の用に供されている土地等の所有者が異なる場合において、36の2−19により、これらの者がともに措置法第36条の2第1項の規定の適用を受ける旨の申告をするときは、当該家屋の譲渡価額と当該土地等の譲渡価額の合計額により判定する。
≪説明≫
措置法第36条の2第1項は「個人が、平成5年4月1日から平成23年3月31日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡資産の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えるもの・・・を除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合」と規定し、更に、同項第1号から第4号において「譲渡資産」の範囲を次のように定めている。
 当該個人が居住の用に供している家屋(当該個人が居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
当該個人が居住の用に供している家屋(当該個人が居住の用に供している期間として政令で定める期間が10年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
 に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったもの(当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
 又は
又は に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等 当該個人の
当該個人の に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る。)
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる「譲渡資産」は、地価等土地対策との整合性を図りつつ、その譲渡の範囲を一般サラリーマンが通常に住替える場合に適用されるものに限定するという趣旨等から、平成9年分譲渡まで譲渡に係る対価の額が2億円以下のものであることの要件が付されていたところであるが、平成10年度税制改正において、地価対策上の要請から設けられた要件を緩和したとしても、直ちに地価への悪影響を及ぼすおそれはないと考えられ、また、住宅を巡る諸状況に配慮するとともに、ライフサイクルに応じた住替えを促進する観点から、同要件が廃止されていたところである。しかし、税制調査会の「租税特別措置の見直しに関する基本方針」(平成21年11月17日)に従って議論が行われた平成22年度税制改正において、譲渡資産の譲渡について、高額の譲渡益が生じるケースについてまで課税を行わない(課税を繰り延べる)ことは税負担の公平性の観点から問題ではないかといった指摘があったことから、再び譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えないものであることの譲渡価額要件が付されることとなった。
ところで、譲渡価額要件の2億円の判定は、![]() 譲渡資産が例えば、夫と妻、親と子、兄弟又は祖父母と孫の共有物である場合には、各所有者ごとに行うのか、
譲渡資産が例えば、夫と妻、親と子、兄弟又は祖父母と孫の共有物である場合には、各所有者ごとに行うのか、![]() 譲渡資産が店舗兼住宅等である場合には、譲渡資産の全体で行うのか又は住宅部分のみで行うのか、
譲渡資産が店舗兼住宅等である場合には、譲渡資産の全体で行うのか又は住宅部分のみで行うのか、![]() 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合において、当該譲渡による所得が事業所得又は雑所得と譲渡所得に該当するときは、譲渡価額要件の2億円の判定をどのように行うのか、
災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合において、当該譲渡による所得が事業所得又は雑所得と譲渡所得に該当するときは、譲渡価額要件の2億円の判定をどのように行うのか、![]() 譲渡資産である家屋と土地等の所有者が異なる場合には、どのように行うのかという問題が生ずる。
譲渡資産である家屋と土地等の所有者が異なる場合には、どのように行うのかという問題が生ずる。
本通達は、これらの場合における譲渡価額要件の2億円の判定方法を次のように行うことを明らかにしている。
- (1) 特定の居住用財産の買換えの特例の適用対象となる譲渡資産は、措置法第36条の2第1項が「個人が、・・・・・・その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、・・・・・・次に掲げるものの譲渡」と規定していることからも明らかなように、その者自身の所有資産であることに疑問の余地はない。したがって、2億円の譲渡価額要件についても他の共有者の譲渡価額を含める余地はないことから、当該譲渡資産が共有の場合であっても、各所有者ごとの譲渡対価により判定することとなる。
- (2) 譲渡資産が店舗兼住宅等である場合において、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる部分について措置法令第24条の2第7項は「第20条の3第2項の規定は、法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。」と規定されていることから、店舗兼住宅等のうち譲渡者が居住の用に供している部分の譲渡対価の額、具体的には、本通達に定める算式により計算することとなる。
なお、この算式により計算した居住の用に供している部分が、31の3−8《店舗等部分の割合が低い家屋》に定める90%基準の取扱いにより、譲渡資産の全体が居住の用に供していると取り扱われる場合は、譲渡資産の全体の譲渡対価の額により判定することとなる。 - (3) 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供していた土地等に区画形質の変更等を加えて譲渡(例えば、災害跡地に建売住宅を建設して分譲)した場合の所得は、原則として事業所得又は雑所得に該当するのである(所基通33−4)が、当該区画形質の変更等に係る土地等が極めて長期間(おおむね10年以上)引き続き所有されていたものであるときは、区画形質の変更等による加工利益に対応する部分は事業所得又は雑所得、その他の部分は譲渡所得として差し支えないことと取り扱われている(所基通33−5)ことから、後段の取扱いによる場合において、譲渡価額要件の2億円をどのように判定するのかという問題が生ずる。
この点については、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる所得は、「居住用財産を譲渡した場合の課税の特例(措法31の3)」と同様に譲渡の年の1月1日において所有期間が10年超の長期譲渡所得であることから、災害跡地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合には、31の3−14《災害滅失家屋の跡地等の用途》の取扱いと同様に、当該譲渡による所得のうち譲渡所得(事業所得又は雑所得に該当するものを除く。)に該当する部分の譲渡対価の額により判定する。 - (4) 譲渡資産である家屋と土地等の所有者が異なる場合は、これらの者がともに「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける旨の申告をした場合に限り、この特例の適用を受けることができることとされている(36の2−19《居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い》)ので、その場合には、家屋の譲渡対価の額と土地等の譲渡対価の額の合計額で判定する。そもそも「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用対象となる譲渡資産は、所有者が居住の用に供している家屋を核として構成されていることから、譲渡家屋の所有者と当該家屋の敷地の用に供されている譲渡土地等の所有者が異なる場合には、土地等に係る譲渡所得については、この特例の対象外となるのが制度上の原則であるが、他の居住用財産の譲渡に係る特例(措法31の3、35、41の5、41の5の2)においても、譲渡家屋と譲渡土地等の所有者が親族関係にあり、これらの者がともに譲渡家屋に同居して生計を一にしている(一の生活共同体の居住用財産とみることができる。)場合で、かつ、これらの者がともに当該特例の適用を受ける旨の申告をしたときは、譲渡土地等も特例の適用対象資産として取り扱われている(31の3−19《居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い》等)ことから、譲渡家屋の所有者と当該家屋の敷地の用に供されている譲渡土地等の所有者がともに措置法第36条の2第1項の規定の適用を受ける旨の申告をする場合は、当該家屋の譲渡対価の額と当該土地等の譲渡対価の額の合計額により判定することになる。