[ 連結納税関連 ]
第1 連結納税基本通達関係
8 譲渡損益調整額の戻入れ
(譲渡損益調整額の戻入れ事由)
14−3−1 令第155条の22第2項第1号《連結法人間取引の損益の調整》に規定する「その他これらに類する事由が生じた場合」には、例えば、次に掲げる譲渡損益調整資産につき、それぞれ次に掲げる事由が生じた場合が該当する。
(1) 金銭債権 その譲渡を受けた連結法人(以下14−3−1及び14−3−3において「譲受法人」という。) においてその全額が回収された場合又は2−1−37《債権の取得差額に係る調整差損益の計上》の取扱いの適用を受けた場合
(2) 償還有価証券 譲受法人においてその全額が償還期限前に償還された場合
(3) 固定資産 譲受法人において災害等により滅失した場合
(注) 同号の「譲渡」には、次の場合が含まれる。
1 令第119条の11の表の第2号の上欄《有価証券の区分変更によるみなし譲渡》に掲げる満期保有目的等有価証券又は同表の第3号の上欄に掲げるその他有価証券について、当該各号の中欄に掲げる事実が生じたことにより譲受法人が当該有価証券を譲渡したものとみなされた場合
2 令第119条の11の2第1項《分離適格振替有価証券の元利分離等によるみなし譲渡等》に規定する次の有価証券について、その譲受法人がそれぞれ次の事実に該当することになったことにより当該有価証券を譲渡したものとみなされた場合
(1) 分離適格振替有価証券 その譲受法人が当該有価証券について同項に規定する元利分離を行ったこと
(2) 分離元本振替有価証券又は分離利息振替有価証券 その譲受法人がこれらの有価証券について同条第2項に規定する統合を行ったこと
【解説】
連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に譲渡した譲渡損益調整資産について、その譲受法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却のほか、「その他これらに類する事由」が生じた場合には、その態様に応じ、その譲渡に係る譲渡損益調整額について一定額の戻入れを行うこととされている(法81の10![]() )。本通達は、この譲渡損益調整額の戻入れ事由となる「その他これらに類する事由が生じた場合」の具体例を示したものである。
)。本通達は、この譲渡損益調整額の戻入れ事由となる「その他これらに類する事由が生じた場合」の具体例を示したものである。
(1)では、譲渡損益調整資産が金銭債権である場合は、当該金銭債権を有する譲受法人においてその全額が回収されたときには当該金銭債権が消滅することから、金銭債権の全額回収が譲渡損益調整額の戻入れ事由に該当することを明らかにしている。したがって、当該金銭債権に係る一部返済があっても、当該譲渡損益調整額の戻入れは行わないこととなる。
また、金銭債権をその債権金額に満たない価額又は債権金額を超える価額で譲受法人に譲渡した場合には、譲渡法人において売却価額と当該債権の帳簿価額との差額が譲渡損益調整額として処理されることとなるが、一方で、譲受法人においては、その取得価額と債権金額の差額についていわゆるアキュムレーション(益金計上)又はアモチゼーション(損金計上)が行われることから、譲渡法人は譲渡損益調整額の戻入れ計算を行う必要がある。そのため、譲受法人におけるアキュムレーション又はアモチゼーションが譲渡損益調整額の戻入れ事由に該当することを明らかにしている。なお、この場合における譲渡損益調整額の戻入れ計算は、当該金銭債権の最終の支払期日までの期間に応じて行うこととなる(連基通14−3−3)。
(2)では、譲受法人の有する償還有価証券が償還期限前にその券面額の全額が償還された場合には、その償還有価証券が消滅することからその期限前の全額償還が譲渡損益調整額の戻入れ事由に該当することを明らかにしている。
(3)では、譲受法人の有する固定資産が災害などで滅失した場合には、その時において帳簿価額相当額が損失として損金計上されることからその滅失が譲渡損益調整額の戻入れ事由に該当することを明らかにしている。
なお、本通達の(注)においては、譲受法人の有する譲渡損益調整資産である有価証券について、法人税法施行令第119条の11《有価証券の区分変更によるみなし譲渡》又は第119条の11の2《分離適格振替有価証券の元利分離等によるみなし譲渡等》の規定により譲渡があったものとみなされた場合の当該譲渡についても譲渡損益調整額の戻入れ事由における「譲渡」に該当することを念のため明らかにしている。
(金銭債権の一部が貸倒れとなった場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)
14−3−4 連結法人が他の連結法人に対して譲渡した譲渡損益調整資産である金銭債権について、当該他の連結法人において8−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の取扱いにより当該金銭債権の一部が貸倒れとなった場合の当該連結法人における法第81条の10第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により損金の額に算入する金額は、例えば、当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該他の連結法人の当該金銭債権の取得価額のうちに当該貸倒れによる損失の額の占める割合を乗じて計算した金額とする等合理的な方法により計算した金額とする。
(注) 債権金額に満たない価額で取得した債権の一部について8−6−1の事実が生じたことにより貸倒れとして損金の額に算入される金額は、この事実が生じた後においてなお有することとなる債権金額が取得価額を下回る場合のその下回る部分の金額となる。
【解説】
本通達は、金銭債権を譲り受けた連結法人が、その一部を貸倒れ処理した場合の譲渡法人における譲渡損益調整額の戻入れ計算について明らかにしたものである。
連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に譲渡損益調整資産を譲渡したことに伴って生じた譲渡損益調整額に係るその後の戻入れ計算は、譲受法人において譲渡、償却、評価換え又は貸倒れ等の事由が生じた場合に行うこととされている(法81の10![]() )。譲渡損益調整資産が金銭債権で、その譲渡の後に、連結納税基本通達8−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の取扱いにより譲受法人においてその一部を貸倒れ処理した場合に、当該金銭債権の全額が貸倒れとなっていないことをもって戻入れ事由が生じていないとみるのか、それともその貸倒れ処理した部分の金額に応じて譲渡損益調整額の戻入れを行うのかといった問題がある。
)。譲渡損益調整資産が金銭債権で、その譲渡の後に、連結納税基本通達8−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の取扱いにより譲受法人においてその一部を貸倒れ処理した場合に、当該金銭債権の全額が貸倒れとなっていないことをもって戻入れ事由が生じていないとみるのか、それともその貸倒れ処理した部分の金額に応じて譲渡損益調整額の戻入れを行うのかといった問題がある。
この点、金銭債権の一部が法的に消滅した場合には、税務上、同通達の取扱いによりその消滅した部分を、貸倒れとして取り扱っていることを踏まえ、本通達の本文では、![]() 金銭債権の一部貸倒れについても戻入れ事由に該当すること及び
金銭債権の一部貸倒れについても戻入れ事由に該当すること及び![]() その場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算の方法を明らかにしている。
その場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算の方法を明らかにしている。
また、本通達の(注)では、債権金額に満たない価額で取得した債権につき会社更生法等の規定によりその債権の一部が切り捨てられた場合における「貸倒れによる損失の額」は、その切捨て後の債権金額が当該譲受法人の取得価額を下回るときのその下回る部分の金額となることを明らかにしている。
これは、その切捨て後の債権金額が当該譲受法人の取得価額を下回らない場合には当該譲受法人においては貸倒れによる損失の額が生じないことから譲渡損益調整額の戻入れを行う必要はないことを間接的に示している。
(土地の一部譲渡に係る譲渡損益調整額の戻入れ計算)
14−3−5 連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産である土地について、当該他の連結法人がその一部を譲渡した場合の当該連結法人における法第81条の10第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該土地に係る譲渡損益調整額のうち当該他の連結法人が譲渡した土地に係るものとして、例えば、当該譲渡損益調整額を当該連結法人が譲渡した土地の面積と当該他の連結法人が譲渡した土地の面積の比に応じて区分する等合理的な方法により計算した金額とする。
【解説】
本通達は、連結法人が譲渡損益調整資産である土地を譲渡し、譲受法人が当該土地の一部を分筆して譲渡した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算を明らかにしたものである。
譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の調整は、連結納税制度が複数の法人を一の納税単位として課税する制度であることから、連結グループ内の法人間で一定の資産を譲渡した場合にはその譲渡損益に係る課税を繰り延べるとともに、当該資産につき、譲受法人において譲渡、償却等の事実が生じたときにその譲渡損益の実現(いわゆる譲渡損益調整額の戻入れ)をさせようとするものである。この譲渡損益調整額の戻入れ額については、譲渡、償却等の戻入れ事由に応じてその計算を行うこととされており、例えば、譲受法人が当該資産を譲渡した場合には、その譲渡損益調整額の全額を戻し入れることとされている(令155の22![]() 八)。
八)。
ところで、連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に対して譲渡損益調整資産である土地を譲渡した後、その譲受法人が当該土地の一部を分筆して譲渡した場合には、たとえ当該土地の一部譲渡であっても法人税法施行令第155条の22第3項第8号《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により「譲渡損益調整額の全額」の戻入れが必要との考えも生じ得る。
しかし、当初に譲渡された土地のうち、その一部分が切り売りされた場合などについてもその譲渡という事実のみを形式的にとらえて、譲渡損益調整額の全額を戻し入れるのは実態にそぐわない。むしろ、譲渡法人が譲渡した土地につき、譲受法人がその一部を分筆して譲渡した場合には、譲渡法人においても分筆されたそれぞれの土地に対応する譲渡損益調整額の計上があったものとしてその戻入れ計算を行うのが実態に則しているものと考える。このことから、本通達では、その譲渡された部分に係る譲渡損益調整額を戻し入れることを明らかにするとともに、その譲渡された部分に係る譲渡損益調整額の合理的な算定方法の一つとして面積按分による方法を例示している。
(同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算)
14−3−6 連結法人が譲渡損益調整資産である銘柄を同じくする有価証券を2回以上にわたって他の連結法人に対し譲渡した後に当該他の連結法人が当該有価証券を譲渡した場合には、当該連結法人における譲渡損益調整額の戻入れ計算は、当該他の連結法人が当該連結法人から最も早く取得したものから順次譲渡したものとみなして、令第155条の22第3項第6号《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定を適用する。
【解説】
本通達では、連結法人が譲渡損益調整資産に該当する同一銘柄の有価証券を2回以上にわたり譲渡した場合において、譲受法人がこれを譲渡したときの譲渡損益調整額の戻入れ額の計算方法について明らかにしたものである。
連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に対し譲渡損益調整資産である有価証券を譲渡し、その後、譲受法人が当該有価証券を譲渡した場合には、譲渡法人は当該有価証券に係る譲渡損益調整額の戻入れを行うことになる。ただし、譲受法人が![]() 譲渡法人において譲渡損益調整資産に該当する有価証券と
譲渡法人において譲渡損益調整資産に該当する有価証券と![]() これに該当しない同一銘柄の有価証券との双方を有する場合には、まず、譲受法人が
これに該当しない同一銘柄の有価証券との双方を有する場合には、まず、譲受法人が![]() の有価証券から譲渡したものとして、譲渡損益調整額の戻入れ計算を行うこととされている(令155の22
の有価証券から譲渡したものとして、譲渡損益調整額の戻入れ計算を行うこととされている(令155の22![]() 六)。
六)。
ところで、連結法人(譲渡法人)が同一銘柄の有価証券を同一の他の連結法人(譲受法人)に対し複数回にわたって譲渡した後、その譲受法人が当該有価証券を譲渡した場合には、その譲渡損益調整額の戻入れの計算をどのように行うのかという問題がある。また、どの有価証券から譲渡したかを連結法人(譲渡法人)が任意に選択できることとした場合には、有価証券の譲渡に係る譲渡損益調整額は、これが同一銘柄の有価証券であっても一般的にはその譲渡ごとに異なることから、恣意的な連結所得の金額の計算を認める結果となる。
そこで、本通達においては、同一の連結法人が行った複数の譲渡に伴い生じた譲渡損益調整額はその発生の古いものから順次、戻入れの実現をさせることとし、譲受法人が最も早い連結法人間の譲渡により取得した有価証券から譲渡したものとして譲渡損益調整額の戻入れ計算を行うことを明らかにしている。
なお、複数の連結法人から同一銘柄の有価証券の譲渡を受けた譲受法人がこれらのうちの一部を譲渡した場合においても、上記と同様に、その譲受法人がその発生の最も古い連結法人間の譲渡により取得した有価証券から譲渡したこととして戻入れ計算を行うこととなる。
(有価証券の評価損を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)
14−3−7 令第155条の22第3項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定の適用に当たり、同項第4号に規定する譲渡損益調整資産が有価証券である場合には、当該有価証券に係る譲渡損益調整額のうち同項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、次の算式により計算した金額とする。
(算式)
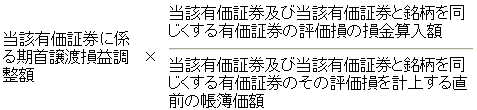
【解説】
本通達は、譲渡損益調整資産たる有価証券の譲渡後、その譲受法人においてその有価証券の評価損が計上された場合のその譲渡法人における戻入れ額の計算について明らかにしたものである。
譲渡損益調整資産の譲渡後、その譲受法人において当該資産の評価換えにより評価損が計上された場合には、その譲渡法人は譲渡損益調整額に譲受法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに評価損の額の占める割合を乗じた金額の戻入れを行うこととされている(令155の22![]() 四)。このことは、譲渡損益調整資産が有価証券である場合であっても異なるものではないが、譲受法人においては
四)。このことは、譲渡損益調整資産が有価証券である場合であっても異なるものではないが、譲受法人においては![]() 同一銘柄の有価証券のうちに連結法人間取引により取得したものとそうでないものとが混在している場合があること、
同一銘柄の有価証券のうちに連結法人間取引により取得したものとそうでないものとが混在している場合があること、![]() 有価証券の譲渡原価の計算を行う場合のその一単位当たりの帳簿価額は、取得又は譲渡を行うごとに移動平均法や総平均法の計算により修正されること、
有価証券の譲渡原価の計算を行う場合のその一単位当たりの帳簿価額は、取得又は譲渡を行うごとに移動平均法や総平均法の計算により修正されること、![]() 保有する同一銘柄の有価証券のすべてを対象に評価損の額の計算が行われることから、戻入れ額の計算の基礎とすべき「有価証券のうち譲渡損益調整資産に該当するものに係る評価損の額」を特定することは、実務上、困難である。
保有する同一銘柄の有価証券のすべてを対象に評価損の額の計算が行われることから、戻入れ額の計算の基礎とすべき「有価証券のうち譲渡損益調整資産に該当するものに係る評価損の額」を特定することは、実務上、困難である。
ところで、譲受法人の有する有価証券の期末帳簿価額は、譲渡法人から取得した有価証券の取得価額と譲渡法人以外の者から取得した有価証券の取得価額を基礎として計算されることとなるため、評価損の額についてもこれら有価証券のすべてに係る期末帳簿価額について減額することとなる。このことから、「有価証券のうち譲渡損益調整資産に該当するものに係る評価損の額」は評価損を計上する直前の帳簿価額から平均的に損金算入されたものとしてその戻入れ額の計算を行うこととした。本通達は、このことを明らかにしている。
なお、評価損の計上される前に当該有価証券の一部が譲渡されている場合には、その譲渡された部分に係る譲渡損益調整額については既に戻し入れが行われていることから、当然のことながら、期首譲渡損益調整額を基礎としてその戻入れ計算を行うこととなる。
(譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用)
14−3−8 令第155条の22第5項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定の適用については、連結法人が連結事業年度において他の連結法人に対し複数の減価償却資産(当該他の連結法人において減価償却資産に該当することとなるものに限る。以下14−3−8において同じ。) を譲渡した場合であっても、個々の減価償却資産ごとに同項の規定を適用をすることができる。
連結法人が当該連結事業年度において他の連結法人に対し複数の繰延資産の譲渡を行った場合についても、同様とする。
【解説】
本通達は、連結法人が同一の連結事業年度において複数の減価償却資産又は繰延資産を他の連結法人に譲渡した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の適用単位を明らかにしたものである。
連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に対して譲渡損益調整資産である減価償却資産を譲渡したことに伴い生じた譲渡損益調整額の戻入れ計算については、原則として、その譲渡損益調整額に譲受法人における当該減価償却資産の取得価額のうちに当該減価償却資産につき損金の額に算入された減価償却費の額の占める割合を乗じて計算される金額を戻し入れることとされている(令155の22![]() 二)。
二)。
一方、当該減価償却資産(譲受法人においても減価償却資産となるものに限る。)について譲受法人が適用する耐用年数を基礎としてその戻入れ額の計算を行う方法(いわゆる簡便法)によることもできるとされている(令155の22![]() )。
)。
ところで、同一連結事業年度に譲渡損益調整資産に該当する複数の減価償却資産を譲渡した場合の簡便法は、譲渡した個々の減価償却資産ごとに適用できるのか、あるいはその連結事業年度において譲渡した譲渡損益調整資産に該当するすべての減価償却資産について適用すべきか問題となる。
この点について、法令上は簡便法による譲渡損益調整額の戻入れ計算は、例えば、種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額の計算(規18)のようにその適用単位について要件を付しているわけではないことから、個々の譲渡資産ごとに簡便法の適用ができることとなる。
なお、譲渡損益調整資産が繰延資産である場合の簡便法の適用単位についても同様の考え方によって取扱うこととなる。
(譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算)
14−3−10 連結法人が令第155条の22第8項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定を適用するに当たり、同項に規定する譲渡損益調整資産を譲り受けた他の連結法人が当該譲渡損益調整資産についてその譲受日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下14−3−10において「連結事業年度等」という。) 後の連結事業年度等において、令第57条《耐用年数の短縮》の規定により当該減価償却資産の耐用年数を短縮することの承認を受けたときには、当該承認を受けた日の属する当該連結法人の連結事業年度及びその後の連結事業年度等における令第155条の22第5項第1号ロ(令第122条の14第6項第1号ロ《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定を含む。) の耐用年数は、当該承認に基づく耐用年数となることに留意する。
【解説】
本通達は、譲渡損益調整額の戻入れ計算につき簡便法を選択した減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の戻入れ計算について明らかにしたものである。
連結法人(譲渡法人)が他の連結法人(譲受法人)に対して譲渡損益調整資産である減価償却資産を譲渡した場合において、譲渡法人がその譲渡損益調整額につき戻入れ計算を行う場合の計算方法として、譲受法人がその減価償却資産について適用する耐用年数を基礎として計算する方法(いわゆる簡便法)がある。そして、この簡便法の適用単位について、譲渡した譲渡損益調整資産ごとに適用できることを連結納税基本通達14−3−8《譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用》において明らかにしている。
ところで、譲受法人の譲り受けた譲渡損益調整資産である減価償却資産が陳腐化等によりその使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短くなった場合には、所轄国税局長の承認を受けることを要件として、その承認に係る使用可能期間をもって法定耐用年数とみなされることとされている(令57)。
譲受法人が当該耐用年数の短縮の承認を受けた場合における譲渡法人の簡便法による戻入れ計算は、引き続き、当該承認前に適用していた耐用年数を基礎として計算を行うのか、それとも当該承認後の短縮された耐用年数を基礎として計算を行うのか疑問が生じ得る。
この点、簡便法による計算は譲受法人の適用する耐用年数に基づいて行うものであるからこれが短縮された場合には、当然にその短縮後の耐用年数を基礎として計算することになる。本通達は、このことを念のため明らかにしている。