別紙
預保第61号
平成23年2月7日
国税庁 課税部
課税部長 西村 善嗣 殿
預金保険機構
理事長 田邉 昌徳
金融機関が破綻した場合における預金保険制度による保護の対象外の預金に係る所得税及び法人税の取扱いについて(照会)
Ⅰ 照会の経緯
預金保険機構(以下「機構」といいます。)は、昭和46年7月、預金保険法(以下「預保法」といいます。)に基づき、我が国の預金保険制度の運営主体として政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立された法人です。
預金保険制度は、金融機関が破綻して預金や金融債などの預金保険制度の対象となる預金等の払戻しができなくなった場合などに預金者等を保護し、信用秩序の維持に資することを目的とするものです。
したがって、金融機関が破綻した場合、預金保険制度により預金等の一部は保護されることになりますが、保護されない部分の預金等については、破綻した金融機関に対して倒産手続が適用される結果、その全額が破産配当・弁済金により弁済されるとは限らず、一部が切り捨てられることがあります。
ところで、預金保険制度の対象となる預金等のうち預金については、平時においては寄託債権に該当することから、貸倒引当金を計上したり、預金の元本に対して貸倒損失を計上することは想定されないところです。
しかしながら、金融機関が破綻した場合、上記のとおり、預金であっても元本の一部の返済が受けられないことがあり得ますが、このような場合における預金に係る税務上の取扱いを整理したものは見当たりません。
そこで、預金者の予測可能性に資するため、預金者が破綻した金融機関に預け入れている預金に対する税務上の取扱いを明確にするべく本件照会を行うこととしたところです。
Ⅱ 事実関係
1 預金保険制度による預金者保護の概要等
(1) 金融機関が破綻した場合、預金保険制度の対象となる預金の元本(既に支払われて元本に組み込まれた利息を含み、以下「保護対象預金」といいます。)だけでなく、その預金に係る支払が未だなされていない利息(破綻日までの期間に係るものに限り、以下「経過利息」といいます。)も預金保険制度による保護の対象となります。
しかしながら、保護対象預金及び経過利息(以下「保護対象預金等」といいます。)の全額が保護されるとは限らず、その預金の区分に応じた範囲が設定されています。
具体的には、保護対象預金のうち決済用預金に該当するものは、預金の元本の全額が保護の範囲とされ、決済用預金以外の預金に該当するものは、1金融機関ごとに預金者1人当たりの預金の元本のうち1,000万円以下の部分の金額が保護の範囲とされています(保護対象預金のうちこれらの保護の範囲に該当するものを以下「付保預金」といいます。)。
また、決済用預金以外の保護対象預金に係る経過利息については、付保預金に対応する部分のみが保護の範囲とされています。
以下においては、預金保険制度の保護の範囲となる付保預金とその経過利息を「付保預金等」といいます。
(注)
- 1 預金であっても、外貨預金、無記名預金など一定のものについては保護の対象になりません。
- 2 上記の「決済用預金」とは、無利息、要求払い、決済サービスを提供できることという3要件を満たす預金をいいます。
(2) 保護対象預金のうち付保預金の範囲を超える部分及び保護対象預金に該当しない預金の元本(既に支払われて元本に組み込まれた利息を含みます。以下においてはこれらを合わせて「非付保預金」といいます。)並びに非付保預金に係る支払が未だなされていない利息(以下「未払利息」といい、非付保預金と合わせて「非付保預金等」といいます。)に係る弁済については、民事再生法等の倒産手続による弁済が行われることから、一般的にはその弁済までに長期間を要することが見込まれますので、機構が預金者における預金の早期の流動性の回復の必要があると認める場合には、非付保預金等のうち担保権の目的となっていない預金等債権(以下「非担保債権」といいます。)を買い取ることができます(預保法70)。この非担保債権の買取りによる支払を、以下「概算払」といいます。
(注) 非担保債権に該当するものであっても、他の金融機関から受け入れた預金など一定のものについては、上記の買取りの対象とはなりません。
(3) 非付保預金等を有する預金者((2)による非担保債権の買取りをした機構を含みます。)に対しては、民事再生法等の倒産手続により破綻した金融機関の財産の状況に応じて弁済が行われるとともに、その一部が切り捨てられることがあります。
(注) (2)による非担保債権の買取りをした機構が上記の弁済を受けた場合において、その弁済を受けた金額が(2)の概算払により支払われた金額と非担保債権の買取りに要した一定の費用の合計額を超えるときには、元預金者の不当利得返還請求権の行使に代替するものとして、その超える部分の金額を(2)による非担保債権の買取りに応じた元預金者に対して支払います(預保法70![]() ただし書)。以下においては、この支払を「精算払」といい、この精算払を受ける権利を「精算払受領権」といいます。
ただし書)。以下においては、この支払を「精算払」といい、この精算払を受ける権利を「精算払受領権」といいます。
2 金融機関が破綻した場合の預金の弁済に係る手続
金融機関が破綻した場合の預金者に対する預金の弁済に係る手続は、唯一の手順が定められているわけではありませんが、次の手順で行われることが想定されるため、本件の照会においては、この手順によることを前提とします。
(1) 金融庁長官は、金融機関がその財産をもって債務を完済することができないと認める等一定の要件に該当する場合には、当該金融機関に対し「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」(以下「管理を命ずる処分」といいます。)を行うとともに、機構を金融整理管財人に選任します(預保法74![]() 、77
、77![]() 、78
、78![]() 、139
、139![]() )。
)。
また、管理を命ずる処分があった場合には、当該金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属することとなります(預保法77![]() )。
)。
この管理を命ずる処分があった金融機関を、以下「破綻金融機関」といいます。
(2) 破綻金融機関においては、預金者をはじめとする債権者の間の平等を保ち、財産の流出を防ぐために、預金の払戻しなどの業務に制約を課して財産を保全することが必要となりますので、管理を命ずる処分を受けた日と同日に、裁判所に対して民事再生法における再生手続開始の申立てを行うとともに、財産の保全処分の申立てを行い保全処分命令を受けます(民事再生法21、30)。
ただし、付保預金等については、預金保険制度で保護されるため、裁判所の許可を得ることにより、保全処分の例外として預金者からの請求により再生手続開始の決定があるまでの間、払戻しが認められます(民事再生法30)。
(注) 機構は、破綻金融機関に対する倒産手続として、民事再生法による手続を予定していることから、上記においても同法の手続に従って記載しています(以下における説明についても同様です。)。
(3) 破綻金融機関が民事再生法における再生手続開始の決定を受けた場合には、預金者が再生手続開始前に預け入れた預金も再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権に該当しますので、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない再生債権となります(民事再生法84![]() 、85
、85![]() )。
)。
ただし、付保預金等については、預金保険制度で保護されるため、裁判所の許可を得ることにより、民事再生法第85条の規定にかかわらず、預金者からの請求により、裁判所が定めた一定の期間内において払戻しが認められます(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律473![]()
![]() )。
)。
(4) 機構は、預金者が有する非担保債権を預金者からの請求に基づいて概算払額に相当する金額で買い取ることができます(預保法70![]() )。
)。
この概算払額の算定及び非担保債権の買取りは、次の手続等により行われます。
![]() 機構は、概算払率の算定をする場合、金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば弁済を受けることができると見込まれる額(破産配当見込額)等を考慮しなければならないとされており(預保法71
機構は、概算払率の算定をする場合、金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば弁済を受けることができると見込まれる額(破産配当見込額)等を考慮しなければならないとされており(預保法71![]() )、実務上は、破綻金融機関の資産及び負債について、監査法人による資産査定の結果等を踏まえ清算価値で評価して算定することとなります。
)、実務上は、破綻金融機関の資産及び負債について、監査法人による資産査定の結果等を踏まえ清算価値で評価して算定することとなります。
また、概算払率の決定に当たっては、機構の運営委員会の議決を経た後、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けます(預保法71![]() 、139
、139![]() )。
)。
![]() 機構は、概算払率が決定した場合、概算払に係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法、買取りの取扱時間、買取りの際に機構に提出又は提示すべき書類等を定め、当該概算払率とともに公告します(預保法72
機構は、概算払率が決定した場合、概算払に係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法、買取りの取扱時間、買取りの際に機構に提出又は提示すべき書類等を定め、当該概算払率とともに公告します(預保法72![]() 、同法施行令18)。
、同法施行令18)。
![]() 機構は、買取りを希望する預金者から買取りの請求があった場合、その内容を確認し、速やかに買取代金(以下「概算払額」といいます。)を振り込みます。
機構は、買取りを希望する預金者から買取りの請求があった場合、その内容を確認し、速やかに買取代金(以下「概算払額」といいます。)を振り込みます。
この概算払額は、機構が預金者から買い取る非担保債権の額から、未払利息のうち金融機関の破綻後の期間に対応する利息の額を控除した金額に機構が定める概算払率を乗じて計算した金額により算定されます(預保法70![]() )。
)。
(注) なお、上記の買取りにおいては、預金者から買い取った非担保債権を預金者が買い戻すような権利を付与することはありません。
(5) 民事再生法における再生計画認可の決定が行われた場合には、預金者が有する非付保預金等の一部が切り捨てられるとともに、切り捨てられなかった部分に対する弁済が行われます。
(注)
- 1 この弁済の額は、再生計画において、非付保預金等のうち非付保預金から充当することが定められ、弁済の額が非付保預金の額を超えない限り、未払利息に対する充当は行われない予定です。
- 2 上記(4)により概算払を受けた元預金者においては、上記1(3)の(注)に記載する精算払を受ける場合があります。
Ⅲ 照会事項(照会趣旨)
金融機関が破綻した場合、個人預金者及び法人預金者における税務上の取扱いについては、次のとおりと解してよろしいか伺います。
なお、所得税法及び法人税法上の取扱いにつき、本件照会の対象とするのは、非付保預金等です。
ただし、所得税法上の取扱いについては、個人事業主の所得計算に影響を及ぼす事業の遂行上生じた非付保預金(以下「事業用預金」といいます。)及びその未払利息(事業用預金と合わせ、以下「事業用預金等」といいます。)に限ります。
また、法人税法上の取扱いについては、法人預金者が法人税基本通達2-1-25(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)を準用して、未払利息を益金算入していないことを照会の前提としています。
1 民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合
[所得税法]
個人預金者の有する事業用預金は、所得税法第52条第1項に規定する個別評価貸金等に該当することから、同法施行令第144条第1項第3号に定めるところにより、当該事業用預金の額の100分の50に相当する金額に達するまでの金額を、貸倒引当金として再生手続開始の申立てがあった日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る所得金額(以下「事業所得等の金額」といいます。)の計算上、必要経費に算入することができる。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金は、所得税法の取扱いと同様に算出した貸倒引当金の額を、再生手続開始の申立てがあった日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法法52![]() 、法令96
、法令96![]() 三ロ)。
三ロ)。
(注) 上記の取扱いは、これを適用しようとする年の末日(又は事業年度終了の日)において再生計画認可の決定に至っていない場合に限る。
2 概算払率が決定した場合
(1) 概算払が行われていないとき
[所得税法]
個人預金者の有する事業用預金について概算払率が公告された年の12月31日までに概算払を受けていない場合には、所得税法施行令第144条第1項第2号に定めるところにより、個別評価貸金等に係る取立て等の見込みがないと認められる金額に達するまでの金額を貸倒引当金として、その年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入することができる。この場合における「取立て等の見込みがないと認められる金額」は、事業用預金の額から事業用預金の額に概算払率を乗じて計算した金額を控除した金額とすることができる。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金について概算払率が公告された日を含む事業年度終了の日までに概算払を受けていない場合には、所得税法の取扱いと同様に算出した貸倒引当金の額を、その概算払率を公告した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法法52![]() 、法令96
、法令96![]() 二)。
二)。
(注) 上記の取扱いは、これを適用しようとする年の末日(又は事業年度終了の日)において再生計画認可の決定に至っておらず、かつ、上記1の適用を受けない場合に限る。
(2) 概算払が行われたとき
[所得税法]
個人預金者の有する事業用預金について概算払が行われた場合には、概算払額と概算払の対象となった事業用預金の額との差額については、所得税法第51条第2項の規定による貸倒れによる損失が生じたものとしてその支払を受けた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金について概算払が行われた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度において、概算払額を益金の額に算入するとともに概算払の対象となった非付保預金の額を損金の額に算入する(法法22![]()
![]() )。
)。
3 再生計画認可の決定が行われた場合
(1) 概算払が行われていないとき
[所得税法]
個人預金者が有する事業用預金等について、破綻金融機関の再生計画認可の決定により、事業用預金等の額の一部が切り捨てられることとなった場合には、再生計画認可の決定時に現に有する事業用預金の額から再生計画により弁済を受ける金額を控除した額について、所得税法第51条第2項の規定により貸倒れによる損失が生じたものとして当該認可決定があった日の属する年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する。
この点について、具体例を示せば下図のとおりとなります。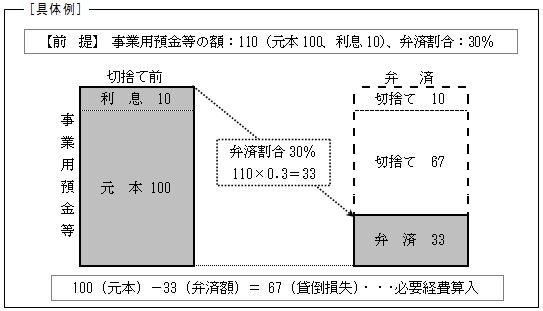
[法人税法]
法人預金者が有する非付保預金等について、破綻金融機関の再生計画認可の決定により、非付保預金等の額の一部が切り捨てられることとなった場合には、再生計画認可の決定時に現に有する非付保預金の額から再生計画により弁済を受ける金額を控除した額について、所得税法の取扱いと同様に、当該認可決定があった日の属する事業年度における貸倒損失の額として損金の額に算入する(法法22![]() 、法基通9-6-1(1))。
、法基通9-6-1(1))。
(2) 精算払を受けたとき
[所得税法]
個人預金者が機構から精算払を受けた場合には、精算払により支払われた金額をその支払を受けた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上総収入金額に算入する(所法36)。
[法人税法]
法人預金者が機構から精算払を受けた場合には、精算払により支払われた金額をその支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する(法法22![]() )。
)。
Ⅳ 理由(照会者の求める見解となることの理由)
1 民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合
[所得税法]
(1) 貸倒引当金の設定対象となる金銭債権は、所得税法第52条第1項に規定する個別評価貸金等と同条第2項に規定する一括評価貸金に区分されています。
(2) このうち、個別評価貸金等とは、事業者が更生計画認可の決定に基づいてその有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権(以下この1において「対象債権」といいます。)で当該事業の遂行上生じたものの弁済を猶予される場合などの一定の場合(以下2までにおいて「一定の場合」といいます。)において、その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる貸金等をいいます。
(3) また、個別評価貸金等に係る損失の見込額として貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として所定の方法により計算した金額(以下2までにおいて「算入限度額」といいます。)は、事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができることとされています(所法52![]() )。
)。
(4) そして、所得税法施行令第144条第1項各号においては、一定の場合ごとに算入限度額が規定されており、民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合には、個別評価貸金等の額の50%に相当する金額を必要経費に算入することができることとされています(所令144![]() 三ロ)。
三ロ)。
(5) したがって、本件照会の事業用預金については、これが「対象債権」に該当すれば、所得税法第52条第1項の規定による貸倒引当金を計上することができることとなります。
(6) この点、一括評価貸金の対象となる債権は、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」と規定されるとともに(所法52![]() )、「保証金、敷金、預け金その他これらに類する金銭債権」といった寄託債権は除かれることが明らかにされており(所基通52-17(1))、預金についても一括評価貸金の対象となる債権に該当しないものと解されるところです。このため、個別評価貸金等の対象債権からも預金は除かれるのではないかとの疑問が生ずるところです。
)、「保証金、敷金、預け金その他これらに類する金銭債権」といった寄託債権は除かれることが明らかにされており(所基通52-17(1))、預金についても一括評価貸金の対象となる債権に該当しないものと解されるところです。このため、個別評価貸金等の対象債権からも預金は除かれるのではないかとの疑問が生ずるところです。
(7) しかしながら、個別評価貸金等の対象債権は、「売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権」と一括評価貸金の対象となる債権に比して、前渡金と前渡金に準ずる金銭債権を含む広い概念として規定され(所法52![]() )、建物等の賃借りのために差し入れたものではありますが「保証金、敷金、預け金等の金銭債権」という寄託債権が個別評価貸金等の対象債権に含まれることが例示的に明らかにされているところからすれば(所基通52-1(3))、預金についても個別評価貸金等の対象債権に含まれるものと考えられます。
)、建物等の賃借りのために差し入れたものではありますが「保証金、敷金、預け金等の金銭債権」という寄託債権が個別評価貸金等の対象債権に含まれることが例示的に明らかにされているところからすれば(所基通52-1(3))、預金についても個別評価貸金等の対象債権に含まれるものと考えられます。
(8) したがって、本件照会の事業用預金についても、民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合には、事業用預金の額の50%に相当する金額を必要経費に算入することができると解することが相当です(所法52![]() 、所令144
、所令144![]() 三ロ)。
三ロ)。
(9) なお、会計上も、預金は金銭債権に該当すると解されるところ、破綻金融機関に対する預金は貸倒見積高の算定において破産更生債権等に該当することから、その預金の額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額した残額により貸倒見積高を算定することとされているところです(金融商品に関する会計基準27(3)、28(3)、金融商品会計に関する実務指針116)。
(注)
- 1 どのような預金が事業用預金に該当するかは、個々の事実関係によることとなりますが、少なくとも家事用の資金が混在することなく事業用の資金として明確に区分管理されていることが必要と考えます。
例えば、「普通預金などの流動性を有する預金のうち、その事業の遂行上生じた売上金が当該預金口座に入金され、これをその事業に係る必要経費の支払(決済)のためのみに用いているなど、専ら事業用の資金(運転資金)として預けていることが明らかなものであって、家事用の預金とは別に開設されているもの」は事業用預金に該当するものと考えます。
いずれにしても、客観的事実に基づき判断されることとなりますが、個人事業者が有する事業用預金の範囲については限定的に捉える必要があるものと考えます。
なお、この取扱いは、3までにおいて同様です。 - 2 個人事業者の事業用預金以外の預金については、所得税法第51条(資産損失の必要経費算入)及び第72条(雑損控除)の適用がないことについて特に疑義はなく、所得金額の計算上何ら考慮されないものと考えます。
なお、この取扱いは、3までにおいて同様です。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金についても、民事再生法における再生手続開始の申立てが行われた場合には、所得税法と同様の理由により、非付保預金の額の50%に相当する金額を、貸倒引当金として損金の額に算入することができると解することが相当です(法法52![]() 、法令96
、法令96![]() 三ロ)。
三ロ)。
2 概算払率が決定した場合
(1) 概算払が行われていないとき
[所得税法]
イ 個別評価貸金等に対する貸倒引当金について、所得税法施行令第144条第1項第2号においては、「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことや、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由」が生じていることにより、個別評価貸金等の一部の金額につき取立て等の見込みがないと認められる場合(一定の場合)には、その一部の金額に相当する金額(算入限度額)を必要経費に算入することができることとされています。
ロ 概算払率は、上記Ⅱの2「金融機関が破綻した場合の預金の弁済に係る手続」の(4)に記載したとおり、破綻金融機関の資産及び負債についての監査法人による資産査定の結果等を踏まえた清算価値で非付保預金等を評価して算定され、機構の運営委員会の議決を経た上で、金融庁長官及び財務大臣の認可を受けて決定されます。
ハ このような手続を経なければ決定できない概算払率が決定されている場合には、非付保預金である事業用預金を有する個人預金者においては、「経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由」が生じており、その事業用預金の一部の金額につき回収の見込みがないため、一定の場合に該当すると考えられます。
ニ また、このような手続を経て決定された概算払率を事業用預金の額に乗じて計算した金額は、当該事業用預金に係る回収可能額として合理的な金額と考えられますから、概算払率が決定した場合において概算払が行われていないときには、事業用預金の額から概算払率により計算した回収可能額を控除した金額を必要経費に算入することができると解することが相当です(所法52![]() 、所令144
、所令144![]() 二)。
二)。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金についても、概算払率が決定された場合には、所得税法と同様の理由により、非付保預金の額から概算払率により計算した回収可能額を控除した金額を、貸倒引当金として損金の額に算入することができると解することが相当です(法法52![]() 、法令96
、法令96![]() 二)。
二)。
(2) 概算払が行われたとき
[所得税法]
イ 所得税法の適用上、事業者が金銭債権を譲渡したことにより生じた損失の金額については、その損失の金額に相当する金額の貸倒れによる損失が生じたものとして、事業所得等の金額の計算上、必要経費の額に算入されることが明らかにされています(所基通51-17)。
したがって、個人預金者が機構に対して非担保債権たる事業用預金等を譲渡し、この譲渡による損失の額が確定していれば、その損失の額は貸倒れによる損失の額として必要経費に算入することができます。
ロ 次に、事業用預金等の譲渡による損失の額についてですが、個人預金者が機構に対して事業用預金等を譲渡した場合には、その譲渡時に概算払額を受け取るほか、民事再生法による再生計画認可の決定が行われた時点で精算払を受けることがあり、精算払の金額が確定するまでは事業用預金等の譲渡による損失が確定しないのではないかとの疑問が生じます。
ハ この点、精算払については、以下の事項を踏まえれば、その性質は非担保債権の譲渡の対価の一部の支払ではなく、元預金者が預保法に基づいて取得した精算払受領権を行使した対価と解されますから、事業用預金等の譲渡による損失の額については、その譲渡時において確定しているものと考えられます。
ⅰ 機構が行う非担保債権の買取りは、その手続において機構が預金者から非担保債権の買取請求書を受領し、機構が預金者に買取代金(概算払額)の振込みを行い、債務者である破綻金融機関の確定日付のある証書による承諾を得ることにより、当該債権譲渡に対する第三者対抗要件を具備していること。
ⅱ 非担保債権の買取りにより事業用預金等に係る預金者となった機構は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて弁済を受けることとなりますが(Ⅱ1の(3))、この弁済額と概算払額との差額を公的な機関である機構が利得したままとすることは、買取りに応じなかった預金者との均衡を考慮した預金者保護の観点から適当ではないという理由から、預保法において精算払を行うことが機構に義務付けられていること(預保法70![]() ただし書)。
ただし書)。
ⅲ 金融商品に関する会計基準においては、金融資産の契約上の権利に関する支配が他に移転するための3要件を、![]() 譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること、
譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること、![]() 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること、及び
譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受できること、及び![]() 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこととしているところ(金融商品に関する会計基準9)、機構による非担保債権の買取りについては、上記ⅰのとおり債権譲渡に対する第三者対抗要件を具備し、上記ⅱのとおり破綻した金融機関の財産状況に応じて弁済を受けることから、上記
譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこととしているところ(金融商品に関する会計基準9)、機構による非担保債権の買取りについては、上記ⅰのとおり債権譲渡に対する第三者対抗要件を具備し、上記ⅱのとおり破綻した金融機関の財産状況に応じて弁済を受けることから、上記![]() 及び
及び![]() の要件を充足していると考えられ、上記Ⅱ2(4)の(注)のとおり預金者に買い戻す権利を付与するような契約により行わないこととしていることから上記
の要件を充足していると考えられ、上記Ⅱ2(4)の(注)のとおり預金者に買い戻す権利を付与するような契約により行わないこととしていることから上記![]() の要件も充足していると考えられること。
の要件も充足していると考えられること。
ニ また、譲渡損失の額についてですが、上記ハの検討を踏まえれば、機構による非担保債権の買取りの対価として預金者が受領するのは、概算払額と精算払受領権ということになります。
ただし、概算払額は、上記(1)に記載のとおり、破綻金融機関について破産手続が行われたならば弁済を受けることができると見込まれる額(破産配当見込額)等を考慮して算定された概算払率に基づき、非付保預金等を評価して算定される合理的な金額であり、その後の金融整理管財人である機構の回収努力等の結果として精算払額が生じることはありますが、概算払額の算定時における非付保預金等の評価額としても適正な金額と考えられます。
ホ このため、精算払受領権の価額をゼロとし、概算払の対象となった事業用預金の額から概算払額を控除した金額を事業用預金等の譲渡による損失の額とし、この損失の額に相当する貸倒れによる損失が生じたものとし、概算払が行われた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費の額に算入して差し支えないものと解することが相当です。
(注)
- 1 会計上、金融資産の消滅時に新たに生じた資産について時価を合理的に測定できない場合、その時価はゼロとして譲渡損益を計上することとされています(金融商品会計に関する実務指針38)。
- 2 機構に譲渡される非担保債権には未払利息が含まれますが、この未払利息については、公社債を譲渡した場合の未収利息と同様に譲渡原価を構成しないと考えられることから、上記譲渡による損失の額の算定においても「事業用預金等の額」ではなく、未払利息を含まない「事業用預金の額」から概算払額を控除して計算することとしています。
[法人税法]
法人税法における譲渡による損失の認識についても、上記所得税法におけるものと同様ですが、法人税法においては金銭債権を譲渡したことにより生じた損失の金額を貸倒れによる損失が生じたものとするような規定は存在しません。
したがって、法人預金者において、概算払額の支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する事業年度の所得の計算上、当該概算払額を益金の額に算入するとともに、譲渡の対象となった非付保預金の額を損金の額に算入して差し支えないものと解することが相当です(法法22![]()
![]() 、法基通2―1-44)。
、法基通2―1-44)。
3 再生計画認可の決定が行われた場合
(1) 概算払が行われていないとき
[所得税法]
個人事業者が有する貸金等に貸倒れが生じた場合には、その貸倒れによる損失の額は必要経費に算入されるところ(所法51![]() )、民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことにより、その決定により切り捨てられることとなった貸金等の部分の金額については、この貸倒れによる損失の額に該当することが所得税基本通達51-11により明らかにされています。
)、民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことにより、その決定により切り捨てられることとなった貸金等の部分の金額については、この貸倒れによる損失の額に該当することが所得税基本通達51-11により明らかにされています。
したがって、個人預金者の有する事業用預金について、再生計画認可の決定により、その一部が切り捨てられることとなった場合にも、その切り捨てられる部分の金額については所得税法第51条第2項の規定により貸倒れによる損失が生じたものとして、その切捨てが行われた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入して差し支えないものと解することが相当です。
[法人税法]
法人預金者の有する非付保預金について、その一部が切り捨てられることとなった場合には、所得税法と同様に、その切り捨てられる部分の金額については、その切捨てが行われた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、貸倒損失として損金の額に算入して差し支えないものと解することが相当です(法法22![]() 、法基通9-6-1(1))。
、法基通9-6-1(1))。
(2) 精算払を受けたとき
[所得税法]
精算払は、上記2(2)のニのとおり精算払受領権に基づいて行われるものであり、事業用預金等の譲渡による損失の額の計算に当たり、精算払受領権の価額をゼロとして、その計算を行うことが相当としているところです。
換言すれば、精算払受領権の取得価額を認識しないこととするのが相当であり、個人預金者においては、取得価額のない精算払受領権を行使して精算払額を受領することとなりますので、当該精算払額を、これに対応する必要経費を計上することなく、その支払を受けた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなります。
なお、預保法第73条第2項において、精算払の金額と当該非担保債権に係る概算払の金額との合計額が、当該非担保債権に係る基準日における元本の額以下であるときには、所得税法上の適用においては、当該精算払の金額は元本の払戻しの額とみなす旨の規定があることから、収入金額に算入すべきではないとの疑義も生じるところです。
しかしながら、所得税法において、貸倒処理した債権の回収がなされた場合には、所得税法第36条の収入金額に算入すべきものであるところ、上記2(2)により、その譲渡により生じた損失の金額を貸倒損失として必要経費に算入していることからすれば、その後に受け取る精算払額を事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入すべきと解するのが相当と考えます。
[法人税法]
法人預金者においても、精算払額を受領した場合には、所得税法と同様に、当該精算払額を、これに対応する損金の額を計上することなく、その支払を受けた日の属する事業年度において、益金の額に算入することになります(法法22![]() )。
)。