住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険契約等に係る法人税法上の所得計算について(照会)
(別紙)
国住担第16号
平成22年5月27日
国税庁 課税部
審理室長 山川 博樹 殿
国土交通省 住宅局
住宅生産課長 橋本 公博
1 照会の経緯
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行法」といいます。)が平成21年10月1日から施行されました。
この履行法の施行により、新築住宅の引渡しをする建設業者又は宅地建物取引業者(以下「建設業者等」といいます。)は、発注者又は買主(以下「発注者等」といいます。)へ引渡しをした新築住宅について住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)第94条第1項(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)又は第95条第1項(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)の規定に基づく10年間の瑕疵担保責任(以下「特定住宅瑕疵担保責任」といいます。)の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金(以下「担保保証金」といいます。)の供託をするか、住宅建設瑕疵担保責任保険契約又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下「住宅瑕疵担保責任保険契約」といいます。)を締結するかのいずれかの措置を講ずることが義務付けられております(履行法3、11)。
このうち、住宅瑕疵担保責任保険契約については、履行法第17条第1項(指定)の規定に基づき国土交通大臣に住宅瑕疵担保責任保険法人として指定された法人(以下「保険法人」といいます。)が引受けを行うこととなります(履行法19)。
この引受けを行う保険法人においては、各事業年度において住宅瑕疵担保責任保険契約に係る所得計算を行うこととなるところ、新たな保険契約であることからその計算基準が明らかでないため、本件の照会を行うに至ったところです。
2 事実関係(照会に係る取引等の事実関係)
(1) 住宅瑕疵担保責任保険契約
住宅瑕疵担保責任保険契約とは、新築住宅の建設業者等が発注者等に引き渡した新築住宅に瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金により補てんされるものです。
その保険期間は、新築住宅の引渡しの日から10年間です。また、その保険料は、保険金支払限度額や新築住宅の床面積などに応じて定められており、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための保険であることから、保険期間の開始前に建設業者等から一括して保険法人に払い込まれます。
なお、住宅瑕疵担保責任保険契約は、原則として、建設業者等が特定住宅瑕疵担保責任を履行したことにより生じた損害をてん補するものであることから(履行法2![]() 二イ、
二イ、![]() 二イ)、損害賠償責任保険として規定されています。
二イ)、損害賠償責任保険として規定されています。
本来、損害賠償責任保険契約は、保険業法第3条(免許)に規定する損害保険業免許を内閣総理大臣から受けた者(以下「損害保険会社」といいます。)が引受けを行うこととされていますが(保険業法3![]()
![]()
![]() )、住宅瑕疵担保責任保険契約の制度設計に当たり、新築住宅の現場検査の専門性などから、保険業法の例外として、損害保険会社ではなく専門性を有する保険法人が引受けを行うこととされたものです(保険業法2
)、住宅瑕疵担保責任保険契約の制度設計に当たり、新築住宅の現場検査の専門性などから、保険業法の例外として、損害保険会社ではなく専門性を有する保険法人が引受けを行うこととされたものです(保険業法2![]() 一、履行法17、19一)。
一、履行法17、19一)。
(注) 住宅瑕疵担保責任保険契約は、発注者等の損害を補てんすることも予定されていますが、これは建設業者等の倒産といった例外的な事象により建設業者等が相当の期間を経過しても特定住宅瑕疵担保責任を履行しない場合に対応するためのものであり(履行法2![]() 二ロ、
二ロ、![]() 二ロ)、原則としては被保険者たる建設業者等の損害をてん補するための賠償責任保険に該当します。
二ロ)、原則としては被保険者たる建設業者等の損害をてん補するための賠償責任保険に該当します。
(2) 保険法人の収支決算書等
保険法人は、毎事業年度経過後3月以内に、公認会計士又は監査法人の監査を受けた収支決算書及び財産目録等を国土交通大臣に提出しなければなりません(履行法22![]() 、履行法規則30
、履行法規則30![]() )。
)。
また、保険法人は、毎事業年度末において、責任準備金及び支払備金を積み立てなければならないこととされています(履行法24、26、履行法規則32、33、35)。
なお、国土交通大臣は、保険法人に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができるほか、報告の徴求及び立入検査を実施することもでき、責任準備金の未計上などが把握された場合には、業務停止命令や保険法人としての指定の取消しを行うことができます(履行法27、28、30)。
(3) 普通責任準備金
保険法人において積立てを要する責任準備金とは、次の2種類の責任準備金をいいます(履行法規則32)。
ただし、住宅瑕疵担保責任保険契約を再保険に付した場合において、保険業法に規定する保険会社などに再保険を付した部分に相当する責任準備金は積み立てないことができます(履行法規則33)。
 普通責任準備金 収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち各事業年度末において、まだ経過していない期間をいいます。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。
普通責任準備金 収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち各事業年度末において、まだ経過していない期間をいいます。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。 異常危険準備金 住宅瑕疵担保責任保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。
異常危険準備金 住宅瑕疵担保責任保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。
なお、具体的な責任準備金の算出方法は、各保険法人において国土交通大臣の認可を受ける業務規程に定められることになります(履行法21![]() 、履行法規則28九)。
、履行法規則28九)。
(注)
- 1 損害保険会社においても、上記
 の普通責任準備金については普通責任準備金のうちの未経過保険料として、上記
の普通責任準備金については普通責任準備金のうちの未経過保険料として、上記 の異常危険準備金については危険準備金として、履行法と同様の規定が保険業法に定められ、その積立てが義務付けられています(保険業法116
の異常危険準備金については危険準備金として、履行法と同様の規定が保険業法に定められ、その積立てが義務付けられています(保険業法116 、保険業法規則70
、保険業法規則70 一ロ、二の二)。
一ロ、二の二)。 - 2 上記
 の普通責任準備金の金額は、上記のとおり、「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて(平成15年12月19日付課法2−24法令解釈通達)」(以下「損保通達」といいます。)の「8 普通責任準備金の意義」の「(2) 未経過保険料」の金額の計算方法に準じた計算方法により計算されます。
の普通責任準備金の金額は、上記のとおり、「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて(平成15年12月19日付課法2−24法令解釈通達)」(以下「損保通達」といいます。)の「8 普通責任準備金の意義」の「(2) 未経過保険料」の金額の計算方法に準じた計算方法により計算されます。
(4) 支払備金
保険法人において積立てを要する支払備金とは、次の2種類の支払備金をいいます(履行法規則35![]() )。
)。
ただし、住宅瑕疵担保責任保険契約を再保険に付した場合において、保険業法に規定する保険会社などに再保険を付した部分に相当する支払備金は積み立てないことができます(履行法規則33、35![]() )。
)。
 普通支払備金 住宅瑕疵担保責任保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が継続しているものを含みます。)のうち、事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合の、その支払のために必要な金額。
普通支払備金 住宅瑕疵担保責任保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が継続しているものを含みます。)のうち、事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合の、その支払のために必要な金額。
なお、この「必要な金額」の具体的な計算方法は、各保険法人において国土交通大臣の認可を受ける業務規程に定められることになります(平成20年3月28日付「住宅瑕疵担保責任保険法人業務規程の認可基準(指示)」14(1))。 IBNR備金 事業年度末において未だ支払事由の発生の報告を保険法人が受けていないが、住宅瑕疵担保責任保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額(以下「IBNR積立必要額」といいます。)。
IBNR備金 事業年度末において未だ支払事由の発生の報告を保険法人が受けていないが、住宅瑕疵担保責任保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額(以下「IBNR積立必要額」といいます。)。
なお、このIBNR積立必要額は、保険種目別に次の算式(この算式における支払保険金及び普通支払備金は、再保険による他の保険者からの受取保険金に相当する金額があるときは、当該金額を控除した金額とします。)により計算した金額の直近3事業年度の平均額を限度としています(平成22年5月26日国土交通省告示第558号「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の規定に基づき、支払備金として積み立てるべき金額を定める件」)。
[算式]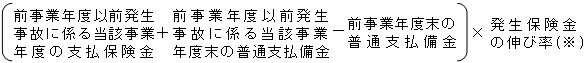
※ 上記算式の発生保険金の伸び率とは、次により計算されます。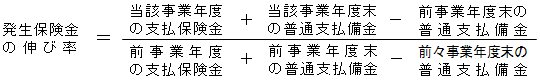
(注)
- 1 損害保険会社においても、上記
 の普通支払備金及び
の普通支払備金及び のIBNR備金について、履行法と同様の規定が保険業法に定められ、その積立てが義務付けられています(保険業法117
のIBNR備金について、履行法と同様の規定が保険業法に定められ、その積立てが義務付けられています(保険業法117 、保険業法規則73
、保険業法規則73 一、二)。
一、二)。 - 2 上記
 の普通支払備金及び
の普通支払備金及び のIBNR備金の金額については、上記のとおり、損保通達の「2 支払備金の意義」の「普通支払備金」及び「IBNR備金」の金額の計算方法に準じた方法により計算されます。
のIBNR備金の金額については、上記のとおり、損保通達の「2 支払備金の意義」の「普通支払備金」及び「IBNR備金」の金額の計算方法に準じた方法により計算されます。
3 照会事項(照会の趣旨)
上記の保険法人が積み立てる普通責任準備金及び支払備金に関して、保険法人の所得計算上の取扱いは、以下のとおり解して差し支えないか、ご照会申し上げます。
(1) 普通責任準備金について
保険法人がその業務規程に定められる方法により各事業年度において普通責任準備金を積み立てた場合には、保険法人の当該事業年度の所得の計算上、その積立金額が損金の額に算入される。
(注) この考え方は、損保通達の「7 普通責任準備金の損金算入」、「8(2) 未経過保険料」、「10 未経過保険料の計算方法」及び「12 普通責任準備金の益金算入」に定める取扱いを準用したものです。
(2) 支払備金について
イ 普通支払備金について
保険法人がその業務規程に定められる方法により各事業年度において普通支払備金を積み立てた場合には、保険法人の当該事業年度の所得の計算上、その積立金額が損金の額に算入される。
ロ IBNR備金について
保険法人がその業務規程に定められる方法により各事業年度においてIBNR備金を積み立てた場合には、保険法人の当該事業年度の所得の計算上、その積立金額が損金の額に算入される。
(注) これらの考え方は、損保通達の「1 支払備金の損金算入」、「2 支払備金の意義」、「3 普通支払備金の積立限度額」、「5 IBNR備金の積立限度額」及び「6 支払備金の益金算入」に定める取扱いを準用したものです。
4 理由(照会者の求める見解となることの理由)
(1) 保険の種類について
住宅瑕疵担保責任保険契約は、保険業法を根拠法として損害保険会社が引受けを行う損害賠償責任保険契約とは異なり、新築住宅の現場検査の専門性などから履行法を根拠法として保険法人のみが引受けを行うことができることとされていますが、建設業者等が特定住宅瑕疵担保責任を履行したことにより生じた損害をてん補するという(履行法2![]() 二イ、
二イ、![]() 二イ)、損害賠償責任保険契約の一種であることに変わりはありません。
二イ)、損害賠償責任保険契約の一種であることに変わりはありません。
(2) 積立ての必要性について
住宅瑕疵担保責任保険契約に係る普通責任準備金並びに普通支払備金及びIBNR備金は、損害保険会社が引受けを行う損害賠償責任保険契約について保険業法により内閣総理大臣の監督下で積立てを義務付けされているものとは異なりますが、上記2(2)のとおり、履行法に規定された保険業法と同様の規定より国土交通大臣の監督下で積立てを義務付けられているものであり、その計算方法も上記2(3)及び(4)のとおり、保険業法に準じたものとされているところです。
(3) 積立てを要する金額について
イ 普通責任準備金及び普通支払備金
履行法における普通責任準備金及び普通支払備金の定義(履行法規則32一、35![]() 一)は、保険業法における普通責任準備金のうち未経過保険料及び普通支払備金の定義(保険業法規則70
一)は、保険業法における普通責任準備金のうち未経過保険料及び普通支払備金の定義(保険業法規則70![]() 一ロ、73
一ロ、73![]() 一)と同様の規定となっています。
一)と同様の規定となっています。
このうち、履行法における普通責任準備金及び普通支払備金については、上記2(3)及び(4)に記載のとおり、具体的な計算方法が各保険法人の業務規程に定められ、その業務規程は国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
これに対して、保険業法における未経過保険料及び普通支払備金については、具体的な計算方法が算出方法書に定められ、その算出方法書は内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
このように、規定上は同様の定義により定められ、かつ、所管大臣の監督下において具体的な算出方法が定められることから、その積立てを要する金額についても同様のものと考えられます。
ロ IBNR備金
履行法におけるIBNR備金の定義(履行法規則35![]() 二)は、保険業法におけるIBNR備金の定義(保険業法規則73
二)は、保険業法におけるIBNR備金の定義(保険業法規則73![]() 二)と同様の規定となっています。
二)と同様の規定となっています。
このうち、履行法におけるIBNR備金は国土交通省告示により具体的な計算方法が定められ、保険業法におけるIBNR備金は金融庁告示により具体的な計算方法が定められ、その計算方法は同一のものとなっています。
したがって、その積立てを要する金額も同様のものと考えられます。
(注) 国土交通大臣の認可を受ける各保険法人の業務規程においては、上記国土交通省告示の計算方法により算出されたIBNR積立必要額を積み立てる旨が定められるため、保険法人がその業務規程に定められる方法により各事業年度においてIBNR備金を積み立てた場合には、その積立額はIBNR積立必要額となります。
(4) 積立ての内容について
上記(1)から(3)までのとおり、住宅瑕疵担保責任保険契約は、損害保険会社が引受けを行うものと同様に損害賠償責任保険契約の一つであり、これに対して計上を求められる普通責任準備金並びに普通支払備金及びIBNR備金の金額についても、行政庁の指導監督の下、損害保険会社が引受けを行う損害賠償責任保険契約に対して計上を求められるこれらの準備金と同様の計算により算出される金額であると認められます。
したがって、保険法人が行う本件照会に係る事業の実態は、損害保険会社において行われる損害保険に係る事業と同様のものと認められますから、保険法人においても、普通責任準備金並びに普通支払備金及びIBNR備金については、損害保険会社の所得計算に係る取扱いである損保通達により認められた計算方法を準用して、各事業年度の所得計算を行って差し支えないものと考えています。
なお、保険法人において損保通達を準用する箇所については、「5 参考(PDF/190KB)」のとおりとなります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。