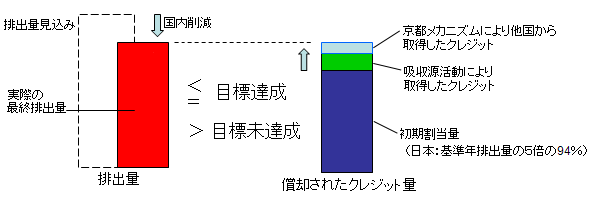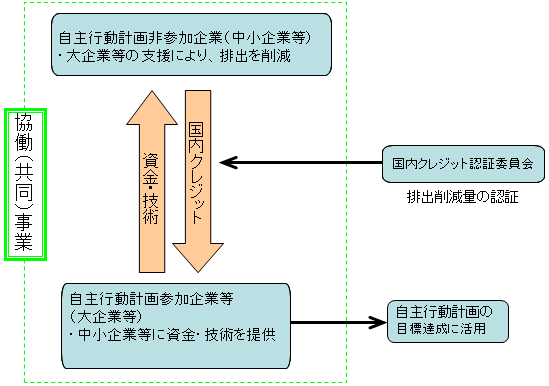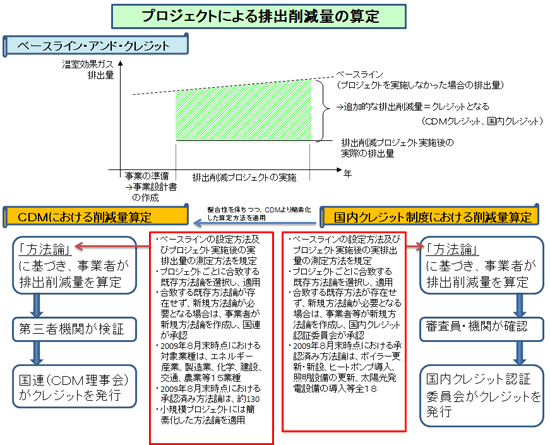国内クレジットの取引に係る法人税の取扱いについて(照会)
(別紙)
平成22年3月23日
国税庁課税部
審理室長
山川 博樹 殿
経済産業省 産業技術環境局
環境経済室長
近藤 智洋
環境省 地球環境局
地球温暖化対策課市場メカニズム室長
戸田 英作
1 照会の趣旨
我が国においては、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)(注1)に基づく我が国の温室効果ガス排出削減約束を達成するために、各種の対策を京都議定書目標達成計画(以下「目標達成計画」という。)として定めており、その中で、大企業等が技術・資金等を提供して中小企業等が行った二酸化炭素の排出抑制のための取組による排出削減量(クレジット)を政府が認証し、自主行動計画(民間企業が自主的に策定した温室効果ガス排出削減計画)等の目標達成に活用する制度(以下「国内クレジット制度」という。)を設けている(国内クレジット制度の概要は、「2 照会に係る取引等の概要」のとおり)。
この制度の下で、排出削減事業共同実施者である大企業等(以下「内国法人」という。)は、排出削減事業者である中小企業等から当該認証された排出削減量(以下「国内クレジット」という。)を取得し、これを償却等することとしている。この国内クレジットの取引に係る法人税の取扱いに関して、次のとおり解して差し支えないか、照会申し上げる。
(注1) 地球温暖化防止に向けた具体的な方針を示す国際的枠組みとして、1997年12月に京都において採択され、2005年2月に発効した。
(照会事項)
内国法人が当該国内クレジットの償却のためにこれを国内クレジット管理システムにおける当該内国法人の保有口座から政府が管理する償却口座に移転する場合には、当該国内クレジットが償却口座に移転された日を含む事業年度において、原則として、当該国内クレジットの価額に相当する金額を国等に対する寄附金として、当該内国法人における損金の額に算入する。
この場合における当該国内クレジットの価額とは時価を言うこととなり、当該国内クレジットが償却口座に記録された日に近い売買実例等を参考として適正に算定することとなる。ただし、売買実例の把握が容易でないこと等により時価の算定が困難である場合には、当該内国法人の帳簿価額を当該国内クレジットの価額として取り扱う。
2 照会に係る取引等の概要
(1)国内クレジット制度の概要
イ 国内クレジット制度を取り巻く状況について
![]() 京都議定書
京都議定書
京都議定書においては、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出削減に関して、先進国(「附属書Ⅰ国」という。)に対して法的拘束力のある数値約束を課し、その全体で温室効果ガスの排出量を基準年(概ね1990年)における排出量と比較して、第一約束期間(2008年から2012年までの5年間)の平均排出量について少なくとも5%削減することを定めており、我が国は、基準年比で6%削減するという約束を負っている。
京都議定書に基づく排出削減約束を達成するためには、第一約束期間における温室効果ガスインベントリ(国連の指針に基づきとりまとめた、毎年の温室効果ガス排出実績。以下「インベントリ」という。)上の排出実績量と比較して少なくとも同量相当の京都議定書に基づくクレジット(以下「京都クレジット」という。)(注2)を保有する必要がある(別添・図1参照)。
(注2) 初期割当クレジットである割当量単位(AAU)を含む6種類のクレジットがある。
![]() 目標達成計画
目標達成計画
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、以下「地球温暖化対策法」という。)は、京都議定書が我が国に対して発効する際に、我が国の6%削減約束を確実に達成するために必要な措置を定めるものとして、目標達成計画を定めることとしており(第8条)、2005年2月に京都議定書が発効したことを受け、同計画が閣議決定されている(同計画は、2006年7月の一部改定を経て、2008年3月に全部改定され現在に至っている。)。
目標達成計画は、我が国の6%削減約束達成に向け、温室効果ガス種別ごとの排出削減対策(国内対策)を規定するとともに、森林等における温室効果ガス吸収源対策、京都メカニズム(注3)の活用等について規定している。各種対策により見込まれる排出削減効果を集計した結果として、6%削減のうち、国内対策で0.6%、吸収源対策で3.8%、京都メカニズムの活用によって残り1.6%をそれぞれ達成するとの目安を示している。
(注3) 京都議定書に定められている、海外における排出削減量又は初期割当を自国の排出削減約束の達成に利用することができる制度。共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出量取引の3つの制度がある。
![]() 自主行動計画
自主行動計画
目標達成計画においては、自主行動計画を我が国産業界における温室効果ガス排出を抑制するための手段の一つとして位置づけている。同計画は、日本経済団体連合会傘下の個別業種及び同連合会に加盟していない個別業種の団体・組織が自主的に策定した温室効果ガス排出削減計画であり、目標達成計画によれば、産業・エネルギー転換部門の排出量の約8割、全部門の約5割をカバーするに至っている。自主行動計画に基づく排出削減対策の進捗状況は、政府が設置する審議会等において定期的に評価・検証を受けている。
ロ 国内クレジットとは
![]() 国内クレジット制度の仕組み
国内クレジット制度の仕組み
国内クレジット制度は、自主行動計画等における温室効果ガス排出削減目標を負う大企業等が、こうした目標を負わない中小企業等に技術・資金等を提供し、当該中小企業等がこれら技術・資金等を活用して実現した排出削減量について、政府が認証し、当該大企業等の目標達成に使用させる制度である(スキームについては、別添・図2参照)。目標達成計画においてその創設が言及され、排出量取引の国内統合市場の試行的実施に係る地球温暖化対策推進本部決定を受け、平成20年10月に発足した(2(2)イ(参考)参照)。
国内クレジット制度では、京都議定書に基づく京都メカニズムの一つ、クリーン開発メカニズム(以下「CDM」という。)と同様に、いわゆるベースライン・アンド・クレジットのアプローチが採用されている。これは、排出削減事業が存在しなかった場合に発生したと想定される排出量をベースラインとし、事業実施によって実現した、ベースラインからの追加的削減分をクレジットとして認証するものである(別添・図3参照)。
国内クレジット制度においては、国連におけるCDMの実施方針も踏まえ、対象事業の認証、排出削減量の認定といった制度の中核をなす意思決定について、一定の条件を満たす審査員又は審査機関が事前審査を行い、その審査結果を踏まえて、学識経験者からなる国内クレジット認証委員会(以下「認証委員会」という。)が決定を下す、といった仕組みが導入されており、第三者の専門家の知見を活用することによって制度の厳格性・透明性を確保することが志向されている。
また、国内クレジットは、電子的に管理されており、政府によって開発された電子システム(国内クレジット管理システム)により、その全てについて1トン単位の識別番号が割り振られ、その発行、保有等の各種取引が記録・管理されている。
![]() 国内クレジット制度の意義
国内クレジット制度の意義
温暖化対策及び国民経済の視点からみた場合、国内クレジット制度は、産業部門において、自主行動計画のような組織的な取組のない中小企業だけでなく、我が国の二酸化炭素排出の増大の要因となっている業務その他部門、民生部門の削減につなげる極めて重要な対策の一つである。京都クレジットが海外における排出削減量や排出枠を活用するのに対し、国内クレジット制度は、大企業等の資金・技術を国内への投資に向け、これらを国内において有効活用し、かつ、実際の削減を国内に生じせしめ、これを第一約束期間後においても継続させることを狙いとしている。また、国内クレジットは、京都メカニズムに倣った仕組みで一定の厳格性・追加性を確保しつつ排出削減量を認証し、インベントリにおける排出量算定と同様の係数を用いる等保守的な方法により当該排出削減量を算定していることから、国内クレジット1トン分は、インベントリにおける実排出量1トン分の排出削減に対応している、ということができる。すなわち、国内クレジットを1トン分活用することは、実質、インベントリにおける我が国の排出実績を1トン分引き下げる効果を有しており、我が国の京都議定書約束達成に関して実質的な意義を有している。
(2)国内クレジットの評価等について
イ 目標達成計画における位置づけ
目標達成計画において、国内クレジットは、「京都メカニズムクレジットに適用される簡便な認証方法に倣った基準により認証を行うことにより、一定の追加性・厳格性を確保するとともに、中小企業等の利便性確保の観点から手続の簡素化等を行う。」とされており、その認証方法は、京都クレジットに倣ったものとされている。
目標達成計画の下で、自主行動計画の達成状況について政府から評価・検証を受けるに当たっては、京都クレジットと国内クレジットはいずれも同様の効果があるものとして評価されることとなる。すなわち、京都クレジットや国内クレジットを事業者が取得し、政府に無償移転した場合には、自主行動計画の目標達成確認プロセスにおいて、譲渡量に対応する当該事業者の実排出量を相殺する効果が認められている。
(参考) 「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における評価
排出量取引の国内統合市場の試行的実施は、平成20年10月から地球温暖化対策本部決定(平成20年10月21日)に基づき実施されているものである。当該試行的実施は、1)企業等が削減目標を設定し、その目標の超過達成分(排出枠)や「クレジット」の取引を活用して目標達成を行う試行排出量取引スキーム(以下「試行スキーム」という。)と、2)上記「クレジット」を生成・取引させる国内クレジット及び京都メカニズムの2つの主な制度から構成される。試行スキームにおいて発生した排出枠や国内クレジット及び京都クレジットは、等しく試行スキームの目標達成に使用可能となっている。
ロ 国内クレジットの資産性
国内クレジットは、元々、事業者が政府への無償移転を通じて自主行動計画等における目標達成に使用できるように制度設計されていること、排出削減事業の実施により実際に発生した排出削減量を第三者機関が認証し、認証された分がクレジット化されること、我が国の実排出量を引き下げることにより我が国の京都議定書約束達成に実質的に貢献するものであること、排出削減事業の実施主体である中小企業等からクレジットの需要者である大企業等に金銭等を介して移転することが想定されていること(注4)、大企業等が取得した後、専用の国内クレジット管理システム上で他の事業者に移転することが可能であること、といった特徴を有しており、これらを踏まえると、その性格は、京都議定書の約束達成に使用するよう制度設計され、第三者認証を経て発行された後、事業者間を一定の価格により流通することが想定されている京都クレジットに極めて類似しているということができる。このことは、国内クレジットと京都クレジットが、自主行動計画や試行スキームにおいて、同等の価値を有するものとして扱われていることにも反映されている。なお、京都クレジットは、2006年度に環境省が設置した研究会(注5)において、権利移転方法の簡便性・明確性及び取引の安全の確保といった観点から、「動産類似の財産権」的な存在として扱うことが妥当であるとしているところ、上述のような取引の特徴を踏まえると、国内クレジットもほぼ同様に扱うことが妥当と考えることができる。また、大企業等が自主行動計画の目標達成のために取得するという期待をもって価値が付くものであることから、一義的に、その資産性を認めることも可能である。
(注4) 本件照会は、別紙「国内クレジットの取引価格の決定プロセスについて」に基づいて価格が算定されている事案を対象としている。
(注5) 京都メカニズムを安定的に運用するために必要な国別登録簿を法制化するに当たり、必要な法的論点等について検討するため、環境省において研究会を設置し、その検討結果を「京都議定書に基づく国別登録簿制度を法制化する際の法的論点の検討について」(2006年1月公表)として取りまとめている。
(3)国内クレジットの移転(償却等)手続きについて
国内クレジットをその管理システム内の自己の保有口座から他者の保有口座に移転する場合には、経済産業省、環境省及び農林水産省が共同で定めた「国内クレジット制度(国内排出量認証制度)運営規則(平成20年10月)」に基づき、認証委員会に対して、同委員会が定めた様式に基づく申請書を提出することが必要である。申請書が受理された場合には、認証委員会の事務局(経済産業省産業技術環境局、環境省地球環境局及び農林水産省大臣官房)において国内クレジット管理システムを操作し、当該移転を記録することとなる。記録に際しては、移転元となる内国法人の口座から対象となる国内クレジットの識別番号(京都クレジットと同様、1トン毎に固有の番号が割当てられる)が削除されるとともに、同様の番号が移転先となる内国法人の口座に追記される。
また、自主行動計画における目標達成等のために国内クレジットを償却する(政府の管理する償却口座に無償で移転する)場合には、内国法人は償却用の申請書を認証委員会に提出し、これを受けて、対象となる国内クレジットが、移転元の保有口座から償却口座に直接移転される。償却がなされた段階で認証委員会の事務局から当該内国法人に対して償却通知が発行される。ひとたび償却されると、当該国内クレジットは他の取引には使用できなくなる。したがって、償却口座に移転されたことをもって、目標達成に使用されることが確定することとなる。
(4)会計上の取扱い
試行スキームにおいて必要と考えられる会計処理について明確化した「実務対応報告第15号 排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(最終改正平成21年6月23日 企業会計基準委員会)においては、「京都メカニズム以外のクレジットについても、会計上、その性格が類似していることから、本実務対応報告の考え方を斟酌し、会計処理を行うものとする。」とされている。これに基づけば、国内クレジットを償却目的で取得する場合は「無形固定資産」又は「投資その他の資産」、転売を目的として取得する場合は「棚卸資産」として計上し、償却時にはこれを費用として処理(原則として「販売費及び一般管理費」で計上)することになる。
3 照会者の求める見解となることの理由
国内クレジット制度の下で、内国法人が、その償却を目的として国内クレジットを取得(購入)し、当該国内クレジットを国内クレジット管理システムにおける当該内国法人の保有口座から政府が管理する償却口座に移転する場合には、基本的には、![]() 上記2(2)ロのとおり、国内クレジットは資産性を有するものであること、
上記2(2)ロのとおり、国内クレジットは資産性を有するものであること、![]() 国内クレジットが我が国の京都議定書に基づく温室効果ガスの削減約束達成に寄与するため政府にとって実質的価値を有するものであること、
国内クレジットが我が国の京都議定書に基づく温室効果ガスの削減約束達成に寄与するため政府にとって実質的価値を有するものであること、![]() 国内クレジット制度に参加する内国法人から政府への国内クレジットの無償移転(具体的には国内クレジット管理システムにおける償却口座への移転)が条約や法律等に基づき課せられた義務ではなくあくまで当該内国法人の任意に行われる我が国の取組への貢献であること、
国内クレジット制度に参加する内国法人から政府への国内クレジットの無償移転(具体的には国内クレジット管理システムにおける償却口座への移転)が条約や法律等に基づき課せられた義務ではなくあくまで当該内国法人の任意に行われる我が国の取組への貢献であること、![]() 内国法人の事業と直接の関係がないこと、
内国法人の事業と直接の関係がないこと、![]() 内国法人に経済的に裨益するものではないこと、
内国法人に経済的に裨益するものではないこと、![]() 無償譲渡であり対価性がなく、内国法人から政府への資産の贈与と認められることが特徴として挙げられる。
無償譲渡であり対価性がなく、内国法人から政府への資産の贈与と認められることが特徴として挙げられる。
したがって、当該国内クレジットの政府に対する無償移転は、原則として、法人税法第37条第7項に規定する「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に該当し、その相手先が我が国政府であることから、当該国内クレジットの価額に相当する金額を法人税法第37条第3項第1号に規定する「国等に対する寄附金」として、その支出があったと認められる日、具体的には当該国内クレジットが政府保有口座に記録された日(当該国内クレジットの償却口座への移転が完了した日)を含む事業年度において損金算入することが相当であると考えられる。
ところで、この場合の国内クレジットの価額は、売買実例等を参考として適正に時価を算定する必要があるが、国内クレジットの政府に対する無償移転を行う内国法人においては、現状において我が国に国内クレジットの取引市場が形成されておらず、第三者間で行われる売買実例等の指標を把握することが容易でないことも考えられる。
このような場合であっても、国内クレジットの政府に対する無償移転が国等に対する寄附金として損金算入されることを考えると、内国法人がこの無償移転を行うに当たって、売買実例の把握が容易でないこと等により時価の算定が困難である場合には、国内クレジットの帳簿価額を国内クレジットの価額とみて処理することとしても課税上の弊害は特段生じないものと考えられる。
なお、内国法人が、仮に転売を目的として国内クレジットを取得(購入)し、これを他の者に売却(有償譲渡)した場合には、原則として、会計処理と同様に棚卸資産の譲渡として扱い、その売却により生じた損益の額を、その確定した日を含む事業年度の損金又は益金の額に算入することが相当であると考えられる。
別添
別紙
国内クレジットの取引価格決定プロセスについて
国内クレジットについて、排出削減事業者(中小企業等)と共同実施者(大企業等)との間で取引価格を決定する場合には、相対取引を原則として、個別の価格交渉によって決定されている。しかしながら、当該交渉の基礎としては、各種メディアを通じて提供されている京都クレジットの取引価格、欧州域内排出量取引制度の下で取引されている欧州排出枠の取引価格等を指標として活用する場合が多い。特に、京都クレジットについては、自主行動計画及び試行排出量取引スキームにおける目標達成において、国内クレジットと同等に活用することが可能であるため、京都クレジットの取引価格は必然的に国内クレジットのそれに影響を与えることとなる。また、欧州排出権取引市場においては、欧州排出枠の価格を基礎として京都クレジットの価格が決められているため(一般的に、京都クレジットの価格が欧州排出枠の価格の8~9割相当)、間接的に欧州排出枠の価格が国内クレジットの価格に影響を与えることとなる。
なお、具体的な価格決定プロセスとしては、以下のような事例が挙げられる。
- 事例1
日経・JBIC排出量取引参考気配(http://www.joi.or.jp/carbon/h_index.html)において公表されている京都クレジットの現物価格気配値を参考にしつつ、クレジット発生の数量不確実性等の要素を考慮し、売買価格を決定。 - 事例2
海外に拠点を置く排出権トレーダー、Point Carbon社が提供する京都クレジットの価格情報を参考にしつつ、クレジットの発行量、発行のタイミング、契約年数などの条件等の要素を考慮し、売買価格を決定。
4 参考法令
○ 法人税法(抄)
(寄附金の損金不算入)
第三十七条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
- 2 (省略)
- 3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
- 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
- 二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
- イ 広く一般に募集されること。
- ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
- 4~6 (省略)
- 7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
- 8 (以下省略)