私法上の制約等が法人税法22条2項の収益の額に与える影響について−東京高裁平成26年6月12日判決を題材にして−
幡野 正仁
税務大学校
研究部教授
要約
1 研究の目的(問題の所在)
法人税法22条2項に規定する「収益の額」(以下、単に「収益の額」という。)は、同条4項に規定する「公正処理基準」に従って計算することとされている。
同条2項に関しては、例えば、無償取引に係る収益の取扱いについて多くの議論があるなど、この規定の性格、目的、適用範囲等について種々の見解がある。また、同条4項に関しても「公正処理基準」が必ずしも明確でなく、ある基準が「公正処理基準」に該当するのか否かについて、判断が難しい場合もあり、裁判例も多数存在する。
今般、収益の額をいかに考えるべきか。この点について改めて検討を必要と考えさせる事案(以下「本事案」という。)が発生した。本事案の概略は次のとおりである。
原告の各子会社(以下「本件各子会社」という。)が減資等を行い、これに伴い旧商法(平成17年法律第87号による改正前の商法をいう。以下同じ。)213条1項に基づく株式の強制消却(以下「本件株式消却」という。)を有償で行った(以下、旧商法における強制消却時の払戻規制を「本件払戻規制」という。)。法人税法上、強制消却は有価証券の譲渡に該当するところ、強制消却による払戻の額が消却された本件各子会社株式(以下、当該消却された本件各子会社株式を「本件消却株式」という。)の時価を下回ることから、課税庁は払戻しを受けた親会社に対して有価証券の低額譲渡に当たるとして課税処分を行った(本事案における減資等をする場合の払戻しの金額の限度額を「本件払戻限度額」といい、課税庁が課税処分の対象とした本件払戻限度額を超える部分を「本件払戻限度超過額」という。)。本事案では、本件払戻限度超過額を収益の額として認定(以下「収益認定」という。)した形となった。
訴訟では、第一審及び第二審ともこの課税処分を適法であるとして、原告の請求が棄却されている。
なお、本事案は最高裁判所で上告棄却・不受理決定となり既に確定している。
本事案における最大の論点は、本件払戻限度超過額を収益の額として認識できるか否かである。本事案については、このほかに多数の論点があるが、私法上の制約や公法上の規制(以下「私法上の制約等」という。)が収益の額にどのように影響を与えるのかという点に絞って研究を行うこととする。
2 研究の概要
(1)本件高裁判決の判示事項等
本事案に係る高裁判決(東京高裁平成26年6月12日判決(訟月61巻2号394頁)、以下「本件高裁判決」という。)は、最高裁平成7年12月19日判決(民集49巻10号3121頁)(以下「最高裁平成7年判決」という。)を引用し、株式の低額譲渡に該当するとした課税処分を適法と判断した。また、法律上収受することができない本件払戻限度超過額を「収益」として計上することは許されないという納税者側の主張に対して、本件高裁判決は、次のように判示して同主張を排斥している。
「法人税が企業の経済活動によって稼得された成果(企業利益)を課税物件とするものであることに照らすと、法人税法22条2項にいう『収益』とは経済的な実態に即して実質的に理解するのが相当であり、また、このように解するのが同項の趣旨でもある租税の公平な負担の観念に合致することになる。そして、法人税法においては、法人が保有する資産の評価換えによりその帳簿価額が増加した場合でも、原則として、その増額した部分(評価益)は『益金の額』に算入せず(同法25条1項)、保有している段階では課税しないとする一方、資産の売却等によりその支配を離脱したときには、収益としてこれに課税するという仕組みが採用されているのである。以上に照らすと、本件株式消却により消却株式が譲渡されたことに伴い、その評価額である本件払戻限度超過額を含む678億0898万9571円を『収益』として計上することは法人税法上の当然の帰結というべきであるから、控訴人が本件払戻限度超過額を収受することが旧商法の規定により許されないとしても、そのことをもって、直ちにその収益性を否定することはできないと解するのが相当である。」
なお、本件高裁判決については、第一審判決後から反対意見が多数ある。主なものは次のとおりである。
イ 当事者が選択した法形式を無視した強行法規違反となるような引き直し課税は違法である。
ロ 違法所得への課税は現実の収受が行われている場合に限定すべきである。
(2)最高裁平成7年判決の意義
本件高裁判決は、最高裁平成7年判決を引用して、本事案が株式の低額譲渡に該当するとして課税処分を適法と判断している。同判決は、私法上の制約等がある場合を前提として判示されたものではないが、同判決の考え方は、本事案のような私法上の制約等がある場合にも及ぶのであろうか。
同判決は次のように判示している。
「この規定(法人税法22条2項)は、法人が資産を他に譲渡する場合には、その譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を伴わないものであっても、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものと解される。」「右規定の趣旨からして、この場合に益金の額に算入すべき収益の額には、当該資産の譲渡の対価の額のほか、これと右資産の譲渡時における適正な価額との差額も含まれるものと解するのが相当である。」(括弧書き、筆者加筆)
最高裁平成7年判決は、同判決の調査官解説にもあるとおり、譲渡により、資産が法人の支配を離脱する際に、これを契機として顕在化した資産の経済的価値の担税力に着目して清算課税するこということを明らかにしたものであると考える。
(3)私法上の制約等がある場合の収益認定の考え方
一般的には、客観的な交換価値(市場価値)が税務上の時価であるといわれている。私法上の制約等が収益認定にどのような影響を及ぼすのだろうか。便宜上、次のケースに分けて考察を加えたい。
イ 私法上の制約等が収益計上者に影響を与えるケース(ケース1)
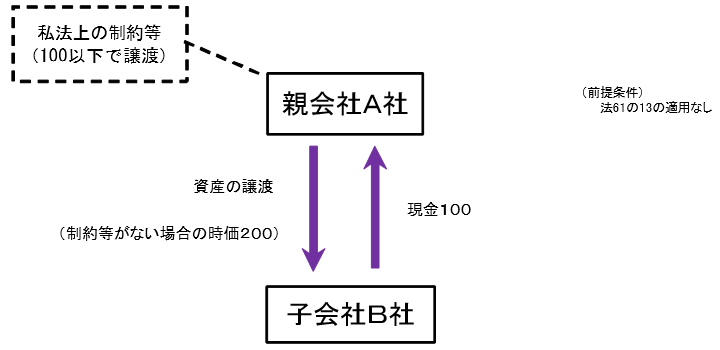
このケースでは、資産を譲渡するに当たり、収益計上者に私法上の制約等が影響を与えることを想定している。私法上の制約等がない場合の譲渡対象資産の時価が200であったとしても、A社は、この制約等の影響を受けて100以下で譲渡しなければいけないことになる。また、別の見方をしてみると、A社は、この資産を利害関係のない第三者に譲渡する場合であっても、この制約に縛られて100以下で譲渡しなければならないことになる。A社には100を超えて譲渡する選択肢がない。したがって、この場合における時価は200ではなく、100になると考えられることから、収益の額は100になり、譲渡対価が100であれば、低額譲渡に該当することはない。
このケースでは、私法上の制約等の影響により、資産の時価が200から100に下落し、その譲渡に係る収益の額が100となることから、私法上の制約等が収益計上者であるA社の収益の額の認定に影響を及ぼすことになる。
(参考事例)
PL農場事件における転売特約
このケースに該当するものにPL農場事件の転売特約がある。この事件は、複数の関係会社間における土地転がしの事件であるが、この事件では、関係会社でない譲受法人との間で土地を坪単価3000円で譲渡することとなった後に、同法人との間に関係会社を介在させて、転売特約を設けて坪単価3000円より低い価額で譲渡を行い、関係会社間に譲渡所得を分散させている。この事件では、転売特約に従って、他の関係会社に低額で譲渡した場合の収益の額が問題になった。
大阪高裁昭和59年6月29日判決(行集35巻6号822頁)は、「法人税法22条2項の収益の額を判断するに当って、その収益が契約によって生じているときは、法に特別の規定がない限り、その契約の全内容、つまり特約をも含めた全契約内容に従って収益の額を定めるべきものである、もし、契約のうち、民法等に定めのない特別の約定の部分を全て省いて収益の額を判断するというのでは、実質的には収益がないのに課税が行われ、あるいは実質的には収益があるのに課税が行えないという不合理が生ずるであろう。」と判示し、納税者側の主張を認めた。
このように、PL農場事件では、転売特約が収益認定に影響を及ぼす形となった。
なお、一般論を述べた上記判示部分は妥当と考えるが、PL農場事件は、関係会社間の土地転がしによる租税回避事件であり、転売特約は租税回避目的で関係会社間に設けられたものである。このような状況を踏まえた場合にも、同様に考えることができるのかという点については疑問が残る(この点については、ケース3の場合でも同じ。詳細は、本文第5章第4節2を参照)。
ロ 私法上の制約等が収益計上者以外の者に影響を与えるケース(ケース2)
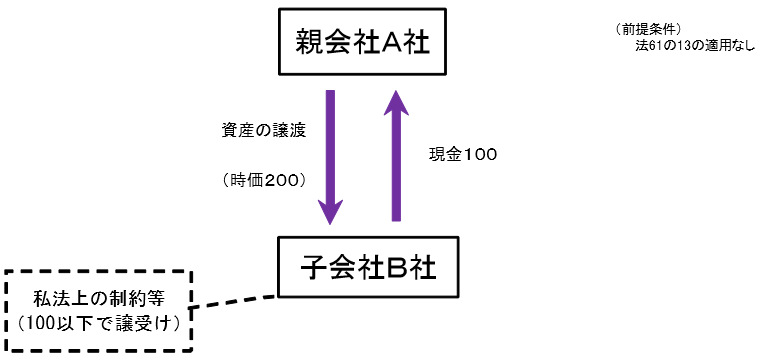
このケースでは、資産を譲渡するに当たり、私法上の制約等が収益計上者以外の者に影響を与えることを想定している(何らかの事情によって私法上の制約等がA社にも影響を及ぼし、A社自身の選択肢がない場合を除く。)。この制約は、収益計上者ではないB社に影響を与えるものであることから、収益計上者であるA社に直接影響を及ぼすことはない。また、A社は、この資産を利害関係のない第三者に譲渡するという選択肢もあり、その場合には、200の収入を得ることができる。このケースで、A社は資産を譲渡することにより、200の収入を得ることができることから、当該資産の時価は200と考えられる。この場合、収益の額は200であり、これに対して譲渡対価100であることから、このケースは低額譲渡に当たる。
このケースでは、私法上の制約等があるものの、収益認定する際にこれに影響されることはない。
(参考事例)
タイ私法の額面発行原則
資産の譲渡に係る事案ではないが、収益計上者以外の者に私法上の制約等が影響を与えるものとして、タイ子会社有利発行事件がある。これは、タイの私法に従って、タイの子会社が額面発行増資を行ったところ、内国法人である親会社が引き受けた新株が有利発行に該当すると課税庁に認定された事案である。
第一審で、納税者側は本件各株式の発行価額は「有利な発行価額」に当たらない旨を主張する際、その理由の一つとして「タイ民事商事法典上、新株発行は額面発行が原則であり、本件各株式の発行会社には、額面超過額による新株発行を可能とする定款の定めがなかったこと」を挙げた。
この点に関して、東京地裁平成22年3月5日判決(税資260号順号11392)は、「原告の…主張は、タイ法律上、新株の発行においては額面額発行が予定されており、本件2社株についても、これに基づいて額面発行されていることを指摘するにすぎず、本件2社株の額面価額(1株1000バーツ)がそれぞれの時価であったことを裏付ける事情であるということはできない。」と判示している(東京高裁平成22年12月15日判決(税資260号順号11571)においても、この部分は支持されている)。この事例では、タイ私法上の額面発行原則は親会社の収益認定に影響を与えないと判断された。
ハ 私法上の制約等が取引の両当事者に影響を与えるケース(ケース3)
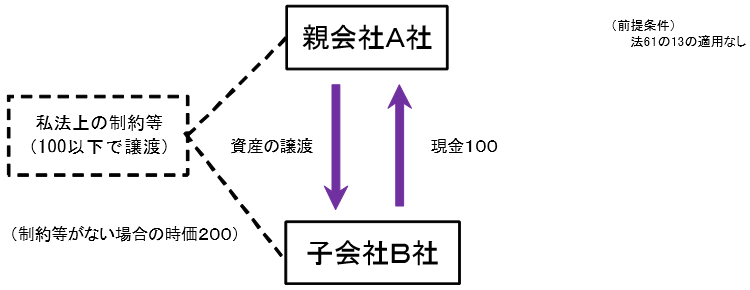
このケースは、資産を譲渡するに当たり、私法上の制約等が譲渡者及び譲受者の両当事者に影響を与えることを想定している。私法上の制約等がない場合の譲渡対象資産の時価が200であったとしても、A社及びB社は、この制約等の影響を受けて、A社は100以下で譲渡しなければいけないことになる。A社には100を超えて譲渡する選択肢がない。したがって、この場合における時価は200ではなく、100になると考えられることから、収益の額は100になり、譲渡対価が100であれば、低額譲渡に該当することはない。
このケースでは、私法上の制約等がA社の収益認定に影響を及ぼす。
(参考事例)
国土利用計画法の土地取引規制
国土利用計画法の土地取引規制には、規制に違反すると契約自体が無効となってしまう許可制と違反しても契約の効力に影響を及ぼさない届出制がある。届出制については、契約の効力に影響を及ぼさないといっても、勧告を無視した場合にその旨が公表されることもあることから、いずれの場合も規制導入後には、土地の時価に直接影響を及ぼし、一定の地価の引下げ効果があり、実勢価格が抑えられていくことになる。
いずれの規制についても、土地取引に影響を与え、これにより土地の時価が下落する。国土利用計画法の土地取引規制がかかる土地を譲渡した場合の収益の額もその下落後の時価となる。
ニ 分析結果
以上の考察のとおり、私法上の制約等が取引当事者に影響を与える場合、その制約等が全ての場面において収益認定に影響を与えるものでないことが確認できた。
私法上の制約等と収益認定の関係について要約すると、私法上の制約等が収益計上者に影響を与える場合(ケース1)及び私法上の制約等が取引の両当事者に影響を与える場合(ケース3)には、私法上の制約等により時価が影響を受けることから、収益計上者の収益認定に当たり、私法上の制約等を考慮する必要がある。ただし、例えば、その制約等がグループ法人間で設けられたもので、恣意性が働くようなものである場合には、利益調整が容易に可能となることから、このような制約等が収益認定に当たり影響を及ぼすと考えることは適当でない。収益認定に影響を及ぼす制約等は、利害関係のない第三当事者間でも成立し得るような合理性が担保できるものに限定すべきであると考える。
一方、私法上の制約等が収益計上者以外の者に影響を与える場合(ケース2)には、時価が制約等の影響を受けないことから、収益計上者の収益認定に当たり、私法上の制約等を考慮する必要がない。この場合の時価は、制約等がない場合のそれと同一になる。
(4)本件高裁判決の妥当性
本事案については、上記(1)イ及びロのとおり「当事者が選択した法形式を無視した強行法規違反となるような引き直し課税は違法である。」、「違法所得への課税は現実に収受が行われている場合に限定すべきである。」という意見がある。
この点については、次のように考える。本件各子会社は、旧商法の規定を遵守し、強制消却に伴う払戻しを行った。違法な取引は行われていない。これに対して、課税庁は払戻し額(対価)が譲渡対象となった株式の時価を下回ることから、低額譲渡に当たるとして課税処分を行った。課税上、私法上の取引を否定するわけでもなく、違法な取引を行ったと引き直したわけでもない。本事案では、旧商法の規定を遵守して行われた行為を前提とした上で、収益の額を測定した結果、低額譲渡と認定できたから課税処分が行われたものであり、本事案は違法所得に対して課税が行われたものではないと考えられる。
本事案の問題の本質は、収益認定に当たり、本件払戻規制が収益認定にどのような影響を与えるのかという点にある。
私法上の制約等がある場合の収益認定の考え方は、上記(3)のとおりと考えているが、これをベースに本事案をみると、本件払戻規制は本件各子会社に影響を与えるものであることから、上記(3)のケース2に該当すると考えられる。そうすると、同規制は原告の収益認定に影響を及ぼさないことから、本事案においては、最高裁平成7年判決の考え方がそのまま妥当することになる。本事案において強制消却された株式の譲渡に係る収益の額は、同規制がない場合の時価となると考える。
ただし、この点については、次のような指摘も考えられる。すなわち、本事案では、本件消却株式の譲渡が行われたのではなく、強制消却が行われたのであり、また、この場合の本件払戻規制は、主観的な特殊事情等ではなく、違反すると無効になる強行法規であることから、取引当事者はこれを無視することはできないため、本件消却株式の時価が本件払戻限度額まで下落したのではないかという指摘である。
時価は「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立する価額」、あるいは「取引当事者を利害関係のない第三者に置き換えて成立するであろう価額」によるべきであると考えるが、本事案においては、本件株式消却とほぼ同時期に行われた合併に先立って、合併比率算定のために、第三者である外部金融機関に依頼して時価純資産法により評価された評価額が存在しており、本件消却株式の時価は、同評価額であると考えられる。本事案において、多額の含み益のある株式を旧商法の規定に従って強制消却すると株式の保有者は損することになることから、取引当事者を利害関係のない第三者に置き換えた場合には、合理的な理由がない限り、本事案のような取引は成立し得ない。本事案の強制消却は、100%子会社であればこそ可能であった取引といえる。本件払戻規制の影響によって、本件消却株式の時価が本件払戻限度額に置き換わることはない。
本件高裁判決は「控訴人が本件払戻限度超過額を収受することが旧商法の規定により許されないとしても、そのことをもって、直ちにその収益性を否定することはできないと解するのが相当である。」と判示している。裁判官がこのように考えた理由は明らかにされていないが、これには、上記のような考え方が背景にあるのではないか。本件高裁判決が最高裁平成7年判決を引用した上で、低額譲渡に該当すると判断したことについて問題はないと考える。
目次
| 項目 | ページ |
|---|---|
| はじめに | 16 |
| 第1章 本事案の概要と判決内容 | 19 |
| 第1節 本事案の概要 | 19 |
| 1 更正処分の概要 | 19 |
| 2 事実関係 | 20 |
| 第2節 各判決の概要 | 21 |
| 1 東京地裁平成24年11月28日判決の概要 | 21 |
| 2 東京高裁平成26年6月12日の概要 | 22 |
| 3 最高裁不受理決定等の概要 | 24 |
| 第2章 法人税法上の所得概念 | 26 |
| 第1節 課税所得の計算構造 | 26 |
| 第2節 昭和40年税制改正当時の状況 | 27 |
| 1 昭和40年税制改正前の規定 | 28 |
| 2 税制調査会答申(昭和38年12月) | 28 |
| 3 昭和40年改正時の立案当局者の説明 | 29 |
| 第3節 所得概念について言及した判例 | 31 |
| 1 最高裁昭和41年6月24日第二小法廷判決 | 31 |
| 2 最高裁昭和43年10月31日第一小法廷判決 | 33 |
| 第4節 所得概念を巡るいくつかの論点 | 34 |
| 1 包括所得概念(純資産増加説) | 34 |
| 2 無償取引の課税の根拠 | 35 |
| 3 法人税法22条2項は創設規定か確認規定か | 37 |
| 4 違法な所得への課税 | 39 |
| 第5節 小括 | 45 |
| 第3章 税務上の一般的な時価概念 | 46 |
| 第1節 法令・通達における時価 | 46 |
| 第2節 裁判例等 | 47 |
| 第3節 学説 | 48 |
| 第4節 小括 | 51 |
| 第4章 最高裁平成7年判決の意義 | 52 |
| 1 事案の概要 | 52 |
| 2 判示事項 | 53 |
| 3 調査官解説 | 55 |
| 4 最高裁平成7年判決の意義 | 56 |
| 第5章 私法上の制約等が収益認定に与える影響 | 58 |
| 第1節 私法上の制約等が収益計上者に影響を与えるケース(ケース1) | 59 |
| 1 PL農場事件における転売特約 | 60 |
| 2 FSB事件における銀行法の規制 | 63 |
| 第2節 私法上の制約等が収益計上者以外の者に影響を与えるケース(ケース2) | 65 |
| 第3節 私法上の制約等が取引の両当事者に影響を与えるケース(ケース3) | 67 |
| 第4節 グループ法人間において制約が設けられた場合の取扱い | 70 |
| 1 グループ法人間取引における低額譲渡事案(グループ法人間における「特殊事情」の評価) | 70 |
| 2 PL農場事件高裁判決の再考 | 71 |
| 3 小括 | 73 |
| 第5節 私法上の制約等と収益認定との関係 | 75 |
| 第6章 本事案の検証 | 77 |
| 第1節 本事案は違法所得への引き直し課税なのか | 77 |
| 第2節 本件消却株式の時価 | 79 |
| 第3節 適正所得算出説によるアプローチ | 81 |
| 第4節 法人税法22条4項との関係 | 84 |
| 1 納税者側の主張と判示事項 | 84 |
| 2 法人税法22条4項の意義 | 85 |
| 3 本事案との関係 | 86 |
| 第5節 強制消却の必要性 | 87 |
| 第6節 小括 | 88 |
| 結びに代えて | 89 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。